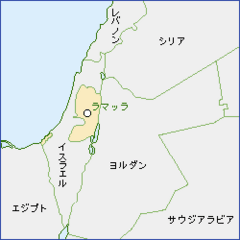12月23日、24日の2日間にわたってヨルダン大学、日本大使館、国際協力機構(JICA)
の協力のもとジャパン・フェスティバルがヨルダン大学で行われた。
我々夫婦も2日目の日本文化紹介のお手伝いでヨルダン大学に出かけた。
フェスティバルについては新年早々の次回の稿に譲り、今回はヨルダン大学について紹介したい。
フェスティバル2日目の24日、我々は生憎の雨の中を会場があるヨルダン大学に向かった。
正門前でタクシーを降りると、そこは学園街らしく学生向けのお店があったが
朝早いせいか閉じてる店が多かった

(正門前の学生向けのお店)
ヨルダン大学はヨルダンにある10ばかりの国立大学の1つであり、最も古い歴史を誇っている。
医学部を含む総合大学で学生数は約7万人とかなりのマンモス大学である。
学生の男女比は五分五分だそうだ。
だが登校する学生を見ていると女子学生が圧倒的に多いようだった。
ここヨルダンでも女子の方が真面目に授業に出席するのかもしれない。
ヨルダンにおいては女性の社会進出は特に官公庁では進んでおり、日本以上とも言われている。

(ヨルダン大学正門前)
ヨルダン大学では日本語講座が開かれており、
1993年の文学部への青年海外協力隊員派遣にさかのぼる、
以来現在まで同隊員派遣による講座が継続されている。
日本語講座は外国語学科の選択必修科目および全学部対象の自由選択科目であり
第2外国語として位置づけられている。
学習動機は理系学生においては日本のテクノロジーへの関心が主なものであり、
その他では日本文化(アニメなどのポップカルチャーを含む)に対する関心によるものが多いようだ。
正門を抜けると正面に時計台がある。

(時計台 右手前は銀行のATMである)
キャンパスはかなり広い。
男女交際も自由なようで男女が談笑する姿もいたるところで見られ、
日本の学生のキャンパス・ライフと大差なく青春を謳歌しているようだった。

(キャンパス内の並木道)
各銀行のATMが数ヶ所で見かけられ利用頻度は高いようだ。
地方から出てきてる学生も多いらしい。

(キャンパス内 左奥はATM)
並木道を通り抜けるとモダンな建物があり、そこがジャパン・フェスティバルの会場だった。

(会場)
この稿はヨルダン大学の紹介のためここで終わる。
ジャパン・フェスティバルの模様については次々回の「ジャパン・フェスティバル」
(カテゴリー:ヨルダンでの日本文化紹介)をご覧頂くようお願いします。
の協力のもとジャパン・フェスティバルがヨルダン大学で行われた。
我々夫婦も2日目の日本文化紹介のお手伝いでヨルダン大学に出かけた。
フェスティバルについては新年早々の次回の稿に譲り、今回はヨルダン大学について紹介したい。
フェスティバル2日目の24日、我々は生憎の雨の中を会場があるヨルダン大学に向かった。
正門前でタクシーを降りると、そこは学園街らしく学生向けのお店があったが
朝早いせいか閉じてる店が多かった

(正門前の学生向けのお店)
ヨルダン大学はヨルダンにある10ばかりの国立大学の1つであり、最も古い歴史を誇っている。
医学部を含む総合大学で学生数は約7万人とかなりのマンモス大学である。
学生の男女比は五分五分だそうだ。
だが登校する学生を見ていると女子学生が圧倒的に多いようだった。
ここヨルダンでも女子の方が真面目に授業に出席するのかもしれない。
ヨルダンにおいては女性の社会進出は特に官公庁では進んでおり、日本以上とも言われている。

(ヨルダン大学正門前)
ヨルダン大学では日本語講座が開かれており、
1993年の文学部への青年海外協力隊員派遣にさかのぼる、
以来現在まで同隊員派遣による講座が継続されている。
日本語講座は外国語学科の選択必修科目および全学部対象の自由選択科目であり
第2外国語として位置づけられている。
学習動機は理系学生においては日本のテクノロジーへの関心が主なものであり、
その他では日本文化(アニメなどのポップカルチャーを含む)に対する関心によるものが多いようだ。
正門を抜けると正面に時計台がある。

(時計台 右手前は銀行のATMである)
キャンパスはかなり広い。
男女交際も自由なようで男女が談笑する姿もいたるところで見られ、
日本の学生のキャンパス・ライフと大差なく青春を謳歌しているようだった。

(キャンパス内の並木道)
各銀行のATMが数ヶ所で見かけられ利用頻度は高いようだ。
地方から出てきてる学生も多いらしい。

(キャンパス内 左奥はATM)
並木道を通り抜けるとモダンな建物があり、そこがジャパン・フェスティバルの会場だった。

(会場)
この稿はヨルダン大学の紹介のためここで終わる。
ジャパン・フェスティバルの模様については次々回の「ジャパン・フェスティバル」
(カテゴリー:ヨルダンでの日本文化紹介)をご覧頂くようお願いします。