今回は我々が一時帰国から戻った3日後の2009年3月7日に行われた
「日本語弁論大会」について記したい。
この大会は今回で12回目だそうだ。
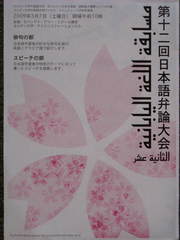
(桜が図案化されたポスター)
会場は昨年開催された「ジャパン・フェスティバル」と同じく
ヨルダン大学構内で行われた。

(上が大会を示す横断幕 赤字で日本語弁論大会と書かれている)
会場は正門左側に位置するアドミニストレーション・ビルで、
なかなかモダンなものである。

(アドミニストレーション・ビル)
ロビーも広く明るくホテルを連想させる雰囲気である。

(国王の写真が飾られたロビー)
会場受付には日本紹介の雑誌も希望者に配られていた。

(日本紹介雑誌)
ここヨルダンでは青年海外協力隊員を中心とした「アル・オルドン奨学基金」が
設立されており、毎年2名の学生を選びサポートしている。
それの募金活動が同じく受付で行われていた。

(アル・オルドン奨学基金の募金活動)
大会はヨルダン国、日本国の国歌演奏で始まる。

(国歌演奏 左より塩口日本大使、外国語学部長、JICA所長)
塩口日本大使、外国語学部長の挨拶のあと大会はいよいよ始まった。
大会は俳句の部と弁論の部の2部構成となっている。
俳句の部では出場者が選んだ俳句についての解釈を英語とアラビア語で
行うものであり、漱石、蕪村、芭蕉、一茶などの句に対してヨルダン人からの
解釈が試みられ興味深かった。
しかし日本語による解釈はなく、ややもすると英語力に左右されやすく
ちょっと物足りない感じである。
あとで関係者に聞いてみると、俳句の部の参加者はまだ初級レベルであり
日本語で説明するほどのレベルに達してないとのことである。
俳句の部の発表者は男性3名、女性7名の計10名であった。

(俳句の部 発表風景)
弁論の部はあらかじめテーマが決められているか自分で自由にテーマを見つけるかは
参加者に任されている。
参加者は男性4名、女性8名の計12名であり、規定のテーマを選んだものが
9名、自由テーマを選んだものが3名であった。
規定のテーマには次の3つが挙げられていた。
1.わたしの宝物
2.人生で一番嬉しかった日/悲しかった日
3.日本/ヨルダンの( )がクールだ
内訳は1を選んだものが4名、2を選んだものが1名、3を選んだものが4名で
( )の中はそれぞれ、日本の(桜/お辞儀)の2つと
ヨルダンの(パーソナリティー/コーヒー文化)の2つであった。
自由テーマは下記の3つである。
・ロボットの時代
・自分のルール
・羽を伸ばす

(弁論の部 発表風景)
弁論の部の発表終了後表彰式がおこなわれた。

(表彰式)
俳句の部での1位は一茶の「元日や 上々吉の 浅黄空」の解釈を披露した
女性が選ばれた。
3位までの入賞者はすべて女性であった。
また弁論の部では規定テーマ「人生で一番悲しかった日、嬉しかった日」で
15歳で結婚した友人が、早すぎる結婚のために結婚式そのものが一番
悲しかった日であると訴え、早婚の問題点をえぐったものであった。
発表には演技力もあり説得性のあるものであったが、私としては同じような
内容を以前に新聞記事で読んだことがあり、また自分の体験ではなく友達の
体験を題材としてることに疑問が残った。
私としてはむしろ2位、3位に入った「ヨルダン人のパーソナリティがクールだ」、
「ヨルダンのコーヒー文化がクールだ」のほうがヨルダン人が自国の文化を
主張してくれて、今まで気づかなかった、あるいは知らなかったヨルダン文化の
一面を指摘され、また教えられ興味深かった。
こちらでも3位までの入賞者はすべて女性だった。

(弁論の部 一位表彰)
最後に発表者、関係者が記念写真をとって大会は終わった。

(記念写真)
結局、総計22名の発表者のうち女性が15名であり、また入賞者6名すべてが
女性というわけで、ヨルダンにおける女性上位のパワーに圧倒された大会であった。
「日本語弁論大会」について記したい。
この大会は今回で12回目だそうだ。
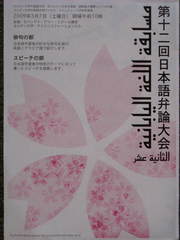
(桜が図案化されたポスター)
会場は昨年開催された「ジャパン・フェスティバル」と同じく
ヨルダン大学構内で行われた。

(上が大会を示す横断幕 赤字で日本語弁論大会と書かれている)
会場は正門左側に位置するアドミニストレーション・ビルで、
なかなかモダンなものである。

(アドミニストレーション・ビル)
ロビーも広く明るくホテルを連想させる雰囲気である。

(国王の写真が飾られたロビー)
会場受付には日本紹介の雑誌も希望者に配られていた。

(日本紹介雑誌)
ここヨルダンでは青年海外協力隊員を中心とした「アル・オルドン奨学基金」が
設立されており、毎年2名の学生を選びサポートしている。
それの募金活動が同じく受付で行われていた。

(アル・オルドン奨学基金の募金活動)
大会はヨルダン国、日本国の国歌演奏で始まる。

(国歌演奏 左より塩口日本大使、外国語学部長、JICA所長)
塩口日本大使、外国語学部長の挨拶のあと大会はいよいよ始まった。
大会は俳句の部と弁論の部の2部構成となっている。
俳句の部では出場者が選んだ俳句についての解釈を英語とアラビア語で
行うものであり、漱石、蕪村、芭蕉、一茶などの句に対してヨルダン人からの
解釈が試みられ興味深かった。
しかし日本語による解釈はなく、ややもすると英語力に左右されやすく
ちょっと物足りない感じである。
あとで関係者に聞いてみると、俳句の部の参加者はまだ初級レベルであり
日本語で説明するほどのレベルに達してないとのことである。
俳句の部の発表者は男性3名、女性7名の計10名であった。

(俳句の部 発表風景)
弁論の部はあらかじめテーマが決められているか自分で自由にテーマを見つけるかは
参加者に任されている。
参加者は男性4名、女性8名の計12名であり、規定のテーマを選んだものが
9名、自由テーマを選んだものが3名であった。
規定のテーマには次の3つが挙げられていた。
1.わたしの宝物
2.人生で一番嬉しかった日/悲しかった日
3.日本/ヨルダンの( )がクールだ
内訳は1を選んだものが4名、2を選んだものが1名、3を選んだものが4名で
( )の中はそれぞれ、日本の(桜/お辞儀)の2つと
ヨルダンの(パーソナリティー/コーヒー文化)の2つであった。
自由テーマは下記の3つである。
・ロボットの時代
・自分のルール
・羽を伸ばす

(弁論の部 発表風景)
弁論の部の発表終了後表彰式がおこなわれた。

(表彰式)
俳句の部での1位は一茶の「元日や 上々吉の 浅黄空」の解釈を披露した
女性が選ばれた。
3位までの入賞者はすべて女性であった。
また弁論の部では規定テーマ「人生で一番悲しかった日、嬉しかった日」で
15歳で結婚した友人が、早すぎる結婚のために結婚式そのものが一番
悲しかった日であると訴え、早婚の問題点をえぐったものであった。
発表には演技力もあり説得性のあるものであったが、私としては同じような
内容を以前に新聞記事で読んだことがあり、また自分の体験ではなく友達の
体験を題材としてることに疑問が残った。
私としてはむしろ2位、3位に入った「ヨルダン人のパーソナリティがクールだ」、
「ヨルダンのコーヒー文化がクールだ」のほうがヨルダン人が自国の文化を
主張してくれて、今まで気づかなかった、あるいは知らなかったヨルダン文化の
一面を指摘され、また教えられ興味深かった。
こちらでも3位までの入賞者はすべて女性だった。

(弁論の部 一位表彰)
最後に発表者、関係者が記念写真をとって大会は終わった。

(記念写真)
結局、総計22名の発表者のうち女性が15名であり、また入賞者6名すべてが
女性というわけで、ヨルダンにおける女性上位のパワーに圧倒された大会であった。






























