2日前のこと。
湯島天神に出かけることにしました。
今、梅が見頃だといいます。
で、その前に、秋葉原で降りて、

ここへ↓。

どでかい海鮮丼を食べさせる、と評判の店。

食材がなくなり次第、その日は閉店にするシステム。

店内にはアニメのポスターやグッズが。

モニターでは、ずっとアニメの映画がかかっています。

出ました。

これ、まるき丼といいます。
まぐろ、づけまぐろ、白身、厚焼き玉子、ぶつ、うに、いくら・・・
白飯に届くまで、刺身を発掘。
女性は大変でしょう。
なんとか完食。
その後、徒歩で、ここ↓へ。

実は、まぐろ亭と湯島天神はすぐ側、
のつもりでしたが、
地図で見ると、違う。
つまり、湯島天神と湯島聖堂を混同していたのだと判明。

ずっと、御茶の水駅から聖橋を渡ったところにあるのを、
湯島天神だと思い込んでいた。
東京に何十年と住んでいながら、
この勘違いは恥ずかしい。

湯島聖堂(ゆしませいどう)は、
江戸時代の元禄3年(1690年)、
江戸幕府5代将軍徳川綱吉によって建てられた孔子廟。
後に幕府直轄の学問所となった。
「昌平黌(しょうへいこう)」がそれ。
「昌平」とは、孔子が生まれた村の名前。
学問に関わるため、
湯島天神とともに、合格祈願のために、参拝に来る受験生が訪れる場所。



孔子像。

世界最大の孔子像。

ここは、大成殿。



大成殿では、1872年(明治5年)、
東京初の博覧会「湯島聖堂博覧会」が開催された。
これが後の東京国立博物館の始まり。
↓の展示が行われていました。






1922年(大正11年)3月8日、
敷地が国の史跡に指定された。
御茶ノ水駅の上で神田川をまたぐ聖橋(ひじりばし)は、
「二つの聖堂(湯島聖堂とニコライ堂)を結ぶ橋」
であることからその名を得ている。

すぐそばにある神田明神へ。

正式名称は神田神社。
江戸三大祭の一つである神田祭を行う神社として知られている。



大己貴命(オオナムチノミコト、だいこく様)。縁結びの神様。
少彦名命(スクナヒコナノミコト、えびす様)。商売繁昌の神様。
平将門命(タイラノマサカドノミコト、まさかど様)。除災厄除の神様。
の3柱を祭神として祀る。

社伝によれば、天平2年(730 年)、
武蔵国豊島郡芝崎村に入植した出雲系の氏族が、
大己貴命を祖神として祀ったのに始まるといわれる。
相当古い。
江戸時代には「神田明神」と名乗り、
周辺の町名にも神田明神を冠したものが多くあった。
銭形平次が神田明神下の長屋に住居を構えていたということから、
「明神下の親分」と呼ばれていた。
東に出ると、坂が。

神社が丘の上にあったのだと分かります。

さて、この後、本日の目的地、
湯島天神へ向かいます。
続きは、今度。










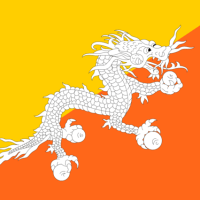









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます