今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、一連の経過を経て 実にさまざまな方面から、さまざまな意見や見解などが提起されることになっています。
表面的なマスコミ報道や、この事案を深く掘り下げた新聞記事、また(この面は私 ヨク分かりませんが)側聞すれば Twitterなどの〝裏〟の部分でも議論?が盛り上がっているようです。
社会の片隅にある遊園地で起こった争議。
その内容は、一見すると「一部の住民からの苦情⇔そこで遊ぶ子どもへの著しい制限」との〝対立の構図〟であり、このことがマスコミの食指を動かし ついには全国的な話題へと発展しました。
そして 多くの人たちが、表面的な部分から深層に至るまで さまざまな見解(意見)を交わすことになっています。
私は、このことは 非常に歓迎すべき事象だと思います。
今回の案件は「これが正解」という明快な結論を導き出すには 非常に複雑な経過を辿っていることから、向き合う人の「思い」や「立場」などによって見解は分かれるところであり、現に 遊園地の存廃に向けて いわば賛否が渦巻くことになっています。
そして この議論は、ついに大手地方紙の「社説」にも掲載されることになりました。
2月14日(火)付の信濃毎日新聞[社説]公園の存廃~判断の過程から見直して~ です。
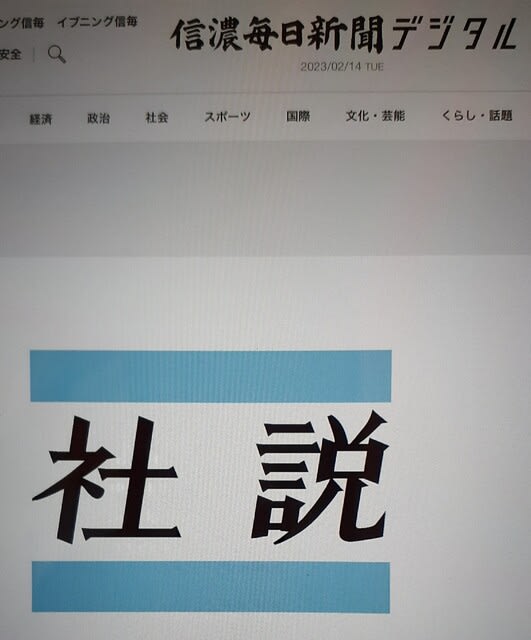
社説では先ず、荻原市長の「再検討の表明」を評価しています。
「(市長が)再検討に変わったのは、地元説明会で 多くの住民の困惑や不信感に直接触れたためだろう」とし、そのうえで「白紙」に戻して「苦情を寄せた住民も含めて対話の場を設けるところからやり直してほしい」としています。
さらに、市の対応について「苦情への対応を重ねる一方で、地域への十分な合意形成をおろそかにしてきた」と指摘しています。
その後は さまざまな経過を経たうえで「市は地元区長会を窓口に協議を進め、廃止を決めている」としたうえで「多くの住民は 秋になって廃止を突然知った。説明会では 廃止理由に反論が相次ぎ、協議の進め方に反発の声も上がった」としています。
そのうえで この社説においても、市と住民 とりわけ遊園地を利用する子どもや保護者の声を「直接聞く」努力が足りなかったことを指摘したうえで 判断の過程を見直すことを促しています。
そして、もしかしたら これが一番大切なのかもしれませんが「地域で子どもを育ててゆくうえで、公園(や遊園地)がいかに重要であるかを気づかせることとなった」としています。
そして 社説は最後に「公園(や遊園地)は、住みよい地域にするための共有地だ。騒音などで不快の源になってもいけない。そのためにどうあるべきか。どこでも起こりうる問題として考えたい。」と結んでいました。
この論説には、私自身 共感するところであり、私としても 今回の遊園地問題は、地域社会における多様な課題を供出したものであり 今回の件を契機に、さまざまな立場の者が「考え直す」機会となればと強く考える一人であります。
地域における事業などの決定プロセス・事業の起案の時点からの周知 説明の必要性と重要性・苦情などの問題が発生したときの対応の仕方・一部の者(所管)だけで対応せず 全体に諮(はか)ることの重要性・住民代表たる区長会や住民自治協議会の役割とあるべき姿(運営の仕方)等々、もしかしたら 今後の住民自治そのものに対する総合的な課題を提起してくれたとも言えると思います。
前日も触れましたが、今回の 一見ゴタゴタに思える案件は、今後の長野市政を助けるキッカケになり得ることになると思います。
そのためには、この 一見ピンチに思える事象をチャンスに転換するためには、関係する(私を含む)全ての者が発想を転換し 事態をイイ意味で吸収する度量をもって臨むことが欠かせません。
長野市が、一旦は その評価を失墜させかけた長野市が 逆に成長するチャンスが到来しました。
そのことに心を置いて、課題に向き合うべきであります。









