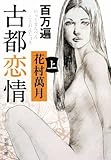そろそろ、来年のカレンダーが気になる季節になってきた。
百貨店や大手の書店では、どこでも、カレンダー・コーナーができている。
今年、真っ先に買った2009年のカレンダーは、笹倉鉄平さんのもの。
笹倉鉄平さんが、1~2年ほど前に京都の絵を何作かまとめて描かれ、青山の近くで個展を開かれるというので、観に行こうと思っていながら、結局、行けずじまいだったことがある。
そのときの個展の案内のパンフレットに載っていた、「八坂の塔」を描いた絵が、如何にもメルヘンチックで、一度大きなサイズで観たい、と思っていた。
大手の書店で、笹倉さんの画集も何冊か見たが、最近の作品のためか、まだ、どの画集にも載っていない。
次の画集がでるのを待つしかないのかな、と思っていたのだが、
先日、よく行く八重洲ブックセンターのカレンダー・コーナーに、笹倉鉄平さんのカレンダーが吊るしてあったので、捲ってみると、1~2月が、その「八坂の塔」の絵なのだ。
目にされた方も多いと思うが、その絵は、庚申堂の方から石畳を上がって行く際に見える、八坂の塔の夜の光景を、紫色を基調に、描いたもので、
前景・左に最近京都でよく見かける観光用の人力車、前景・右に灯の洩れる土産物屋の店内を覗く若いカップル、
中景に、八坂の塔の方へ歩いていく二人の芸者さんの後姿や、若いカップルの後姿などが描かれている。
そして、正面には、月明かりに浮かび上がる、八坂の塔と、塔の先端にかかるかたちで満月が描かれている。
それは、現在の京都の風景をややファンタジー性を持たせて笹倉さんが描いたもの、とも云えるが、
若いとき京都を愛したひとが何十年かたって京都を追憶する際に心に浮かべる心象風景(記憶の中にある京都)を描いたもののようにも見える。
3~12月も、笹倉鉄平ファンには堪らないだろう、ヨーロッパの町の風景画などが続くのだが(そして、私もそれらが好きなのだが)、
私は、多分、月別に日付けが載っている部分を次々に切っていき、
絵の部分は、来年一年を通して、この1~2月の「八坂の塔」でいく(一年中眺めている)、ような気がしている。
(→それほど、この絵は、今の私の京都気分にピッタリと合っているのだ)
これほど、心を捉える絵に出合えることは、人生にそうあることではない。
(追記)
このカレンダーに収録されている6枚の絵のタイトルは、以下の通りです。
- 1・2月 「八坂の塔」、
- 3・4月 「ウェディング・イン・ザ・パーク」、
- 5・6月 「ポンタヴェンの朝」、
- 7・8月 「カダケス」(このカレンダーの表紙にもなっている絵)、
- 9・10月 「メソン」、
- 11・12月 「ルナ・パーク」
「老後は京都で」~トップページに戻る