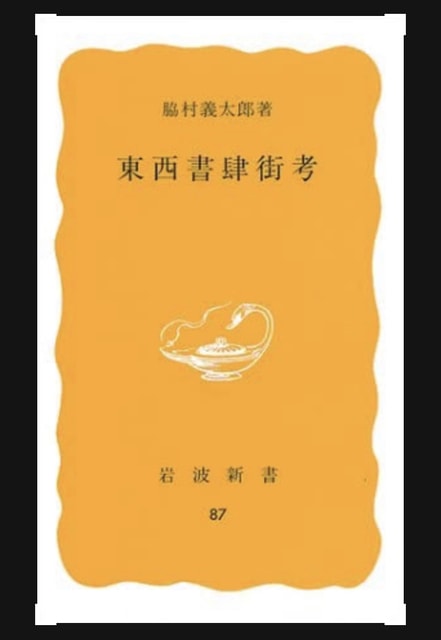薄グリーン色の地に、横に濃い緑の帯のボディの、京都の市バスの車両のデザインは、私の学生の頃(三十数年前)のままだ。
大学を卒業し京都を離れた後、何年か振りで、京都を訪れる度ごとに、まだあのバスが走っている、と確認し安緒していた。
あたかも、その時々の変わりゆく京都と、「私が学生時代を過ごした街、京都」との、連続性や同一性を、バスのデザインが同じであることが担保しているかのように。
今でも市バスはよく使う。
特に、新幹線で京都に着いた夜は、拙宅のある堺町六角の近くにバス停のある、5系統を使う。
地下鉄やタクシーという手もあるのだが、少なくとも京都に着いた夜に地下にもぐる気はしないため地下鉄はバツ、タクシーも(距離が近いので、複数人数だと料金的には割安になるのだが)、視線の位置が低く、視界も狭いため、京都に着いた、という感興がイマイチ盛り上がらないため、これもバツ。
結局、市バスが一番、ということになった。
5系統に乗ると、京都駅から烏丸通りを北上するのだが、ライトアップした東本願寺の山門をかわぎりに、バスのフロント・ガラスやウィンドー越しに、次々に展開する、夜の京都の街は、実に美しい。
四条高倉のバス停(野村證券・京都支店の前)で降りるから、せいぜい10分もない短い時間なのだが、「京都に着いた気分」を高めるには、これ(市バス)が欠かせない、というのが現在の結論だ。