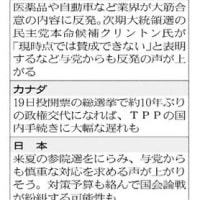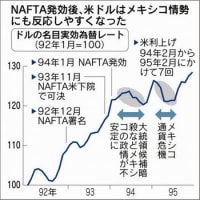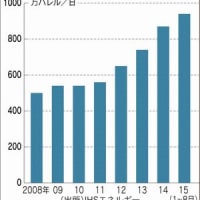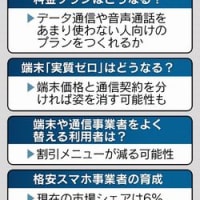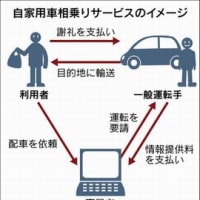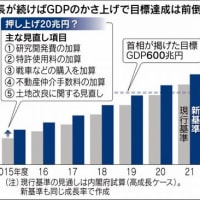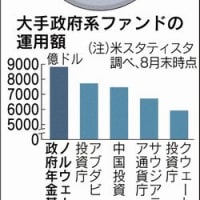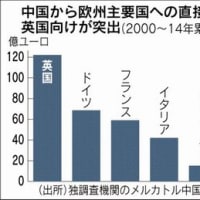〔15.2.18.日経新聞:総合1面〕

トヨタ自動車が2014年12月に発売したばかりの燃料電池車(FCV)「ミライ」の特許の無償化に踏み切った。自動車の分野で5680件もの技術を一斉に開放するのは異例だ。もっともFCV普及を優先して「虎の子」の技術を世にさらす戦略にはしたたかな計算も働いている。
昨年6月25日、トヨタはFCVを世界に先駆けて日本で市販すると発表した。「究極のエコカー発売」という晴れ舞台。しかしその裏で社内には焦燥感が募っていた。
知財委が発案
需要予測に基づく15年の年間生産台数は700台。しかしFCVをその程度しか売らないようでは、水素スタンドなどのインフラ整備に弾みが付かない。補助金でFCVを支援する政府からは「もっと本気になれ」と圧力がかかっていた。
普及をどう進めるか。「特許を無償化して他社も参入しやすくしたらいい」。そんな考えが社内に設置されている「知財委員会」から浮上した。
知財委は法務や技術部だけでなく、社内から幅広く人材を集めたトヨタの知財戦略に関する最高意思決定機関だ。早速、若手メンバーの意見を参考に、FCVの基幹部品となる燃料電池スタックやタンクから水素インフラの特許まで、あらゆる技術を無償化する案がまとまった。委員会は取締役会から独立した組織。方針を豊田章男社長に報告すると、一言、「そうか」と応じたという。
無論、20年以上かけて築き上げたFCVに関する知財をタダであっさり同業者に提供するという案に技術者の多くは当初、難色を示した。ハイブリッド車(HV)というエコカー市場を切り開いた初代プリウスの開発責任者を務めた内山田竹志会長も反対した。
技術者を中心に広がった懸念を払拭したのは知財委のシミュレーションだった。特許を有償で開放しても得られる収入は10億円に満たない。それより参入メーカーが増えて市場が広がり、結果としてインフラ整備が進む方がメリットは大きい。
トヨタが公開するFCVに関する特許を積み上げてもミライと同じ車を造ることはできないことも無償化を後押しした。例えば水素を外に漏らさないためのスタックの密閉技術は特許にもしておらず秘中の秘。厚さ0.2ミリのチタン板を短時間で量産プレス加工するという技術は、特許を活用してもまねができない。
決め手は特許の無償公開の期限を「20年末まで」と区切った点にある。
トヨタは13年、独BMWとFCVの共同開発で提携した。20年にも新型FCVを出す計画だが、その際の技術は「ミライとは全く異なる」(幹部)見通し。今回トヨタが開放した特許を活用して同業他社がFCVを投入してきたとしても、トヨタにはその先を行くロードマップができている。
インテルの先例
商品を普及させるために特許を幅広く他社に利用させる一方、重要な技術は外に漏らさず、市場の創造と利益の確保を両立する。知財の「オープン&クローズ戦略」はグローバル企業で大きな流れになりつつある。
先駆けとなった米インテルは1990年代半ばにパソコンのマザーボードに関する技術を台湾企業に供与。一方で付加価値の高いCPU(中央演算処理装置)にはインテル製を採用させ、莫大な利益を稼ぎ出した。米アップルはスマートフォン(スマホ)普及に向けて端末部品の製造情報を中国企業に開放しながら、基本ソフト(OS)「iOS」の知財を完全に秘密にしてスマホ市場で主導権を握った。
企業の知財戦略に詳しい小川紘一・東大客員研究員は「今やグローバル企業でオープン&クローズ戦略は常識だ。トヨタが同じ領域に入ったのは当然だろう」とみる。
トヨタは97年、HVプリウスを発売した際に技術を囲った結果、市場拡大でつまずいた。世界の自動車市場に占めるHVのシェアは今もまだ2%程度だ。その苦い経験を糧にした今回のオープン&クローズ戦略は実を結ぶのか。特許開放を表明後、「3社程度」(関係者)から引き合いがあるという。 (中西豊紀、編集委員 渋谷高弘)

トヨタ自動車が2014年12月に発売したばかりの燃料電池車(FCV)「ミライ」の特許の無償化に踏み切った。自動車の分野で5680件もの技術を一斉に開放するのは異例だ。もっともFCV普及を優先して「虎の子」の技術を世にさらす戦略にはしたたかな計算も働いている。
昨年6月25日、トヨタはFCVを世界に先駆けて日本で市販すると発表した。「究極のエコカー発売」という晴れ舞台。しかしその裏で社内には焦燥感が募っていた。
知財委が発案
需要予測に基づく15年の年間生産台数は700台。しかしFCVをその程度しか売らないようでは、水素スタンドなどのインフラ整備に弾みが付かない。補助金でFCVを支援する政府からは「もっと本気になれ」と圧力がかかっていた。
普及をどう進めるか。「特許を無償化して他社も参入しやすくしたらいい」。そんな考えが社内に設置されている「知財委員会」から浮上した。
知財委は法務や技術部だけでなく、社内から幅広く人材を集めたトヨタの知財戦略に関する最高意思決定機関だ。早速、若手メンバーの意見を参考に、FCVの基幹部品となる燃料電池スタックやタンクから水素インフラの特許まで、あらゆる技術を無償化する案がまとまった。委員会は取締役会から独立した組織。方針を豊田章男社長に報告すると、一言、「そうか」と応じたという。
無論、20年以上かけて築き上げたFCVに関する知財をタダであっさり同業者に提供するという案に技術者の多くは当初、難色を示した。ハイブリッド車(HV)というエコカー市場を切り開いた初代プリウスの開発責任者を務めた内山田竹志会長も反対した。
技術者を中心に広がった懸念を払拭したのは知財委のシミュレーションだった。特許を有償で開放しても得られる収入は10億円に満たない。それより参入メーカーが増えて市場が広がり、結果としてインフラ整備が進む方がメリットは大きい。
トヨタが公開するFCVに関する特許を積み上げてもミライと同じ車を造ることはできないことも無償化を後押しした。例えば水素を外に漏らさないためのスタックの密閉技術は特許にもしておらず秘中の秘。厚さ0.2ミリのチタン板を短時間で量産プレス加工するという技術は、特許を活用してもまねができない。
決め手は特許の無償公開の期限を「20年末まで」と区切った点にある。
トヨタは13年、独BMWとFCVの共同開発で提携した。20年にも新型FCVを出す計画だが、その際の技術は「ミライとは全く異なる」(幹部)見通し。今回トヨタが開放した特許を活用して同業他社がFCVを投入してきたとしても、トヨタにはその先を行くロードマップができている。
インテルの先例
商品を普及させるために特許を幅広く他社に利用させる一方、重要な技術は外に漏らさず、市場の創造と利益の確保を両立する。知財の「オープン&クローズ戦略」はグローバル企業で大きな流れになりつつある。
先駆けとなった米インテルは1990年代半ばにパソコンのマザーボードに関する技術を台湾企業に供与。一方で付加価値の高いCPU(中央演算処理装置)にはインテル製を採用させ、莫大な利益を稼ぎ出した。米アップルはスマートフォン(スマホ)普及に向けて端末部品の製造情報を中国企業に開放しながら、基本ソフト(OS)「iOS」の知財を完全に秘密にしてスマホ市場で主導権を握った。
企業の知財戦略に詳しい小川紘一・東大客員研究員は「今やグローバル企業でオープン&クローズ戦略は常識だ。トヨタが同じ領域に入ったのは当然だろう」とみる。
トヨタは97年、HVプリウスを発売した際に技術を囲った結果、市場拡大でつまずいた。世界の自動車市場に占めるHVのシェアは今もまだ2%程度だ。その苦い経験を糧にした今回のオープン&クローズ戦略は実を結ぶのか。特許開放を表明後、「3社程度」(関係者)から引き合いがあるという。 (中西豊紀、編集委員 渋谷高弘)