
戸籍法ってのについて、ちょっと調べてみた。
だって、この夏、久々にホットな話題、でしょ?
186歳男性「戸籍上生存」十三代将軍・家定と同い年
戸籍上は生存する「超高齢者」の存在が相次いで発覚する中、山口県防府市は26日、186歳の男性の戸籍が残っていたことを明らかにした。男性が生まれた1824(文政7)年は、篤姫が嫁いだ徳川十三代将軍の家定が生まれた年だった。
***********
何ともホノボノするイイお話しじゃありません事?
戸籍法制定
ちょっと抜粋
明治4年(1871)4月、戸籍法が制定され、それまで各府県ごとに行われていた戸籍作成に関する規則を全国的に統一されました。戸籍法は、翌年に全国的戸籍を作成することを命じましたが、それによって作成された戸籍を「壬申戸籍」と言います。

明治4年の戸籍法を収録した文書の写真はこちらから。
***********
明治5年(1872)2月1日に戸籍法が施行され、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。この年の干支が壬申だったことから壬申戸籍と呼ぶ。
封建社会を打破し、中央集権を目指す明治新政府において「家」間の主従関係・支配関係の解体は急務だった。新政府は戸籍を復活させ、家単位ではなく戸単位の国民把握体制を確立した。「家」は国家体制とは関係ない私的共同体とされ、新政府は家を通さずに個人を支配できるようになった。しかし個人単位の国民登録制度ではないため、婚外子・非嫡出子問題などの戸に拘束された社会問題も現れた。
***********
してみると、徳川十三代将軍家定と同い年の彼は、戸籍法が施行された年には48歳だったんだね。
後日、ショパンと同い年、長崎県壱岐市の文化7年(1810年)生まれ200歳男性の戸籍が残っているってなことが発表されて、影が薄くなっちゃったけどさ。
2010年8月28日 読売新聞
明治5年の時点では62歳、ありうる話し。
それにしてもまぁ、こう暑くちゃぁ、チョイと頑張りすぎただけでシヲマネキ、なんて書いたのも束の間。
ホントなら涼しくなって過ごしやすくなるはずの夜中に熱中症で死亡だなんて、かつての日本では考えられなかった話しが続くねぇ。
</object>
なんでも、死亡時の直腸内の温度は39度だったとか、息子と外出し、帰宅直後に突然、昏睡(こんすい)状態に陥ったという80歳代の女性の直腸温度を測ると42度もあったとか、「今年の夏はまさに死体がアツイ!」ってな、イヤ、失笑してる場合じゃないってばさ。
扇風機回してても、熱風を攪拌するばかり。
返って体温が上がってしまうんだから恐ろしい。
かくいう僕も、先々週あたり、軽い熱中症に。
なんなのよ、この暑さは?って思ってググってみた。
気象庁の統計によると、各地で猛暑が続いた8月は、全国にある154の観測点のうち半分の77か所で平均気温が観測開始以降、最も高くなったとかで、30年に一度の「異常気象」と認めたってな話し。
なるほど~暑いわけだわさ。
ん?
でも、この「30年に一度の異常気象」って、チョイと前にも小耳に挟んだ記憶が。
んで、さらにググると、あった。
大雪の原因、北極発の寒波「30年に一度の異常気象」
2010年3月18日

この冬、米国東部や欧州、中国、韓国など、北半球のほぼ全域が強い寒気に包まれた。たびたび大雪に見舞われた米・ワシントンでは2月に積雪量が約141センチとなり、過去最高だった1898~99年の約138センチを上回った。温暖な気候で知られるフロリダ州オーランドでは1月に零下4.4度を記録。欧州では異常低温による凍死者が続出し、韓国・ソウルでは1月に1937年の観測開始以来、最高となる約26センチの積雪を記録した。
***********
ってことは、なにかえ?
今年は暑さ寒さ共に30年に1度あるかないかの記録更新を成し遂げたってか?
そりゃぁ、死人も出るわなぁ......
冷汗冷汗冷汗冷汗冷汗冷汗
かと思えば、7月29日の「全国で長寿2番目に認定されていた東京都足立区の男性(111)が、実は約30年前に死亡していたことが29日、分かった。祖父は『ミイラになりたい』『即身成仏したい』と言って30年前に自室に閉じこもったままだ」なんて記事を発端に、死臭ならぬ何やらきな臭い話しも出てくる出てくる。
もう皆さんご存じですが、「無職の長男(64)が老齢福祉年金120万円を不正受給していた」なんて話しから、
「あるとき100歳以上の女性宅を訪問したら、ベッドに寝ていた本人の外見が急に若返っていた。よく見たら、彼女の娘である80代女性で『なぜお母さんのベッドに寝ているのか』と聞くと『私が母親だ。娘は外出している』と言い張る。どう見ても親に成りすましていた」(大阪の元民生委員)
なんてのまで、よりどりみどり、加藤みどり。
もう後は呆れるばかり。
「なんと言うことでしょう」by みどり
とはいえ、こんな意見も。
「親の死亡隠しなどの背後に、「実家」に頼らざるをえない若年層の圧倒的な貧困がある。そして頼れない人たちは容易にホームレスにならざるをえない現実。親世代の食いつぶしで先延ばししている問題が、今の不安定雇用が続けば一気に噴出するだろう。」

これがまぁ、自然番組の一コマだったら、こんなナレーションが入ったかも知れない。
「親樹は枯れて倒れた後も、その栄養分で子孫を養っていくのです。」
なんてね。
和んでる場合じゃないか。
死んでもなお、すねをかじられる親の気分はどんなんかしらん?
長引く親の介護で職も失い再就職の道も絶たれ、のたれ死にしていく運命の我が子の命を、死してもなおその体からしたたり落ちる老齢年金の甘露で支えてきた....
もちろん、心情的にわからないでもない話だってある。
************
所在不明高齢者 “長寿国家”の実像
2010年08月06日 産経新聞
100歳以上の所在不明は和歌山市や奈良市など6道府県で新たに28人判明し、産経新聞の集計では5日夜の段階で少なくとも71人になった。それぞれの事例を検証すると、「徘徊(はいかい)したまま行方不明」「独居生活のまま連絡を絶つ」などのパターンが目立つ。家族がお年寄りを支えられないという長寿国家の実像が浮かび上がってくる。
奈良市は5日、100歳の女性1人が約30年前から行方が分からなくなっていると発表した。この女性の養女は、市の調査に「母は認知症による徘徊癖があり30年前に家を出たきり、行方がわからない」と説明しているという。岡山県でも「7月下旬に1人でふらりと家を出たきり、帰ってこない」(家族)という男性の行方が分かっていない。
ほかにも「放浪」「徘徊」したまま行方不明といった事例は多い。認知症による徘徊は、深刻な社会問題だ。
独居老人がそのまま生死不明となるパターンも散見されている。
************
行方不明になった親の死をあっさりと認めるのは辛いとか、縁を切った親のことなど思い出すのもしゃくに障るとか、悲喜こもごもな感じ。
んで、騒ぎが広がるにつれ、だんだん国のボロが出てくる。
************
行方不明老人問題で明らかになった「崩れゆく"長寿国"ニッポン」の現実
http://news.livedoor.com/article/detail/4935647/
2010年08月09日 日刊サイゾー
「悪質な不正受給などもあるので、いくらかは仕方ない部分もありますが、高齢者に対しては各地で長寿の表彰があったり、日ごろから所在を確認できる流れはできています。東京でも100歳以上は3,500人程度で、これは自治体で手分けすれば確認できる数字。普段から手抜き仕事をしていたツケがまわってきただけです」
ってな、民営の老人介護関係者からの反論の声も出ている。
中略
「厚労省は、年金受給者と人口の数すら合っていないのを把握しているんです。これを全て調べたら莫大な規模の相違が出てしまい、職務怠慢を追及され責任問題にも発展するので小さいまま終わらせたいんでしょう」と同関係者。
************
前後してこんな話しも。
************
[年金番号]100歳以上2倍超に 重複・死亡未整理?
http://news.livedoor.com/article/detail/4930577/
2010年08月06日 毎日新聞
1人一つずつ割り当てられている基礎年金番号が、成人人口より123万件も多く、新たな未解明年金記録問題となっているが、100歳以上では番号数が人口の2倍以上となっている。
中略
79歳以上は全年齢で番号の方が多く、人口推計(09年10月)の893万人より81万件多い。100歳以上では人口推計(同)の4万8000人より5万5000件多く、番号が2倍以上になる。
************
ん~、まさに非実在老人問題噴出ってな様相ですなぁ。
ここでちょっと息抜きに、こんなのをやってみてはどうだろうか?
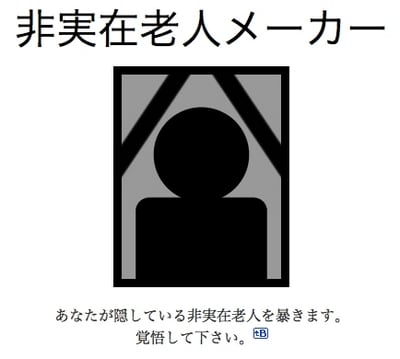
非実在老人メーカー←クリック!
あなたが隠している非実在老人を暴きます。
覚悟して下さい。
さっそく試してみたッス。
************
くまえもんさんは
阿部定
(1905年生・戸籍上105歳)
と同い年の老人を犬小屋に隠していました。
警察の調べに対し
「鬼ヶ島に鬼退治に出て行った」
と釈明しています。
************
だって!チョ~あがる!!

阿部 定(あべ さだ、1905年5月28日 - ?)は、日本の芸妓。阿部定事件の犯人として知られる。
さて、怠慢の記録更新を追っていくとイヤになっちゃうので、もちっとおめでたい方向から話しを眺めてみたいと思う。
えぇ、死んでもなお年齢を重ね、記録を更新していく条件ってのをね。
バーチャル長寿国日本万歳(お手上げ)ってなね。
まずは、愛知県高浜市。
所在不明で戸籍上は生存している120歳以上が98人いた。最高齢者の生まれた年は1862(文久2)年148歳。
大阪市の最高齢152歳 戸籍上120歳以上5125人
2010年8月25日
最高齢は江戸時代の末期、ペリーの黒船来航から4年後の1857(安政4)年生まれで、天王寺区が本籍の152歳の男性だった。
大阪、すごい!
とか思ったらまだ甘かったね。
************
大阪市高齢者不明あいりん地区に集中 給付金目的に住民登録か
8月14日
100歳以上の高齢者63人の所在不明が判明した大阪市で、不明者が最も多かった西成区では、大半が日雇い労働者の街・あいりん地区の半径数百メートル以内のエリアに集中していることが13日、市への取材で分かった。
中略
日雇い労働者は仕事が見つからず、そのままホームレスになるケースもある。市が19年度、ホームレス約500人を調査したところ、約4割があいりん地区での求職経験があった。こうした労働者が身元不明のまま死亡した場合、「行旅死亡人」として扱われ、都道府県や政令市が火葬。一方で住民登録は生き続けることになる。
************
何だ、自動的に非実在高齢者が増える仕組みになってる訳ね。
今回のようなケースからの発覚がなければ、「産めよ殖やせよ地に満ちよ」どころか、その内に生きてる人間より非実在性老人の人口の方が上回っちゃったかも知れないのにねぇ....ちょっと残念な感じ。
かくて長寿国日本は、ゾンビの島と化すのであった。
なんてね、汗
んじゃ、気を取りなおして、これまでのところで非実在性老人の最高齢は何歳?
【京都府で559歳女性所在不明】京都市で、生存していれば日本最高齢となる559歳の女性が行方不明。女性は1451年(宝徳3年)生まれ、16歳の時に発生した応仁の乱の混乱以来行方が分からなくなっていると発表した。また、同市に住民登録はなく、生存は確認できないという。

しかしてその正体は八百比丘尼、まだまだあと200年は余裕で生き続けるさぁ~、とかは無しにしてね。
汗
【和歌山県で1236歳男性未登録】和歌山県の戸籍調査で、和歌山県伊都郡高野町在住の佐伯眞魚(さえきのまお)さんが未登録であることが判明。関係者によると佐伯さんは宝亀5年(774年)生まれで今年1236歳。当時の戸籍の原簿(庚午年籍)が紛失したことによるという。
ちょっと待て。
んなこと言ったら、山下町洞人3万2,000歳、狩りに出かけたきり行方不明になんてのもOKになっちゃう?
いや、ご安心アレ。
初めに書いたように、日本で本格的な戸籍制度が開始されたのは明治5年(1872)2月1日で、その時点で生存していたことになっていた者たちだけが今回の一連の不手際の恩恵に浴することが出来るのだ。
....まてよ?明治5年の時点でも、不手際はあったのかもね。
だって、江戸時代からの宗門改帳や分限帳からの転載が、書式も不統一だった壬申戸籍へと滞りなく進められたとは考えにくいし。
実際こんな事が知られている訳だし。
***********
苗字のルーツは日本の歴史
明治5年(1871)の戸籍法は不備が多く、たくさんの機能(印鑑証明・地券など)をもたせたため複雑になった。必要要件さえ記載されていれば様式も特に設けられなかったので地方によって書式に差が生まれた。6年に1度改編する規定も大区小区制施行と併せて実施された1回程度だった。明治11年(1878)以前は基本的に戸籍を戸長が管理し、郡村制施行後は役場が管理した。
明治19年(1886)に壬申式から統一書式を用いた戸籍へ変更され、11月より徐々に移行された。本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更された。除籍制度も設けられた。
***********
ま、かなりの転記漏れやら記載の間違いもあったと思った方が自然よね?
これは、現代科学の粋を集めた1994年6月(平成6年6月)の戸籍事務のコンピュータ化に伴う転記のときにも実際起こってたわけで、科学技術の進歩とそれを運用する側が引き起こすエラーの発生頻度の間には、何の関連性もないことを証明する良い材料だとも言えそうね。
えぇ、どんなに素晴らしい道具を発明しても、使うヤツがバカで誠実さのカケラも持ってないのなら意味がないってな、そんな言い古された話しに。
A(^_^;
とはいえ、せっかく200歳まで齢を重ねてきた人や、それこそ全国に五万と居る120歳以上まで生き延びて?来た人たちに、もっと記録を更新するチャンスを与えてあげてみたいなぁ、なんて妄想してみたりもするのだ。
ギネスにも載るよねぇ?
日本の快進撃は。www
生存者よりも幽霊人口の多い国、なんてさ。
A(^_^;
この生き抜きにくい日本で、これから熱中症で死んでも生きてることにされて親族を養い続けるかも知れない人や、管理システムの狭間で記録更新してきた人やこれからも記録を更新し続けるかも知れない人々に、死人のベテランたち?に、せめてものエールを送りたい。
そう、死してなお、いや、死して後にこそ悠々自適の人生を。汗
じゃないか、もう死んじゃってるんだから「幽々自適な毎日を」なんてね。









