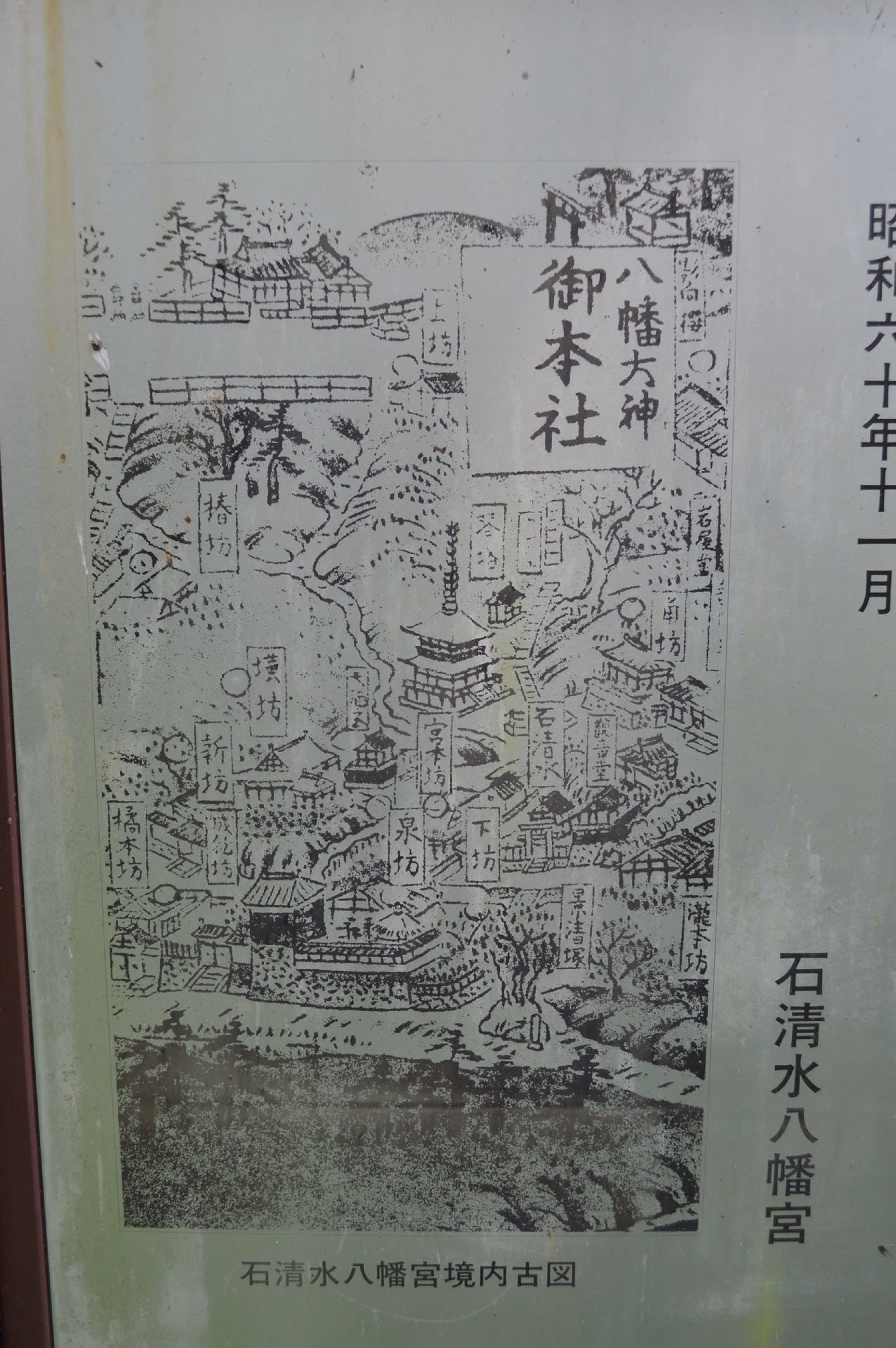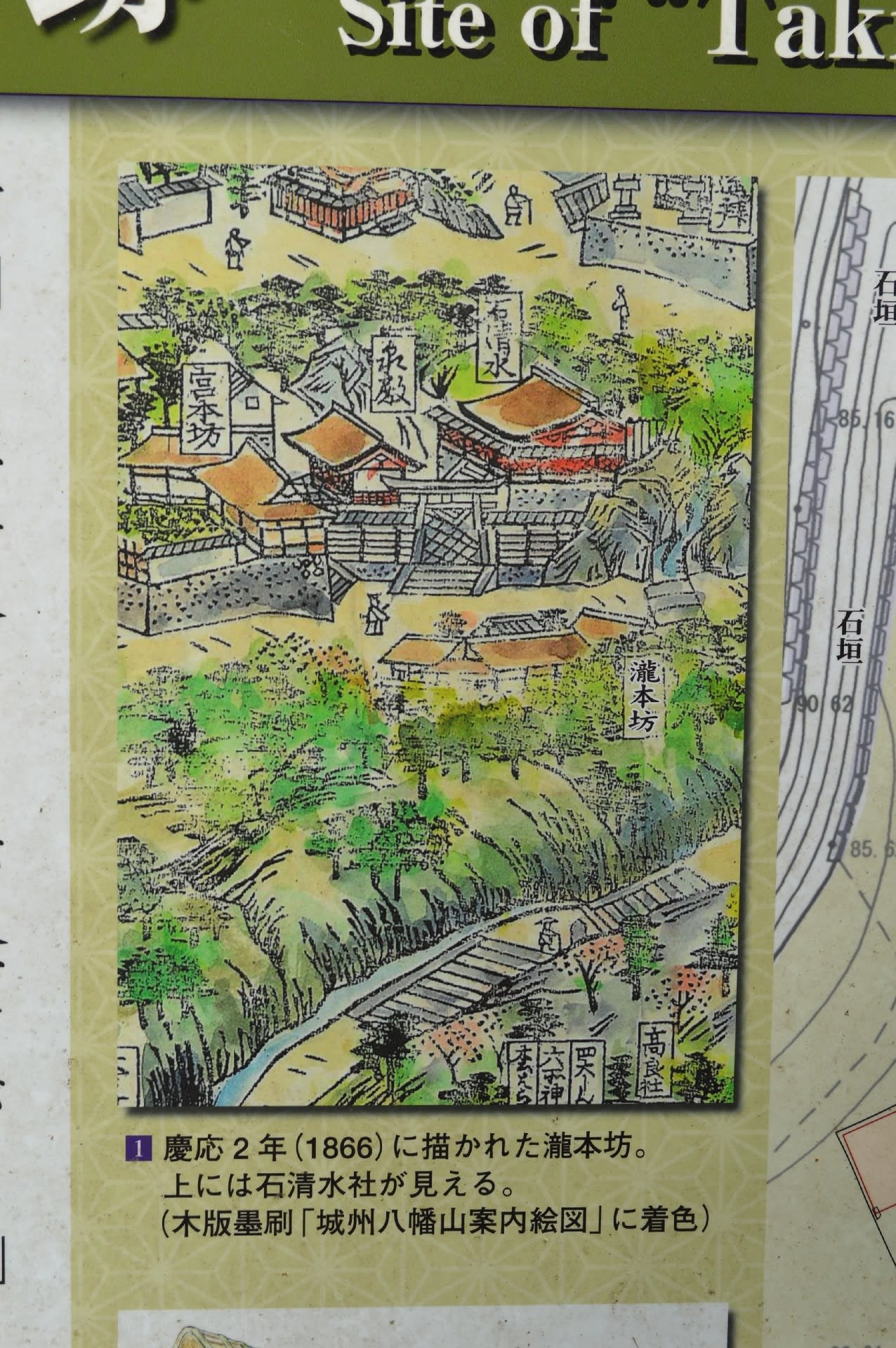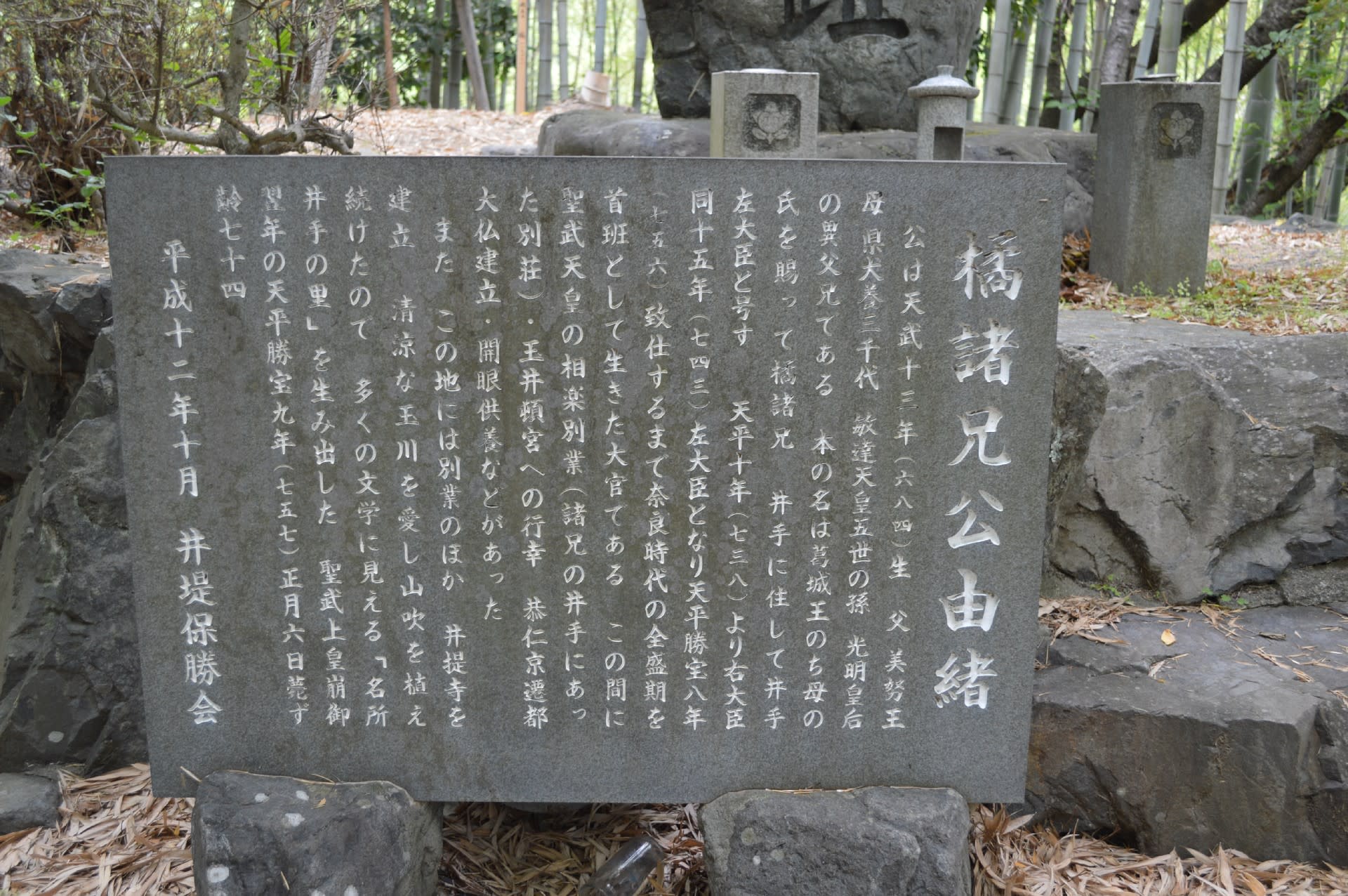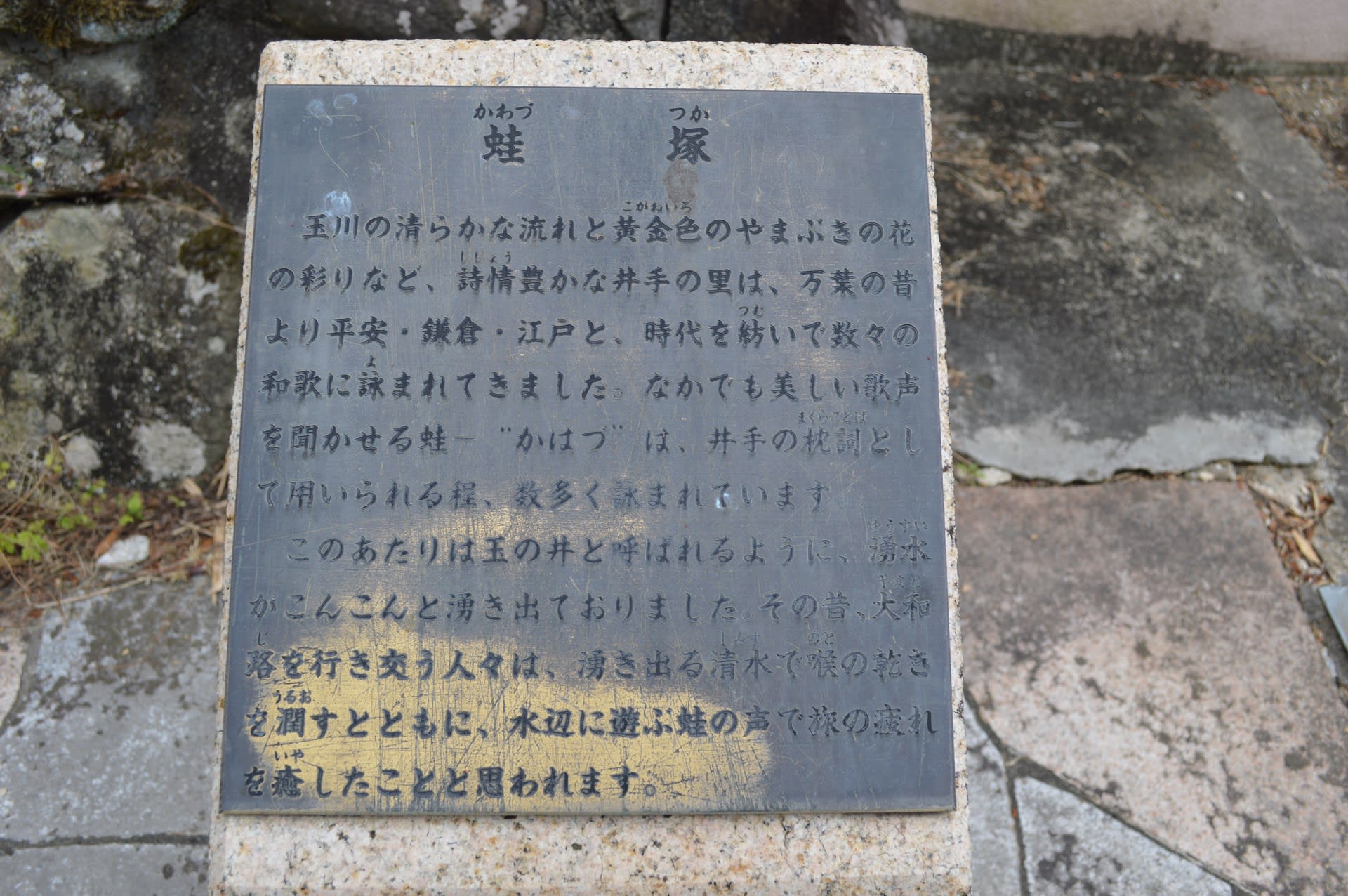太子坂・萩坊跡
二の鳥居の北に至る「裏参道」は、江戸時代まで「太子坂」といい、古くは約700年前、鎌倉時代の上皇が参詣の帰りにこの道を通った記録があります。
坂の途中を造成して造られた坊のひとつ、「萩坊」は、安土桃山時代の高名な画家・狩野山楽が、豊臣秀吉に追われ隠れ住んだことでも知られ、客殿は山楽が描いた金張付極彩色の図で飾られていました。山楽の子・狩野山雪の襖絵は八幡宮の北側にある神応寺に所蔵されています。
坂を下ると、聖徳太子3歳の像を祀った「太子堂」があり、室町時代には他に丈六(一丈六尺)という像高3m程の巨大な阿弥陀仏を安置した行願院もありました。
明治時代の初めの神仏分離令ですべて破却されましたが、難を逃れた太子堂は、現在も滋賀県お大津市の国分聖徳太子会で大切に守られています。



萩坊跡 昭和3年建立 京都三宅安兵衛依遺志

関連記事 ⇒ 49 八幡 地区 記事検索一覧 その2
史跡 前回の記事 ⇒ 史跡八幡070 石清水八幡宮 影清塚
下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます