
キマダラヒロバカゲロウ?
灯火に飛来しました。
この後すぐに飛ばれてしまったので、別角度からの画像がありません。
同定間違いの可能性大だと思います。
過去に載せたカスリヒロバカゲロウと比べると、首(前胸)が短くて、眼が茶色。
(カスリヒロバカゲロウは首が長くて、眼は深い緑色。)
前胸背の中央に縦条、横に黒点、さらに横にいびつな「X」字状の黒筋があるようです。
(カスリヒロバカゲロウでは頭部~前胸背の中央を貫く黒条、前胸背の両側に黒条。)
翅の後縁に沿ってまだら模様、翅頂にも細かい斑模様があるようです。
なお、このキマダラヒロバカゲロウについて、「昆虫エクスプローラ」さんは、別名を「ヒロバカゲロウ」としていますが、「身近な水生昆虫を調べてみよう」さんは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」を明らかに別種として扱っています。
過去に何か経緯があったのでしょうか?
ここでは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」は別種として扱います。
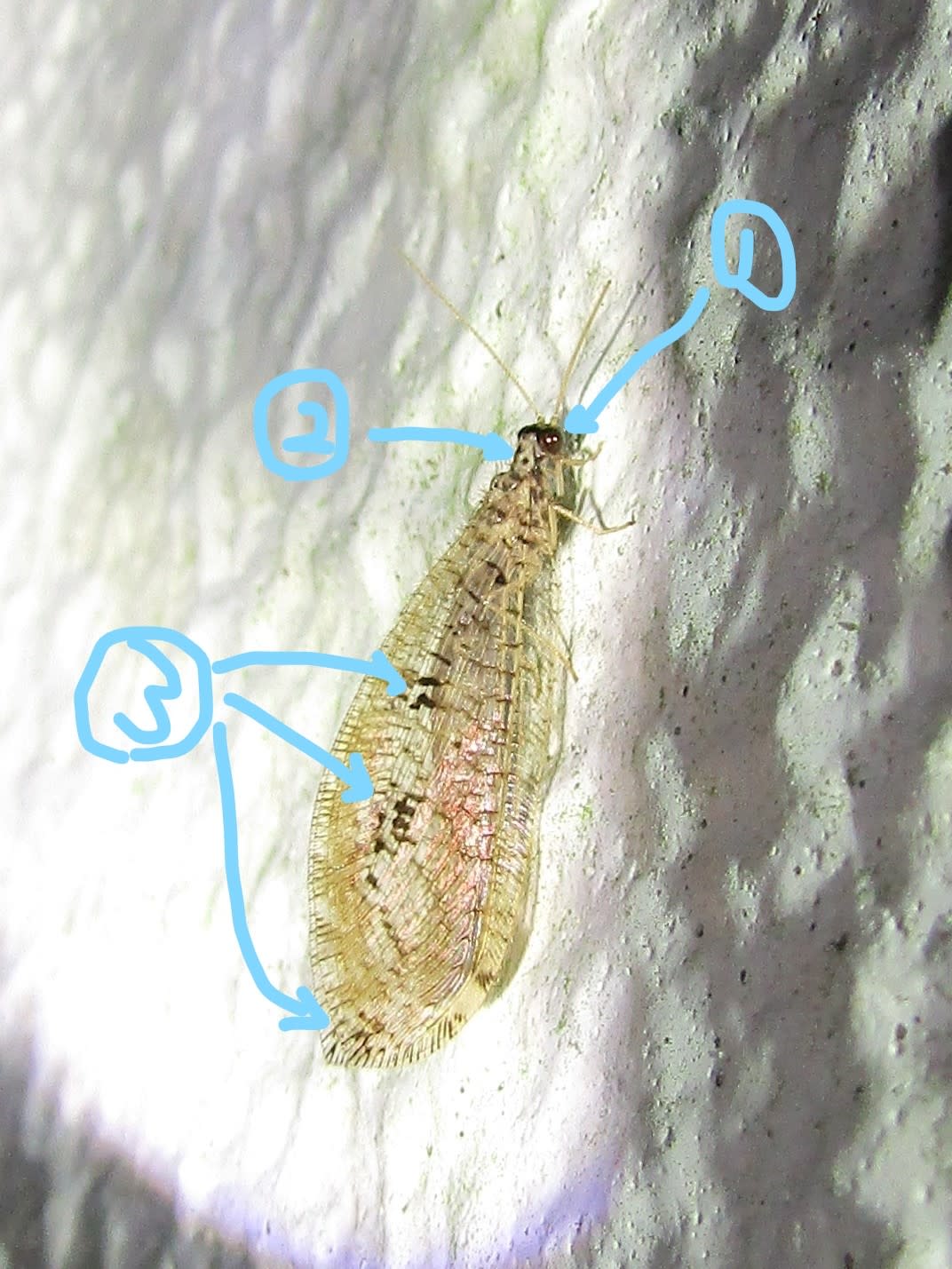
①複眼は茶色
②前胸は短め
③翅脈は褐色で、黒色の斑模様がある

分類:
アミメカゲロウ目ヒロバカゲロウ科
体長:
14~18mm
翅を広げた長さ:
30~35mm
分布:
北海道?、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:
6~9月
越冬形態?
エサ:
成虫・・・甘露?
幼虫・・・トビムシや小昆虫?
その他:
翅脈は前・後翅とも褐色。
前翅に淡褐色の線状紋や灰褐色の雲状紋がある。
湿地の周りで見られる。
灯火に飛来する。
本州から得られる9種のヒロバカゲロウ科のうち、成虫と幼虫が一致しているのは、本種のみ。
幼虫は薄暗い池沼に半ば埋没した倒木から見い出される。
ヒロバカゲロウ科の幼虫は半水生とのことなので、本種も同様と思われる。
ヒロバカゲロウ科の幼虫は、
①直線的な吸収顎(大顎と小顎が接着して管を形成したもの)を持ち、エサの体液等を吸う
②触角は吸収顎より短い
③腹端に肉質の突起が二本あり、伸び縮みして歩行に使う
という特徴があるそうなので、本種も同様と思われる。
垂直分布について、低山地~山地とするサイトもあるが、平地では好適な環境が失われやすく、そのため、個体数が少ない可能性がある。
参考:
学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)
レッドデータブックまつやま2012
ZATTAな昆虫図鑑
あおもり昆虫記
身近な川の水生昆虫を調べてみよう!
日本産淡水魚の世界へようこそ!
昆虫エクスプローラ
てんとう虫の歳時記
旧「いもむしうんちは雨の音」置き場
春夏秋冬の昆虫写真館
身近な川の水生昆虫を調べてみよう
水生アミメカゲロウ図鑑
灯火に飛来しました。
この後すぐに飛ばれてしまったので、別角度からの画像がありません。
同定間違いの可能性大だと思います。
過去に載せたカスリヒロバカゲロウと比べると、首(前胸)が短くて、眼が茶色。
(カスリヒロバカゲロウは首が長くて、眼は深い緑色。)
前胸背の中央に縦条、横に黒点、さらに横にいびつな「X」字状の黒筋があるようです。
(カスリヒロバカゲロウでは頭部~前胸背の中央を貫く黒条、前胸背の両側に黒条。)
翅の後縁に沿ってまだら模様、翅頂にも細かい斑模様があるようです。
なお、このキマダラヒロバカゲロウについて、「昆虫エクスプローラ」さんは、別名を「ヒロバカゲロウ」としていますが、「身近な水生昆虫を調べてみよう」さんは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」を明らかに別種として扱っています。
過去に何か経緯があったのでしょうか?
ここでは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」は別種として扱います。
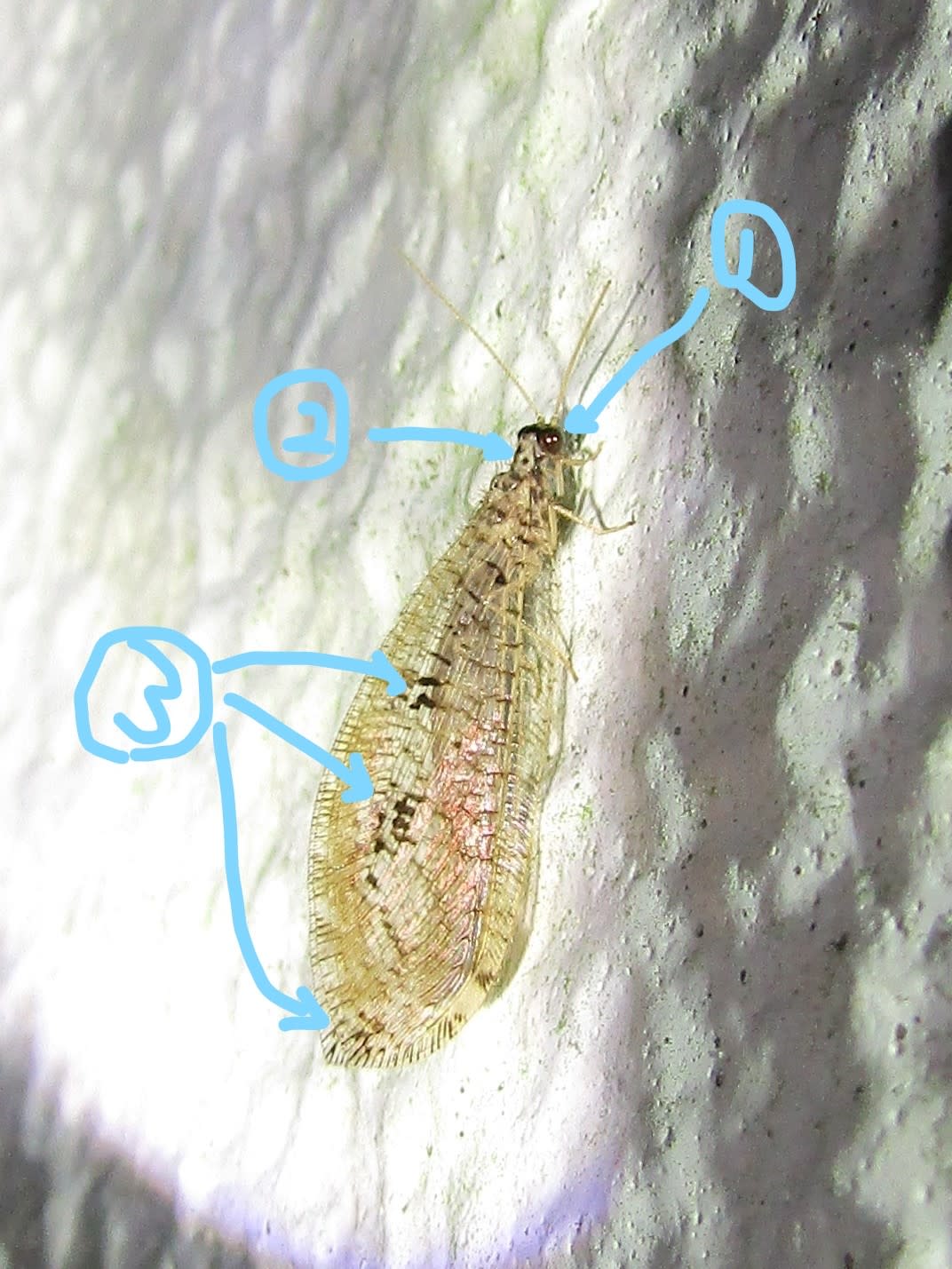
①複眼は茶色
②前胸は短め
③翅脈は褐色で、黒色の斑模様がある

分類:
アミメカゲロウ目ヒロバカゲロウ科
体長:
14~18mm
翅を広げた長さ:
30~35mm
分布:
北海道?、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:
6~9月
越冬形態?
エサ:
成虫・・・甘露?
幼虫・・・トビムシや小昆虫?
その他:
翅脈は前・後翅とも褐色。
前翅に淡褐色の線状紋や灰褐色の雲状紋がある。
湿地の周りで見られる。
灯火に飛来する。
本州から得られる9種のヒロバカゲロウ科のうち、成虫と幼虫が一致しているのは、本種のみ。
幼虫は薄暗い池沼に半ば埋没した倒木から見い出される。
ヒロバカゲロウ科の幼虫は半水生とのことなので、本種も同様と思われる。
ヒロバカゲロウ科の幼虫は、
①直線的な吸収顎(大顎と小顎が接着して管を形成したもの)を持ち、エサの体液等を吸う
②触角は吸収顎より短い
③腹端に肉質の突起が二本あり、伸び縮みして歩行に使う
という特徴があるそうなので、本種も同様と思われる。
垂直分布について、低山地~山地とするサイトもあるが、平地では好適な環境が失われやすく、そのため、個体数が少ない可能性がある。
参考:
学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)
レッドデータブックまつやま2012
ZATTAな昆虫図鑑
あおもり昆虫記
身近な川の水生昆虫を調べてみよう!
日本産淡水魚の世界へようこそ!
昆虫エクスプローラ
てんとう虫の歳時記
旧「いもむしうんちは雨の音」置き場
春夏秋冬の昆虫写真館
身近な川の水生昆虫を調べてみよう
水生アミメカゲロウ図鑑












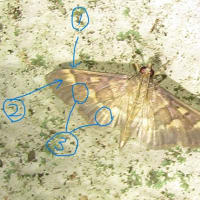

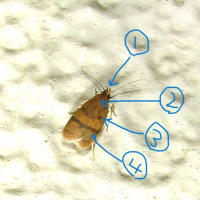

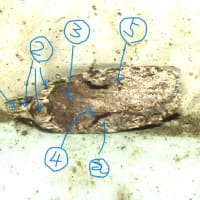











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます