何故「選挙権」と「政治活動」を分けるのか。発想のベースは、「政治活動は選挙に限定したい」政府側の思考ではないだろうか。デモや署名活動など、草の根の民主主義を排除しようとする。
保育士の離職が多いのは、業務量に比して低賃金だからだ。待機児童解消のために、保育士の人員配置基準を見直して、保育士1人あたりが負担する子どもの数を増やしたら、実質的に給料減額じゃないか。ますます離職が進むよね。
業務量増大の要因は「親」なんだろうねえ。保育所でも幼稚園でもケガをするとか骨折するとか以前は普通だったし、親も祖父母も「子どもがケガするのは当然」の感覚だったと思う。少子化で一人一人に金も手間もかかっているせいか、そのあたり過敏になっている気がする。
(承前)このあたり、親も自縄自縛に陥っているのかも。「失敗してはいけない」から、と様々な情報に右往左往している。「そこまで親が考えても、あんまり変わらない」と思うんだけどねえ。3代目の「いかけや」のマクラを聞くと、そんなことを感じる。
「萎縮させる意図はない」って、意図があったら論外であって、意図がないからOK、ではない。意図の有無に関わらず萎縮させる恐れがあれば、メリデメ比較してそれでも校則に入れるべきか、と考えるのが本来の思考でしょう。
中日スポーツ
中日ドラゴンズは15日、賭博等の調査を行いましたが、球団代表は「ここ数年、円陣を組むような団結力はなかった」と自虐に似た否定を行い、担当記者たちから失笑を誘った。
#中日ドラゴンズ
昨年10月には100人超、今年の2月には29人、さらに3月には37人が死亡するテロが相次いでいるのに、なぜ、外務省はアンカラに危険レベルを設定しない?イスタンブールは1だが、アンカラは0。スポットの注意喚起ですむレベルではないはず
www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfecti…
(続き)ことが大きなことだと実感した』と話す」ブラックバイトや奨学金の問題など、高校生が自分で声を上げないと事態が改善されない社会になっている。デモ参加届け出制を義務づける教育委員会は、ブラックバイト抗議デモなどで高校生が自分で声を上げる機会にハードルを課して実質的に邪魔をする。
デモに参加したことがある人なら知っている通り、途中参加もOKなので、事前に参加する意図はなくても、たまたまその場に居合わせてデモの主旨に賛同できると思ったから合流する、という身軽な形の参加も珍しくない。民主主義が日本よりも成熟した西欧諸国では、そんな形でデモの規模が拡大していく。
ショーン・Kなる人の経歴詐称が騒々しいが、高市早苗大臣の経歴詐称の方が問題だろう。高市氏の経歴に「アメリカ合衆国議会立法調査官」とあるが同志社大学浅野健一 氏によると実際はパトリシア・シュローダー下院議員の個人事務所の二十数人いるスタッフの無給アルバイトの一人だった。
民主主義は大嫌い、立憲主義なんかクソ食らえ。こんな安倍政権を支持することは、自分の首を絞めること。19日、日比谷へ??
【拡散希望】『戦争法廃止・安倍政権の暴走許さない3.19総がかり日比谷大集会』13時半~(集会後、銀座パレード) sogakari.com/?p=1626
柳家三三が平成27年度芸術選奨新人賞(大衆芸能部門)を受賞し、贈呈式が3月15日、都市センターホテルで行われました。詳細は東京かわら版5月号にて。ほかにオール阪神・巨人、松本隆、ケラリーノ・サンドロヴィッチ、村上隆、皆川明らが受賞。 pic.twitter.com/rV9mKLTLA9
「『保育園落ちた』の署名を渡したママはブランド品の抱っこ紐を使ってるからプロ市民」に対する反応 - Togetterまとめ togetter.com/li/949308 本当かどうか知らんけど、戦争中「赤い服を来てるからあいつはアカのスパイだ」という密告があった話を思い出した
そもそも、〈お上のやることが気に入らなきゃ日本に住むな〉てのは、決定的に思考法が間違ってる。お上のやることが気に入らなければお上を変えましょ、てのが民主主義。あ、お上ではない云々のリプは遠慮しますね。レトリックとしてお上といってるだけですから。
米ノーベル経済学者が「消費税引き上げる時期ではない」と安倍首相に直言(産経)
これで消費税増税「凍結」は確定だろう。与党は選挙に向けて「凍結は景気回復に向けた安倍首相の大英断!」と喧伝する。
騙されてはいけない。野党は安倍首相の「8%増税失策」の責任を追及し、辞任に追い込む好機だ
「日本死ね」はさんざん非難し、「朝鮮人死ね」はOKな連中は、日本人の面汚し。恥さらし。
反中と言いつつ、日本を北朝鮮や中国のようにしたい連中が多くて困る。金様か習様か安倍様かの違いは、人治である点で見れば大同小異。
新華社が「中国最後の指導者習近平」と報道 ワールド 最新記事 ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト newsweekjapan.jp/stories/world/…










 前進亭かくまる @kkmaru
前進亭かくまる @kkmaru らめーん @shouwayoroyoro
らめーん @shouwayoroyoro こぺっちょ@スレイヤー練習中 @copepord
こぺっちょ@スレイヤー練習中 @copepord masanorinaito @masanorinaito
masanorinaito @masanorinaito 山崎 雅弘 @mas__yamazaki
山崎 雅弘 @mas__yamazaki ひるあんどん? @hiruandon_japan
ひるあんどん? @hiruandon_japan m TAKANO @mt3678mt
m TAKANO @mt3678mt 東京かわら版 @tokyo_kawaraban
東京かわら版 @tokyo_kawaraban
 アオイ模型:パンツァーガールズ!09 @aoi_mokei
アオイ模型:パンツァーガールズ!09 @aoi_mokei 松井計 @matsuikei
松井計 @matsuikei 盛田隆二?Morita Ryuji @product1954
盛田隆二?Morita Ryuji @product1954 カールマルクス 名言集 @karlmarxbot001
カールマルクス 名言集 @karlmarxbot001 二の舞@非社畜SE:(´゜ω゜`): @nino_mine
二の舞@非社畜SE:(´゜ω゜`): @nino_mine いとうじん 考える人プロジェクト @ThinkSmart2011
いとうじん 考える人プロジェクト @ThinkSmart2011 デモクラシーな言葉 @whatsdemocracy
デモクラシーな言葉 @whatsdemocracy 人見 基埜 @hitomimotoya196
人見 基埜 @hitomimotoya196 耳湯 @mimiyu2533
耳湯 @mimiyu2533 gurico03 @gurico234
gurico03 @gurico234
 牟田口廉也(fake)(空腹実現党総裁) @renya_mutaguchi
牟田口廉也(fake)(空腹実現党総裁) @renya_mutaguchi ひろみ @hiromi19610226
ひろみ @hiromi19610226 919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919
919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919
 百年前新聞 @100nen_
百年前新聞 @100nen_ 嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara 死ぬかと思った @_ae86ae_
死ぬかと思った @_ae86ae_ 平和への道@彡トシピコ彡 @toshipiko1
平和への道@彡トシピコ彡 @toshipiko1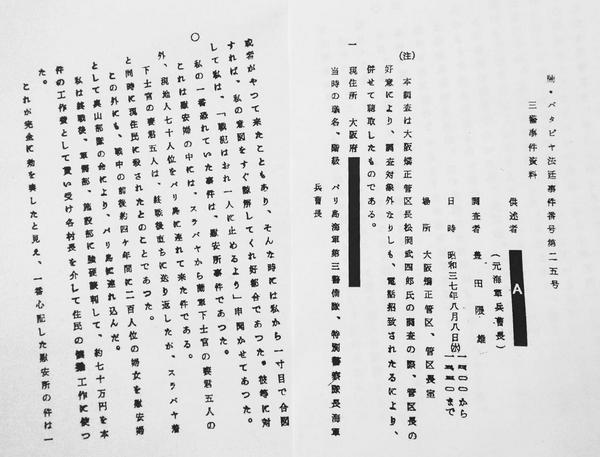
 社会人としての自覚?るる @lulutter_ruru
社会人としての自覚?るる @lulutter_ruru ぱんだ @oka_panda
ぱんだ @oka_panda Simon_Sin @Simon_Sin
Simon_Sin @Simon_Sin 渡辺輝人 @nabeteru1Q78
渡辺輝人 @nabeteru1Q78 Shimanami Ryo @shimanamiryo
Shimanami Ryo @shimanamiryo きしだ? @kis
きしだ? @kis 増田聡 @smasuda
増田聡 @smasuda 東京新聞ほっとWeb オフィシャル @tokyohotweb
東京新聞ほっとWeb オフィシャル @tokyohotweb