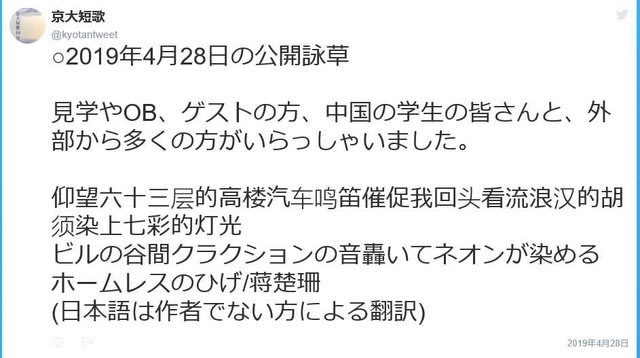25日の「新緑」日本取材チーム報告会で、リーダーの付玉梅(ジャーナリズム専攻4年)は「京町家の再生」をテーマにPPTを用いながら講演をした。京都の町づくりにおいて最も重要な課題の一つであり、歴史と現代の融合を取り込んだ都市振興を目指す中国にとっても関心が高い。


現地の取材でお世話になったのはNPO「京町家再生研究会」のもとに生まれた職人集団「京町家作事組」。作事組代表理事で設計士の木下龍一さんと、施工担当理事で大下工務店代表の大下尚平さんが、町家や改修現場の視察など親切に対応してくださった。



「京都にとって京町家はbodyのようなもの」
木下さんのこのひとことが、学生たちにとって最も印象に残ったようだ。付玉梅も報告会で特にこの言葉を取り上げ、
「建物そのものには命がない。人がいて初めて呼吸をし、新たな血液を送り込むことで、生まれ変わっていく。京町家の再生は建築文化にとどまらず、庶民の生活と物語を後世に伝えていくことなのだ」
と総括した。大下さんからは、できるだけ材料を残し「復元を第一」にする職人気質を学んだ。物事の核心をしっかり把握した取材成果で、多くの参加者から共感を得た。

また、琵琶や茶道、歌の会を開き、伝統文化継承の舞台として京町家を生かしている京扇子「大西常商店」四代目女将、大西里枝さんの試みも紹介された。ちょうど同店で茶道と薩摩琵琶のイベントに居合わせた際、出演者が漢服姿で現れたのを見て、日中文化の深い縁を感じたようだ。



付玉梅の書いた原稿は最新号の新華社『環球』第11期(5月29日出版)に掲載され、表紙にも見出しが紹介された。破格の扱いである。一大学生が国家レベルのメディアに原稿を発表するのは容易ではない。よく頑張ったとほめてあげたい。



同じ原稿は29日、新華社の微信公式アカウントでも配信され、翌日にはアクセスが50万を超えた。
(http://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/6165344?channel=weixin)
学生たちはまだ多くの文字や映像作品の制作に取り組んでいる。続々と日の目を見ることを期待している。
(続)


現地の取材でお世話になったのはNPO「京町家再生研究会」のもとに生まれた職人集団「京町家作事組」。作事組代表理事で設計士の木下龍一さんと、施工担当理事で大下工務店代表の大下尚平さんが、町家や改修現場の視察など親切に対応してくださった。



「京都にとって京町家はbodyのようなもの」
木下さんのこのひとことが、学生たちにとって最も印象に残ったようだ。付玉梅も報告会で特にこの言葉を取り上げ、
「建物そのものには命がない。人がいて初めて呼吸をし、新たな血液を送り込むことで、生まれ変わっていく。京町家の再生は建築文化にとどまらず、庶民の生活と物語を後世に伝えていくことなのだ」
と総括した。大下さんからは、できるだけ材料を残し「復元を第一」にする職人気質を学んだ。物事の核心をしっかり把握した取材成果で、多くの参加者から共感を得た。

また、琵琶や茶道、歌の会を開き、伝統文化継承の舞台として京町家を生かしている京扇子「大西常商店」四代目女将、大西里枝さんの試みも紹介された。ちょうど同店で茶道と薩摩琵琶のイベントに居合わせた際、出演者が漢服姿で現れたのを見て、日中文化の深い縁を感じたようだ。



付玉梅の書いた原稿は最新号の新華社『環球』第11期(5月29日出版)に掲載され、表紙にも見出しが紹介された。破格の扱いである。一大学生が国家レベルのメディアに原稿を発表するのは容易ではない。よく頑張ったとほめてあげたい。



同じ原稿は29日、新華社の微信公式アカウントでも配信され、翌日にはアクセスが50万を超えた。
(http://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/6165344?channel=weixin)
学生たちはまだ多くの文字や映像作品の制作に取り組んでいる。続々と日の目を見ることを期待している。
(続)