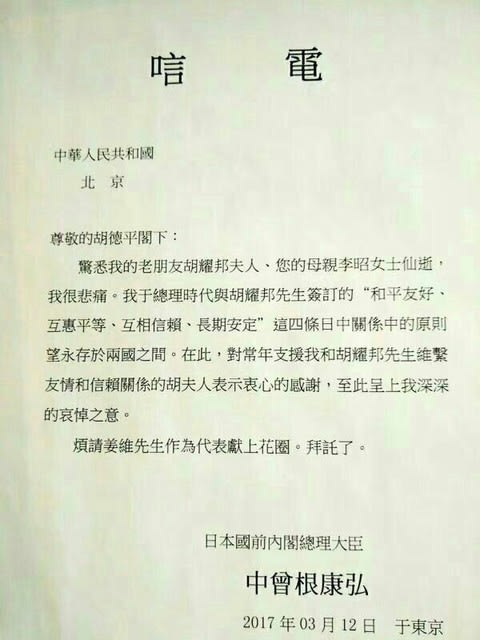しばしば公共マナーが問題となるのは、毎日の通勤に欠かせない地下鉄や電車でのことだ。日本でクレームの主因となるのは、降りる人を待たずに乗ろうとする、混雑しているのに奥に詰めない、ドア付近からテコでも動こうとしない・・・わき目も降らず席を取ろうとする年配者の行為も褒められたものではない。平気で携帯で話す、イヤフォンの音がもれている、遊びまわる子どもを注意しない親などは言語道断だ。

私が一番気になるのは、コミュニケーションの欠如だ。無言のまま人を押しのけようとするのには閉口する。どうしてひとこと、「失礼」と言えないのか。せっかく席を譲ろうとしたのに、黙ったままその場を去り、席を譲るべき人に声をかけない行為も不可解だ。声を掛け合わずに、すべて無言で済ましてしまう社会には違和感を覚えずにはいられない。最近、日本で聞いた話だが、地下鉄の中で携帯電話で話していた若い女性の頭を、年配の男性がいきなり持っていた雑誌でたたき、立ち去ったという。「迷惑だからやめなさい」と、なぜ注意しないのか。
以前、拙著『中国社会の見えない掟 潜規則とはなにか』(講談社現代新書)で次のように書いたことがある。
「一時帰国した際、都内の地下鉄で見かけた光景だ。駅に停車し、つえを突いた目の不自由な男性が乗り込んで来ると、ちょうどシルバーシートに座っていた若者二人がきまり悪そうに席を立った。席を譲ろうとしたのだと思って見ていると、つえを手にドアの戸袋に立つ男性に声もかけず、二人はその場から離れてしまった。『ひと声かけてあげなければ、席の空いていることさえわからないではないか』と不可解な思いがこみ上げてきた」
ルールと人情に関する日中の違いについて言及したものだ。中国ではおせっかいと思えるほど、弱い立場にある妊婦や老人を家族の一員のように気遣う反面、驚くほど公衆マナーには無頓着である。地下鉄で飲みかけの牛乳をひっかけられた、ごみを捨てたのを注意したらけんかになった、などの愚痴は日常茶飯事だ。中国人も「素質(民度)」が低いということは認めている。
もちろん最低限の公衆マナーは必要だが、私は、日本社会と中国社会に決定的なコミュニケーションの違いがあることのほうが大事だと感じている。
中国のバスや地下鉄では、もし自分が次の駅で降りようと思ったら、強くアピールしなくてはならない。隣の人に「降りるのかどうか」を確かめて位置を変え、できるだけドアに近づこうとする。聞かれる方も当たり前のように場所を入れ替える。到着する前に乗降口に立っていなければ、ドアが開いたとたん、ホームから人波が流れ込んで来るかもしれない。運転手がすぐにドアを閉めて出発してしまうかもしれない。日本のように停車してから降りようと動き出すのは、むしろ「なんで早くから準備しないのか」と煙たがられる。
発展途上にある地方では、バスの運転手が気まぐれでストップしないこともあるので、「次停まって!」と大声を上げなければならない場合もある。みながルールを守り、秩序だって行動する日本の社会に慣れきった者からすれば、非常に疲れる。「なんでこんなことまで言わなきゃならないの」と。だが、単一ではない複雑な社会で、異なる環境で育ち、様々な考え方を持った人たちが一緒に暮らす場所では、声に出して言わないと通じないことがある。「わかってくれるはずだ」という期待は役に立たないどころか、誤解のもとになる。「空気が読めない」という社会の不文律はまったく通用しない。
日本への取材ツアーに参加した中国人学生が、大学に戻ってから、九州でバスに乗った時の印象を話してくれた。目的地のバス停に近づいたので、乗降口に待機したが、ほかの乗客は停まってからようやく席を立って、譲り合いながら降りていった。この違いは何かと彼女は考えた。日本人は列を作り、降りてから乗る順序を守り、秩序が保たれていること。公共交通のダイヤも停車時間も正確で、あわてる必要がないこと。こうした相互の信頼があるからだ。彼女はそう答えを出した。
そういう理解もあるのかも知れないと思った。ただ、文化比較に正解はないので、そうした答えを求めようとしても無駄だ。いい悪いで割り切れるはずのない問いかけである。私が彼女に答えたのは、「むしろ、異なる視点を共有することにこそ意味があるのではないか」ということだ。

私が一番気になるのは、コミュニケーションの欠如だ。無言のまま人を押しのけようとするのには閉口する。どうしてひとこと、「失礼」と言えないのか。せっかく席を譲ろうとしたのに、黙ったままその場を去り、席を譲るべき人に声をかけない行為も不可解だ。声を掛け合わずに、すべて無言で済ましてしまう社会には違和感を覚えずにはいられない。最近、日本で聞いた話だが、地下鉄の中で携帯電話で話していた若い女性の頭を、年配の男性がいきなり持っていた雑誌でたたき、立ち去ったという。「迷惑だからやめなさい」と、なぜ注意しないのか。
以前、拙著『中国社会の見えない掟 潜規則とはなにか』(講談社現代新書)で次のように書いたことがある。
「一時帰国した際、都内の地下鉄で見かけた光景だ。駅に停車し、つえを突いた目の不自由な男性が乗り込んで来ると、ちょうどシルバーシートに座っていた若者二人がきまり悪そうに席を立った。席を譲ろうとしたのだと思って見ていると、つえを手にドアの戸袋に立つ男性に声もかけず、二人はその場から離れてしまった。『ひと声かけてあげなければ、席の空いていることさえわからないではないか』と不可解な思いがこみ上げてきた」
ルールと人情に関する日中の違いについて言及したものだ。中国ではおせっかいと思えるほど、弱い立場にある妊婦や老人を家族の一員のように気遣う反面、驚くほど公衆マナーには無頓着である。地下鉄で飲みかけの牛乳をひっかけられた、ごみを捨てたのを注意したらけんかになった、などの愚痴は日常茶飯事だ。中国人も「素質(民度)」が低いということは認めている。
もちろん最低限の公衆マナーは必要だが、私は、日本社会と中国社会に決定的なコミュニケーションの違いがあることのほうが大事だと感じている。
中国のバスや地下鉄では、もし自分が次の駅で降りようと思ったら、強くアピールしなくてはならない。隣の人に「降りるのかどうか」を確かめて位置を変え、できるだけドアに近づこうとする。聞かれる方も当たり前のように場所を入れ替える。到着する前に乗降口に立っていなければ、ドアが開いたとたん、ホームから人波が流れ込んで来るかもしれない。運転手がすぐにドアを閉めて出発してしまうかもしれない。日本のように停車してから降りようと動き出すのは、むしろ「なんで早くから準備しないのか」と煙たがられる。
発展途上にある地方では、バスの運転手が気まぐれでストップしないこともあるので、「次停まって!」と大声を上げなければならない場合もある。みながルールを守り、秩序だって行動する日本の社会に慣れきった者からすれば、非常に疲れる。「なんでこんなことまで言わなきゃならないの」と。だが、単一ではない複雑な社会で、異なる環境で育ち、様々な考え方を持った人たちが一緒に暮らす場所では、声に出して言わないと通じないことがある。「わかってくれるはずだ」という期待は役に立たないどころか、誤解のもとになる。「空気が読めない」という社会の不文律はまったく通用しない。
日本への取材ツアーに参加した中国人学生が、大学に戻ってから、九州でバスに乗った時の印象を話してくれた。目的地のバス停に近づいたので、乗降口に待機したが、ほかの乗客は停まってからようやく席を立って、譲り合いながら降りていった。この違いは何かと彼女は考えた。日本人は列を作り、降りてから乗る順序を守り、秩序が保たれていること。公共交通のダイヤも停車時間も正確で、あわてる必要がないこと。こうした相互の信頼があるからだ。彼女はそう答えを出した。
そういう理解もあるのかも知れないと思った。ただ、文化比較に正解はないので、そうした答えを求めようとしても無駄だ。いい悪いで割り切れるはずのない問いかけである。私が彼女に答えたのは、「むしろ、異なる視点を共有することにこそ意味があるのではないか」ということだ。