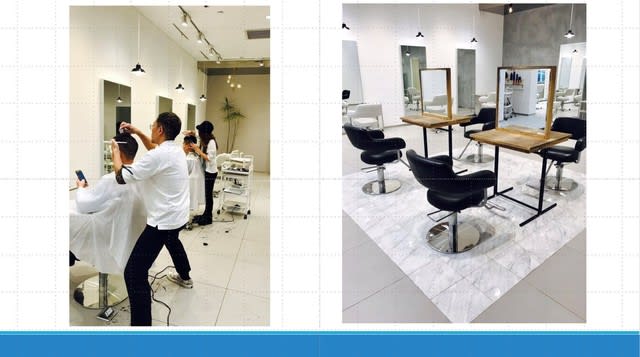昨年の日本取材ツアーで学生の制作したドキュメンタリー・フィルム「師村妙石的人生之旅」(Life of Shimura)が、大学生向けでは権威のある第19回北京大学生映画祭オリジナル映像作品コンクールのドキュメンタリー部門で入選した。全国から総数で4200作の応募があった大きなイベントである。




私はナレーションや翻訳としても参加したので、特に思いが強い。北京で環境ビジネスを手掛ける佐野史明君も、日本の若者の声でナレーションに協力してくれた。5月4日、主催者の北京師範大学で最終受賞作品の発表式典があるので、私は学生に同伴し出席することにした。どんな結果になっても、褒めたたえ、励ましてあげたい。
取材をしたのは1年前のことだ。6人の女子学生を引率し、九州、主として福岡へ環境保護をテーマとした取材旅行へ出かけた。北京時代に知り合った外三上正裕・元日本大使館文化公使(現外務省国際法局長)から「北九州に行くのであればぜひ」と紹介を受けた。師村氏との出会いについては1年前、ブログで紹介したので繰り返さない。
【日本取材ツアー⑫】毎日、「寿」を彫り続ける篆刻家(2017年4月17日)
https://blog.goo.ne.jp/kato-takanori2015/e/918216ddb7775e3ba8b603f73fd560d0
【日本取材ツアー⑬】反日デモをくぐり抜けた篆刻石柱碑(2017年4月18日)
https://blog.goo.ne.jp/kato-takanori2015/e/1a1281615d994277ffdadaac9c933e94
取材対象としてはまったく考えていなかったが、師村氏の自宅に招かれ、不慮の事故で、24歳で亡くなった長男、八(ひらく)さんの話をしているうちにみなが引き込まれていった。彼女たちはいつの間にか、日ごろに培った記者精神を発揮し、カメラを回していたのである。容易にできるものではない。
映像作品は、師村氏本人の語り以外、長男が残した日記『駆け抜けたヒラク 人生の旅』の内容を再現しながら、師村自身の中国とのかかわりを重ねて描いた。タイトルの「人生の旅」は、親子の旅を含んでいる。



「これには『寿』が彫ってあります。息子が亡くなってから毎日、『寿』の文字を一つずつ彫り続け、もう3000を超えました。88歳には1万個になる予定です」
師村氏は、われわれに贈ってくれた取材チーム名「新緑」の書に、「寿」の印を押しながら、こう説明してくれた。「寿」には、生命の尊さと若者の成長を願う気持ちが込められている。長男の日記には、おんぼろの自転車で中国や日本を走りながら、自分を見つめ、人生とのかかわりを見出そうとする若者の姿が描かれている。先日、無錫で師村氏にあった際、すでに日記の中国語版発行が決まり、次男の冠臣さんが翻訳をすることになったと聞いた。その後、私が監訳を頼まれたので、喜んで引き受けた。人の縁とは不思議なものだ。


「自然は本当に厳しいものだ。それも全部自分で冬を選んだ結果であって、その和解策を見つけなければならないのも自分だ。頑張って身に付けたい。今の人間にかけている何かが何なのか、分かりそうな感じがする」
不慮の事故で亡くなる前日、八さんはこう書き残した。これが遺言となった。中国の学生が日本人の親子から感じとり、伝えようとしたものが形になり、多くの人から評価を受けた。わずかにかかわった日本人教師として、こんなうれしいことはない。4日は晴れ晴れとした気持ちで臨みたい。そして大いに祝杯をあげよう!




私はナレーションや翻訳としても参加したので、特に思いが強い。北京で環境ビジネスを手掛ける佐野史明君も、日本の若者の声でナレーションに協力してくれた。5月4日、主催者の北京師範大学で最終受賞作品の発表式典があるので、私は学生に同伴し出席することにした。どんな結果になっても、褒めたたえ、励ましてあげたい。
取材をしたのは1年前のことだ。6人の女子学生を引率し、九州、主として福岡へ環境保護をテーマとした取材旅行へ出かけた。北京時代に知り合った外三上正裕・元日本大使館文化公使(現外務省国際法局長)から「北九州に行くのであればぜひ」と紹介を受けた。師村氏との出会いについては1年前、ブログで紹介したので繰り返さない。
【日本取材ツアー⑫】毎日、「寿」を彫り続ける篆刻家(2017年4月17日)
https://blog.goo.ne.jp/kato-takanori2015/e/918216ddb7775e3ba8b603f73fd560d0
【日本取材ツアー⑬】反日デモをくぐり抜けた篆刻石柱碑(2017年4月18日)
https://blog.goo.ne.jp/kato-takanori2015/e/1a1281615d994277ffdadaac9c933e94
取材対象としてはまったく考えていなかったが、師村氏の自宅に招かれ、不慮の事故で、24歳で亡くなった長男、八(ひらく)さんの話をしているうちにみなが引き込まれていった。彼女たちはいつの間にか、日ごろに培った記者精神を発揮し、カメラを回していたのである。容易にできるものではない。
映像作品は、師村氏本人の語り以外、長男が残した日記『駆け抜けたヒラク 人生の旅』の内容を再現しながら、師村自身の中国とのかかわりを重ねて描いた。タイトルの「人生の旅」は、親子の旅を含んでいる。



「これには『寿』が彫ってあります。息子が亡くなってから毎日、『寿』の文字を一つずつ彫り続け、もう3000を超えました。88歳には1万個になる予定です」
師村氏は、われわれに贈ってくれた取材チーム名「新緑」の書に、「寿」の印を押しながら、こう説明してくれた。「寿」には、生命の尊さと若者の成長を願う気持ちが込められている。長男の日記には、おんぼろの自転車で中国や日本を走りながら、自分を見つめ、人生とのかかわりを見出そうとする若者の姿が描かれている。先日、無錫で師村氏にあった際、すでに日記の中国語版発行が決まり、次男の冠臣さんが翻訳をすることになったと聞いた。その後、私が監訳を頼まれたので、喜んで引き受けた。人の縁とは不思議なものだ。


「自然は本当に厳しいものだ。それも全部自分で冬を選んだ結果であって、その和解策を見つけなければならないのも自分だ。頑張って身に付けたい。今の人間にかけている何かが何なのか、分かりそうな感じがする」
不慮の事故で亡くなる前日、八さんはこう書き残した。これが遺言となった。中国の学生が日本人の親子から感じとり、伝えようとしたものが形になり、多くの人から評価を受けた。わずかにかかわった日本人教師として、こんなうれしいことはない。4日は晴れ晴れとした気持ちで臨みたい。そして大いに祝杯をあげよう!