岩波文庫の『モンテ・クリスト伯』を読み終わり、その終わりの方にあったモンテ・クリスト伯の言葉の一部をタイトルにしました。
この小説を読み出したのは『乱』を読んでいて19世紀のフランスが舞台になった小説だから、と手にしたのものです。まず、書き出しの「一八一五年二月二十四日」は、『乱』の書き出しの文久三年(1863)から半世紀近く離れた時代ですが、ナポレオンのエルバ島を脱出が書き出しから物語の大きな要素になっており、引きつけられてしまいました。
子供の頃『巌窟王』として読んだ記憶がありますが、「本物」を読んだのは始めてで、カタカナの名前に悩ませられながら筋の展開に、頁閉じる能わずの感で久しぶりに長編小説の醍醐味を堪能しました。
このタイトルの部分は、全編で117章の117章目「十月五日」舞台はモンテ・クリスト島、モンテ・クリストが息子とも思うマクシミリヤンに語りかけている言葉です。
「あなたはいま、重要な言葉をおっしゃいました。死は、わたしたちがそれと正しい対しかたをするか、まちがった対しかたをするかによって、或ときは乳母のようにわたしたちを揺すってくれるよい友だちになってくれ、或いは、わたしたちの魂を肉体から手あらくもぎとる仇敵のようにもなるものなのです。」
この後、
「いまから一千年ののち、人間が、自然のあらゆる破壊力を征服して、それを人類の一般的な福祉のために利用するようになったあかつき、すなわち人間が、ついいましがたあなたがおっしゃったように死のあらゆる秘密を知りつくすことになったあかつき、死はおそらく、恋人の腕にいだかれて味わう眠りのようにやさしく、また、たまらないものになるでしょう。」
と。
次の世界がどういう社会になるかを資本主義の次の生産様式について語るとか、人工知能の発展した未来社会像を描くなどなど、あるでしょう。何れにしてもその時代であっても一千年前の世界と同じように一人一人の生死病死が問題になり最終的には死をもって閉じるわけです。
そうなるとこのモンテ・クリスト伯の言葉が意味することが社会のありようの基本的なことだと思うのです。

















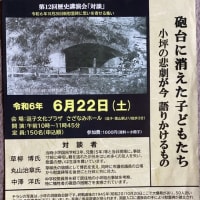


いつも将来・・を見据えて考えよ
近い将来、中ほどの将来、そして
遠い将来、それが一千年ののち・・
いろんな科学や文明文化が発達しても
平和な世界は・・無理だと思っても
やはり其処に向けて考えないと
全ての幸福も平和も無になって
しまうでしょう。
私は近未来、明日の発想が浮かばなくて
苦慮しています。
デュマの書いた小説としての『モンテ・クリスト伯』はこれから1000経っても読まれ続けるでしょう。
人生もそれを生み出した芸術と共に生き続けるのは、神がいなくなった世界に再生された神として現れるでしょう。