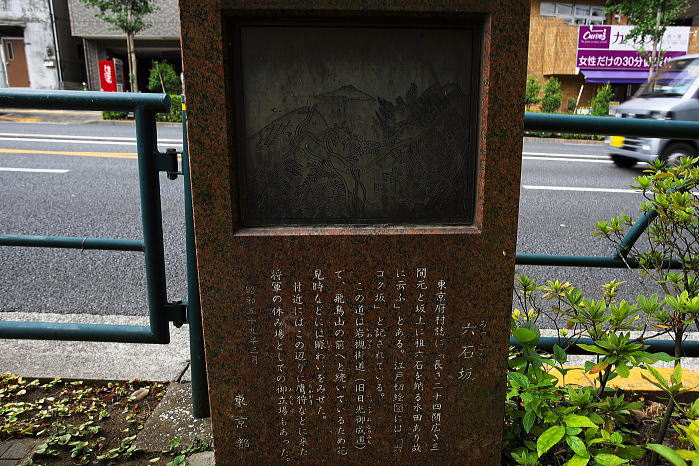上流は石神井川、王子辺りから音無川と名前を変えます、
八代将軍吉宗の故郷、紀州の音無川に似ているとの命名です。
でもこの川、名にし負う暴れ川で今でも集中豪雨のときなど
あっという間に増水し被害が出ることもあります。

音無橋から川沿いに上流に行くと左に正受院、
中国風の鐘楼は昭和16年頃まで朝夕に鐘をついていたという。
赤ちゃん寺として有名で、
この世に生まれることなく儚く消えた命、生まれてすぐ天に上った命、
お詣りする人の姿は途切れません。

前はよく行った、春にはカタクリなんか咲いていたりしていたけど。
この廻りはぬいぐるみとかのお供え物でいっぱいだったが
久しぶりに来てみたらかなり整理されていた。

正受院の裏側から下を見る。
この辺りの地名は「滝野川」、この高台から音無川へたくさんの滝が流れ落ちていました。
俗に言う「王子七滝」です。江戸時代には日帰りで行ける避暑地として賑わいました。

川に戻ってさらに数分、窪地があります、音無さくら緑地。
アマゾン川のように蛇行していた音無川も改修され真っ直ぐになったけど、
一番蛇行が強かった場所は残されて緑地公園に。
強い水流が崖を浸食していた跡が残っています、
自然露頭ですね。

さらにちょっとで金剛寺、「紅葉寺」として有名。
(上のはめ込みの地図右に「寺剛金」、分かりますか?)
頼朝が鎌倉へ帰る際に陣を置いた所、そのあと鎌倉幕府を立ち上げます。
岩槻街道は鎌倉街道の一部とか脇道とか言われますね。

さらに上流へ歩くと音無川の遊水地、
ちょっと強い雨が降るとすぐ増水するので蛇行していた跡が遊水地になっています。
普段は水辺の遊び場、増水したらここに一時濁流を溜めて洪水を防ぐ仕組みですね。
このままさらに進むと板橋へ出ますが今日はここまで。
板橋では中山道と交差するけどそこには板の橋が架かっていました、
「板橋」の名の由来です。

音無橋まで戻って川へ降りてみましょう、音無親水公園です。
昔の避暑地が偲ばれる風景、
江戸時代には桜の季節と夏の時期には
お店もたくさん並んで大賑わいだったようです。

私が東京へ出てきたころはこの川はまだどぶ川、
後ろの崖には赤茶けたトタン屋根のバラックが並び
まだ戦後を引きずっていました。
あれから50年、戦後を知ってる人はもう僅かですねぇ、、、。

王子といえば「玉子焼きの扇屋」、
江戸名所図会にも描かれ、いろいろな落語にも登場する超有名店でした。
吉宗が飛鳥山に桜を植えるずっと前からあったとされます。
何が変わったってこんなに変わった店は類を見ない、
私もよく知ってる、以前は料亭として堂々たる店を構えて
辺りを睥睨していたあの扇屋は今・・・。
隣りの自販機と同じような大きさになってしまった、
中ではおじさんが一人でどこで作ったのか分からない
玉子焼きを売ってる、いつかTVでも見たけど、、、
いや、見てはいられなかった。
栄枯盛衰は世の習いというけど
あまりの変わりように言葉も出ない、何があったのか、、、。
一応「食べログ」には載っているけど・・・。
最後湿っぽくなったけど、ま、いっかぁ。
山の日に端を発した街歩き、懐かしい王子の街を歩きました、
ここまで歩いて次を歩かない手はない。
このあと日暮里崖線を歩くのはいつかな?。(爆)
8月11日 懐かしの音無川を歩く

八代将軍吉宗の故郷、紀州の音無川に似ているとの命名です。
でもこの川、名にし負う暴れ川で今でも集中豪雨のときなど
あっという間に増水し被害が出ることもあります。

音無橋から川沿いに上流に行くと左に正受院、
中国風の鐘楼は昭和16年頃まで朝夕に鐘をついていたという。
赤ちゃん寺として有名で、
この世に生まれることなく儚く消えた命、生まれてすぐ天に上った命、
お詣りする人の姿は途切れません。

前はよく行った、春にはカタクリなんか咲いていたりしていたけど。
この廻りはぬいぐるみとかのお供え物でいっぱいだったが
久しぶりに来てみたらかなり整理されていた。

正受院の裏側から下を見る。
この辺りの地名は「滝野川」、この高台から音無川へたくさんの滝が流れ落ちていました。
俗に言う「王子七滝」です。江戸時代には日帰りで行ける避暑地として賑わいました。

川に戻ってさらに数分、窪地があります、音無さくら緑地。
アマゾン川のように蛇行していた音無川も改修され真っ直ぐになったけど、
一番蛇行が強かった場所は残されて緑地公園に。
強い水流が崖を浸食していた跡が残っています、
自然露頭ですね。

さらにちょっとで金剛寺、「紅葉寺」として有名。
(上のはめ込みの地図右に「寺剛金」、分かりますか?)
頼朝が鎌倉へ帰る際に陣を置いた所、そのあと鎌倉幕府を立ち上げます。
岩槻街道は鎌倉街道の一部とか脇道とか言われますね。

さらに上流へ歩くと音無川の遊水地、
ちょっと強い雨が降るとすぐ増水するので蛇行していた跡が遊水地になっています。
普段は水辺の遊び場、増水したらここに一時濁流を溜めて洪水を防ぐ仕組みですね。
このままさらに進むと板橋へ出ますが今日はここまで。
板橋では中山道と交差するけどそこには板の橋が架かっていました、
「板橋」の名の由来です。

音無橋まで戻って川へ降りてみましょう、音無親水公園です。
昔の避暑地が偲ばれる風景、
江戸時代には桜の季節と夏の時期には
お店もたくさん並んで大賑わいだったようです。

私が東京へ出てきたころはこの川はまだどぶ川、
後ろの崖には赤茶けたトタン屋根のバラックが並び
まだ戦後を引きずっていました。
あれから50年、戦後を知ってる人はもう僅かですねぇ、、、。

王子といえば「玉子焼きの扇屋」、
江戸名所図会にも描かれ、いろいろな落語にも登場する超有名店でした。
吉宗が飛鳥山に桜を植えるずっと前からあったとされます。
何が変わったってこんなに変わった店は類を見ない、
私もよく知ってる、以前は料亭として堂々たる店を構えて
辺りを睥睨していたあの扇屋は今・・・。
隣りの自販機と同じような大きさになってしまった、
中ではおじさんが一人でどこで作ったのか分からない
玉子焼きを売ってる、いつかTVでも見たけど、、、
いや、見てはいられなかった。
栄枯盛衰は世の習いというけど
あまりの変わりように言葉も出ない、何があったのか、、、。
一応「食べログ」には載っているけど・・・。
最後湿っぽくなったけど、ま、いっかぁ。
山の日に端を発した街歩き、懐かしい王子の街を歩きました、
ここまで歩いて次を歩かない手はない。
このあと日暮里崖線を歩くのはいつかな?。(爆)
8月11日 懐かしの音無川を歩く