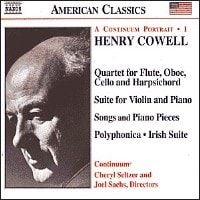明治帝が、日清戦争開戦時、伊勢神宮と孝明天皇陵とに報告の勅使をさしむけることを拒否して、
つまり、
また、もっとはっきりした発言としては、
一方、その大臣たちは、
つまりは、日本の利益線は朝鮮半島にあり、この独立が失われるならば、
しかし、この明治帝と大臣たちとの認識の違いは、何ら問題になることなしに、明治27(1894)年には、実際の日清開戦となるわけです。
なぜ問題にならなかったといえば、天皇は憲法上の立憲君主だったから、というのが、教科書的な答え。
確かにそのとおりなのですが、ここには、明治帝は、維新時に担がれた神輿だったという、かつての「維新の志士」たちの意識/無意識的な心理も大きく働いていたのではないのか。
そのような意見を述べているのが、次のような文章。
そして、「維新の志士」たちがいなくなるにしたがって、天皇親政論が台頭してくる(「昭和維新」)。
このような観点から、天皇親政論と天皇国家機関説とを読み解くことも可能でありましょう。
*ドナルド・キーン『明治天皇』下巻には、次のように書かれています。
「かくの如くもともと不本意ながらの儀なれば、おそれながら神明へ申上候事は、はばかるべし」*と言ったことは、知る人ぞ知るエピソードです。
つまり、
「不本意ながらの儀とありますが、これは婉曲な表現で、はっきりいえば『義戦にあらず』という意味です。(中略)憲法はすでに発布され、内閣に輔弼される立憲君主として、明治天皇は開戦に反対を唱えることは、制度上、できなかったのです。そのかわり、伊勢神宮と孝明天皇陵への勅使派遣を拒みました。義戦にあらざる戦争のことを、父や祖先の霊に告げることをいさぎよしとしなかったのです。」(陳舜臣『中国の歴史 14』平凡社)
また、もっとはっきりした発言としては、
「このたびの戦いは、大臣の戦いであって、朕の戦いではない」というものもあります(こちらの発言の方が、有名かもしれない)。
一方、その大臣たちは、
「蓋し国家独立自営の道に二途あり、第一に主権線を守護すること、第二には利益線を保護することである。この主権線とは国の彊域をいひ、利益線とは其の主権線の安危に密着の関係ある区域を申したのである。およそ国として主権線及利益線を保たぬ国はござゐませぬ。方今列国の間に介立して一国の独立を維持するには、独り主権線を守禦するのみにては、決して十分とは申されませぬ。必ず利益線を保護致さなくてはならぬことと存じます。」(山県有朋。明治23(1890)年の施政方針演説)との考えを持っていたのね。
つまりは、日本の利益線は朝鮮半島にあり、この独立が失われるならば、
「我が対馬諸島の主権線は頭上に刃を掛くるの勢い」となってしまう、と認識していたわけです。ですから、朝鮮の宗主権のある清国が、当時最大の仮想敵国だった。
しかし、この明治帝と大臣たちとの認識の違いは、何ら問題になることなしに、明治27(1894)年には、実際の日清開戦となるわけです。
なぜ問題にならなかったといえば、天皇は憲法上の立憲君主だったから、というのが、教科書的な答え。
確かにそのとおりなのですが、ここには、明治帝は、維新時に担がれた神輿だったという、かつての「維新の志士」たちの意識/無意識的な心理も大きく働いていたのではないのか。
そのような意見を述べているのが、次のような文章。
「伊藤博文と並ぶ元勲である山県有朋は、天皇(明治天皇・大正天皇)や皇族に対して、しばしば不遜な言動をとっていたという(典型的な事例としては「宮中某重大事件」がある。一風斎註)。山県のそのような言動の背後には、武力によって討幕をなしとげ、新政府を形成した革命家(=「維新の志士」。一風斎註)としての自負があったのだろう。山県にとっては、おそらく幕末から大正期にいたるまで、皇室はつねに権謀の対象でしかなかったではあるまいか。」(礫川全次『史疑 幻の家康論』)
そして、「維新の志士」たちがいなくなるにしたがって、天皇親政論が台頭してくる(「昭和維新」)。
このような観点から、天皇親政論と天皇国家機関説とを読み解くことも可能でありましょう。
*ドナルド・キーン『明治天皇』下巻には、次のように書かれています。
「天皇の宣戦の詔勅が公布された直後、宮内大臣土方久元は天皇の御前に伺候し、神宮ならびに孝明天皇陵に派遣する勅使の人選について尋ねた。天皇の応えは、次のようなものだった。
『其の儀に及ばず、今回の戦争は朕素より不本意なり、閣臣等戦争の已むべからざるを奏するに依り、之れを許したるのみ、之れを神宮及び先帝陵に奉告するは朕甚だ苦しむ』と。」