■新宿鮫XI 暗約領域/大沢在昌 2021.7.19
2021年版 このミステリーがすごい! 国内編 9位
『新宿鮫XI 暗約領域』 を読みました。
前作、『新宿鮫X 絆回廊』 を読んだのは、2012年6月。それから、もう9年。
月日の流れは、なんとはやいことでしょうか。
終局の部分にたどり着くまで、話は、丁寧に語られています。
しかし、詰めの部分にきて、少しあっけなく終わった気がしました。
p700余りの長い作品でしたが、飽きずに楽しく読むことが出来ました。
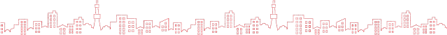
鮫島取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いている。
レポートの作成はさして苦にはならない。多くの現場警察官が苦手とする書類仕事を鮫島は他人の何倍もの速さでこなすことができる。それはいわば才能で、同僚や上司を驚かせ、あきれさせてきた。キャリア出身であるからできるわけではない。キャリア警察官でも、書類仕事の苦手な人間はいる。
コーヒーを飲み、毛布と双眼鏡、コンビニで買った食料をもち、車に乗り込んだ。引っ越すべきだというのはわかっていた。今のマンションには思い出が多すぎる。だが引っ越しにあてる時間はない。
そうではない。引っ越したくないのだ。引っ越したとたん、思い出のすべてが分解し、雲散霧消してしまうような気がしていた。
それで何が悪い。思い出をひきずって生きるよりはマシだ。
そうじゃない。思い出から逃げ出す弱さが嫌なのだ。
新宿警察署に、新しい課長が赴任してくる。新課長は、意外にも“女性”だった。
彼女は、鮫島の天敵として、警視庁本部から送り込まれてきたのか。
新課長阿坂は、信念の人であった。
阿坂の目に強い光が宿った。
「『新宿鮫』という名は、いつも聞いていました。新宿には、すごい刑事がいる。キャリア警察官なのに現場にとどまり、どんなに凶悪な犯罪者だろうと、いつもひとりで食いつき、決してあきらめない。まさか自分が、そんな人といっしょに働くことになるとは、夢にも思っていませんでした」
「尾鰭のついた噂です」
阿坂は微笑んだ。
「確かにもっとごつい方を想像していました。この部屋に入ってこられたとき、意外でした。大男だとばかり、思っていたので」
「与えられたチャンスにどう応えるか。三十年間、警察官としてずっと守ってきたことがあります。
それを鮫島さんにも聞いていただきたくて、今日、ご無理をお願いしました」
「はい」
「それは、基本を守る。ルールを決して曲げない、ということです。警視庁は大きな組織で、わたしたちはその歯車のひとつです。ひとつですが、与えられている力は大きく、責任は重い。力の使い方をあやまれば、誰かを傷つけるだけでなく、警察への信頼を裏切る結果になります。世界にはいろいろな警察があって、組織の利益を公務より優先させる警察、権力者を守るために平気で市民に武器を向ける警察、さらには犯罪組織とあたり前のように手を組む警察すら、存在します。日本の警察はちがう。世界一清潔で、規律正しく、そしてすぐれた捜査能力があります。海外への留学を命じられたときも、わたしは日本の警察官であることを何より誇りに思い、言葉は喋れなくとも、。肩身の狭い思いは決してしませんでした」
本心からの言葉なのだろう。目元が赤らんでいた。
「基本を守る。ルールを曲げない」
鮫島はくり返した。
そうです。新宿署においても、わたしはその信念でやっていきたいと思っていて、先ほど署長にも確認をさせていただきました」
「ご立派なお考えだと思います」
阿坂はわずかに顎をひいた。目元の赤みが消え、口もとの皺に深さが増している。
新課長阿坂は、一匹狼の鮫島にパートナーとなる新人刑事をつける。何時も行動を共にすることを求めるのだが..........。
「今日の午後、会ってくるつもりです」
「その件ですが、新人の課員を同行して下さい」
「新人を、ですか」
「基本です。単独捜査は、わたしの課ではありえません」
鮫島は息を吸いこんだ。
「つまり、その新人を、私の相方にせよといわれるのですか」
「そうです。後ほど紹介しますが、矢崎さんといいます。矢崎隆男巡査部長です。鮫島さんに指導をお願いします」
阿坂は老眼鏡を外し、鮫島の目を見つめた。
「よろしいですか?」
課の空気が張りつめている。口調は柔らかいが、反駁を許さない響きが阿坂の声にはあった。
「その新人の経歴に傷をつけることになってもよいのですか」
鮫島は訊き返した。
「傷?」
阿坂は意外そうにつぶやいた。
「なぜ鮫島さんと組むことが、傷になるのです?」
「私が警察官であることを快く思わない人間がいるからです」
阿坂は目を広げた。
「どこにいるのです?」
「警視庁、警察庁両方です。彼らにとって私は病原菌のようなものです。誰かと組めば、その人物も菌に冒されたと考えるかも知れない。そうなったら、将来を失うことになる」
阿坂は首をふった。
「そんなに情けない人たちが警察を動かしているとはわたしは思いません。鮫島さんに事情があるというのは知っています。その事情がまるで黴菌のように他の人に感染するというのですか」
「可能性の問題です。将来において、私と組んだことが人事のマイナス材料にならないとはいいきれません」
パートナーが、出来たことに、鮫島は戸惑い、そして、危惧も感じるのだが。
「潔いっていうか、まあ愚かしいといえば愚かしいけど、どれだけ麻雀が好きなんだって、話を聞いていて思いました。しかも本人は食われちまってるのに、まるで不幸せそうじゃない。賭け麻雀にひっかからなかったら、今でもふつうに勤めて家族に囲まれていたかもしれないのに」
「だとしても、それを幸福と感じているかどうかはわからないさ。ただ、今が不幸じゃないからといって権現が感謝される筋合いじゃない。権現はただ食いものにしただけだ。
もちろん権現が現れなくても、呉竹が他の極道に食われた可能性はある。場合によっては今より悲惨な結果になったろう。
あるいは殺されていても不思議はない。呉竹はそれを感じているから、恩義のように思っているんだ」
「結局、ああいう人は、木の葉が水に流されるように、いきつくところにいってしまうんですかね」
矢崎がいった。鮫島は思わずその顔を見直した。
「俺、変なことをいいましたか」
「いや。大人だと思った」
「やめて下さい。で、これからどうします?」
「そうだな」
鮫島は箸を止め、宙を見つめた。奇妙な気分だった。これまで捜査の過程には報告しかなかった。
誰にも相談することなくひとりで動き、判明した事実と仮説を桃井に伝えた。
これからどうする、という相談を誰かから受けることはなかった。
初対面で、ふと感じることがあった。
読者としても、もしかしたら、ととても嫌な予感を感じる。
そのことは、大きな意味をもっていた。
鮫島は後々知ることになる。
中背だががっちりした体つきで眼鏡をかけている。機動隊にいたと副署長はいったが、そのわりには色が白い。
水と油の鮫島と香田。
仲を取り持つ古本屋主人黒井。
三者三様のやり取りが面白い。
特に、黒井のキャラが生きている。
そんな彼らが、協力して権現の救出に当たる。
極道以外の日本人に賄賂をせびる警察官は少ない。が外国人に対しては賄賂を求める警察官がいるという話を鮫島は聞いたことがあった。
開発途上国からきた人間にとって、袖の下を受けとる公務員は珍しくない。賄賂が社会の潤滑油として機能しているからだ。そこにつけこみ、金を要求する。被害者が告発しようにも、言葉や制度のちがいなどから泣き寝入りすることが多い。
「何という名前ですか?」
香田の顔が赤くなった。
「公安の風上にもおけない奴だ」
「もう警察にはおらんよ。存外、君の近くかもしれんぞ」
黒井が答えたので、目をみひらいた。
「本当ですか」
「『東亜通商』ではないが、似たようなところにいった筈だ」
「許せんな」
香田はつぷやいた。
「それはエリートの考え方だ。立場を金にかえられるだけの頭がある者は、スパイに向いている。杓子定規の考え方しかせん者は、すぐに正体が露見するからな」
黒井がいうと、香田は頬をふくらませた。
「それとも何か。規律を守れんような人間は国も守れん、と君は思うのか」
香田は首をふった。
「そこまで頭でっかちではありません」
「なら、明日、武器を用意してこられるな」
表情を硬くしたが、決心したように香田は頷いた。
鮫島は、香田とは相容れない。
しかし、読んでいると香田には公安とは思えない可愛らしいところもある。
彼の言う「国益」には、理解に苦しむところもあるのだが、彼なりに一本筋が通っているような気もした。
『 新宿鮫XI 暗約領域/大沢在昌/光文社 』
2021年版 このミステリーがすごい! 国内編 9位
『新宿鮫XI 暗約領域』 を読みました。
前作、『新宿鮫X 絆回廊』 を読んだのは、2012年6月。それから、もう9年。
月日の流れは、なんとはやいことでしょうか。
終局の部分にたどり着くまで、話は、丁寧に語られています。
しかし、詰めの部分にきて、少しあっけなく終わった気がしました。
p700余りの長い作品でしたが、飽きずに楽しく読むことが出来ました。
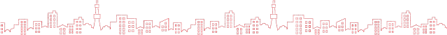
鮫島取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いている。
レポートの作成はさして苦にはならない。多くの現場警察官が苦手とする書類仕事を鮫島は他人の何倍もの速さでこなすことができる。それはいわば才能で、同僚や上司を驚かせ、あきれさせてきた。キャリア出身であるからできるわけではない。キャリア警察官でも、書類仕事の苦手な人間はいる。
コーヒーを飲み、毛布と双眼鏡、コンビニで買った食料をもち、車に乗り込んだ。引っ越すべきだというのはわかっていた。今のマンションには思い出が多すぎる。だが引っ越しにあてる時間はない。
そうではない。引っ越したくないのだ。引っ越したとたん、思い出のすべてが分解し、雲散霧消してしまうような気がしていた。
それで何が悪い。思い出をひきずって生きるよりはマシだ。
そうじゃない。思い出から逃げ出す弱さが嫌なのだ。
新宿警察署に、新しい課長が赴任してくる。新課長は、意外にも“女性”だった。
彼女は、鮫島の天敵として、警視庁本部から送り込まれてきたのか。
新課長阿坂は、信念の人であった。
阿坂の目に強い光が宿った。
「『新宿鮫』という名は、いつも聞いていました。新宿には、すごい刑事がいる。キャリア警察官なのに現場にとどまり、どんなに凶悪な犯罪者だろうと、いつもひとりで食いつき、決してあきらめない。まさか自分が、そんな人といっしょに働くことになるとは、夢にも思っていませんでした」
「尾鰭のついた噂です」
阿坂は微笑んだ。
「確かにもっとごつい方を想像していました。この部屋に入ってこられたとき、意外でした。大男だとばかり、思っていたので」
「与えられたチャンスにどう応えるか。三十年間、警察官としてずっと守ってきたことがあります。
それを鮫島さんにも聞いていただきたくて、今日、ご無理をお願いしました」
「はい」
「それは、基本を守る。ルールを決して曲げない、ということです。警視庁は大きな組織で、わたしたちはその歯車のひとつです。ひとつですが、与えられている力は大きく、責任は重い。力の使い方をあやまれば、誰かを傷つけるだけでなく、警察への信頼を裏切る結果になります。世界にはいろいろな警察があって、組織の利益を公務より優先させる警察、権力者を守るために平気で市民に武器を向ける警察、さらには犯罪組織とあたり前のように手を組む警察すら、存在します。日本の警察はちがう。世界一清潔で、規律正しく、そしてすぐれた捜査能力があります。海外への留学を命じられたときも、わたしは日本の警察官であることを何より誇りに思い、言葉は喋れなくとも、。肩身の狭い思いは決してしませんでした」
本心からの言葉なのだろう。目元が赤らんでいた。
「基本を守る。ルールを曲げない」
鮫島はくり返した。
そうです。新宿署においても、わたしはその信念でやっていきたいと思っていて、先ほど署長にも確認をさせていただきました」
「ご立派なお考えだと思います」
阿坂はわずかに顎をひいた。目元の赤みが消え、口もとの皺に深さが増している。
新課長阿坂は、一匹狼の鮫島にパートナーとなる新人刑事をつける。何時も行動を共にすることを求めるのだが..........。
「今日の午後、会ってくるつもりです」
「その件ですが、新人の課員を同行して下さい」
「新人を、ですか」
「基本です。単独捜査は、わたしの課ではありえません」
鮫島は息を吸いこんだ。
「つまり、その新人を、私の相方にせよといわれるのですか」
「そうです。後ほど紹介しますが、矢崎さんといいます。矢崎隆男巡査部長です。鮫島さんに指導をお願いします」
阿坂は老眼鏡を外し、鮫島の目を見つめた。
「よろしいですか?」
課の空気が張りつめている。口調は柔らかいが、反駁を許さない響きが阿坂の声にはあった。
「その新人の経歴に傷をつけることになってもよいのですか」
鮫島は訊き返した。
「傷?」
阿坂は意外そうにつぶやいた。
「なぜ鮫島さんと組むことが、傷になるのです?」
「私が警察官であることを快く思わない人間がいるからです」
阿坂は目を広げた。
「どこにいるのです?」
「警視庁、警察庁両方です。彼らにとって私は病原菌のようなものです。誰かと組めば、その人物も菌に冒されたと考えるかも知れない。そうなったら、将来を失うことになる」
阿坂は首をふった。
「そんなに情けない人たちが警察を動かしているとはわたしは思いません。鮫島さんに事情があるというのは知っています。その事情がまるで黴菌のように他の人に感染するというのですか」
「可能性の問題です。将来において、私と組んだことが人事のマイナス材料にならないとはいいきれません」
パートナーが、出来たことに、鮫島は戸惑い、そして、危惧も感じるのだが。
「潔いっていうか、まあ愚かしいといえば愚かしいけど、どれだけ麻雀が好きなんだって、話を聞いていて思いました。しかも本人は食われちまってるのに、まるで不幸せそうじゃない。賭け麻雀にひっかからなかったら、今でもふつうに勤めて家族に囲まれていたかもしれないのに」
「だとしても、それを幸福と感じているかどうかはわからないさ。ただ、今が不幸じゃないからといって権現が感謝される筋合いじゃない。権現はただ食いものにしただけだ。
もちろん権現が現れなくても、呉竹が他の極道に食われた可能性はある。場合によっては今より悲惨な結果になったろう。
あるいは殺されていても不思議はない。呉竹はそれを感じているから、恩義のように思っているんだ」
「結局、ああいう人は、木の葉が水に流されるように、いきつくところにいってしまうんですかね」
矢崎がいった。鮫島は思わずその顔を見直した。
「俺、変なことをいいましたか」
「いや。大人だと思った」
「やめて下さい。で、これからどうします?」
「そうだな」
鮫島は箸を止め、宙を見つめた。奇妙な気分だった。これまで捜査の過程には報告しかなかった。
誰にも相談することなくひとりで動き、判明した事実と仮説を桃井に伝えた。
これからどうする、という相談を誰かから受けることはなかった。
初対面で、ふと感じることがあった。
読者としても、もしかしたら、ととても嫌な予感を感じる。
そのことは、大きな意味をもっていた。
鮫島は後々知ることになる。
中背だががっちりした体つきで眼鏡をかけている。機動隊にいたと副署長はいったが、そのわりには色が白い。
水と油の鮫島と香田。
仲を取り持つ古本屋主人黒井。
三者三様のやり取りが面白い。
特に、黒井のキャラが生きている。
そんな彼らが、協力して権現の救出に当たる。
極道以外の日本人に賄賂をせびる警察官は少ない。が外国人に対しては賄賂を求める警察官がいるという話を鮫島は聞いたことがあった。
開発途上国からきた人間にとって、袖の下を受けとる公務員は珍しくない。賄賂が社会の潤滑油として機能しているからだ。そこにつけこみ、金を要求する。被害者が告発しようにも、言葉や制度のちがいなどから泣き寝入りすることが多い。
「何という名前ですか?」
香田の顔が赤くなった。
「公安の風上にもおけない奴だ」
「もう警察にはおらんよ。存外、君の近くかもしれんぞ」
黒井が答えたので、目をみひらいた。
「本当ですか」
「『東亜通商』ではないが、似たようなところにいった筈だ」
「許せんな」
香田はつぷやいた。
「それはエリートの考え方だ。立場を金にかえられるだけの頭がある者は、スパイに向いている。杓子定規の考え方しかせん者は、すぐに正体が露見するからな」
黒井がいうと、香田は頬をふくらませた。
「それとも何か。規律を守れんような人間は国も守れん、と君は思うのか」
香田は首をふった。
「そこまで頭でっかちではありません」
「なら、明日、武器を用意してこられるな」
表情を硬くしたが、決心したように香田は頷いた。
鮫島は、香田とは相容れない。
しかし、読んでいると香田には公安とは思えない可愛らしいところもある。
彼の言う「国益」には、理解に苦しむところもあるのだが、彼なりに一本筋が通っているような気もした。
『 新宿鮫XI 暗約領域/大沢在昌/光文社 』














