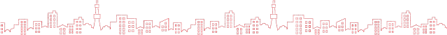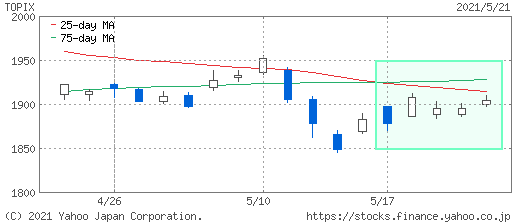■泳ぐ者/青山文平 2021.5.31
青山文平が、徒目付片岡直人の努める御用を描いた 短編集『半席』 を2016年に出してから5年。
今回は、長篇 『泳ぐ者』 の登場です。
片岡直人は、上役の内藤雅之と神田多町の居酒屋、七五屋で季節感あふれる江戸の料理を堪能する。料理といいその時の会話といい、この場面にすごく心が和む。
話は、大ばっぱに三つから構成されている。
いずれも切ない話ばかりなのである。
ぼくには、源内と多町一の比丘尼の話が、特に切なかった。哀れである。
「当家としては心当たりがないが、江戸から遠路はるばる来られたこともあり、また、すでに分霊に還っていることでもあるので、もしも望まれるのであればお預かりする……そう、聞いた」

「お待たせしました」と配した利休飯の善の上には、三枚に下ろした小鯛を出刃の刃先で削いだカキ鯛の小鉢が添えられていた。
口に含んでみれば、酒と梅干しを煮込んで濾した煎り酒が刷かれていて、舌にも腹にも柔らかい。想わず、ふっと息が漏れたとき、不意に雅之が現れたのだった。
「川鱚がありますが」
馴染んだ声を聞きつけて小上がりの脇に立った喜助が、燗徳利と通しの新漬け山椒を置きつつ言う。
「川鱚かぁ。ぶっ込みかい、吸い込みかい?」
「ぶっ込みのほうで」
三年前の文化五年、初めてこの店に連れられてきて食通ぶりを目の当たりにしたとき、「武家が喰い物に淫するのはいかがなものか」と糺したら、「そりゃ、もっともだ」と雅之は答えた。「旨いもんじゃなきゃなんねえ、なんてことはさらさらねえ」。そして、つづけた。「けどな、旨いもんを喰やあ、人間、知らずに笑顔になる」。
「ああ、土垂が旨かったなあ」
深川も小名木川を離れて羅漢寺辺りまで足を延ばせばもう一面の畑地で、月見の季節になるとその地で里芋を育てる農家が茶店を出す。月見に供える喰い物といえば、まずは里芋だ。中秋の月見は里芋の収穫を祝う祭りでもある。雅之の目当ては子芋のほうを喰う土垂という里芋で、農家の庭先に仮組みされた茶店の床机に腰を下ろし、芋だけを肴に飲み、語った。雅之と月見を共にするのはその宵が初めてだった。
「襲撃への心の構え方など、さまざまに導いていただきました」
月見に付き合ってくれた芳賀源一郎の剣の話から回り回って、徒目付が受ける襲撃の話になった。幕吏の昇進、異動に伴う人物調べに当たる徒目付は恨みを買いやすい。関門で阻まれた者のなかには、人物調べのせいではないかと考える者が必ず出る。きっと悪く書かれていたのではないかと想い、わざとではないかと想い、狙われたのではないかと想う。さらに極まれば、このまま捨て置いてなるものかと毒を煮詰める。たいていは思うだけでいずれ正気に戻るが、なかにはとうとう戻らぬ者も居る。で、ある夜、鯉口を切った襲撃者が目の前に立つ。その襲撃者はなぜ戻れなかったのか、いよいよ本身を抜いて進み出たらどう対すべきか……雅之が躰で悟った智慧を惜しみなく分けてもらった。
空かぬ路が空いたからには通らねばならない。
「人は変わる。日々変わる。日々変わる己れと膝突き合わせたらいい。その上でこうと決まったときには、ためらうことなくそいつを選ぶことだ。」
「一度思い切ったことをまた思い直したって下衆にはなんねぇ。そいつを含めてもろもろ迷い抜いたらいい。人がいっとうわからねえのが誰でもねぇ、己れだ。迷いは見抜く力のなによりの肥さ」
鬱屈が溜まりに溜まった人間の背中を最後にひと押しするのは、存外取るに足らぬことだ。その無意味な軽さが、己れの失ったものの重さを際立たせる。
語ると佳津はさらに美しく見えた。いつだったか、雅之が男女に限らず「語って美しい者は照々と考える者だ」と言ったことがある。「人には見えぬものに光を当てて見通す。その目の明るさが様子にでるんだろう」と。
「妹、のこととなると、いつもそうなのです。考えるそばから散っていく」
直人は静かに感じ入る。多四郎は直人の話をただなぞっただけのようだが、そうではない。人は己れの聴きたいようにしか他人の話を聴かない。聴きたい筋の外はあらかたが抜け落ちる。
隠せるはずもないのに隠せると思い込む。そういうことでは子供の悪戯と変わらない。まさかそんなことはすまいと想うことを、人は往々にしてする。もしも、その人が政に携わっていたら、国がすることになる。よくもわるくも国は人で動く。
「頼まれ御用で大事なのは御頭がきれることじゃねえ。てめえが薄いことさ。科人の気持ちの奥底に紛れちまって、滲んでさ、終いにゃ己れが消えちまう奴がいい。」
頼まれ御用で直人がやるべきは事件を調べ直すことではなかった。すでに、科人は罪を認めている。いつ刑が執行されるかわからない。そのわずかな猶予のなかで、科人の口からなぜを引き出すのが頼まれる者の務めだ。
そのためには、己れをできうる限り薄くして、染み通るように人の気持ちの奥底へ分け入らなければならない。そうしてのみ、的を外さぬ仮の筋を、速やかに立てることができる。腹はあの世まで持っていこうと思い詰めている科人も、どこかにすべてを明かしたい情動は残している。
見抜かれることで一気にその栓が外れ、なぜがほとばしる。彼らとて見抜く者を待っているやもしれない。
源内の話はいつも浮き世離れしていて、その気で語り出すと、あらかたがわからなかった。様子も常に飄々として笑みを絶やさず、どこかしら雅之と重なる。そういうわるびれぬ源内に、直人はいつも助けられていた。穿つごとき夏の陽にも、避けようのない驟雨にも変わることのない笑顔を認めると、人間どこに居ようと彼岸はあるのだと思えてきて、取るに足らない言葉を交わしているうちに、川霧が消えるように疲れが薄れていくのだった。
「寄っていくか。紹介する。多町一の比丘尼だ」
「いや、これから向かわなければならん処がある」
嘘ではなかったが、逃げもした。
「惜しいな。これで、おぬしは女で人生棒に振る、希有な機会を逸した」
「俺にそんな甲斐性はない」
「己れをみくびるな。おぬしとて、相手さえ得れば、立派に転がり落ちることができる」
溺死を訴えれば人は離れる。主張は人を遠ざける。
馬鹿と嗤われてこそ人は集まる。
けっして事件は口外せず、見物客の憶測に任せた。
やがて憶測が渦になれば、そこから溺死の真が浮き上がるかもしれない。
そのように期して泳いでいたのだろう。
『 泳ぐ者/青山文平/新潮社 』
青山文平が、徒目付片岡直人の努める御用を描いた 短編集『半席』 を2016年に出してから5年。
今回は、長篇 『泳ぐ者』 の登場です。
片岡直人は、上役の内藤雅之と神田多町の居酒屋、七五屋で季節感あふれる江戸の料理を堪能する。料理といいその時の会話といい、この場面にすごく心が和む。
話は、大ばっぱに三つから構成されている。
いずれも切ない話ばかりなのである。
ぼくには、源内と多町一の比丘尼の話が、特に切なかった。哀れである。
「当家としては心当たりがないが、江戸から遠路はるばる来られたこともあり、また、すでに分霊に還っていることでもあるので、もしも望まれるのであればお預かりする……そう、聞いた」

「お待たせしました」と配した利休飯の善の上には、三枚に下ろした小鯛を出刃の刃先で削いだカキ鯛の小鉢が添えられていた。
口に含んでみれば、酒と梅干しを煮込んで濾した煎り酒が刷かれていて、舌にも腹にも柔らかい。想わず、ふっと息が漏れたとき、不意に雅之が現れたのだった。
「川鱚がありますが」
馴染んだ声を聞きつけて小上がりの脇に立った喜助が、燗徳利と通しの新漬け山椒を置きつつ言う。
「川鱚かぁ。ぶっ込みかい、吸い込みかい?」
「ぶっ込みのほうで」
三年前の文化五年、初めてこの店に連れられてきて食通ぶりを目の当たりにしたとき、「武家が喰い物に淫するのはいかがなものか」と糺したら、「そりゃ、もっともだ」と雅之は答えた。「旨いもんじゃなきゃなんねえ、なんてことはさらさらねえ」。そして、つづけた。「けどな、旨いもんを喰やあ、人間、知らずに笑顔になる」。
「ああ、土垂が旨かったなあ」
深川も小名木川を離れて羅漢寺辺りまで足を延ばせばもう一面の畑地で、月見の季節になるとその地で里芋を育てる農家が茶店を出す。月見に供える喰い物といえば、まずは里芋だ。中秋の月見は里芋の収穫を祝う祭りでもある。雅之の目当ては子芋のほうを喰う土垂という里芋で、農家の庭先に仮組みされた茶店の床机に腰を下ろし、芋だけを肴に飲み、語った。雅之と月見を共にするのはその宵が初めてだった。
「襲撃への心の構え方など、さまざまに導いていただきました」
月見に付き合ってくれた芳賀源一郎の剣の話から回り回って、徒目付が受ける襲撃の話になった。幕吏の昇進、異動に伴う人物調べに当たる徒目付は恨みを買いやすい。関門で阻まれた者のなかには、人物調べのせいではないかと考える者が必ず出る。きっと悪く書かれていたのではないかと想い、わざとではないかと想い、狙われたのではないかと想う。さらに極まれば、このまま捨て置いてなるものかと毒を煮詰める。たいていは思うだけでいずれ正気に戻るが、なかにはとうとう戻らぬ者も居る。で、ある夜、鯉口を切った襲撃者が目の前に立つ。その襲撃者はなぜ戻れなかったのか、いよいよ本身を抜いて進み出たらどう対すべきか……雅之が躰で悟った智慧を惜しみなく分けてもらった。
空かぬ路が空いたからには通らねばならない。
「人は変わる。日々変わる。日々変わる己れと膝突き合わせたらいい。その上でこうと決まったときには、ためらうことなくそいつを選ぶことだ。」
「一度思い切ったことをまた思い直したって下衆にはなんねぇ。そいつを含めてもろもろ迷い抜いたらいい。人がいっとうわからねえのが誰でもねぇ、己れだ。迷いは見抜く力のなによりの肥さ」
鬱屈が溜まりに溜まった人間の背中を最後にひと押しするのは、存外取るに足らぬことだ。その無意味な軽さが、己れの失ったものの重さを際立たせる。
語ると佳津はさらに美しく見えた。いつだったか、雅之が男女に限らず「語って美しい者は照々と考える者だ」と言ったことがある。「人には見えぬものに光を当てて見通す。その目の明るさが様子にでるんだろう」と。
「妹、のこととなると、いつもそうなのです。考えるそばから散っていく」
直人は静かに感じ入る。多四郎は直人の話をただなぞっただけのようだが、そうではない。人は己れの聴きたいようにしか他人の話を聴かない。聴きたい筋の外はあらかたが抜け落ちる。
隠せるはずもないのに隠せると思い込む。そういうことでは子供の悪戯と変わらない。まさかそんなことはすまいと想うことを、人は往々にしてする。もしも、その人が政に携わっていたら、国がすることになる。よくもわるくも国は人で動く。
「頼まれ御用で大事なのは御頭がきれることじゃねえ。てめえが薄いことさ。科人の気持ちの奥底に紛れちまって、滲んでさ、終いにゃ己れが消えちまう奴がいい。」
頼まれ御用で直人がやるべきは事件を調べ直すことではなかった。すでに、科人は罪を認めている。いつ刑が執行されるかわからない。そのわずかな猶予のなかで、科人の口からなぜを引き出すのが頼まれる者の務めだ。
そのためには、己れをできうる限り薄くして、染み通るように人の気持ちの奥底へ分け入らなければならない。そうしてのみ、的を外さぬ仮の筋を、速やかに立てることができる。腹はあの世まで持っていこうと思い詰めている科人も、どこかにすべてを明かしたい情動は残している。
見抜かれることで一気にその栓が外れ、なぜがほとばしる。彼らとて見抜く者を待っているやもしれない。
源内の話はいつも浮き世離れしていて、その気で語り出すと、あらかたがわからなかった。様子も常に飄々として笑みを絶やさず、どこかしら雅之と重なる。そういうわるびれぬ源内に、直人はいつも助けられていた。穿つごとき夏の陽にも、避けようのない驟雨にも変わることのない笑顔を認めると、人間どこに居ようと彼岸はあるのだと思えてきて、取るに足らない言葉を交わしているうちに、川霧が消えるように疲れが薄れていくのだった。
「寄っていくか。紹介する。多町一の比丘尼だ」
「いや、これから向かわなければならん処がある」
嘘ではなかったが、逃げもした。
「惜しいな。これで、おぬしは女で人生棒に振る、希有な機会を逸した」
「俺にそんな甲斐性はない」
「己れをみくびるな。おぬしとて、相手さえ得れば、立派に転がり落ちることができる」
溺死を訴えれば人は離れる。主張は人を遠ざける。
馬鹿と嗤われてこそ人は集まる。
けっして事件は口外せず、見物客の憶測に任せた。
やがて憶測が渦になれば、そこから溺死の真が浮き上がるかもしれない。
そのように期して泳いでいたのだろう。
『 泳ぐ者/青山文平/新潮社 』