就職氷河期世代-データで読み解く所得・家族形成・格差 (中公新書 2825) 新書 –近藤 絢子 (著)
筆者と同じく1979年生まれで就職氷河期世代に属する身として思わず手に取ってしまった本です。この氷河期世代の定義としては1993年~2004年に高校や大学を卒業した世代で1970年から1986年生まれの人たち(38―54歳)になります。氷河期の言葉が出てきたのが92年で本格的に始まったのが93年なのですが主に要因はバブルの崩壊、でその後97年の北海道拓殖銀行と山一証券の破綻を境位にさらに悪化するPhaseになります。こういった背景から筆者は93―98卒を氷河期前期、98―04卒を氷河期後期と区切って分析しており特に後期側(自分の世代…)が特に状況が悪かった世代として位置付けています。自分が感じた主たるポイントは以下。
・氷河期世代(特に後期世代)は年収の分布の上層の変化が少なく、下層が増加しており主要因は非正規雇用の影響。
・上記の影響は卒業後15年たっても解消しない。
・氷河期後期世代より下の世代以降でも非正規増加の影響が継続している。
・氷河期後期世代が産む子供数はむしろ増えている(個人レベルでは影響が出るようだが世代全体としては影響が出ていない)
景気と出生率の相関は総じて低いと考えられる。
・ 新卒時点では女性の方が就職氷河期世代の影響が大きいものの3年で解消。(ただ男女間の格差は変わらない)
・氷河期のインパクトには地域差があった(代表的には東海地区は受けにくく近畿地区はインパクト大きい)
概ねイメージと合ってはいたのですが今の格差のスタート地点がこの氷河期世代だったというような感じ。社会的にもこの氷河期世代を救い上げる試みもなされていますが40,50代に差し掛かっていることを考えるとひっさyの指摘にあるように今後のセーフネットのケアが必要なのかと思います。
自分はというと・・・大学院に進んだこともあり最終的な卒業は06年でこの氷河期の影響を直接受けることは無くある意味、恵まれてたのかとは思います。ただ会社の中での年齢層の構成とかひずみが生じていて景気によるものは致し方ないとは感じながら適材適所での活用の道筋を作っていく必要はあると感じます。











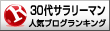

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます