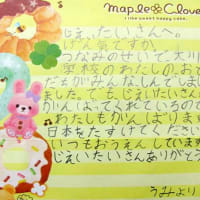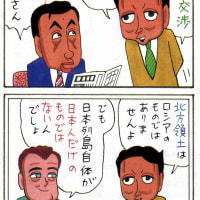慶応大学教授 竹中平蔵
2011/03/18 産経新聞
東日本大震災は、時間とともに深刻な被害状況が明らかになっている。歴史上類を見ないような大災害に当たり、日本社会全体の対応が世界の耳目を集めている。
これまで日本は民間人・現場の優れた対応に反し、政治・中枢部門の戦略的対応が劣っていることが何かにつけて指摘されてきた。今回も、各個人のモラルある行動や現場での秩序・相互扶助が海外メディアなどで紹介されている。こうした中で、今まさに、政府の対応が問われる局面となった。
これまでのところ、概(おおむ)ね過去の災害で蓄積された「マニュアル」に沿ったものとなっている。災害対策本部を立ち上げ、自衛隊を派遣、激甚災害指定などを行った。こうしたノウハウは官僚が十分に持っているが、政治の課題はこれらを十二分に活用しつつ、同時に随所で官僚の対応を超えた思い切った指示を発することだ。検証は今後行われようが、現時点では、(1)記者会見で質問に応じなかったなど総理の国民との対話が十分とはいえない(2)原子力発電所に関する説明が不明確(3)計画停電の発表が遅れその後も交通などの混乱を招いた-点を指摘しておこう。
≪絶対に誤ってならぬ原発対応≫
当面は、被害者の救出、避難者への支援、被害状況の把握が重要となる。また原発問題への対応は絶対に誤ってはならない。そのうえで、物資確保を含む国民生活への影響に注視しつつ復興へ対応することや経済政策が問われる。
マクロ的に見ると、今回の災害で経済には二つの変化が生じている。第一は東北地方を中心に生産“能力”が低下したこと、第二はそれに伴い現実の生産=所得が減少することだ。これは全国的なもので、首都圏で通勤困難となり生産活動が減退していること、部品調達が困難になり他地域の製造工場が休業に追い込まれていることなど現実化している。実際、首都圏のスーパーやコンビニでも目に見えて品不足が広がってきた。
需要面では二つの力が働く。所得減で消費・投資が鈍る半面、緊急支出としての消費・投資が進んで、いわば特需が生じることだ。結論からいうと、短期的には特需が生まれるが、中期的には減収で需要も縮小する可能性が高い。
≪対策費、阪神大震災の3倍超す≫
こうした中、当面の政策として求められるのは救済・応急復興予算を遅滞なく計上、実行することだ。阪神淡路大震災の時、政府は3度の補正予算で3兆円を上回る予算を計上した。今回被害の全容が明らかでないので厳密な議論はできないが、大雑把(おおざっぱ)に見積もってもその3倍以上、10兆円を上回る規模の対策費が必要となろう。
激甚災害指定が行われた結果、国はインフラ復旧のための公共投資で、地方への助成を大幅に拡大することになる。民間への助成では私有財産への補償は難しいが、阪神大震災では瓦礫(がれき)撤去などギリギリの線で公的支出を行った。
今回も政治決断で踏み込んだ施策が必要だ。民間部門の復興にはもっぱら低利・無利子融資など政策金融を活用することになる。現政権は大きな政府を志向し、全て政府が直接関与する傾向があるが、地域の民間金融機関の活用など柔軟な対応が求められよう。
≪増税でなく国債増発で対応を≫
財源調達手段として、国民に一定の負担を求める構想、つまり増税案が浮上している。だが、所得が少なくなる国民にさらに負担を求めるのは経済の論理に反する。今回のような場合こそ、国債増発で対応すべきである。ばらまきと批判の強い子ども手当などをこの際思い切って棚上げし災害対策に振り向ける政治決断が必要だ。
増税以前に行うべき政策として寄付の控除拡大も挙げられる。国民の高いモラルと連帯意識を考えれば、税制上の考慮で、相当額の寄付が集まると考えられる。その分、税収減となるが、資金に余裕のある人からの調達であり、そうでない人にも負担を課す増税よりはるかに優れた措置といえる。
経済正常化後に国民負担を求める、いわば「つなぎ国債」のような工夫はあり得よう。今回の教訓を生かした長期的な対応策もとる必要があり、リスク管理の検証チームを現段階から機能させておくことも、あってしかるべきだ。
当面の問題は、以上の措置をいつどんな形で実施するかだ。本来なら速やかな補正予算で対応すべきだが、補正予算を組むにしても2週間程度の時間が必要であり、年度末であることを考えると、審議中の来年度本予算との関連が出てくる。与党は本予算を通したうえでの補正予算編成を主張、野党は本予算の組み替えを求める。
政局より国民生活を優先する観点でいえば、子ども手当の一時棚上げなど大幅な予算組み替えで対応するのが望ましかろう。少なくとも、こうした選択肢の検討を首相は急ぎ指示すべきではないか。その際、使途を定めず国庫債務負担行為(契約など)を可能にする「ゼロ国債」も考慮に値しよう。
優れた民間の現場と非効率な政府の中枢管理…。こうした日本への評価を払拭できるのか、政治指導者たちの奮起が求められる。
2011/03/18 産経新聞
東日本大震災は、時間とともに深刻な被害状況が明らかになっている。歴史上類を見ないような大災害に当たり、日本社会全体の対応が世界の耳目を集めている。
これまで日本は民間人・現場の優れた対応に反し、政治・中枢部門の戦略的対応が劣っていることが何かにつけて指摘されてきた。今回も、各個人のモラルある行動や現場での秩序・相互扶助が海外メディアなどで紹介されている。こうした中で、今まさに、政府の対応が問われる局面となった。
これまでのところ、概(おおむ)ね過去の災害で蓄積された「マニュアル」に沿ったものとなっている。災害対策本部を立ち上げ、自衛隊を派遣、激甚災害指定などを行った。こうしたノウハウは官僚が十分に持っているが、政治の課題はこれらを十二分に活用しつつ、同時に随所で官僚の対応を超えた思い切った指示を発することだ。検証は今後行われようが、現時点では、(1)記者会見で質問に応じなかったなど総理の国民との対話が十分とはいえない(2)原子力発電所に関する説明が不明確(3)計画停電の発表が遅れその後も交通などの混乱を招いた-点を指摘しておこう。
≪絶対に誤ってならぬ原発対応≫
当面は、被害者の救出、避難者への支援、被害状況の把握が重要となる。また原発問題への対応は絶対に誤ってはならない。そのうえで、物資確保を含む国民生活への影響に注視しつつ復興へ対応することや経済政策が問われる。
マクロ的に見ると、今回の災害で経済には二つの変化が生じている。第一は東北地方を中心に生産“能力”が低下したこと、第二はそれに伴い現実の生産=所得が減少することだ。これは全国的なもので、首都圏で通勤困難となり生産活動が減退していること、部品調達が困難になり他地域の製造工場が休業に追い込まれていることなど現実化している。実際、首都圏のスーパーやコンビニでも目に見えて品不足が広がってきた。
需要面では二つの力が働く。所得減で消費・投資が鈍る半面、緊急支出としての消費・投資が進んで、いわば特需が生じることだ。結論からいうと、短期的には特需が生まれるが、中期的には減収で需要も縮小する可能性が高い。
≪対策費、阪神大震災の3倍超す≫
こうした中、当面の政策として求められるのは救済・応急復興予算を遅滞なく計上、実行することだ。阪神淡路大震災の時、政府は3度の補正予算で3兆円を上回る予算を計上した。今回被害の全容が明らかでないので厳密な議論はできないが、大雑把(おおざっぱ)に見積もってもその3倍以上、10兆円を上回る規模の対策費が必要となろう。
激甚災害指定が行われた結果、国はインフラ復旧のための公共投資で、地方への助成を大幅に拡大することになる。民間への助成では私有財産への補償は難しいが、阪神大震災では瓦礫(がれき)撤去などギリギリの線で公的支出を行った。
今回も政治決断で踏み込んだ施策が必要だ。民間部門の復興にはもっぱら低利・無利子融資など政策金融を活用することになる。現政権は大きな政府を志向し、全て政府が直接関与する傾向があるが、地域の民間金融機関の活用など柔軟な対応が求められよう。
≪増税でなく国債増発で対応を≫
財源調達手段として、国民に一定の負担を求める構想、つまり増税案が浮上している。だが、所得が少なくなる国民にさらに負担を求めるのは経済の論理に反する。今回のような場合こそ、国債増発で対応すべきである。ばらまきと批判の強い子ども手当などをこの際思い切って棚上げし災害対策に振り向ける政治決断が必要だ。
増税以前に行うべき政策として寄付の控除拡大も挙げられる。国民の高いモラルと連帯意識を考えれば、税制上の考慮で、相当額の寄付が集まると考えられる。その分、税収減となるが、資金に余裕のある人からの調達であり、そうでない人にも負担を課す増税よりはるかに優れた措置といえる。
経済正常化後に国民負担を求める、いわば「つなぎ国債」のような工夫はあり得よう。今回の教訓を生かした長期的な対応策もとる必要があり、リスク管理の検証チームを現段階から機能させておくことも、あってしかるべきだ。
当面の問題は、以上の措置をいつどんな形で実施するかだ。本来なら速やかな補正予算で対応すべきだが、補正予算を組むにしても2週間程度の時間が必要であり、年度末であることを考えると、審議中の来年度本予算との関連が出てくる。与党は本予算を通したうえでの補正予算編成を主張、野党は本予算の組み替えを求める。
政局より国民生活を優先する観点でいえば、子ども手当の一時棚上げなど大幅な予算組み替えで対応するのが望ましかろう。少なくとも、こうした選択肢の検討を首相は急ぎ指示すべきではないか。その際、使途を定めず国庫債務負担行為(契約など)を可能にする「ゼロ国債」も考慮に値しよう。
優れた民間の現場と非効率な政府の中枢管理…。こうした日本への評価を払拭できるのか、政治指導者たちの奮起が求められる。