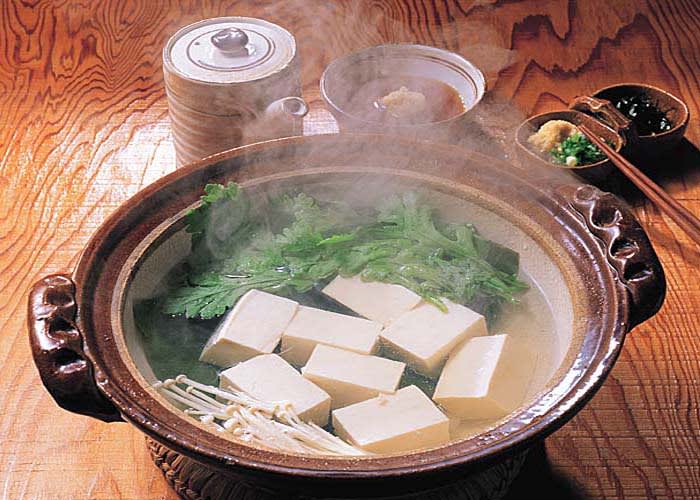***
週末コラム 4
***

私のもう一つのブログmy Favorites photoで
写真ネタが不足したり、話題に困ると書いている
子供のころから好きだったお菓子にまつわる話
名前が一緒なのに呼び方が違うものがあります
そこで週末コラムのネタもないことから
「同じ呼び名なのに~~~」について~書いてみました
私の好きなお菓子にマドレーヌがあります
スタッフと話をしていて気がついたことですが
話の内容がかみ合わないことがあって・・
それは形が違うことだった
マドレーヌといえば、スタッフたちは「貝」
私は「菊」の形を想像しながらの話
名前が同じで、味も一緒、でも見た目が違う
そんなお菓子がこの世には存在します
本来貝の形をしていたマドレーヌが日本では菊形に
それはパン・ド・ジェーヌと混同したためだそうです
菊型のマドレーヌにアーモンドスライスが乗っているのはその影響
マドレーヌは聖ヤコブのシンボルの帆立て貝がもととされています
しかし日本では丸く菊型でも同じ名前です

他にも、私の好きなお菓子に「ワッフル」があります
これも名前が同じで、味も一緒なのに見た目が違います
もともとはベルギーのお菓子です
格子状のワッフルを説明するときはベルギーのワッフルと
言った方が間違いなさそうですね(笑)
でも丸い形のワッフル自体が独特なんですけどね

下の別ブログ名前をクリックすれば移動します
ぱふぱふの別館 ① 「my Favorites photo」 入口