姫神の伝承と前方後方墳
↓現地案内版より

2003年の調査では、
葺石の状況から周壕がめぐる全長78m~約80mの滋賀最大級の前方後方墳である事が確認されました。
出土土器から、何と意外にも、3世紀後半~4世紀前半の築造と推定されている立派な前方後方墳です。
↓細長い前方部が魅力的です。

↓後方部の墳丘の裾部は円墳と間違えやすい「地表」形状をしています。水田が曲がっています。

後方部の現況として鋭く盛り上る高塚になっています。墳丘上には社殿の址と思しき痕跡もあります。

遠望すると古墳の形状が大変魅力的に見えます。以下にも古様の古墳の雰囲気を伝えて魅力満点です。

平野部に築造された前方後方墳としては滋賀県下最大の墳丘と言う事になります。これは意外な驚き。
★発想の転換①!高月大森山の前方後方墳の紹介。
※大森古墳(山畑1号墳)
また前方後方墳が見学したくなった。旧滋賀県伊香郡高月町松尾山の丘陵先端「大森山切通の南」
1号墳は尾根上に分布する古墳群中唯一の前方後方墳で、全長62m、2002年の調査で後方部から庄内
式土器が出土し、三世紀前半の築造と見られ驚く。更にまた三世紀後半に後方部にさらに盛り土を
高くし、方形張り出し部を加え双方中円墳の様相に作り替えられているらしい事が解った。まさか?
こんな身近な長浜市に卑弥呼と同時代の特殊な墳丘があるとは驚きで近江国伊香郡と言う地域の歴史
的起源の古さに驚く。古墳と延喜式神社は違う時代の遺跡なのだが、往々にして集落においては祖先
の塚として遠い遠祖の神代の旧跡として解釈される場合もある。
↓大森古墳遠望 魅力的な古墳のたたずまいだ。現地見学は城郭と同じく、樹木のない冬期が最適だ!

★発想の転換②!更なる発想の転換。長浜市高月町の東柳野へ神社探訪。
仕事も仲間もツテもいない私。よるべなき孤独の身の私は東柳野を一人でに歩いた。神社が見えて
きたが石柱は明確に神社名が読めず見ずらかった。

社殿に到着すると正確に読めた。売比田神社である。ひめた神社と読むのだ。

売比田と書いて「ヒメタ」と読む事は正しく古い。何故ならば延喜式の原典にも項註して解説している。
もちろん比売多と書くのも正しい。現地神社はより古い神社名を用いたものだろう?もっとも売比田と書
いて「ヒメタ」と読む事に意味が深いと思われる。
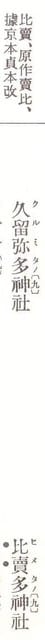
しかし売比田神社の相殿「あいどの」の久留美弥多神社「クルミタ」の名称には私は仰天して驚く!
「近江・若狭・越前 寺院神社大事典」には
売比多神社 ヒメタ神社
東柳野「近江国伊香郡/現長浜市」の青柳に鎮座する。 祭神豊玉姫命。相殿に久留弥多神「くるみたのかみ」を祀る。 「延喜式」神名帳の伊香郡「比売多神社」に、相殿「あいどの」は同じく「久留弥多神社」に比定される。
[中略]
相殿の久留弥多神は、唐川「旧近江国伊香郡高月町」日吉神社境内の観音堂に安置する平安時代作千手観音と菩薩像の足枘と像底に「久留弥多大明神」「御本地」と墨書(製作時より後世のもの)があり、両像が同神の本地仏であったことが知られる。 もとは唐川に鎮座していたが、天正年中(1573-92)兵乱に罹災し、売比多神社に合祀されたと伝える。
赤後寺
湧出山の南麓に鎮座する日吉神社の境内にあった寺で、現在は観音堂が残る。 行基の草創と伝え、最澄が聖観音像を納めたという。[中略]
堂内に安置する木造千手観音立像・木造菩薩立像は平安時代の作で、国指定重要文化財。 両像に「久留弥多大明神」「御本地」の墨書があり、式内社久留弥多神社の本地仏であったことが知られ、日吉神社を式内社に比定する説もある。
※さてさてややこしい 「御本地垂迹」ほんちすいじやく説が登場して頭がシビレルのだが?この久留弥多大明神が変化してやがて「ころり弥陀」と解釈されコロリカンノンへと解釈されたのであろうか?「微笑」
★発想の転換③!ころり転んで振りの出しの姫塚へ戻る
滋賀県神社庁の資料によると ※は長谷川解説
【延喜式神名帳】比売多神社 近江国 伊香郡鎮座
(旧地)売比多神社旧地
(合祀)久留弥多神社 ※A合祀とは併せて祀ると言う意味。
【現社名】売比多神社
【住所】滋賀県長浜市高月町東柳野1192
北緯35度28分17秒,東経136度12分50秒
【祭神】莵上壬命 (合祀)豊玉姫命 久留彌多神
【例祭】4月2日 例祭
【社格】旧村社
【由緒】由緒不詳
もとは姫塚古墳の地に鎮座※B比売多神社は元来姫塚古墳に鎮座していた。
応永年中現地へ遷
明治9年2月村社
【関係氏族】比売陀君
【鎮座地】当初鎮座の地は姫塚古墳(前方後円墳)が応永年中に現在の地に
【祭祀対象】氏祖
【祭祀】
【社殿】本殿銅板葺仏堂形式
拝殿・鐘楼
【境内社】
現社地の東南方に「へい塚」とも云う姫塚古墳があり、ここが旧社地であったとされる。
相殿に久留彌多神を祀る。※C 姫塚古墳は「へい塚」とも呼ばれていたこれは御幣の事であろう。
賣比多神社
伝によれば古事記に記すところの比売多君の氏族の本源の地でその祖神を祀り且つその墳塋を遺したものであると伝える。延喜式内社。
滋賀県神社庁
芭蕉句碑
正風宗師
八九間そらて雨ふる柳かな
『続猿蓑』(沾圃編)巻頭の句である。
正風宗師とは松尾芭蕉のことで、この句は元禄7年(1694年)芭蕉最晩年の春の句といわれる。
芭蕉は同年10月12日大阪で没した。
この句は柳が春雨に煙る情景を見て詠んだ句と言われている。
しとしと降る春雨が八九間の空から柳の糸を伝わってしたたるその雫を「空で雨ふる」と表現している。
八九間は陶淵明の漢詩から引用したもので、八間ないし九間の意味である。(一間は六尺=1.8m)
社頭掲示板
↓現地案内版より

2003年の調査では、
葺石の状況から周壕がめぐる全長78m~約80mの滋賀最大級の前方後方墳である事が確認されました。
出土土器から、何と意外にも、3世紀後半~4世紀前半の築造と推定されている立派な前方後方墳です。
↓細長い前方部が魅力的です。

↓後方部の墳丘の裾部は円墳と間違えやすい「地表」形状をしています。水田が曲がっています。

後方部の現況として鋭く盛り上る高塚になっています。墳丘上には社殿の址と思しき痕跡もあります。

遠望すると古墳の形状が大変魅力的に見えます。以下にも古様の古墳の雰囲気を伝えて魅力満点です。

平野部に築造された前方後方墳としては滋賀県下最大の墳丘と言う事になります。これは意外な驚き。
★発想の転換①!高月大森山の前方後方墳の紹介。
※大森古墳(山畑1号墳)
また前方後方墳が見学したくなった。旧滋賀県伊香郡高月町松尾山の丘陵先端「大森山切通の南」
1号墳は尾根上に分布する古墳群中唯一の前方後方墳で、全長62m、2002年の調査で後方部から庄内
式土器が出土し、三世紀前半の築造と見られ驚く。更にまた三世紀後半に後方部にさらに盛り土を
高くし、方形張り出し部を加え双方中円墳の様相に作り替えられているらしい事が解った。まさか?
こんな身近な長浜市に卑弥呼と同時代の特殊な墳丘があるとは驚きで近江国伊香郡と言う地域の歴史
的起源の古さに驚く。古墳と延喜式神社は違う時代の遺跡なのだが、往々にして集落においては祖先
の塚として遠い遠祖の神代の旧跡として解釈される場合もある。
↓大森古墳遠望 魅力的な古墳のたたずまいだ。現地見学は城郭と同じく、樹木のない冬期が最適だ!

★発想の転換②!更なる発想の転換。長浜市高月町の東柳野へ神社探訪。
仕事も仲間もツテもいない私。よるべなき孤独の身の私は東柳野を一人でに歩いた。神社が見えて
きたが石柱は明確に神社名が読めず見ずらかった。

社殿に到着すると正確に読めた。売比田神社である。ひめた神社と読むのだ。

売比田と書いて「ヒメタ」と読む事は正しく古い。何故ならば延喜式の原典にも項註して解説している。
もちろん比売多と書くのも正しい。現地神社はより古い神社名を用いたものだろう?もっとも売比田と書
いて「ヒメタ」と読む事に意味が深いと思われる。
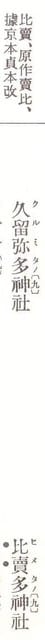
しかし売比田神社の相殿「あいどの」の久留美弥多神社「クルミタ」の名称には私は仰天して驚く!
「近江・若狭・越前 寺院神社大事典」には
売比多神社 ヒメタ神社
東柳野「近江国伊香郡/現長浜市」の青柳に鎮座する。 祭神豊玉姫命。相殿に久留弥多神「くるみたのかみ」を祀る。 「延喜式」神名帳の伊香郡「比売多神社」に、相殿「あいどの」は同じく「久留弥多神社」に比定される。
[中略]
相殿の久留弥多神は、唐川「旧近江国伊香郡高月町」日吉神社境内の観音堂に安置する平安時代作千手観音と菩薩像の足枘と像底に「久留弥多大明神」「御本地」と墨書(製作時より後世のもの)があり、両像が同神の本地仏であったことが知られる。 もとは唐川に鎮座していたが、天正年中(1573-92)兵乱に罹災し、売比多神社に合祀されたと伝える。
赤後寺
湧出山の南麓に鎮座する日吉神社の境内にあった寺で、現在は観音堂が残る。 行基の草創と伝え、最澄が聖観音像を納めたという。[中略]
堂内に安置する木造千手観音立像・木造菩薩立像は平安時代の作で、国指定重要文化財。 両像に「久留弥多大明神」「御本地」の墨書があり、式内社久留弥多神社の本地仏であったことが知られ、日吉神社を式内社に比定する説もある。
※さてさてややこしい 「御本地垂迹」ほんちすいじやく説が登場して頭がシビレルのだが?この久留弥多大明神が変化してやがて「ころり弥陀」と解釈されコロリカンノンへと解釈されたのであろうか?「微笑」
★発想の転換③!ころり転んで振りの出しの姫塚へ戻る
滋賀県神社庁の資料によると ※は長谷川解説
【延喜式神名帳】比売多神社 近江国 伊香郡鎮座
(旧地)売比多神社旧地
(合祀)久留弥多神社 ※A合祀とは併せて祀ると言う意味。
【現社名】売比多神社
【住所】滋賀県長浜市高月町東柳野1192
北緯35度28分17秒,東経136度12分50秒
【祭神】莵上壬命 (合祀)豊玉姫命 久留彌多神
【例祭】4月2日 例祭
【社格】旧村社
【由緒】由緒不詳
もとは姫塚古墳の地に鎮座※B比売多神社は元来姫塚古墳に鎮座していた。
応永年中現地へ遷
明治9年2月村社
【関係氏族】比売陀君
【鎮座地】当初鎮座の地は姫塚古墳(前方後円墳)が応永年中に現在の地に
【祭祀対象】氏祖
【祭祀】
【社殿】本殿銅板葺仏堂形式
拝殿・鐘楼
【境内社】
現社地の東南方に「へい塚」とも云う姫塚古墳があり、ここが旧社地であったとされる。
相殿に久留彌多神を祀る。※C 姫塚古墳は「へい塚」とも呼ばれていたこれは御幣の事であろう。
賣比多神社
伝によれば古事記に記すところの比売多君の氏族の本源の地でその祖神を祀り且つその墳塋を遺したものであると伝える。延喜式内社。
滋賀県神社庁
芭蕉句碑
正風宗師
八九間そらて雨ふる柳かな
『続猿蓑』(沾圃編)巻頭の句である。
正風宗師とは松尾芭蕉のことで、この句は元禄7年(1694年)芭蕉最晩年の春の句といわれる。
芭蕉は同年10月12日大阪で没した。
この句は柳が春雨に煙る情景を見て詠んだ句と言われている。
しとしと降る春雨が八九間の空から柳の糸を伝わってしたたるその雫を「空で雨ふる」と表現している。
八九間は陶淵明の漢詩から引用したもので、八間ないし九間の意味である。(一間は六尺=1.8m)
社頭掲示板









