第6話 メタエンジニアリングによる文化の文明化のプロセスの確立(その5)
2000年代の文化と文明に関する著書
2000年代に発行された文化と文明に関する13件の著書を列挙します。
この時代になると、インターネットの急速な普及により様々な専門家による多様な文明批判が交わされ始めた。その反面、情報の氾濫と、それをコントロールするアーキテクチャのあり方など、問題点も続出。
「レッシングは憲法学者として、物事を設計するための設計が存在することを指摘する。」(文献3)とか、「それはあたかも近代の合理主義への懐疑から、もう一度非合理的なものを見直そうという動向に合致したものであった。」(文献4)などの表現が続出し始めた。
この時期からは、「メタエンジニアリングによる文化の文明化のプロセスの確立」いう命題を設定した経緯とも関係が深まるので、文章の引用だけではなく、メタエンジニアリング的な感想やコメントを追加することにしました。特に、「物事を設計するための設計が存在する」(文献3)とは、エンジニアリングに対するメタエンジニアリングの位置を示したものにも捉える事ができるのです。
更に、比較文明学から導かれた、「正確には、真だけでは不十分、真と善だけでも不十分、真・善・美の三位一体を備えたものであってはじめて文明に値するということである」(文献5)との結論は、真=自然科学、善=哲学、美=芸術と大胆に置き換えると、その合体により新たなもの創造することは、まさにメタエンジニアリングの基本機能となっている。
また、西欧のルネッサンスが現代文明の基になったとのことから「ガリレオは学者であると同時に職人(技術者)だった。デカルト、ダビンチも同じ、知識人がものに触れていた。職人的伝統と学者的伝統が市民社会で結合した」(文献5)との説には、現代の科学・技術の極端な専門分化と、原子力村という表現の如き、明らかな市民生活との乖離への反省をともなう、ルネッサンスへの回帰が次の文明へのプロセスであることを暗示している。
1.藤原正彦「この国のけじめ」文芸春秋2006 (MMB219)
・「情報軽視、お人好しの日本の悲劇」
ところが近代となり、日本が生き馬の目を抜くような国際社会に投げ出されると、これが国益を大いに損ねる原因となった。現実よりも精神を上位におく、という民族的美徳が、強固な精神さえあれば現実を変えうる、何事もなしうる、という精神原理主義に飛躍したのである。そして、信じたくない現実には目をつぶり、信じたくない情報には耳をふさぐ、という態度にまでつながった。世界は自分や国益のことしか考えない小人ばかりだから、当然つけいられることとなった。
2.藤原正彦「藤原正彦の日本国民に告ぐ」文芸春秋(2001.7)
「一学究の救国論」との副題で始まるこの寄稿は、26頁およぶ長いもので、中間には彼のかなり右傾化した考えが一方的に主張されており、全面的には共感できないのだが、彼の日本文化に対する洞察は、著書の「国民の品格」に示されたように定評が高いので、その部分に限って引用し、メタエンジニアリング的な感想を付け加えてみよう。
冒頭は、次の文章で始まる。
・日本が危機に立たされている。何もかもがうまくゆかなくなっている。経済に目を向けると、・・・、政治に目を向ければ相変わらずの・・・、自国の防衛さえ、・・・、
・全文の構成は次のように組まれている。
「誰もがモラルを失いつつある国」 ( )は、本論と関係が薄い部分。
・独立文明を築いた日本
・現代知識人の本能的自己防衛
・外国人を魅了した日本文化の美徳とは何か
(・アメリカによる巧妙な属国化戦略)
(・魂を空洞化した言論統制)
(・法的な根拠を欠くアメリカの言い分)
(・二つの戦争は日本の侵略だったか)
(・事実上の宣戦布告だったハル・ノート)
(・独立自尊のための戦争は不可避だった)
・日本が追求した穏やかで平等な社会
・日本文化が持つ普遍的価値
・「過去との断絶」「誇り」を回復せよ
3.宮台真司「21世紀の現実―社会学の挑戦」ミネルヴァ書房2004 (KMB076)
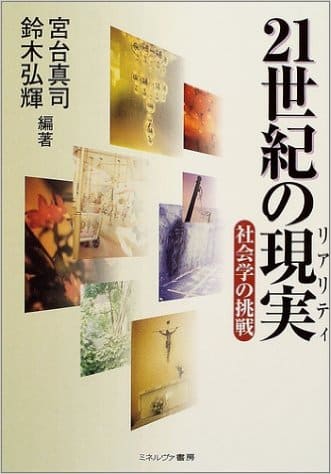
・「インターネット技術の文化的前提」
「所有」が個人に紐づけられる資本主義社会を前提として生きてきた人にとっては、コンピュータやプログラムはコミュニティーの所有物であるという感覚は新鮮なものだったのかもしれない。
こうしたコミュニティーへの貢献のためにプログラムソースを改編する人たちが、いわゆる「ハッカー」であった。今ではコンピュータに不正に侵入して悪さをする人だと捉えられがちだが、普通はそういう人たちのことは「クラッカー」という。
・インターネットとコンピュータがあらゆるものごとの中心に据えられるようになってきた社会では、OSやソフトウエアは単なる商品ではなく、公的なサービスのインフラとして機能するからだ。ということは、例えば行政サービスに商用のあるソフトウエアを採用することで寡占状態が発生するだけでなく、サービスそのものが一企業の裁量に任されるという事態を呼び起こしかねない。
・「アーキテクチャと設計の思想」
レッシグによれば、個人の振る舞いをコントロールする手法は4つあるそれが「規範」「法」「市場」「アーキテクチャ」である。アーキテクチャによるコントロールとは、個人ではなく個人の環境を設定することで間接的に個人の振る舞いを規制する手段である。
レッシグが問題と考えるのは以下の2点だ。アーキテクチャによるコントロールはそれに従うものにとって意識されにくく、「コントロールされている」という不自由感を味わうことが少ないということ。これはアーキテクチャをいじればユーザーに気付かれることのないままコードの記述者の思い通りにユーザーをコントロールできるということを意味する。第2の問題点は、現実の社会の基幹的な部分にネットやコンピュータが入り込んでくると、ネットの外でさえもコードの記述の仕方によって完全にコントロール可能になってしまうことだ。
・「設計の思想、選択すべき価値の不在」
絶望的なかかる状態に対してレッシングが考える処方箋は「設計の思想を問う」というものだ。レッシングは憲法学者として、物事を設計するための設計が存在することを指摘する。例えば、憲法であれば、その意義は国民に対する義務を記述することではなく、法律や行政など国民に対する命令がどのように記述されなければならないかという「統治権力に対する義務」を記述することにある。そこで行われているのは、憲法の記述によって社会をどのように設計するか、といゆ「価値」を選択するという振る舞いだ。それゆえにレッシングは、アーキテクチャのような完全な管理が可能なテクノロジーを前にして、アメリカ国民がそもそもどのような「価値」を選択したなか、その「設計の思想」を思い起こせと主張するのである。
・「社会学からの全体性の脱落」
今日の社会学から「全体性」が失われて久しい。個別領域への穴籠りが進み、異なる穴の住民同士では言葉さえ通じにくくなった。それに並行して、過去三十年間、なだらかに一般理論志向が失われて、理論社会学は低迷している。むろんこれは社会学だけの問題ではない。経済学や政治学からも・・・。
この全「体性の脱落」は、あらゆる分野で進行した。特に、学術の分野では「個別領域への穴籠り」でないと、論文として認められ難いという、基本問題が存在する。技術(エンジニアリング、設計)の場でも同様なのだが、その弊害はこの分野が、直接に日中生活に影響を与えるので恐ろしい。したがって、我田引水ですが、「メタエンジニアリングのすすめ」なるわけです。
4.京都国立博物館・他編集「弘法大師入唐1200年記念 空海と高野山」NHK大阪放送局(2003)

本書は、2003年に京都国立博物館を初めとして全国的に行われた展覧会の図録である。335頁の大型本で解説が充実している。その中から、末木文美士(東大教授)の「空海と日本の密教」から引用する。
・近代の研究者によって、密教は仏教の中でも前近代的なものとして否定的に見られることが多かった。近代の日本は、西欧に追いつくことを至上命令としてきたが、仏教界でも近代性にかなったプロテスタント的な要素が重視された。具体的に言えば、いわゆる鎌倉仏教、即ち、法然や親鸞の浄土教、道元の禅、そして日蓮らがもっとも日本仏教を代表する高い水準の仏教であり、密教は彼らのよって否定されて、克服されるべきものと考えられた。鎌倉仏教の祖師たちが単純で明快な実践を説いたのに対し、密教は複雑な儀礼と呪術の集合体であり、到底近代的な合理主義の批判に耐えられないものとみなされた。密教ブームが起こってその再評価が進んだのはやっと1980年代からのことである。それはあたかも近代の合理主義への懐疑から、もう一度非合理的なものを見直そうという動向に合致したものであった。
5.川勝平太「文化力 日本の底力」ウエッジ(2006)KMB002&346
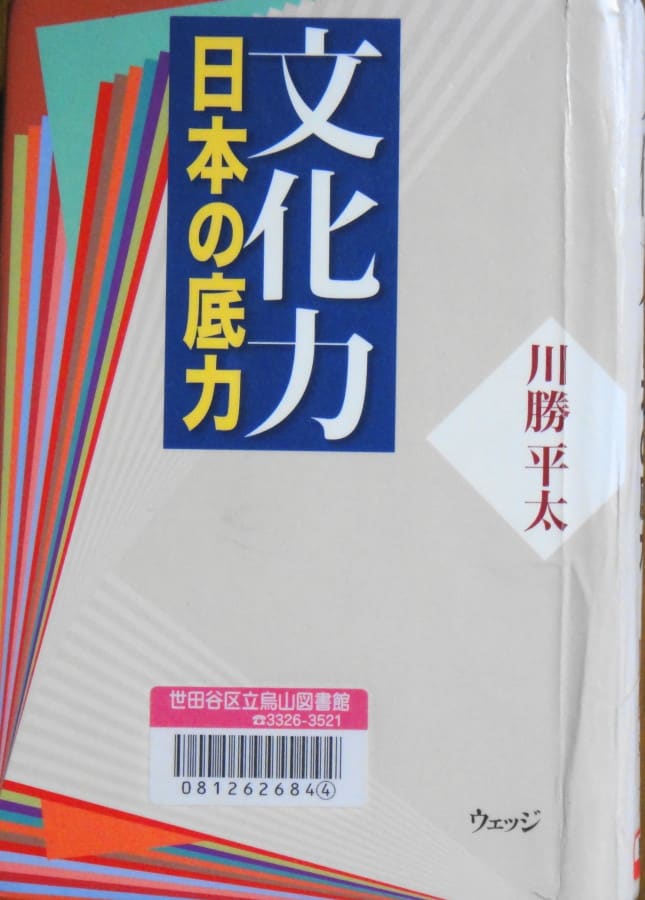
(1)日本的な融合をする・ハイブリッド文化
・パックスヤポニカ
日本史における平安時代の250年間と、江戸時代の270年間の平和な時代を指す。
戦後の日本の60年間が、第3のパックスヤポニカになり得るのだが、・・。
パクス(Pax)は、ラテン語の「平和の女神」。
この時代は、人口が定常状態になる傾向にある。すなわち、「女のルネッサンス」。
地球環境問題における立脚すべき価値は何か?
⇒「美」⇒地球は美しいか
西洋社会の価値観は、真⇒善⇒美
日本文化の価値観は、美⇒善⇒真 とは逆である。
・縄文文化や江戸文化への見直し論。
・17世紀以降の科学革命の時代は、初めは「真」だったが、21世紀になって「善」への移行が見られる。
・文化力の時代
1985のプラザ合意から始まった。⇒円高、ドル安の要請 ⇒日本の資金が米国に流れる
⇒日本が豊かになる
文化の元義は、「文を以て、人民を教化する」⇒文化大革命
文化力とは、「美の文明」になること、へ。
Culture= way of life、生き方、暮らし方
・日本文明論
唯物史観から格物史観へ
唯物史観は、生産する人間の社会関係を重視
「格物」は、「大学」の言葉、ものにいたる、ものをただすの意味。
・格物致知 意味(GOO辞典より)
物事の道理や本質を深く追求し理解して、知識や学問を深め得ること。『大学』から出た語で、大きく分けて二説ある。宋の朱熹は出典を「知を致いたすは物に格いたるに在り」と読んで、自己の知識を最大に広めるには、それぞれの客観的な事物に即してその道理を極めることが先決であると解釈する。一方、明(みん)の王守仁(おうしゅじん)(王陽明)は「知を致すは物を格ただすに在り」と読んで、生まれつき備わっている良知を明らかにして、天理を悟ることが、すなわち自己の意思が発現した日常の万事の善悪を正すことであると解釈している。他にも諸説ある。▽「致知格物ちちかくぶつ」ともいう。
・格物史観は、デカルト以来の「もの」と「こころ」の二分を一体化させるもの。
万物には、神が宿る。
「日にその物をみてすなわち心を入れ、心にその物を通じ、物通してすなわちいう」(空海)
・戦国時代に世界最大の鉄砲製造・使用国だった日本が、なぜ江戸時代は刀の時代になったのか?
⇒審美感、西欧(特に現代の米国)との違い
・主たる食器が、金属器や木器から陶磁器になった。この事実は、西洋科学文明化らは出て来ない。
・科学革命から、人間革命・環境革命へ
・神仏習合
文字に書かれなかった縄文の自然信仰と文字に書かれた仏教信仰
無文字文化と文字文化の融合
(2)伊東俊太郎との対話
・8~9世紀のアラビア・ルネサンス ユークリッド・アルキメデス・アリストテレス等のギリシャの科学書の翻訳
・12世紀のアラビヤ語からラテン語への翻訳
専門用語の語源はアラビヤ語で残った(代数学のアルジェブラ)
スペインのトレドでヨーロッパ人に伝達 & 1453コンスタンチノーブル陥落でビザンチンの学者がイタリアに亡命
・イタリア・ルネッサンスへ
相互交流を通じてアイデンティティーが豊かになる(川勝)
・なぜ科学革命だけがヨーロッパに限定されているのか?
伊東俊太郎の考え
① ギリシャ科学の伝統が中国やインドに伝わらなかった
② 市民社会の成立によるマーケットの拡大
③ ガリレオは学者であると同時に職人(技術者)だった
デカルト、ダビンチも同じ、知識人がものに触れていた
職人的伝統と学者的伝統が市民社会で結合した
アリストテレスはどんな実験をしましたか。実験はギリシャでは十分でなかった、観察はしたが実験はなかった
④ 17世紀のヨーロッパは貧しかったし、気候も悪い。外へ出たいと外へ出たいと
東はオスマントルコなので、西へ出た ⇒大航海時代
6.川勝平太「美の文明をつくるー力の文明を超えて」ちくま書房(2002) KMB355
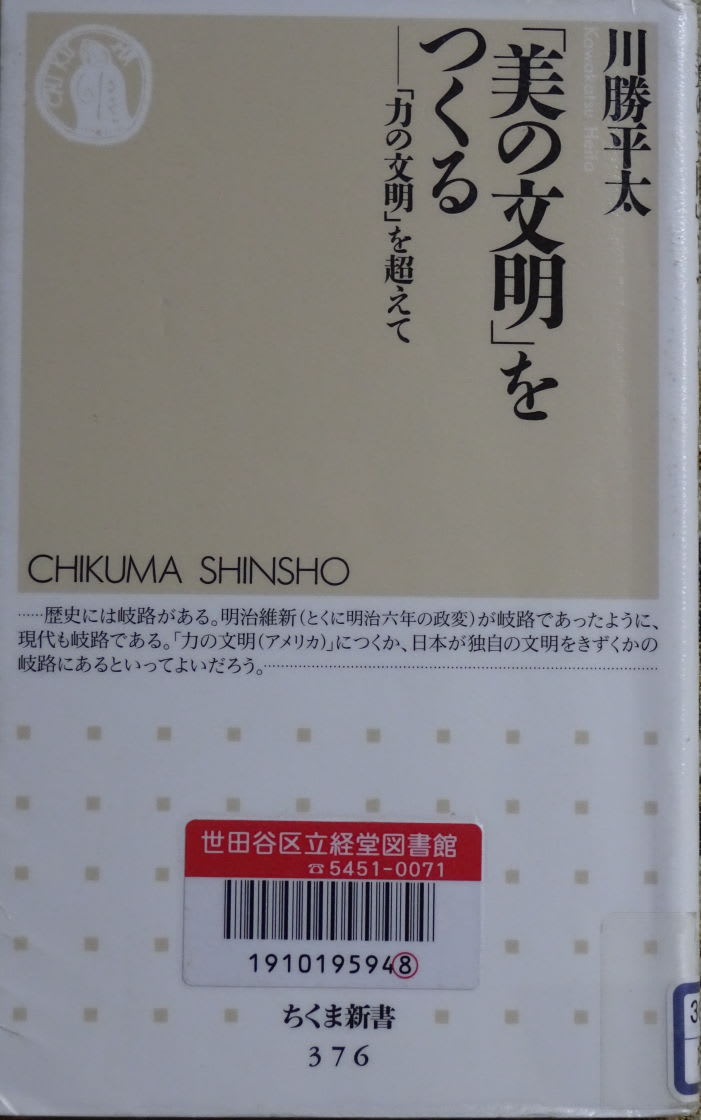
川勝氏は、オクスフォード大学の哲学博士の称号を持つ比較経済史の専門家と云われているが、私は、比較文明学会の役員としての著書に興味を覚えた。
この著書は、プロローグが意味深い。「日本の明日を考える」と題して、次の文章で始まる。
・戦後半世紀の内外の日本論の基調は「日本文化論」であった。しかし、これからの日本論の基調は「日本文明論」になるとみこまれる。地球環境を意識した新しい国づくりと連動して、未来志向的な性格を帯びた文明論になるだろう。未来志向であることによってそれは実践論となり、国民運動ともなって、日本を一新するだろう。
・この著書では、内外の多くの文献がリファーされている。全てを紹介できないが、いくつかを挙げてみる。
・ルース・ベネディクトの「菊と刀」からは、「欧米の罪の文化と日本の恥の文化、欧米の個人主義と日本の集団主義」
・ジョン・ダワーの「敗北を抱きしめて」からは、「戦後から立ち直ってゆく戦後の日本人の精神文化が、(中略)膨大な資料によって検証し、「日本人は特殊だ」という思いこみをしりぞけた。日本異質論は90年代に入って下火になったのである。」
・ハンチントンの「文明の衝突」からは、「地域政治では民族が中心になって民族紛争が生じ、世界政治では文明が中心になって文明の衝突が起こることを予想した。予想はほぼ的中している。ハンチントンは文明を八つあげている。その一つが日本文明である。
・西郷隆盛の「西郷南州の遺訓」からは、「文明ならば、未開の国に対しなば、慈愛を本とし、懇々と説論して開明に導くべきに、さはなくして未開蒙味の国に対するほど、むごく残忍のことを致し、おのれを利するは野蛮だと申せしかば、その人口をつぼめて言無なかりきとて笑われける。」
・湯川秀樹博士の「人間にとって科学となにか」からは、「私は自分の専門の物理学でも、ある法則なり論理体系なりを宜しいと納得するときは、そこになにか美しいものを感じ、・・・ある種の美意識や好悪感がある」
などを挙げている。そして、
文化には反対語がない。文明には負の価値をもつ野蛮という反対語がある。「力の文明」を超えて「美の文明」をつくりあげることをもって日本の文明の道(civilized way)としてよいのではないか。
で結んでいる。
本文の第1章では、次の言葉がある。
・科学法則は応用ができる。科学が技術と結びついて十八世紀に産業革命が始まった。その結果、はやくも十九世紀にはいると、機械技術を悪の権化として、機械を打ち壊すラッダイト運動がおこった。機械打ち壊し運動はイングランド中・北部でとくに激しく、一八一〇年代に頂点に達した。
富を公平に分配する平等を正義とする人々と、富を獲得する自由を正義とする人々の争いとなり、・・・。(中略)司馬遼太郎はそれ(イデオリギー)を「正義の体系」と言いかえていた。(中略)自由をもって正義と信じる集団と、平等をもって正義の体系と信じる集団とに分かれたのである。
・地球環境保全とは、「地球を汚してはならない」と云うことである。汚さないというのは、価値としては「美」に立脚している。(中略)正確には、真だけでは不十分、真と善だけでも不十分、真・善・美の三位一体を備えたものであってはじめて文明に値するということである。
このように論理を辿ると、やはり文化の文明化のプロセスとしては、メタエンジニアリングの応用が最も適しているように感じらてくる。
7.梅棹忠夫、「近代世界のおける日本文明、比較文明学序説」中央公論新社 (2000) KMB077

国立民族学博物館で1982年から1998年まで開催された谷口国際シンポジウム文明学部門での梅棹忠夫氏の基調講演の内容が纏められているものだ。
第10回のテーマは「技術の比較文明学」であり、その中で興味深い記述がいくつかあったので、メタエンジニアリングの研究の一部として考察を試みる。
その前に、比較文明学について少し触れておこう。梅棹は、「比較文明学というような学問領域は、純粋に知的な興味の対象になり得ても、どのような意味でも、実用的な、あるいは、実際的なものにはならないであろう」と言い切っておられる。なんと工学と対照をなす領域ではないか。
文明と文化の関係についての見方は、「時間的な前後関係をもつものと考えてよいのかどうか、すこし違った見方をしています。文化というものは、その全システムとしての文明のなかに生きている人間の側における、価値の体系のことである。」としている。また、システム学とシステム工学の違いを、「システム工学は目的があるけれども、システム学は必ずしも目的を持っていない。「目的なきシステム」というものもあるのではないか」と記している。
8.関、中澤、丸山、田中共著「環境の社会学」有斐閣(2009)
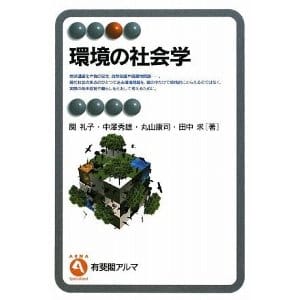
・「冒頭の言葉」
環境の社会学は、私たちがこの時代に、この社会の中に生きているということの意味を問うための学である。環境を考えることは生き方を考えることである。
社会学での言葉に「目的移転」という表現がある。「いったん技術とか制度が安定すると、それらの手段を使って達成するはずだった目的がどこかへ行ってしまい、手段の維持をめぐる問題にエネルギーがそそがれるということになりやすい。」ということなのだ。
一般に、リスクが見つかる度に、それを新たな科学技術によって抑え込むと云うのが、20世紀後半の社会がとってきたやり方である、と社会科学者が指摘をする。しかし、原因が地球単位で複雑化をすると、自然科学者は不確実な予測を出さざるをえなくなる。そこからエンジニアリングのジレンマが始まっているのだ。
・「国的移転」とは、エンジニアリングでは、手段の目的化と云えることなのだろう。実は、エンジニアリングの世界ではこのことが頻繁に起こっているのではないだろうか。目先の技術的な成果に集中してしまい、本来の大目的からそれてしまうことがしばしば見受けられる。このことは、過去の環境問題ではしばしば見受けられたことであり、環境問題が社会学への傾倒となった一つの原因であったように思えてくる。
・工学から社会学への主役の移動について、なぜそうなったかを考えてみる。この著書には、「信用されなくなった専門家たちは、「科学的知識が足りない」「ゼロ・リスク症候群にかかっている」といって大衆を攻撃する。リスクについて述べる場合には、われわれはこう生きたい、という観点が入ってくるのである。リスクというのは煎じつめると価値観と文化の問題であるとの指摘が古くからある。」とある。これが、社会学から見た工学への見方になる。
・以前に、「物理学はなぜを問わない。なぜ万有引力が存在するのか。なぜ相対性原理があるのかは問わない。」と書いた書を紹介した。工学も近代機械文明の中にあっては、WhatとHowに夢中になり、次第にWhyが軽視されてきたように思える。そこに落とし穴があったようだ。
一方でメタエンジニアリングは、学問分野を超えた根本的な「なぜ」を問い直すことを一つの手段としている。
9.堺屋太一「東大講義録、文明を解く」講談社(2003)
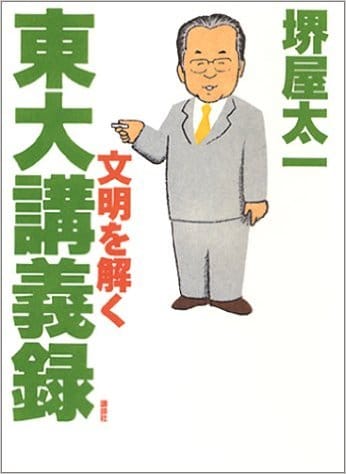
・これからの知価社会で経済閣僚は一体、何をすればいいか。第一は、市場の機能を保つ番人。
第二は、外部経済を内部化する。環境問題は典型です。公害をまき散らせばその分だけコストは安くできます。しかし、社会全体としては環境が悪化するという不経済が生じます。そのときに各企業に対してどのようなシステムによってこれをコスト負担させるか、つまり内部コストにするか。公害防止の技術や施設をつくらせ、産業廃棄物をきちんと処理させる、など外部経済を内部化することが必要になるでしょう。
10.日下公人「21世紀、世界は日本化する」PHP研究所(2000) KMB196

・日本から世界へ発信している文化が沢山ある
脱軍備、脱武器輸出、脱宗教、脱イデオロギー、経済第一、清潔第一、勤勉第一、陛下第一、少子高齢化、女尊男卑、民主主義、自由主義、家族主義、省エネ、巨大都市、教育の普及、知識と文化の尊重
11.中西輝政「国民の文明史」産経新聞社(2003) KMB083

・文明史観なき国家は、必ず滅ぶ。過去の歴史と未来の歴史をつなげてゆくもの、それが文明史である。文明史---それは、歴史をマクロな視野から、長いスパンで洞察する眼差しです。単なる歴史研究を超えた、一国を取り巻く文明全体の大きな流れを見極める目を持たないと、国家衰亡の危機には対処できません。グローバリゼーションの挑戦、国家観の喪失、教育の荒廃、治安の悪化、そして「危機」に気づかない国民精神の堕落…。
・文明の定義
① 文明とは、世界を構成する単位
② 文明は、国家や社会を動かす「活力の源)
③ 日本における、「文化」と「文明」の使い分けの問題
・世界の中の日本文明
現代の日本人の多くは、「日本文明」があったとしても、それは「中華文明と西欧文明の混合体のようなもの」だろう、と思っているかもしれないがそれこそまさしく「自虐的」文明史観といえよう。従来からの欧米の文明史家の間では、日本文明は、その独自性と体系性において、中華文明あるいはイスラム文明などと並んで、世界の主要文明の次の六たう、ないしは七つに分析している。
・90年代には「民間活力」とか「民でできることは民で」という言葉が口喧しく唱えられてきたが、このような「民間の力」の衰え、とりわけその技術応用力とそれへの強いコミットメントの減退は、つまるところ社会の創造性につながる知的・精神的な活力の低下に見いだすしかないのではないか。
・「短期の楽観、長期の悲観」は、滅びの構図
12.中西輝政「日本文明の興廃」PHP研究所(2006) KMB082

・文明史的岐路に立つ日本
今の日本人に必要なことは、文明的視野をもってこの時点を捉え直すことである。「文明的な視野」というのは、分かりやすくいえば、百年や二百年の単位ではなく、最低限千年の単位で考えるような歴史の視野である。千年の単位で見るならば、当然のこととして物質的なものはほとんど影をとどめない。問題になるのは、文化や国民の精神、民族性などというもの、つまり、「それがあったからこの国がずっと続いている」といえるような、「歴史を動かす精神的な核」である。
戦後の日本が「大いなる嘘」に立脚して出発せざるをえなかったということである。それは、誰もが知っていながら見過ごしてきた嘘であった。
かつて、日本にやってきた多くの西洋人が日本人の倫理性の高さを賞賛しているが、それを支えてきたのが、このような人としての美しさを重んじる「こころ」のあり様だったのである。しかし、その「こころ」自体が、「大きな嘘」で傷つけられてしまった。「まこと」を基調とする日本人の精神伝統つまり日本文明は、戦後という時代が遺した「嘘」と「賎め」の傷跡によって、いまその生命力を大きく全体させている。
13.松本健一「泥の文明」新潮社(2006) KMB384
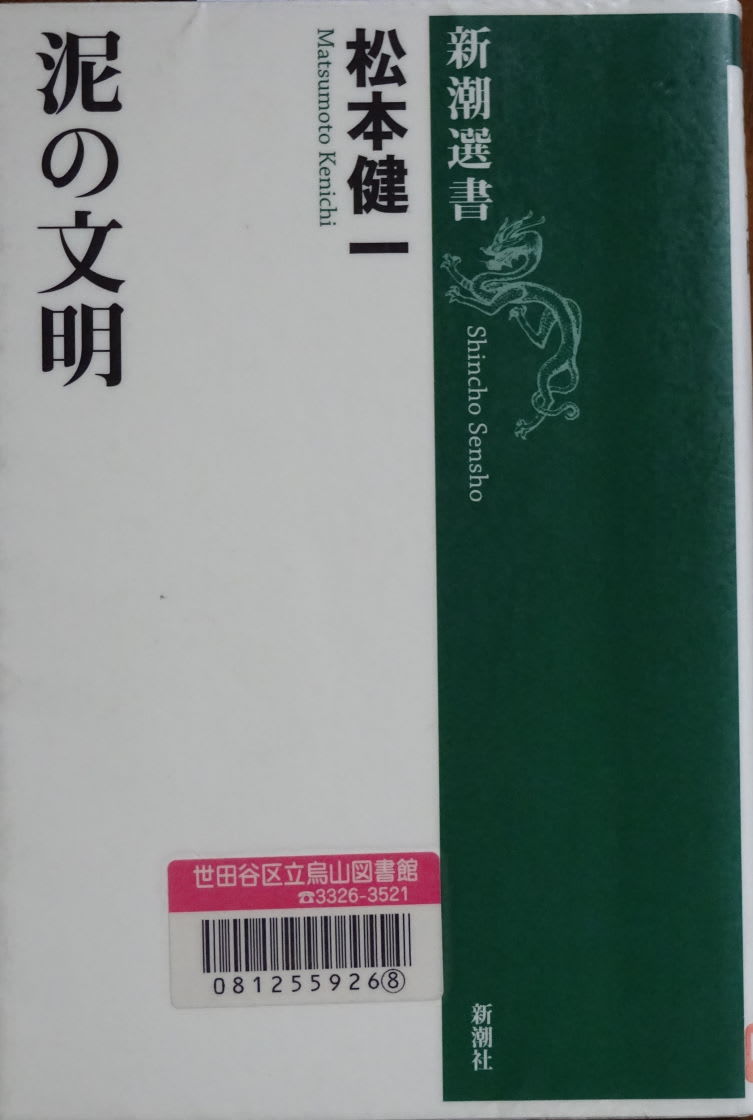
・泥の文明こそ、西欧文明が生んだ環境・人口問題を解決できる
世界は、「石」「砂」「泥」の三文明に分けることができる。「石の文明」すなわち西欧文明は「外に進出する力」を特徴とし、「砂の文明」であるイスラム文化圏は「ねーっとワークする力」が本質だ。そしてアジアに広がる「泥の文明」の本質は「内に蓄積する力」である。このアジア文明こそ、近代社会を牽引してきた「石の文明」の欠点を補える唯一の文明なのである。
・和辻が「モンスーンの風土」とよぶものと、わたしが「泥の文明」とよぶものは、「緑豊か」という点で共通する。しかし、和辻はその風土に「受容的・忍従的」な精神類型と文明が育つと説くのに対して、わたしがその「泥の文明」が「内に蓄積する力」をはぐくむと説いている。
わたしがその仮説を立てた根拠は何か、という点については、後に詳しく触れることにしよう。いま「モンスーンの風土」にしろ「泥の風土」にせよ、そこには農耕が主産業として成立するが、それによって生まれる民族の「エートス」(精神類型)なり文化の本質を、和辻は「受容的・忍従的」と捉え、わたしが「内に蓄積する力」と捉えている点に大いなる違いがある、ということのみ確認しておきたい。
・ヨーロッパの風土を和辻は「牧場」と捉えているが、それは松本も同じ。しかし、その牧場を20センチも掘れば石にぶち当たるので、松本は「一の文明」とするのである。そして牧畜がいかに広大な土地を必要とするかという話から、「石の文明」が「外に進出する力」を醸成するという話へとすすむ。それがヨーロッパ列強がアジア進出へとむすびつくのだが、この辺りの記述は、これまでのしゃかいがくの古典とされてきた大塚久雄の「共同体の基礎理論」をも論破して、迫力に富む。
・「もの作り」の文化
半導体の生産は欧米よりも、日本や韓国、台湾、中国、マレーシアなど、長年「田つくり」に微妙な精度と、その土から不純物を排除することに努力してきた国々ばかりである。更に触れたように、石川県たったかの山際に精確に作られ、水をゆっくりとすべての田に流してゆく棚田をみたソニーの技術者が、「これ(棚田)は半導体だ」と叫んだというエピソードを思い出さざるを得ない。
2000年代の文化と文明に関する著書
2000年代に発行された文化と文明に関する13件の著書を列挙します。
この時代になると、インターネットの急速な普及により様々な専門家による多様な文明批判が交わされ始めた。その反面、情報の氾濫と、それをコントロールするアーキテクチャのあり方など、問題点も続出。
「レッシングは憲法学者として、物事を設計するための設計が存在することを指摘する。」(文献3)とか、「それはあたかも近代の合理主義への懐疑から、もう一度非合理的なものを見直そうという動向に合致したものであった。」(文献4)などの表現が続出し始めた。
この時期からは、「メタエンジニアリングによる文化の文明化のプロセスの確立」いう命題を設定した経緯とも関係が深まるので、文章の引用だけではなく、メタエンジニアリング的な感想やコメントを追加することにしました。特に、「物事を設計するための設計が存在する」(文献3)とは、エンジニアリングに対するメタエンジニアリングの位置を示したものにも捉える事ができるのです。
更に、比較文明学から導かれた、「正確には、真だけでは不十分、真と善だけでも不十分、真・善・美の三位一体を備えたものであってはじめて文明に値するということである」(文献5)との結論は、真=自然科学、善=哲学、美=芸術と大胆に置き換えると、その合体により新たなもの創造することは、まさにメタエンジニアリングの基本機能となっている。
また、西欧のルネッサンスが現代文明の基になったとのことから「ガリレオは学者であると同時に職人(技術者)だった。デカルト、ダビンチも同じ、知識人がものに触れていた。職人的伝統と学者的伝統が市民社会で結合した」(文献5)との説には、現代の科学・技術の極端な専門分化と、原子力村という表現の如き、明らかな市民生活との乖離への反省をともなう、ルネッサンスへの回帰が次の文明へのプロセスであることを暗示している。
1.藤原正彦「この国のけじめ」文芸春秋2006 (MMB219)
・「情報軽視、お人好しの日本の悲劇」
ところが近代となり、日本が生き馬の目を抜くような国際社会に投げ出されると、これが国益を大いに損ねる原因となった。現実よりも精神を上位におく、という民族的美徳が、強固な精神さえあれば現実を変えうる、何事もなしうる、という精神原理主義に飛躍したのである。そして、信じたくない現実には目をつぶり、信じたくない情報には耳をふさぐ、という態度にまでつながった。世界は自分や国益のことしか考えない小人ばかりだから、当然つけいられることとなった。
2.藤原正彦「藤原正彦の日本国民に告ぐ」文芸春秋(2001.7)
「一学究の救国論」との副題で始まるこの寄稿は、26頁およぶ長いもので、中間には彼のかなり右傾化した考えが一方的に主張されており、全面的には共感できないのだが、彼の日本文化に対する洞察は、著書の「国民の品格」に示されたように定評が高いので、その部分に限って引用し、メタエンジニアリング的な感想を付け加えてみよう。
冒頭は、次の文章で始まる。
・日本が危機に立たされている。何もかもがうまくゆかなくなっている。経済に目を向けると、・・・、政治に目を向ければ相変わらずの・・・、自国の防衛さえ、・・・、
・全文の構成は次のように組まれている。
「誰もがモラルを失いつつある国」 ( )は、本論と関係が薄い部分。
・独立文明を築いた日本
・現代知識人の本能的自己防衛
・外国人を魅了した日本文化の美徳とは何か
(・アメリカによる巧妙な属国化戦略)
(・魂を空洞化した言論統制)
(・法的な根拠を欠くアメリカの言い分)
(・二つの戦争は日本の侵略だったか)
(・事実上の宣戦布告だったハル・ノート)
(・独立自尊のための戦争は不可避だった)
・日本が追求した穏やかで平等な社会
・日本文化が持つ普遍的価値
・「過去との断絶」「誇り」を回復せよ
3.宮台真司「21世紀の現実―社会学の挑戦」ミネルヴァ書房2004 (KMB076)
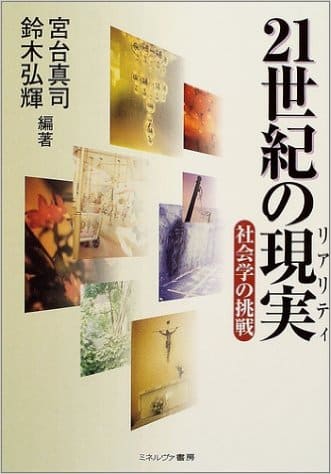
・「インターネット技術の文化的前提」
「所有」が個人に紐づけられる資本主義社会を前提として生きてきた人にとっては、コンピュータやプログラムはコミュニティーの所有物であるという感覚は新鮮なものだったのかもしれない。
こうしたコミュニティーへの貢献のためにプログラムソースを改編する人たちが、いわゆる「ハッカー」であった。今ではコンピュータに不正に侵入して悪さをする人だと捉えられがちだが、普通はそういう人たちのことは「クラッカー」という。
・インターネットとコンピュータがあらゆるものごとの中心に据えられるようになってきた社会では、OSやソフトウエアは単なる商品ではなく、公的なサービスのインフラとして機能するからだ。ということは、例えば行政サービスに商用のあるソフトウエアを採用することで寡占状態が発生するだけでなく、サービスそのものが一企業の裁量に任されるという事態を呼び起こしかねない。
・「アーキテクチャと設計の思想」
レッシグによれば、個人の振る舞いをコントロールする手法は4つあるそれが「規範」「法」「市場」「アーキテクチャ」である。アーキテクチャによるコントロールとは、個人ではなく個人の環境を設定することで間接的に個人の振る舞いを規制する手段である。
レッシグが問題と考えるのは以下の2点だ。アーキテクチャによるコントロールはそれに従うものにとって意識されにくく、「コントロールされている」という不自由感を味わうことが少ないということ。これはアーキテクチャをいじればユーザーに気付かれることのないままコードの記述者の思い通りにユーザーをコントロールできるということを意味する。第2の問題点は、現実の社会の基幹的な部分にネットやコンピュータが入り込んでくると、ネットの外でさえもコードの記述の仕方によって完全にコントロール可能になってしまうことだ。
・「設計の思想、選択すべき価値の不在」
絶望的なかかる状態に対してレッシングが考える処方箋は「設計の思想を問う」というものだ。レッシングは憲法学者として、物事を設計するための設計が存在することを指摘する。例えば、憲法であれば、その意義は国民に対する義務を記述することではなく、法律や行政など国民に対する命令がどのように記述されなければならないかという「統治権力に対する義務」を記述することにある。そこで行われているのは、憲法の記述によって社会をどのように設計するか、といゆ「価値」を選択するという振る舞いだ。それゆえにレッシングは、アーキテクチャのような完全な管理が可能なテクノロジーを前にして、アメリカ国民がそもそもどのような「価値」を選択したなか、その「設計の思想」を思い起こせと主張するのである。
・「社会学からの全体性の脱落」
今日の社会学から「全体性」が失われて久しい。個別領域への穴籠りが進み、異なる穴の住民同士では言葉さえ通じにくくなった。それに並行して、過去三十年間、なだらかに一般理論志向が失われて、理論社会学は低迷している。むろんこれは社会学だけの問題ではない。経済学や政治学からも・・・。
この全「体性の脱落」は、あらゆる分野で進行した。特に、学術の分野では「個別領域への穴籠り」でないと、論文として認められ難いという、基本問題が存在する。技術(エンジニアリング、設計)の場でも同様なのだが、その弊害はこの分野が、直接に日中生活に影響を与えるので恐ろしい。したがって、我田引水ですが、「メタエンジニアリングのすすめ」なるわけです。
4.京都国立博物館・他編集「弘法大師入唐1200年記念 空海と高野山」NHK大阪放送局(2003)

本書は、2003年に京都国立博物館を初めとして全国的に行われた展覧会の図録である。335頁の大型本で解説が充実している。その中から、末木文美士(東大教授)の「空海と日本の密教」から引用する。
・近代の研究者によって、密教は仏教の中でも前近代的なものとして否定的に見られることが多かった。近代の日本は、西欧に追いつくことを至上命令としてきたが、仏教界でも近代性にかなったプロテスタント的な要素が重視された。具体的に言えば、いわゆる鎌倉仏教、即ち、法然や親鸞の浄土教、道元の禅、そして日蓮らがもっとも日本仏教を代表する高い水準の仏教であり、密教は彼らのよって否定されて、克服されるべきものと考えられた。鎌倉仏教の祖師たちが単純で明快な実践を説いたのに対し、密教は複雑な儀礼と呪術の集合体であり、到底近代的な合理主義の批判に耐えられないものとみなされた。密教ブームが起こってその再評価が進んだのはやっと1980年代からのことである。それはあたかも近代の合理主義への懐疑から、もう一度非合理的なものを見直そうという動向に合致したものであった。
5.川勝平太「文化力 日本の底力」ウエッジ(2006)KMB002&346
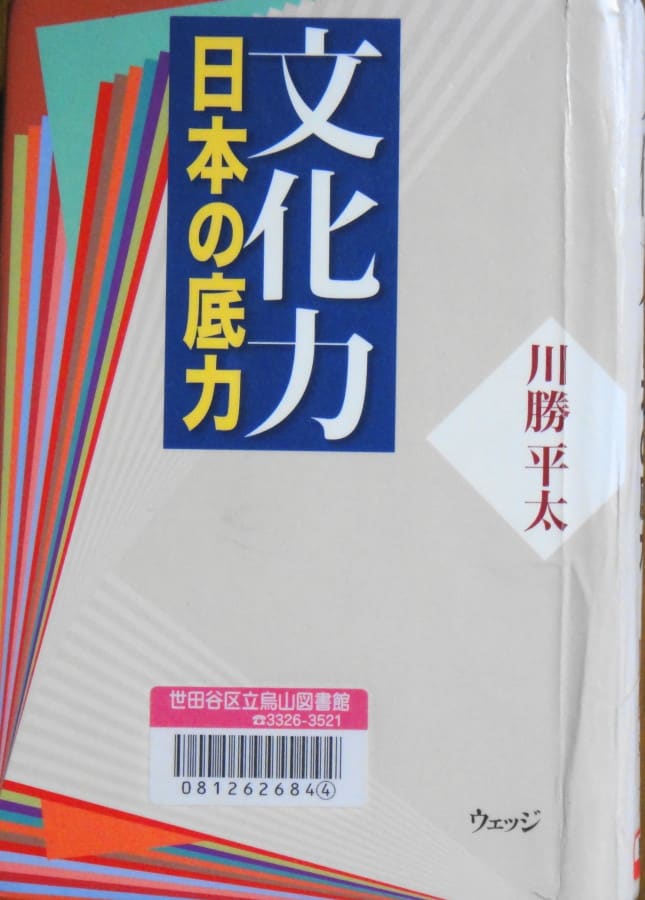
(1)日本的な融合をする・ハイブリッド文化
・パックスヤポニカ
日本史における平安時代の250年間と、江戸時代の270年間の平和な時代を指す。
戦後の日本の60年間が、第3のパックスヤポニカになり得るのだが、・・。
パクス(Pax)は、ラテン語の「平和の女神」。
この時代は、人口が定常状態になる傾向にある。すなわち、「女のルネッサンス」。
地球環境問題における立脚すべき価値は何か?
⇒「美」⇒地球は美しいか
西洋社会の価値観は、真⇒善⇒美
日本文化の価値観は、美⇒善⇒真 とは逆である。
・縄文文化や江戸文化への見直し論。
・17世紀以降の科学革命の時代は、初めは「真」だったが、21世紀になって「善」への移行が見られる。
・文化力の時代
1985のプラザ合意から始まった。⇒円高、ドル安の要請 ⇒日本の資金が米国に流れる
⇒日本が豊かになる
文化の元義は、「文を以て、人民を教化する」⇒文化大革命
文化力とは、「美の文明」になること、へ。
Culture= way of life、生き方、暮らし方
・日本文明論
唯物史観から格物史観へ
唯物史観は、生産する人間の社会関係を重視
「格物」は、「大学」の言葉、ものにいたる、ものをただすの意味。
・格物致知 意味(GOO辞典より)
物事の道理や本質を深く追求し理解して、知識や学問を深め得ること。『大学』から出た語で、大きく分けて二説ある。宋の朱熹は出典を「知を致いたすは物に格いたるに在り」と読んで、自己の知識を最大に広めるには、それぞれの客観的な事物に即してその道理を極めることが先決であると解釈する。一方、明(みん)の王守仁(おうしゅじん)(王陽明)は「知を致すは物を格ただすに在り」と読んで、生まれつき備わっている良知を明らかにして、天理を悟ることが、すなわち自己の意思が発現した日常の万事の善悪を正すことであると解釈している。他にも諸説ある。▽「致知格物ちちかくぶつ」ともいう。
・格物史観は、デカルト以来の「もの」と「こころ」の二分を一体化させるもの。
万物には、神が宿る。
「日にその物をみてすなわち心を入れ、心にその物を通じ、物通してすなわちいう」(空海)
・戦国時代に世界最大の鉄砲製造・使用国だった日本が、なぜ江戸時代は刀の時代になったのか?
⇒審美感、西欧(特に現代の米国)との違い
・主たる食器が、金属器や木器から陶磁器になった。この事実は、西洋科学文明化らは出て来ない。
・科学革命から、人間革命・環境革命へ
・神仏習合
文字に書かれなかった縄文の自然信仰と文字に書かれた仏教信仰
無文字文化と文字文化の融合
(2)伊東俊太郎との対話
・8~9世紀のアラビア・ルネサンス ユークリッド・アルキメデス・アリストテレス等のギリシャの科学書の翻訳
・12世紀のアラビヤ語からラテン語への翻訳
専門用語の語源はアラビヤ語で残った(代数学のアルジェブラ)
スペインのトレドでヨーロッパ人に伝達 & 1453コンスタンチノーブル陥落でビザンチンの学者がイタリアに亡命
・イタリア・ルネッサンスへ
相互交流を通じてアイデンティティーが豊かになる(川勝)
・なぜ科学革命だけがヨーロッパに限定されているのか?
伊東俊太郎の考え
① ギリシャ科学の伝統が中国やインドに伝わらなかった
② 市民社会の成立によるマーケットの拡大
③ ガリレオは学者であると同時に職人(技術者)だった
デカルト、ダビンチも同じ、知識人がものに触れていた
職人的伝統と学者的伝統が市民社会で結合した
アリストテレスはどんな実験をしましたか。実験はギリシャでは十分でなかった、観察はしたが実験はなかった
④ 17世紀のヨーロッパは貧しかったし、気候も悪い。外へ出たいと外へ出たいと
東はオスマントルコなので、西へ出た ⇒大航海時代
6.川勝平太「美の文明をつくるー力の文明を超えて」ちくま書房(2002) KMB355
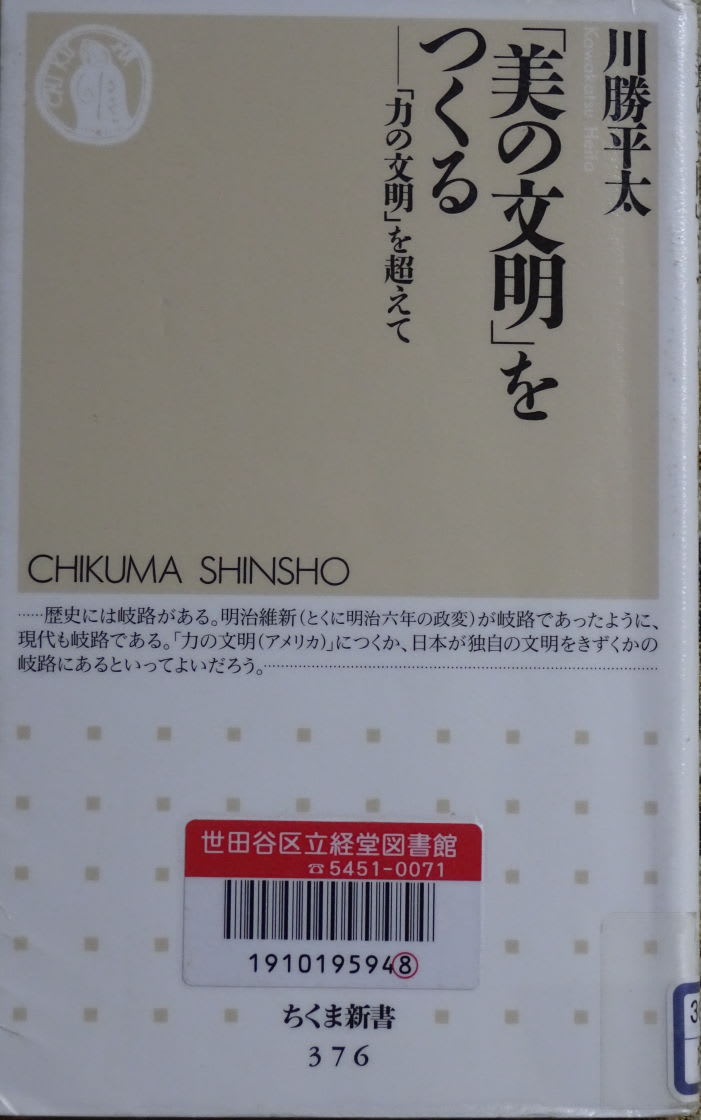
川勝氏は、オクスフォード大学の哲学博士の称号を持つ比較経済史の専門家と云われているが、私は、比較文明学会の役員としての著書に興味を覚えた。
この著書は、プロローグが意味深い。「日本の明日を考える」と題して、次の文章で始まる。
・戦後半世紀の内外の日本論の基調は「日本文化論」であった。しかし、これからの日本論の基調は「日本文明論」になるとみこまれる。地球環境を意識した新しい国づくりと連動して、未来志向的な性格を帯びた文明論になるだろう。未来志向であることによってそれは実践論となり、国民運動ともなって、日本を一新するだろう。
・この著書では、内外の多くの文献がリファーされている。全てを紹介できないが、いくつかを挙げてみる。
・ルース・ベネディクトの「菊と刀」からは、「欧米の罪の文化と日本の恥の文化、欧米の個人主義と日本の集団主義」
・ジョン・ダワーの「敗北を抱きしめて」からは、「戦後から立ち直ってゆく戦後の日本人の精神文化が、(中略)膨大な資料によって検証し、「日本人は特殊だ」という思いこみをしりぞけた。日本異質論は90年代に入って下火になったのである。」
・ハンチントンの「文明の衝突」からは、「地域政治では民族が中心になって民族紛争が生じ、世界政治では文明が中心になって文明の衝突が起こることを予想した。予想はほぼ的中している。ハンチントンは文明を八つあげている。その一つが日本文明である。
・西郷隆盛の「西郷南州の遺訓」からは、「文明ならば、未開の国に対しなば、慈愛を本とし、懇々と説論して開明に導くべきに、さはなくして未開蒙味の国に対するほど、むごく残忍のことを致し、おのれを利するは野蛮だと申せしかば、その人口をつぼめて言無なかりきとて笑われける。」
・湯川秀樹博士の「人間にとって科学となにか」からは、「私は自分の専門の物理学でも、ある法則なり論理体系なりを宜しいと納得するときは、そこになにか美しいものを感じ、・・・ある種の美意識や好悪感がある」
などを挙げている。そして、
文化には反対語がない。文明には負の価値をもつ野蛮という反対語がある。「力の文明」を超えて「美の文明」をつくりあげることをもって日本の文明の道(civilized way)としてよいのではないか。
で結んでいる。
本文の第1章では、次の言葉がある。
・科学法則は応用ができる。科学が技術と結びついて十八世紀に産業革命が始まった。その結果、はやくも十九世紀にはいると、機械技術を悪の権化として、機械を打ち壊すラッダイト運動がおこった。機械打ち壊し運動はイングランド中・北部でとくに激しく、一八一〇年代に頂点に達した。
富を公平に分配する平等を正義とする人々と、富を獲得する自由を正義とする人々の争いとなり、・・・。(中略)司馬遼太郎はそれ(イデオリギー)を「正義の体系」と言いかえていた。(中略)自由をもって正義と信じる集団と、平等をもって正義の体系と信じる集団とに分かれたのである。
・地球環境保全とは、「地球を汚してはならない」と云うことである。汚さないというのは、価値としては「美」に立脚している。(中略)正確には、真だけでは不十分、真と善だけでも不十分、真・善・美の三位一体を備えたものであってはじめて文明に値するということである。
このように論理を辿ると、やはり文化の文明化のプロセスとしては、メタエンジニアリングの応用が最も適しているように感じらてくる。
7.梅棹忠夫、「近代世界のおける日本文明、比較文明学序説」中央公論新社 (2000) KMB077

国立民族学博物館で1982年から1998年まで開催された谷口国際シンポジウム文明学部門での梅棹忠夫氏の基調講演の内容が纏められているものだ。
第10回のテーマは「技術の比較文明学」であり、その中で興味深い記述がいくつかあったので、メタエンジニアリングの研究の一部として考察を試みる。
その前に、比較文明学について少し触れておこう。梅棹は、「比較文明学というような学問領域は、純粋に知的な興味の対象になり得ても、どのような意味でも、実用的な、あるいは、実際的なものにはならないであろう」と言い切っておられる。なんと工学と対照をなす領域ではないか。
文明と文化の関係についての見方は、「時間的な前後関係をもつものと考えてよいのかどうか、すこし違った見方をしています。文化というものは、その全システムとしての文明のなかに生きている人間の側における、価値の体系のことである。」としている。また、システム学とシステム工学の違いを、「システム工学は目的があるけれども、システム学は必ずしも目的を持っていない。「目的なきシステム」というものもあるのではないか」と記している。
8.関、中澤、丸山、田中共著「環境の社会学」有斐閣(2009)
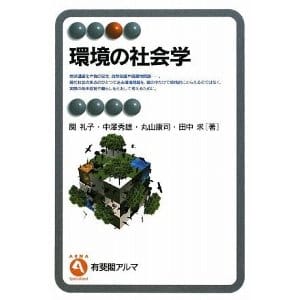
・「冒頭の言葉」
環境の社会学は、私たちがこの時代に、この社会の中に生きているということの意味を問うための学である。環境を考えることは生き方を考えることである。
社会学での言葉に「目的移転」という表現がある。「いったん技術とか制度が安定すると、それらの手段を使って達成するはずだった目的がどこかへ行ってしまい、手段の維持をめぐる問題にエネルギーがそそがれるということになりやすい。」ということなのだ。
一般に、リスクが見つかる度に、それを新たな科学技術によって抑え込むと云うのが、20世紀後半の社会がとってきたやり方である、と社会科学者が指摘をする。しかし、原因が地球単位で複雑化をすると、自然科学者は不確実な予測を出さざるをえなくなる。そこからエンジニアリングのジレンマが始まっているのだ。
・「国的移転」とは、エンジニアリングでは、手段の目的化と云えることなのだろう。実は、エンジニアリングの世界ではこのことが頻繁に起こっているのではないだろうか。目先の技術的な成果に集中してしまい、本来の大目的からそれてしまうことがしばしば見受けられる。このことは、過去の環境問題ではしばしば見受けられたことであり、環境問題が社会学への傾倒となった一つの原因であったように思えてくる。
・工学から社会学への主役の移動について、なぜそうなったかを考えてみる。この著書には、「信用されなくなった専門家たちは、「科学的知識が足りない」「ゼロ・リスク症候群にかかっている」といって大衆を攻撃する。リスクについて述べる場合には、われわれはこう生きたい、という観点が入ってくるのである。リスクというのは煎じつめると価値観と文化の問題であるとの指摘が古くからある。」とある。これが、社会学から見た工学への見方になる。
・以前に、「物理学はなぜを問わない。なぜ万有引力が存在するのか。なぜ相対性原理があるのかは問わない。」と書いた書を紹介した。工学も近代機械文明の中にあっては、WhatとHowに夢中になり、次第にWhyが軽視されてきたように思える。そこに落とし穴があったようだ。
一方でメタエンジニアリングは、学問分野を超えた根本的な「なぜ」を問い直すことを一つの手段としている。
9.堺屋太一「東大講義録、文明を解く」講談社(2003)
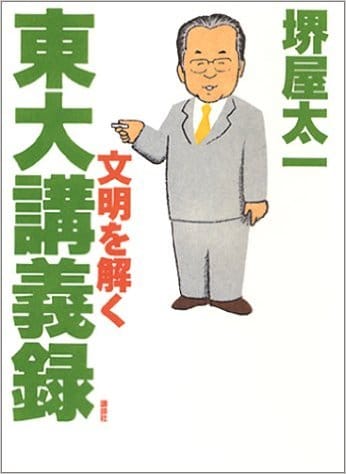
・これからの知価社会で経済閣僚は一体、何をすればいいか。第一は、市場の機能を保つ番人。
第二は、外部経済を内部化する。環境問題は典型です。公害をまき散らせばその分だけコストは安くできます。しかし、社会全体としては環境が悪化するという不経済が生じます。そのときに各企業に対してどのようなシステムによってこれをコスト負担させるか、つまり内部コストにするか。公害防止の技術や施設をつくらせ、産業廃棄物をきちんと処理させる、など外部経済を内部化することが必要になるでしょう。
10.日下公人「21世紀、世界は日本化する」PHP研究所(2000) KMB196

・日本から世界へ発信している文化が沢山ある
脱軍備、脱武器輸出、脱宗教、脱イデオロギー、経済第一、清潔第一、勤勉第一、陛下第一、少子高齢化、女尊男卑、民主主義、自由主義、家族主義、省エネ、巨大都市、教育の普及、知識と文化の尊重
11.中西輝政「国民の文明史」産経新聞社(2003) KMB083

・文明史観なき国家は、必ず滅ぶ。過去の歴史と未来の歴史をつなげてゆくもの、それが文明史である。文明史---それは、歴史をマクロな視野から、長いスパンで洞察する眼差しです。単なる歴史研究を超えた、一国を取り巻く文明全体の大きな流れを見極める目を持たないと、国家衰亡の危機には対処できません。グローバリゼーションの挑戦、国家観の喪失、教育の荒廃、治安の悪化、そして「危機」に気づかない国民精神の堕落…。
・文明の定義
① 文明とは、世界を構成する単位
② 文明は、国家や社会を動かす「活力の源)
③ 日本における、「文化」と「文明」の使い分けの問題
・世界の中の日本文明
現代の日本人の多くは、「日本文明」があったとしても、それは「中華文明と西欧文明の混合体のようなもの」だろう、と思っているかもしれないがそれこそまさしく「自虐的」文明史観といえよう。従来からの欧米の文明史家の間では、日本文明は、その独自性と体系性において、中華文明あるいはイスラム文明などと並んで、世界の主要文明の次の六たう、ないしは七つに分析している。
・90年代には「民間活力」とか「民でできることは民で」という言葉が口喧しく唱えられてきたが、このような「民間の力」の衰え、とりわけその技術応用力とそれへの強いコミットメントの減退は、つまるところ社会の創造性につながる知的・精神的な活力の低下に見いだすしかないのではないか。
・「短期の楽観、長期の悲観」は、滅びの構図
12.中西輝政「日本文明の興廃」PHP研究所(2006) KMB082

・文明史的岐路に立つ日本
今の日本人に必要なことは、文明的視野をもってこの時点を捉え直すことである。「文明的な視野」というのは、分かりやすくいえば、百年や二百年の単位ではなく、最低限千年の単位で考えるような歴史の視野である。千年の単位で見るならば、当然のこととして物質的なものはほとんど影をとどめない。問題になるのは、文化や国民の精神、民族性などというもの、つまり、「それがあったからこの国がずっと続いている」といえるような、「歴史を動かす精神的な核」である。
戦後の日本が「大いなる嘘」に立脚して出発せざるをえなかったということである。それは、誰もが知っていながら見過ごしてきた嘘であった。
かつて、日本にやってきた多くの西洋人が日本人の倫理性の高さを賞賛しているが、それを支えてきたのが、このような人としての美しさを重んじる「こころ」のあり様だったのである。しかし、その「こころ」自体が、「大きな嘘」で傷つけられてしまった。「まこと」を基調とする日本人の精神伝統つまり日本文明は、戦後という時代が遺した「嘘」と「賎め」の傷跡によって、いまその生命力を大きく全体させている。
13.松本健一「泥の文明」新潮社(2006) KMB384
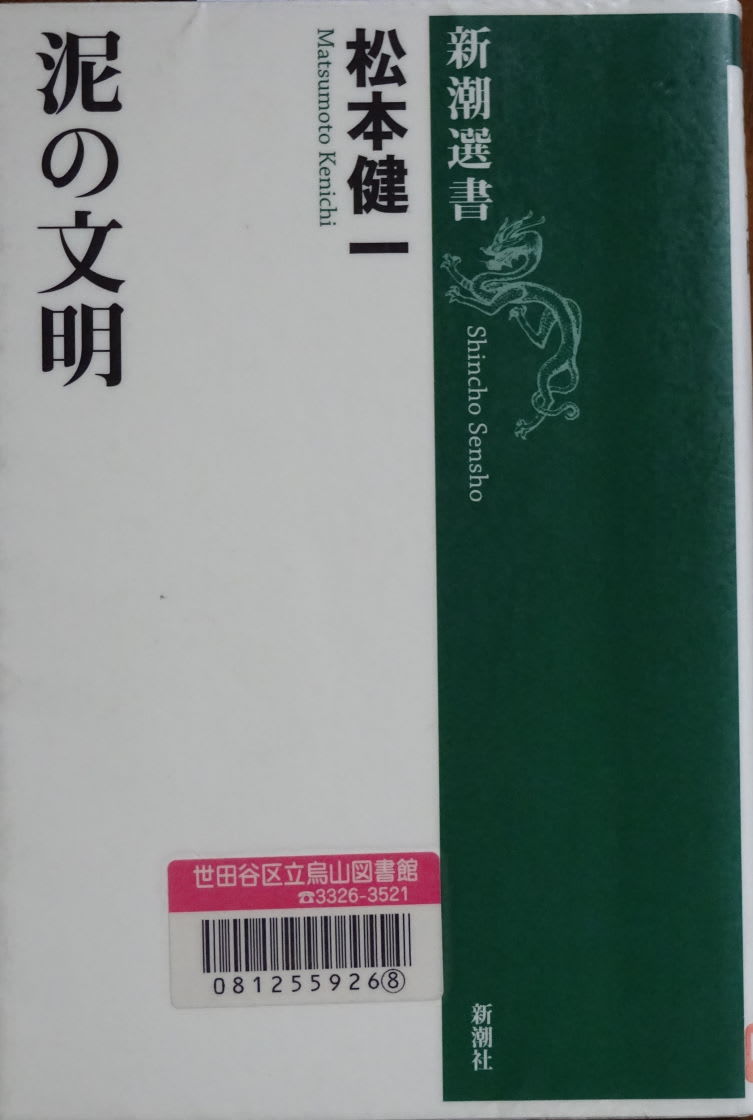
・泥の文明こそ、西欧文明が生んだ環境・人口問題を解決できる
世界は、「石」「砂」「泥」の三文明に分けることができる。「石の文明」すなわち西欧文明は「外に進出する力」を特徴とし、「砂の文明」であるイスラム文化圏は「ねーっとワークする力」が本質だ。そしてアジアに広がる「泥の文明」の本質は「内に蓄積する力」である。このアジア文明こそ、近代社会を牽引してきた「石の文明」の欠点を補える唯一の文明なのである。
・和辻が「モンスーンの風土」とよぶものと、わたしが「泥の文明」とよぶものは、「緑豊か」という点で共通する。しかし、和辻はその風土に「受容的・忍従的」な精神類型と文明が育つと説くのに対して、わたしがその「泥の文明」が「内に蓄積する力」をはぐくむと説いている。
わたしがその仮説を立てた根拠は何か、という点については、後に詳しく触れることにしよう。いま「モンスーンの風土」にしろ「泥の風土」にせよ、そこには農耕が主産業として成立するが、それによって生まれる民族の「エートス」(精神類型)なり文化の本質を、和辻は「受容的・忍従的」と捉え、わたしが「内に蓄積する力」と捉えている点に大いなる違いがある、ということのみ確認しておきたい。
・ヨーロッパの風土を和辻は「牧場」と捉えているが、それは松本も同じ。しかし、その牧場を20センチも掘れば石にぶち当たるので、松本は「一の文明」とするのである。そして牧畜がいかに広大な土地を必要とするかという話から、「石の文明」が「外に進出する力」を醸成するという話へとすすむ。それがヨーロッパ列強がアジア進出へとむすびつくのだが、この辺りの記述は、これまでのしゃかいがくの古典とされてきた大塚久雄の「共同体の基礎理論」をも論破して、迫力に富む。
・「もの作り」の文化
半導体の生産は欧米よりも、日本や韓国、台湾、中国、マレーシアなど、長年「田つくり」に微妙な精度と、その土から不純物を排除することに努力してきた国々ばかりである。更に触れたように、石川県たったかの山際に精確に作られ、水をゆっくりとすべての田に流してゆく棚田をみたソニーの技術者が、「これ(棚田)は半導体だ」と叫んだというエピソードを思い出さざるを得ない。










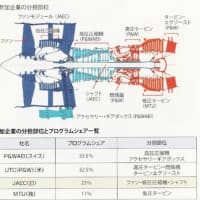
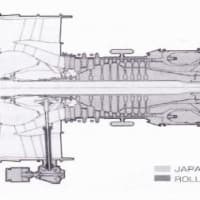



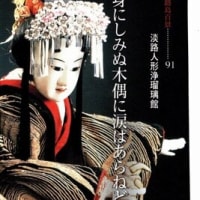
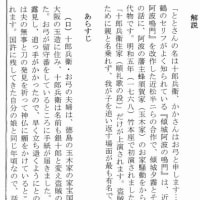


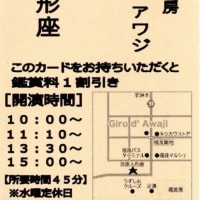
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます