雪下出麦 雪の下で麦が芽を出す(冬至の末候で、1月1日から4日まで)
甲府盆地の朝霧
天気の良い冬の朝の景色は、白い真綿の布団の上に富士が悠然としかもくっきりと座っている。布団の下にはすっぽりと甲府盆地が隠れている。夜には、そこにキラキラと光る町の明かりがある。

冬の朝の散歩は、他の季節とは違った楽しみがある。どの山々もくっきりと見えるし、それぞれの雪のかぶり方を比べるのも面白い。八ヶ岳の南斜面は、さすがに雪は少ない。少し西に廻ると、裏側はびっしり積もった雪山を見ることができる。甲斐駒の岩肌は風が強いせいなのか、岩肌の性質なのか、雪がつくことはない。しかし、北岳と千丈の頂上は常に真っ白で、どの角度から見ても一目瞭然である。そんな事は、毎回繰り返しのことなのだが、寒さを忘れさせる景色なのだ。
つらら
このあたりのつららは見事なものだ。一晩でも立派なものが何本もぶら下がる。屋根の雪が徐々に解けるときはなおさらだが、そうでなくとも驚くほどの水が滴っているのだ。これは、ログハウス特有のものかも知れない。室内の暖気が直接に屋根に当たるので、夜露はどんどん製造されて、軒先へ下る。そして、その途端にマイナス10℃以下の冷気に晒されて一気に凍るのだろう。だから、留守宅につららは決して下がることはない。一方で、長逗留のお宅のつららが、なんと軒先から地面まで繋がって氷柱になっていたことがある。我が家のつららは、さすがにそこまでは無理なようだ。

長く細いつららと、短く太いつららがある。この差は、気温か湿度か風の影響なのだろう。湿度が高ければ、夜露が大量に流れて、地面まで届くつららになるのかもしれない。
むかし、まだ子供の頃につららをアイスキャンディー代わりにしゃぶったことを思い出す。東京でつららを見かけなくなったのは何時からだろうか。ここには、氷りつくために、トヨと云うものがないが、そのためではなかろう。
甲府盆地の朝霧
天気の良い冬の朝の景色は、白い真綿の布団の上に富士が悠然としかもくっきりと座っている。布団の下にはすっぽりと甲府盆地が隠れている。夜には、そこにキラキラと光る町の明かりがある。

冬の朝の散歩は、他の季節とは違った楽しみがある。どの山々もくっきりと見えるし、それぞれの雪のかぶり方を比べるのも面白い。八ヶ岳の南斜面は、さすがに雪は少ない。少し西に廻ると、裏側はびっしり積もった雪山を見ることができる。甲斐駒の岩肌は風が強いせいなのか、岩肌の性質なのか、雪がつくことはない。しかし、北岳と千丈の頂上は常に真っ白で、どの角度から見ても一目瞭然である。そんな事は、毎回繰り返しのことなのだが、寒さを忘れさせる景色なのだ。
つらら
このあたりのつららは見事なものだ。一晩でも立派なものが何本もぶら下がる。屋根の雪が徐々に解けるときはなおさらだが、そうでなくとも驚くほどの水が滴っているのだ。これは、ログハウス特有のものかも知れない。室内の暖気が直接に屋根に当たるので、夜露はどんどん製造されて、軒先へ下る。そして、その途端にマイナス10℃以下の冷気に晒されて一気に凍るのだろう。だから、留守宅につららは決して下がることはない。一方で、長逗留のお宅のつららが、なんと軒先から地面まで繋がって氷柱になっていたことがある。我が家のつららは、さすがにそこまでは無理なようだ。

長く細いつららと、短く太いつららがある。この差は、気温か湿度か風の影響なのだろう。湿度が高ければ、夜露が大量に流れて、地面まで届くつららになるのかもしれない。
むかし、まだ子供の頃につららをアイスキャンディー代わりにしゃぶったことを思い出す。東京でつららを見かけなくなったのは何時からだろうか。ここには、氷りつくために、トヨと云うものがないが、そのためではなかろう。










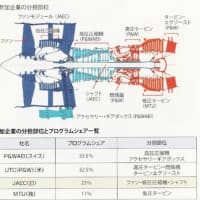
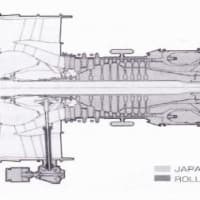



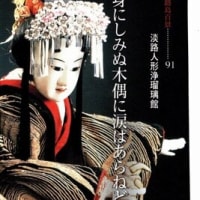
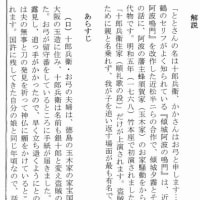


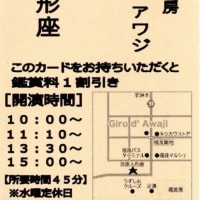
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます