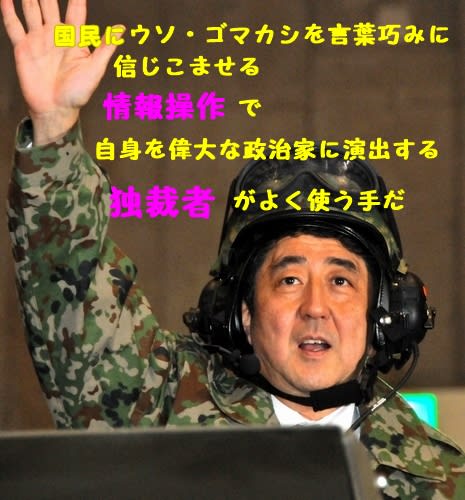
3月13日(2015年)衆院予算委員会での安倍晋三と前原誠司民主党議員との遣り取りで、安倍晋三は自らの国家主義と格差意識が希薄なところを曝け出した。
前原誠司「第2次安倍内閣が発足してから2年余り経った。異次元の金融緩和が始まってから、約2年が経った。果たして国民の生活が改善されているのか。
安倍総理とは何度か実質賃金について議論してきたが、(2015年)2月4日予算委員会で以下のように答弁している」
ボードを出して、答弁の要所を読み上げる。
安倍晋三はその日に次のように答弁している。
安倍晋三「実質賃金について言えば、この国会でも何回も議論したわけでございますが、景気が回復局面になりますと、人々は仕事が得やすくなるわけであります。しかし一方、スタートする時点においては、短時間のパートから始める人も多いと思いますし、また企業側も、なかなか正規の雇用はしない、慎重な姿勢がまだ残っているのも事実であります。その中で、働く人の数はふえている。しかし、働く人の数はふえていきますが、いきなり1000万円とか500万円という収入にはならない、パートからスタートする。
例えば、安倍家において、私がそれまで30万円の収入を得ていて、しかし、女房がどこかで仕事をする、残念ながらそういう経済状況ではない中において、しかし、私が30円の収入であれば、いわば平均すれば30万円なんですが、では、景気がよくなって、女房がパートで10万円の収入を得たとすると、安倍家としては40万円なんですが、平均すれば20万円に減ってしまうという現象がまさに今起こっているのがこの実質賃金の説明であって、ですから、総雇用者所得で見なければいけない」・・・・・・
前原誠司「実質賃金の説明はこれでいいのか」
安倍晋三「昨年の賃上げは最高になっている。倒産件数は24年ぶりで1万件を下がっている。企業の経常利益は過去最高水準になっている。
そこで平均賃金が下がっているという現象があるが、実質に於いて雇用者の所得の総計については、総雇用者所得についてはまさに国民みんなの稼ぎであって、実質についても消費税の引き上げ分を除けば、昨年の6月以降、8ヶ月連続でプラスが続いている。
名目では22ヶ月連続と、このように答えてきた」
前原誠司「実質賃金だと答えたことが正しいのか間違っているのか聞いた」
安倍晋三「実質賃金の平均としてはまさに私の答えたとおりでございます」
前原誠司「総理は実質賃金、名目賃金すらも分かっていない」
前原誠司は実質賃金の説明としては間違っていることを認めさせて、安倍晋三に訂正させ、安倍晋三が経済に無知なところを国民に見せたかったようだ。
だが、安倍晋三は「総雇用者所得」を高々と掲げて、強弁で以って実質賃金についての自身の説明を押し通した。
実質賃金とは言ってみれば賃金の実質的な価値を言うのだから、いくら給料が上がっても、税金が上がったり、物価が上がったりして、これらの上がった合計が賃金の上昇分を上回ると、賃金の実質的な価値が減って、貰っている賃金は名目状態(=名目賃金)のまま推移することになる。
要するに安倍晋三が言うように「消費税の引き上げ分」を除いた実質賃金という説明は成り立たない。
前原誠司にしても他の民主党議員にしてもアベノミクスによる格差拡大を追及しているが、この安倍家の収入を例に取って8ヶ月連続でプラスしているとしている総雇用者所得の説明の中にこそ、安倍晋三の国家主義と国家主義に対応させた格差意識の希薄性がまぶされているのだが、そのことに気づいていない。
私自身にしても安倍家の例は知っていて、一度ブログに取り上げたが、このことに気づいたのはNHKテレビでこの遣り取りを聞いている最中であった。
誰もが今まで使ったことのない、誰に教えられて使い出したのか、あるいは自身が考え出したのか分からないが、「総雇用者所得」という思想は国家主義思想なくして成り立たない。
ここで言う国家主義とは国民の在り様よりも国家の在り様を豊かさを基準に常に優先させる考え方を言う。国家の豊かさを優先することによって、それが阻害されない限り、国民の間に存在する格差は看過される。
そうでなければ、国家優先とはならない。
「総雇用者所得」では括(くく)ることのできない生活者が数多く存在していて、だからこそ給与が上がっても実質賃金が下がる現象が起きているのだが、それを無視して国民の所得の何でもかんでもを「総雇用者所得」という全体で一括りし、一括りできない多くの部分部分を顧みずに全体の増加のみを以ってアベノミクスが成功しているとする証明は中身の国民それぞれの在り様を問題視せずに全体を以って善しとする国家主義以外の何ものでもない。
それが安倍家の例に如実に現れている。
安倍家の夫が30万円の収入。妻が不景気で働き場がない場合は被雇用者という立場にははないから、平均しても2人で30万円の収入のままだが、景気がよくなって働く場所が出てきてパートで働いて10万円の収入を得たとすると、安倍家の平均賃金は20万円に減ってしまう。
これが実質賃金が減っているという現象に当たると説明しているが、安倍家の総収入はあくまでも40万円で、月々40万円全てを使って生活していると仮定したとしても、日銀が物価安定の目標として掲げた消費者物価の前年比上昇率2%と消費税8%を合わせて10%の経費負担が余分に増えたとしても、4万円の経費増額であって、計算上は妻の収入で賄うことができ、6万円を消費に回す余裕は十分にある。
こういった余裕ある例を持ち出して、アベノミクスの経済効果が出ていないために実質賃金が上がらず、国民の生活が苦しくなっているという指摘の反論の説明にしたり、格差が進んでいないことの根拠に用いたりしている。
一家の総収入を月40万円とすると、ボーナス等を加えて年収500万円以上から600万円となる。年収500万円以上、上は株や為替取引で数千万円、あるいは億単位で年収を増やした世帯に限定した場合は物価上昇や消費税分を上回る収入が十二分にあることになって、実質賃金は確実に上がっているということになる。
つまり安倍晋三の例自体が格差の底辺に置かれた国民の収入、そしてその生活を省略し、アベノミクスの外に置いている。
外に置いているからこそ、安倍家の月総収入40万を持ち出して、実質賃金や「総雇用者所得」が増えていることの説明とし、格差が許容範囲を超えていないことの結論としている。
いわば年収200万円以下世帯や100万円以下世帯の決して少なくない存在を除外している点に、あるいは除外できる点に格差に対する意識の希薄性を窺うことができる。
平成25年6月6日現在に於ける全国の世帯総数5011万2千世帯に対しての年収200万円以下の世帯20%近くの1千2万世帯前後がアベノミクス経済効果の対象から外されている。
特に国交省調査による2010 年時点で男性の25〜29 歳では71.8%、30〜34 歳で47.3%、35〜39 歳で35.6%、女性の25〜29 歳で60.3%、30〜34 歳で34.5%、35〜39 歳で23.1%となっている低収入が主たる原因となっている高い未婚率を占めている若者にとって伴侶の収入は期待できないのだから、安倍家の例は彼ら若者にとって何ら参考にならない例外中の例外で、そういった視点も欠いた安倍晋三の経済政策となっている。
国家主義と格差意識の希薄性は極めて深い相関関係があるということであり、このことが象徴的に現れた安倍晋三の国会答弁――安倍家の例であろう。
大体が景気が良くなって雇用が増え、働きに出て「いきなり1000万円とか500万円という収入にはならない、パートからスタートする」という言葉自体に中間以上の所得層にしか目を向けていない姿勢が典型的に現れている。
2012年の非正規雇用1813万人のうち、その約7割を女性が占め、その殆どがパート従業となっている。男女合わせて900万人近くのパート従業者の内、800万人近くが女性である。
例え月10万円で働いても、夫が月30万円の収入があるケースも多く存在するだろうが、パートの賃金は殆ど固定化されているのが現状である。それをパートからスタートして、「1000万円とか500万円という収入」になるようなことを言う。
安倍晋三の目が中間層、それも中間層の上の部から上の所得層に向けられていなければ出てこない言葉であるはずだ。
にも関わらず、格差を固定化させない社会の実現を訴えている。
3月12日(2015年)衆院予算委員会。
長妻民主党代表代行「日本の税による再分配機能は、他の先進国に比べて強い方なのか、弱い方なのか」
安倍晋三「格差の固定化はしてはならない。同時に、許容しえない格差が生じない社会の構築が重要だ。再配分機能は税だけではなく、例えば、社会保障の給付なども合わせて見る必要がある。
(所得の)再配分機能の回復を図るため、所得税の最高税率を引き上げ、給与所得控除や金融所得課税、相続税の見直しなどを随時、実施しているが、経済、社会の構造変化も踏まえながら、税制を含めてよく考えていきたい。例えば、消費税は社会保障にいくわけで、いわば再配分機能を給付の面でも行うことができる」(NHK NEWS WEB)――
安倍晋三が経済政策に於いても国民の在り様よりも国家の在り様を豊かさを基準に優先させている国家主義者であり、それゆえに格差の底辺で低賃金に喘ぐ低収入の国民の在り様には意識が薄く、重きを置いていないことに留意して、各発言を耳に留めなければならない。