
はっきりいって、この映画の4時間近い時間は忍耐の時間だった。だが、その忍耐の途中で少しずつ気づいたこと、ラストに至って確信したことがある。これはすごい映画なのだ。あらゆる既成の映画のどれにも似ていない、アンゲロプロスの「型」を前面に押し出した、歌舞伎の「型」のような一種の形式美に徹底して拘泥して作られた一大叙事詩なのだと。見終わったら感動に包まれている、こういう映画も珍しい。
アンゲロプロスのいつもの長回しが「旅芸人の記録」ほどには緊張感を生まず、冗漫感を醸し出してしまうことが最初のうち少しいらいらしてしまったが、群衆劇の場面での徹底した演劇的演出をロングの長回しで見ているうちに、かつて2000年以上前に屋外で演じられたギリシャ演劇とはこのようなものであったのかもしれないな、と思い始めた。
ストーリーはいたって単純だ。「旅芸人の記録」のような時間軸の交錯もない。
1900年の大晦日、刑務所を脱獄した「アレクサンダー大王」と呼ばれる義賊の頭たちが、貴族と外国人(イギリス人)を人質にとって故郷の北ギリシアに帰る。「アレクサンダー大王」は本名も知られていない孤児だったが、長じて、母親代わりに育ててくれた若く美しい女性と結婚する。だが結婚式を終えたばかりの花嫁は地主の陰謀で殺されてしまうのだ。アレクサンダー大王の素性については物語がかなり進んでからでないと明らかにされない。アレクサンダー大王は人質を盾に、政府に対して仲間の釈放と身代金を要求する。彼らの故郷は「先生」と呼ばれる指導者のもとに共産制コミューンが作られていた。イタリア人アナキストたちも加わって、その村では私有財産制が否定されていた。アレクサンダー大王は政府の密使との協議を行う一方、コミューンへの不満が募って次第に暴虐の限りを尽くすようになる…
ストーリーの展開は遅く、ほとんど台詞もないため、物語全体を把握するのはかなり苦労する。ワンシーンワンカットを多用した演出では、「死んだ時間」が長く、カットを割らないために人物の動きは緩慢で、そこには「時間の節約」がない。上映時間の長さに比べれば、語られていることは少しの言葉で説明できてしまうようなことだ。ゆったりと進む時間の中にたゆたうように写しだされる北ギリシャの寒村の様子は侘しく、この政治的寓話に暗く陰鬱な表情を与える。小川の流れ、暗い空、雪の冬、いずれもギリシャの裏面史を語るに相応しい風景が続く。
義賊がイギリス人を人質にとった事件は実際に19世紀後半に起きたことだそうで、また「アレクサンダー大王伝説」というのも中世からギリシャに伝わる民間伝承だそうだ。
新年の夜明けとともに太陽を背にアレクサンダー大王が白馬にまたがり登場する威風堂々たる映画的な場面と、最後にアレクサンダー大王が「消えて」偶像だけが残る場面との対比が見事だ。その寓意には様々な解釈が可能だろう。彼の思うように事態が運ばないことへの怒りやいらだちがあるということは推測できるが、アレクサンダー大王の内面が何も描かれないため、なぜ彼が殺戮に走るのか観客にはまったくわからない。
理解を超える寓意性に満ちた政治劇を見た、それも枯れた色彩の寂しい風景と共に、民衆の心情の悲劇性をしみじみと感じながら。「理解を超える」と書いたが、ここに描かれたのは20世紀が懐胎してきた思想の実践と壮大な無の悲劇そのものだ。それを、このような手法で描くことも可能だったのだ、と観客に示したアンゲロプロスはやはり並大抵の監督ではない。(DVD)
----------------------
O MEGALEXANDROS
ギリシャ/イタリア/西ドイツ、1980年、上映時間 208分
監督・脚本: テオ・アンゲロプロス、製作: ニコス・アンゲロプロス、音楽: クリストドゥス・ハラリス
出演: オメロ・アントヌッティ、エヴァ・コタマニドゥ、グリゴリス・エバンゲラトス
アンゲロプロスのいつもの長回しが「旅芸人の記録」ほどには緊張感を生まず、冗漫感を醸し出してしまうことが最初のうち少しいらいらしてしまったが、群衆劇の場面での徹底した演劇的演出をロングの長回しで見ているうちに、かつて2000年以上前に屋外で演じられたギリシャ演劇とはこのようなものであったのかもしれないな、と思い始めた。
ストーリーはいたって単純だ。「旅芸人の記録」のような時間軸の交錯もない。
1900年の大晦日、刑務所を脱獄した「アレクサンダー大王」と呼ばれる義賊の頭たちが、貴族と外国人(イギリス人)を人質にとって故郷の北ギリシアに帰る。「アレクサンダー大王」は本名も知られていない孤児だったが、長じて、母親代わりに育ててくれた若く美しい女性と結婚する。だが結婚式を終えたばかりの花嫁は地主の陰謀で殺されてしまうのだ。アレクサンダー大王の素性については物語がかなり進んでからでないと明らかにされない。アレクサンダー大王は人質を盾に、政府に対して仲間の釈放と身代金を要求する。彼らの故郷は「先生」と呼ばれる指導者のもとに共産制コミューンが作られていた。イタリア人アナキストたちも加わって、その村では私有財産制が否定されていた。アレクサンダー大王は政府の密使との協議を行う一方、コミューンへの不満が募って次第に暴虐の限りを尽くすようになる…
ストーリーの展開は遅く、ほとんど台詞もないため、物語全体を把握するのはかなり苦労する。ワンシーンワンカットを多用した演出では、「死んだ時間」が長く、カットを割らないために人物の動きは緩慢で、そこには「時間の節約」がない。上映時間の長さに比べれば、語られていることは少しの言葉で説明できてしまうようなことだ。ゆったりと進む時間の中にたゆたうように写しだされる北ギリシャの寒村の様子は侘しく、この政治的寓話に暗く陰鬱な表情を与える。小川の流れ、暗い空、雪の冬、いずれもギリシャの裏面史を語るに相応しい風景が続く。
義賊がイギリス人を人質にとった事件は実際に19世紀後半に起きたことだそうで、また「アレクサンダー大王伝説」というのも中世からギリシャに伝わる民間伝承だそうだ。
新年の夜明けとともに太陽を背にアレクサンダー大王が白馬にまたがり登場する威風堂々たる映画的な場面と、最後にアレクサンダー大王が「消えて」偶像だけが残る場面との対比が見事だ。その寓意には様々な解釈が可能だろう。彼の思うように事態が運ばないことへの怒りやいらだちがあるということは推測できるが、アレクサンダー大王の内面が何も描かれないため、なぜ彼が殺戮に走るのか観客にはまったくわからない。
理解を超える寓意性に満ちた政治劇を見た、それも枯れた色彩の寂しい風景と共に、民衆の心情の悲劇性をしみじみと感じながら。「理解を超える」と書いたが、ここに描かれたのは20世紀が懐胎してきた思想の実践と壮大な無の悲劇そのものだ。それを、このような手法で描くことも可能だったのだ、と観客に示したアンゲロプロスはやはり並大抵の監督ではない。(DVD)
----------------------
O MEGALEXANDROS
ギリシャ/イタリア/西ドイツ、1980年、上映時間 208分
監督・脚本: テオ・アンゲロプロス、製作: ニコス・アンゲロプロス、音楽: クリストドゥス・ハラリス
出演: オメロ・アントヌッティ、エヴァ・コタマニドゥ、グリゴリス・エバンゲラトス















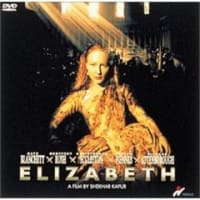


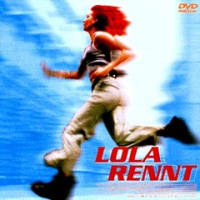
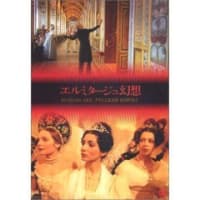
<歌舞伎の「型」のような一種の形式美に徹底して拘泥して作られた一大叙事詩>という表現、この作品に接する上で参考になりました。おもえば本作を始めてみたのは15年前の高校生の頃でしたが、文化も時もかけ離れた神話的な時空間に突然放り出された気がして、呆然としたことを覚えています。
それから沢山の映画をみてきた今、もう一度観て、様々な角度から楽しめるようになりました。
歌舞伎に影響された映画といえばエイゼンシュタインの「イワン雷帝」もありますが、エイゼンシュタイン、タルコフスキー、そしてアンゲロプロスの比較も面白いかなと思っています。
人々のうなりのような音楽(?)は、まさに民衆=peopleの声そのものという感じで、印象に残ります。「アレクサンダーがある日、日没を見て憂いを感じ、旅に出た」という冒頭の語り部の言葉は、まさにアンゲロプロスの映画世界を要約したものでもあると思います。
ともかく見事な映画ガイドに感謝します。
実はここ数年レビューはスランプで、特に最近は遅筆になり、もうレビューを書くのは止めようかという気持ちになりつつあったのですが、このように研究者の方にもお役に立てることが少しでもあるなら、やっぱり書いてきてよかったなぁという気持ちになります。
「イワン雷帝」は未見なのでなんともいえませんが、アンゲロプロスとエイゼンシュタインには類似点があるような気がします。タルコフスキーはアンゲロプロスほど理が勝っていないと感じます。もっと情緒に訴える絵作りをしているのではないでしょうか。
アンゲロプロスの映画は言葉を尽くせばなんとか表現解説できるけれど、タルコフスキーのはもっと詩的で、散文による解説になじまない気がします。全作品見たわけではないのでこれは単なる印象ですが。タルコフスキーもアンゲロプロスもまだ長編未見作がたくさんあって、これからの楽しみにとってあります。
映画論についてちゃんと勉強したことがないのでいつも素人レビューで恥ずかしいです。これからはちゃんと書かないといけないなぁといい意味でプレッシャーを感じました(^_^;)
これからもぜひ、映画論について、健筆を振るってくださいますように。
タルコフスキーが情緒に訴えているという点、同感です。彼自身、かつてこのように語っているのを思い出しました。
「私は感覚的にものをみる傾向がある。現実に対して静観的ともいえる。考えるのではなく、あるがままを見つめ感じようとする。つまり動物や赤ん坊に近い。大人はあれこれ考えたり、結論を出したりするが・・」(レシュコフスキー編「タルコフスキーin サクリファイス」でのインタビュー)
今後とも、レビューを楽しみにしております。
このインタビューが「サクリファイス」について述べたものであるということが興味深いです。というのも、わたしはタルコフスキー作品の中でこの「サクリファイス」はちょっと毛色が違うと感じているからです。この作品は他の作品に比べて情緒的な部分が影を潜めていると思っています。しかしこの作品とて公開時に一度見ただけのおぼろげな記憶しか残っていませんから、今見るとまた違う感想を持つかもしれません。
いずれにしても、タルコフスキーとアンゲロプロスというのはわたしの大好きな監督ですから(さらに言えばベルイマンも加えたい)、またいろいろご教示くださいませ。