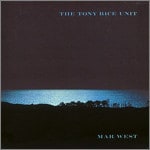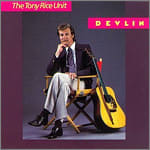Jerry Donahue - guitar, bass
Dave Peacock - banjo
Marc Donahue - keyboard
Dave Pegg - bass
Gerry Conway - drums
Ric Sanders - violin
Freebo - bass
John Jorgenson - mandolin
etc.
久しぶりにギタリストなアルバムを紹介しようかなぁ~なんて思いまして、何にしようか思案していたんですが、ちょうど boostermania さんのところで The Hellecasters の名前を見かけ、即 Jerry Donahue に決定。安易といえば安易ですがキッカケとはそんなもの(笑)。でもいつか取り上げたいと思っていたギタリストなんですよね~。
熱心なギター・ミュージック・ファンであれば、どこかで超絶テレキャスター・トリオ The Hellecasters の名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。「カントリー色の強い楽曲は苦手だがカントリー・ギターそのものには興味がある」という方にはピッタリのインスト・バンドです。今回はそんな HELLECASTERS のメンバーの一人 Jerry Donahue が 1986年にリリースしたソロ・アルバムを紹介したいと思います。Jerry は英国トラッド・ロック・バンド Fairport Convention の後期を支えたアメリカ人ギタリストで、FAIRPORT 加入前は Sandy Denny 擁する Fotheringay にも在籍していました。常識ではとても考えられないようなベンディングを始め、数々の高度なカントリー奏法を極めたギタリストですが、楽曲は意外にもカントリー色が薄いのが特徴です。名手 Albert Lee とは、彼が Heads, Hands & Feet の頃からの友人で、HHF のデビュー作には彼の名前もクレジットされています。この二人は僕自身カントリー奏法にハマっていた頃、最も影響を受けたギタリストですね。
オープニングの "Tokyo" は Jerry が FAIRPORT 時代に発表した曲のセルフ・カヴァーで、オリジナルは 1973年リリースの "Nine" というアルバムに収録されています。タイトルから察するに東洋を意識したものと思われますが「クロマティックな音階が印象的」という程度で東洋人の耳にはそれほど東洋的には聞こえてきません(笑)。ちょっとしたトリビアになりますが、Jerry は過去に Sylvie Vartan のバックで来日したことがあるそうで、"Tokyo" はそのときに書いた曲なんだとか・・・(笑)。それはさておき Jerry のプレイを語る上では避けられない代表曲の一つであることは間違いないでしょう。パッと聴いた感じは単音弾きに聞こえますが、実は複弦の鳴りをうまく利用したカントリー風のリックです。昔、FAIRPORT のヴァージョンで耳コピに挑戦したことがありますが、ポジショニング、弦の選び方などで結構苦労しました(笑)。
全編にわたり、ため息が出るようなスーパー・リック満載の本作ですが、やはり聴きどころは Jerry Reed の名曲 "The Claw" ではないでしょうか(コンポーザーのクレジットはファミリー・ネームの Hubbard)。イントロにオリジナルの "The Beak" を加え、かなり速いテンポにアレンジされています。それでもあっさりと高速ロールを決めてしまうあたり、さすがという他ありません(笑)。またブレイクでは James Burton ばりのチキン・ピッキングも披露。日本のロック系ギター雑誌ではカントリー風のフィンガー・ピッキングのことを総称してチキン・ピッキングと呼んでいるようですが、本来はカントリー・ギター奏法の一つであり、フラット・ピックで中指や薬指を使うことを指すわけではありません。ちなみにこの呼び名は「コッコケー」とニワトリの鳴き声に似た音を出すことから付けられたとされています。例えば Dixie Dregs の "Ice Cakes" に出てくるメイン・リフはチキン・ピッキングを応用したものですが、Eric Johnson の名曲 "Cliffs Of Dover" のイントロで聴けるフィンガー・ピッキングのフレーズは正確にはチキン・ピッキングと呼びません(笑)。チキン・ピッキングに関しては Jose さんのサイトで詳しく解説されていますので是非一度ご覧になってみてください(こちら)。
何かと異ジャンルに関連付けたくなる ghostwind ですが、このアルバムでは The Corrs のデビュー作でもお馴染みのトラディショナル曲 "Toss The Feathers" がメドレーに組み込まれています。CORRS 版はかなりポップでコンテンポラリーなアレンジでしたが、こちらはカントリー風のビートに乗せて Jerry のギターと Ric のヴァイオリンが絶妙なユニゾンを聞かせてくれます。また同メドレーでマンドリンを弾いているのは、後に Jerry と The Hellecasters を結成することになる John Jorgenson です。
参加ミュージシャンについても少し触れておきますね。Dave Pegg, Gerry Conway, Ric Sanders は FAIRPORT 時代の旧友。Freebo は Bonnie Raitt のバンドに在籍していたことで知られるベーシストで、Jerry とは古くからの付き合いだそうです。Little Feat の Paul Barrere や DREGS の T Lavitz らと結成した The Bluesbusters で二枚のアルバムをリリースしています。DREGS ファンはこちらも要チェックですね(笑)。本作でバンジョーをプレイしている Dave Peacock は元々ギタリストで、元 Heads, Hands & Feet の Chas Hodges と組んで Chas & Dave というデュオで活動中です。
"Telecasting" は当時イギリスのみの限定発売だったそうで、残念ながら現在では非常に入手困難な一枚になっています。しかし嬉しいことに 1998年になって、新たにリズム・セクションを録り直し、プロダクションの飛躍的な向上が図られたリニューアル版 "Telecasting Recast" がリリースされました。こちらであれば今でも比較的入手しやすいかと思います。また本作に収録されている "The Beak / The Claw" と "King Arthur's Dream" の二曲は The Hellecasters のデビュー作でも取り上げているので、そちらを聴いてみるのも手かもしれません(笑)。以下は "Telecasting Recast" のジャケットです。

あの Danny Gatton に「惑星一のベンダー男」と言わしめた Jerry Donahue。機会がありましたら是非聴いてみてくださいね。
The Hellecasters Official Website:
http://www.hellecasters.com/
"Telecasting Recast" アルバム試聴(amazon.com)
http://www.amazon.com/gp/product/B00000G14E/102-2167133-0594507