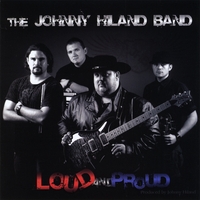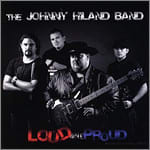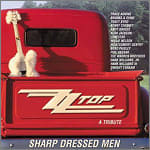Jerry Douglas - dobro
Tony Rice - guitar
Wes Golding - guitar
Ricky Skaggs - fiddle
Terry Baucom - fiddle
Darol Anger - violin
Jack Hicks - banjo
Steve Bryant - bass
Todd Phillips - bass
Bobby Sloan - bass
70年代、The Country Gentlemen, J.D. Crowe & The New South, Boone Creek など数多くのバンドに在籍し、自らの腕に磨きを掛けてきた Jerry Douglas。そんな彼が満を持してリリースしたソロ・デビュー作 "Fluxology" が今回ご紹介する一枚です。ブルーグラスをベースとしながらも、その枠に捉われないアコースティック・ミュージックは当時のシーンにおいて、時代を一歩先行くサウンドだったに違いありません。すでに現在の Jerry を予感させるプレイやアレンジが顔を覗かせており、舵はしっかりと今のスタイルに向けられていたことを伺わせます。
アルバム・タイトルの "Fluxology" は Jerry のニックネームである "flux" と「○○学」を表す接尾辞の "-logy" を組み合わせて作られた造語。ちなみに "flux" とは「絶え間なく変化する」の意で、クロマティック・スタイルの Jerry のプレイを例えて名付けられたそうです。自分のプレイを形容した言葉がニックネームだなんて、何ともカッコイイではないですか!
今のところ、"Fluxology" は CD 化されておらず、アナログ盤が存在するのみですが、2nd アルバム "Fluxedo" とのコンピレーション CD "Everything Is Gonna Workout Fine" で全10曲中9曲を聴くことができます。2nd の方はフル収録ですから、かなりお得な一枚と言えますね(笑)。

唯一割愛されたのは Burt Bacharach の名曲 "Say A Little Prayer For You" のカヴァーで Aretha Franklin や Dionne Warwick の歌唱で有名な大ヒット・ナンバーです。以前 TV ドラマ「大奥」のエンディングとして使われていたこともありますから、ご存じの方も多いのではないでしょうか(この時のカヴァーは Kazami というアーティスト)。収録時間に余裕があるにもかかわらずこの曲が割愛された理由はわかりませんが、やはり 2 in 1 のカップリングでリリースして欲しかったですね。というのも僕が最初にお薦めしたかった曲が "Say A Little Prayer For You" なんですよ(笑)。サステインの豊かなドブロの音色とバカラック節と呼ばれる叙情的なメロディが見事にマッチしていて、美しく官能的な曲に仕上がっているんです。テクニカルなスタイルではないですが、ドブロの魅力がすごく伝わってくるアレンジだと思います。僕自身、この曲を聴いてドブロのサウンドが好きになったようなものですしね(笑)。アナログ盤の再生環境をお持ちの方は是非中古レコード店で "Fluxology" を探してみてください!
・・・とこういう書き方をすると、あたかも僕はアナログ盤を持っているように聞こえますが本当は違うんです(笑)。こんなマニアックな情報、誰が知りたがるのかはわかりませんが、実はこの割愛された一曲が収録されているコンピレーション盤が存在するんですね。もちろんこちらは CD です。Tony Rice の時もそうでしたが、NEC アベニューはまたしてもやってくれました。それが "Best Rounders" シリーズの Jerry Douglas 篇 "Jerry Douglas And Friends" です。Rounder はブルーズやフォーク、ブルーグラスなど、主にルーツ・ミュージックを扱っているアメリカのレーベル。20年近く昔になりますが、NEC アベニューはこの Rounder が所有する音源をアーティスト毎に編纂し、"Best Rounders" という名でシリーズ化していたんです。もちろんブルーグラス系のアーティストも多数リリースされました。幸運なことに、この時期は僕自身がブルーグラスを聴き始めた頃とちょうど重なるんです。右も左もわからないジャンルの音楽でしたから、手っ取り早くアーティストのことを知るにはまさに打ってつけのシリーズでしたね(笑)。

おそらく CD 音源での "Say A Little Prayer For You" はこのアルバムだけだと思います。今となってはアナログ同様こちらも入手困難な一枚になってしまいましたが、二枚の「技あり!」コンピは合わせて「一本!」の "Fluxology" になるわけです(笑)。ごくたまにですが中古屋でもこのシリーズの CD を見かけます。どのジャンルのコーナーに紛れ込んでいるかはわかりませんが、「ベスト・ラウンダーズ」というタイトルを見かけましたら是非一度手に取ってみてください。
おっと、これだけ長々と書いて、曲紹介がまだ一曲だけとは・・・(苦笑)。いい加減、先に進まないとアガサ・クリスティの名作のように誰もいなくなっちゃいそうですね(笑)。
アルバムは Jerry の自作曲とスタンダードがほぼ半々で収録されています。これはある意味「革新」と「伝統」という二つのスタイルをバランスよく織り交ぜた構成といえるでしょう。「革新」という点からいえばジャズやニューエイジの流れを汲んだドーグ・ミュージックの影響が強いですね。これは Tony Rice, Darol Anger, Todd Phillips といった David Grisman Quintet 時代の旧友が参加していることからも明らかです。こういったサウンドは Windham Hill や Narada といったレーベルのアーティストが好きな方なら受け入れやすいかもしれませんね。現に Darol Anger のようにブルーグラス出身でその方面に進出していったアーティストも少なくありません。その他では Ricky Skaggs, Wes Golding, Terry Baucom, Steve Bryant といった Boone Creek 時代の盟友らがバックを支えています。
オープニングは「これぞ Jerry の真骨頂!」といった感の "Fluxology"。タイトル曲であるところに自信のほどが伺えます。まさに Jerry の "flux" たる所以がギッシリ詰まった超絶ドブロ・チューンです。当時はこの斬新なスタイルを受け入れ難かったファンも多かったと聞きます。やはり天才は常に凡人の一歩も二歩も先を歩いているものなんでしょう(笑)。この曲ではそんな Jerry のスーパー・プレイに加えて、ギターに Tony Rice が参加しています。一聴して彼とわかるジャジーなリックがクールでカッコいいです。これもまた一つの聴きどころですね。ちなみに粋なヴァイオリン・ソロを聞かせているのは前述の Darol Anger・・・だと思います。というのも Fiddle として Ricky Skaggs の名前もクレジットされているんですよ。フレージングからすると Darol っぽいんですけどね(笑)。続けて Jerry の自作曲を紹介していきます。"C-Biscuit" はちょっぴりほんわかムード漂うコミカルな一曲。こういうスタイルのプレイを聴くと、ドブロって本当に表情豊かな楽器なんだなぁって思いますね。和音の使い方がクールな "Red Bud Rag"、強力なシンコペーションが味わえる "Alabam'" は Jerry のハイレベルなテクニックとアレンジ・センスが光る佳曲です。
本作に収録されているスタンダードについても簡単に書いておきます。"Randy Lynn Rag" は Earl Scruggs のペンによるバンジョー・チューン。主役の座はバンジョーに譲っているものの、やはりドブロの存在感は圧倒的です。"Wheel Hoss" はブルーグラスの創始者 Bill Monroe の曲で、オーセンティックな路線が好きな人にはたまらない一曲でしょう。Nitty Gritty Dirt Band も取り上げていた "Dixie Hoedown" は新たにドブロ・チューンとして生まれ変わりました。"FLUX" に決まりまくるロールが最高です! "Bill Cheatham" は Jerry のアレンジによるトラディショナル曲。そしてアルバムはドブロの独奏曲 "Blues For Vickie" でしっとりと幕を下ろします。
相変わらず書き出すと止まらないですが、書きたいことはほとんど書けたのでスッキリしました(笑)。二枚目以降はもうちょっと軽めにしなきゃ・・・(笑)。
to be continued...