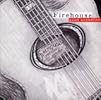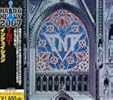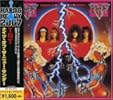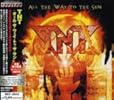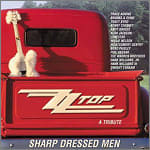デジタル・オーディオ・プレーヤーがポータブル・プレーヤーの主流となり、コンテンツの購入がパッケージ販売から音楽配信という形の無いものへと変わりつつある今日この頃。本書はそのタイトルが示すとおり音楽産業はこの先どうなっていくのだろうという主題を掲げ、過去・現在・未来の流れを軸に経営学的な見地から考察した一冊である。先日の「iPodは何を変えたのか?」ではユーザの心理的側面に迫った分析が興味深かったが、「日本の音楽産業はどう変わるのか」はその性格上、客観的かつ冷静な目で情勢を概観するに終始している。そのため読み物としては面白みや意外性に欠け、僕のような単なる興味本位で読み始めたような読者には少々堅苦しく感じるかもしれない(専門用語に関しては巻末に注釈が付いており、この辺りの配慮はありがたい)。個人的には各章のまとめにもう少し力を入れてくれると読みやすくなると思う。とはいえ読者の大半が何らかの形で音楽ビジネスに係わっている者と推測されるわけで、必要とあらばそれらは読者が自身で行うものなのであろう。
何はともあれ音楽産業の動向について少しでも興味のある方は読んでおいて損はないと思う。個人的には基本的な事柄(例えば国内におけるアルバムの価格設定、アーティストの発掘から販売までの流通の仕組みなど)についての知識を得ることができた。
何はともあれ音楽産業の動向について少しでも興味のある方は読んでおいて損はないと思う。個人的には基本的な事柄(例えば国内におけるアルバムの価格設定、アーティストの発掘から販売までの流通の仕組みなど)についての知識を得ることができた。
      |