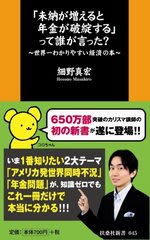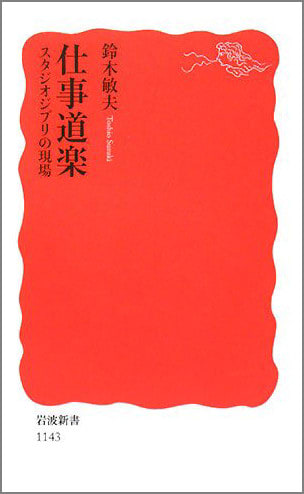挑発的なタイトル及び内容から、一昔前に結構話題になった本らしい。某掲示板では賛否両論だったそうだが、楽観的虚無主義を標榜する私は結構楽しめたかな(笑)。著者の主張には概ね同意。私は「ネットは我々が思う以上に世界を変えるかもしれないが、我々は自分たちが思うほど変わりはしないだろう」というのが持論だからね。これは決して悪い意味ではなく、どこか「人」というものを信じたいという気持ちがあるんだよね。
前から思っていることだけど、ネットに対してはドライな視点が大切だと思う。何といってもネット上には正しい判断を狂わすような情報がウヨウヨしているからね。間違った道を選択したからといって、誰かがその責任を取ってくれるわけではない。常に "at your own risk" であることを心掛けて接していく必要があると思うんだよね。
自分の場合、家にいるとついパソコンに向かってしまう。興味があることについて調べたり、プログラムを書いたり、ソフトウェアを解析したり、そんな感じかな。ただ家の外に出たときは正反対で、ネットとはできるだけ切り離されていたいと感じる。ツイッターも通勤電車で暇になったらやる程度。電脳世界にいたくないというアナログな気持ちが働くんだよね。こういう二面性を持ちながら日々暮らしている筆者でございます。
前から思っていることだけど、ネットに対してはドライな視点が大切だと思う。何といってもネット上には正しい判断を狂わすような情報がウヨウヨしているからね。間違った道を選択したからといって、誰かがその責任を取ってくれるわけではない。常に "at your own risk" であることを心掛けて接していく必要があると思うんだよね。
自分の場合、家にいるとついパソコンに向かってしまう。興味があることについて調べたり、プログラムを書いたり、ソフトウェアを解析したり、そんな感じかな。ただ家の外に出たときは正反対で、ネットとはできるだけ切り離されていたいと感じる。ツイッターも通勤電車で暇になったらやる程度。電脳世界にいたくないというアナログな気持ちが働くんだよね。こういう二面性を持ちながら日々暮らしている筆者でございます。
     |
Google を使い始めたのは確か2000年頃だったと思う。一部のユーザーの間で「検索精度が高い」と評判になっており、初めてその存在を知った。試してみると理由はすぐにわかった。明らかに他の検索エンジンとは次元が違うのである。当時はまだどこの馬の骨ともわからぬ存在であったが「知名度」よりも「質」を信じることにした。まだ「ググる」という言葉すらなかった時代の話である。あれから10年、ネットはすっかり Google 色に染まってしまった。
本書はタイトルが示すとおり Google について書かれたものだが、インターネットによってもたらされたビジネスモデルの変革についても広く言及している。物事の背後に隠された意図も含め、かなり丁寧に書かれている。大胆な未来予測に関しては賛否両論あるだろうが、総じて客観性が保たれた冷静で的確な分析だと思う。このあたり、偏った礼賛や批判に終始する紙資源の無駄遣いとは異なる点だね。読んでおいて損はない一冊。
本書はタイトルが示すとおり Google について書かれたものだが、インターネットによってもたらされたビジネスモデルの変革についても広く言及している。物事の背後に隠された意図も含め、かなり丁寧に書かれている。大胆な未来予測に関しては賛否両論あるだろうが、総じて客観性が保たれた冷静で的確な分析だと思う。このあたり、偏った礼賛や批判に終始する紙資源の無駄遣いとは異なる点だね。読んでおいて損はない一冊。
      |
今更の話題だが何となく読んでみた。出版が四年前いうことで若干内容は古いが、セキュリティ対策に関する基本的なロジックは今も通じるだろう。前半はウィニーによる情報流出問題の考察、後半は本書の要となるセキュリティ対策である。内容的には杓子定規的な説明が大半を占め、読み物としての面白みに欠ける。事務的にこなしたい向きにはいいかもしれないが、書き手の創意工夫があまり感じられない内容である。セキュリティの堅牢化がもたらす弊害についてもほとんど触れられておらず残念(ここが一番重要)。
この手の本に感化されて、なりふり構わずセキュリティ対策を推し進めようとする無能な上司はたくさんいるんだろうなぁ。もちろんその責任は本書にないけどね。
この手の本に感化されて、なりふり構わずセキュリティ対策を推し進めようとする無能な上司はたくさんいるんだろうなぁ。もちろんその責任は本書にないけどね。
    |
画一的な教育方法に迎合せず、無許可というリスクを負いながらも子供達の可能性を信じる道を選んだ保育園のお話。一年あまりの取材が聞き書きという形で綴られる。
何が違うって "覚悟" が違う。とにかくその一語に尽きる。「形だけうちのまねすると大変です」という言葉からは実践と経験に裏付けされた自信が窺える。「韓国の幼稚園」というお話、"破れお堂" と呼ばれることに対する本音の告白には思わず目頭が熱くなった……。
この保育園の方法論が最良なのかはわからない。しかし読んだ者に何かが強く印象付けられることは確かである。私はそれだけでも読む価値のある一冊だと感じた。
何が違うって "覚悟" が違う。とにかくその一語に尽きる。「形だけうちのまねすると大変です」という言葉からは実践と経験に裏付けされた自信が窺える。「韓国の幼稚園」というお話、"破れお堂" と呼ばれることに対する本音の告白には思わず目頭が熱くなった……。
この保育園の方法論が最良なのかはわからない。しかし読んだ者に何かが強く印象付けられることは確かである。私はそれだけでも読む価値のある一冊だと感じた。
今の社会を襲う世界的な不況や日本の年金問題についてその仕組みを分かりやすく解いた本。手描きの挿絵をふんだんに用い、平易な文体で書かれているところは好感が持てた。内容はニュースや新聞の記事などを理解するための予備知識といったところ。掘り下げない分、客観性が維持できていると思う。ただ最低限の理解を優先しているがゆえ、諸問題に対して自分なりの見解を持つには至らないだろう。
ちょっと気になったのが、著者の持論である「数学的思考力」がことあるごとに持ち出される点。穿った見方かもしれないが、それを宣伝するための実例として経済や年金問題が使われていると思える節さえある(他の書評などを読むと元々そういう位置付けの本でもあるようだが・・・)。著者自身、文章を書くのは不得手と告白しているのだから、そこは割り切ってほしかった。自説の論証というよりキャッチセールスの口説き文句に近い文章は読んでいてちょっと萎えてしまう。
ただ世間一般の評価はかなり高く、自分の感覚とはズレがあるのも事実。おそらく自分の思考回路は著者に近いのだろう。論理的に考えるの好きだしね。それゆえ「数学的思考力」云々については「言われなくてもわかってる」という拒否反応が働いてしまうのかもしれない(苦笑)。
少々辛口トークになってしまったが「理解と習得は違う」という言葉は心に沁みた。好奇心だけで動いていると理解した時点で満足してしまうことが多い。これは昔からの悪いクセで、実際時が経つとかなりの部分を忘れている(苦笑)。最近は自分の記憶力をあてにせず、できるだけ記録を残しておくようになったが、本書でそういった自分の行為を的確に表現する言葉に出会い、目からウロコの気分であった。
Customer Reviews
ちょっと気になったのが、著者の持論である「数学的思考力」がことあるごとに持ち出される点。穿った見方かもしれないが、それを宣伝するための実例として経済や年金問題が使われていると思える節さえある(他の書評などを読むと元々そういう位置付けの本でもあるようだが・・・)。著者自身、文章を書くのは不得手と告白しているのだから、そこは割り切ってほしかった。自説の論証というよりキャッチセールスの口説き文句に近い文章は読んでいてちょっと萎えてしまう。
ただ世間一般の評価はかなり高く、自分の感覚とはズレがあるのも事実。おそらく自分の思考回路は著者に近いのだろう。論理的に考えるの好きだしね。それゆえ「数学的思考力」云々については「言われなくてもわかってる」という拒否反応が働いてしまうのかもしれない(苦笑)。
少々辛口トークになってしまったが「理解と習得は違う」という言葉は心に沁みた。好奇心だけで動いていると理解した時点で満足してしまうことが多い。これは昔からの悪いクセで、実際時が経つとかなりの部分を忘れている(苦笑)。最近は自分の記憶力をあてにせず、できるだけ記録を残しておくようになったが、本書でそういった自分の行為を的確に表現する言葉に出会い、目からウロコの気分であった。
     |
「アフターマン」のドゥーガル・ディクソンが著者ということで興をそそられ読んでみました。最初そのタイトルから「恐竜たちの体内構造は現代の地球環境や植生に適応するのか」といった趣旨の専門的な話が書かれていることも想定していたのですが、それは全くの的外れだったようです(今までの著書からすれば、そりゃそうだ)。文章は簡潔に短く、カラー絵を中心とした構成は出来るだけイメージで伝わるように配慮がされており、小学校高学年以上であれば十分理解できるように作られています。映画「ジュラシック・パーク」以降日本での恐竜ブームは久しいですし、今の子供たちに古代生物への関心を持ってもらうための本としては面白い切り口だと思いますね。そういえば三月から国立科学博物館で「大恐竜展」が開かれるんですよ(こちら)。僕も何とか都合をつけて足を運んでみたいなぁなんて思っています。
     |
「あなたはなぜ値札にダマされるのか?」というちょっと挑発的なタイトルに釣られて手に取った一冊。普段ビジネス書なるものはあまり読まないんですが、これはかなり面白かったです。人は誤った判断をしてしまうときにどういう心理状態にあるのか、損得勘定がどう働くのか(こういう分野の研究を行動経済学と呼ぶらしい)。人生で躊躇する場面の多い僕としては「なるほど」という感じでしたね。サブタイトル「不合理な意思決定にひそむスウェイの法則」が示すとおり、本書では「スウェイ」という言葉に焦点が当てられています(原題は "SWAY")。ただそれに関しては別段どうということはなく、個々の話題に関連性を持たせるための副次的な要素に過ぎないでしょう。行動経済学といっても専門用語はほとんど出てきませんし、むしろ雑学的な読み物と捉えてもいいかもしれません。とくに心理学者たちが行った数多くの実験は発想が非常にユニークで、読んでいるだけでも楽しいです。
「○○のための何ヶ条」なんて胡散臭いタイトルの本はそれだけで読む気が失せてしまうんですが、本書のようなビジネス本であればまた手を出してみたいかな。ただ僕の場合、洗練されたビジネスマンを目指しているわけでなく、単に好奇心からそう思うだけなんですけどね(笑)。
      |
「宮崎駿は好きですか?」そうストレートに訊かれたら、おそらく僕は返答に窮するだろう。もちろん好きには違いないのだが、それは "ファン" という括りではないからだ。理屈っぽい表現が許されるならば「一人の人間として非常に興味がある」となる。まだ単なる "ファン" であった頃、彼に関する書籍を手当たり次第読み漁った。それにつれ僕の中で彼の存在は少しずつ変化を遂げてきた。同時に今まで気付かなかった価値観についても色々と考えさせられた・・・。
ジブリ作品が好きで、宮崎駿監督のファンを自認するなら、この「折り返し点 1997-2008」と「出発点 1979-1996」の二冊は読んでおくべきだろう。本人のインタビューや講演、対談などを編纂した資料的色合いの強い構成になっているが、その一つ一つには監督の思想が凝縮されており、そのボリュームもさることながら、とにかく読み応えが十分である。巷ではこれをとってあれやこれやと議論がなされるわけだが、第三者の分析や憶測がいくら束になったところで本人の言葉に勝るものはない。映画から受ける印象でしか彼を知らない人にとっては、そのイメージを壊してしまう発言もあるだろう。しかし彼が「才能の人」である以前に「苦悩の人」であることを理解するだけでも今まで見えなかったものが見えてくるに違いない。それは映画に対しても世の中に対しても言える。
時には専門的な話に傾き、さらっと読んだだけでは到底理解できないものもある。そんなときは無理に理解しようとせず、飛ばしてしまっていいと思う。興味というものは少しずつ芽生えてくるものだし、知識や教養がついてからいつでもその話に戻ってくることができる。まずは重いテーマにとらわれず、自分が興味のあるインタビューから拾い読みしてみるのはどうだろう。映画の裏設定や制作現場の裏話など映画を観ただけでは分からない話も数多い。本人の発言はまさにトリビアの宝庫である。
ジブリ作品が好きで、宮崎駿監督のファンを自認するなら、この「折り返し点 1997-2008」と「出発点 1979-1996」の二冊は読んでおくべきだろう。本人のインタビューや講演、対談などを編纂した資料的色合いの強い構成になっているが、その一つ一つには監督の思想が凝縮されており、そのボリュームもさることながら、とにかく読み応えが十分である。巷ではこれをとってあれやこれやと議論がなされるわけだが、第三者の分析や憶測がいくら束になったところで本人の言葉に勝るものはない。映画から受ける印象でしか彼を知らない人にとっては、そのイメージを壊してしまう発言もあるだろう。しかし彼が「才能の人」である以前に「苦悩の人」であることを理解するだけでも今まで見えなかったものが見えてくるに違いない。それは映画に対しても世の中に対しても言える。
時には専門的な話に傾き、さらっと読んだだけでは到底理解できないものもある。そんなときは無理に理解しようとせず、飛ばしてしまっていいと思う。興味というものは少しずつ芽生えてくるものだし、知識や教養がついてからいつでもその話に戻ってくることができる。まずは重いテーマにとらわれず、自分が興味のあるインタビューから拾い読みしてみるのはどうだろう。映画の裏設定や制作現場の裏話など映画を観ただけでは分からない話も数多い。本人の発言はまさにトリビアの宝庫である。
      |
宮崎駿氏の発言は常に独自の理論に満ちている。その思想の是非は別として、個人的には非常に惹かれるものがある。活字媒体で多くの発言に触れてきたが、いささか理屈っぽいので苦手な人は苦手だろう。一言で言えば頑固親父である(笑)。そんな個性的な監督と苦楽を共にしてきた戦友の一人がジブリ作品のプロデューサー鈴木敏夫氏である。本書では宮崎駿、高畑勲という二大監督との関係を軸として製作現場の裏話が色々と語られる(実際はインタビュー形式で行われた発言を編集者がまとめている)。巷に溢れるジブリ研究本とは異なり、当人だからこそ知りえる話も数多い。また記録よりも記憶を信条とする氏だけに過去の会話を中心とした内容は生の雰囲気をしっかりと伝えてくれる。これが本書の読みやすさにも繋がっていると思う。あわせて「映画道楽」もお奨めしたいが、手っ取り早く氏の話を聞く手段として、TOKYO FM で放送中の「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」という番組がポッドキャストでも配信されているので興味のある向きはどうぞ。
ジブリ汗まみれ:
http://www.tfm.co.jp/asemamire/
      |
ダイオキシンの毒性、リサイクルの必要性、急速に進む地球温暖化、どれも今まで当たり前のように受け入れてきた環境問題である。しかし著者はこれらが必ずしも正しくないことを読者に説く。そこに隠された真意とは何なのか。誰が仕掛け、誰が騙されているのか。我々はメディアから流れてくる情報をそのまま信じてしまう傾向にある。しかしそれらは果たして真実なのだろうか。一旦社会通念とみなされたことを翻すのは容易ではない。誰が天動説の時代に地動説を支持しただろう。今なら一笑に付されるような話だが、我々は本当にそれを笑っていられるのだろうか。本書では「ダイオキシンは無害に等しい」、「リサイクルを進めるほうが環境破壊だ」、「地球温暖化はウソである」といったショッキングな持論が展開されている。読み進めるにつれ何が真実なのか、それすらわからなくなってくる恐怖を感じた。大切なのは何事も鵜呑みにせず自分なりの判断基準を持つことであるが、それを痛感させてくれる一冊でもあった。決してトンデモ本の類ではないのでお間違えなきよう。ちなみに本書はシリーズ化され、現在第三弾まで刊行されている。
      |
本書はタイトルに YouTube という名前を冠しているものの、内容は YouTube にあらず。2007年初頭、ニューヨークはマンハッタンに滞在した著者がアメリカという国の現代そして未来を政治・経済の観点から綴ったエッセイである。YouTube という単語はネット時代の代名詞として何度か出てくるに過ぎず、それを期待していると見事に肩透かしを喰らう。読者の気を引きたいのはわかるが、やっぱり書籍のタイトルは内容を端的に表すものであって欲しい。ときに斬新あるいは奇抜なタイトルはそれ自体が強力な宣伝となり得るが、単に流行語をくっつけるという安易な発想は、せっかくの読者に対して陳腐なイメージを与えるだけだと思う。
とはいえせっかく借りた本だから読んでみた。エッセイという読みやすい形式であったこともあり、最初の悪印象に反して結構楽しめた。ああだこうだと分析が先行する内容だったら、さぞかし詰まらないものになっていただろう。それだけに著者の体験談は固くなりがちな話題に程よく柔らかさを与えている。
読み終えて益々タイトルの選択を誤っていると感じた。これはサブタイトルに用いられている "メディア革命" という言葉にも当て嵌まる。本書では殊更 IT に関して紙面を割いているわけではないからである。オリジナルのコラムは「世界の街角から」だったそう。それに倣って「ニューヨークの街角から」あるいは「マンハッタンの街角から」でも良かったのではないだろうか。そのほうが余程等身大で本書を表していると思う。ただ自分自身 "YouTube" というキーワードで見つけたのも事実。今の時代、ネット検索に迎合したタイトルの付け方が大事ということか? 何となく出版社側の思惑が見え隠れしていて後味の悪さを感じずにはいられなかった。勿体ない・・・。
      |