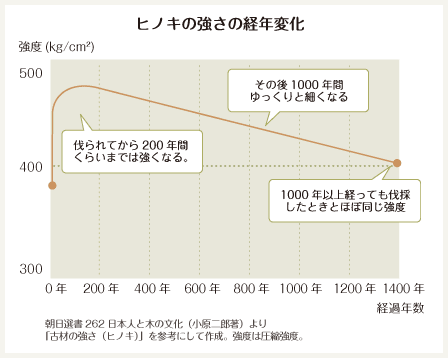床下エアコンは、断熱にさほど興味のない
工務店も引き付ける魅力を持っているようです。
実際、たくさんの工務店が見よう見まねでまねしています。
しかし、1台のエアコンで満足した効果が得られるのは、
最低でも旧IV地域においてQ値1.9以下、C値1以下で、
できれば南からの日射取得を多くし、
東西北面の窓は小さくするといった基本ができた上での話です。
基本ができていないのに、この方式だけまねしても
効果を期待することはできません。
また、床下だけ暖めれば快適だと考える人も
多いようですが、室内空気も暖めなければ暖かさの
実感は得にくいです。特に2階との温度差がより
激しくなってしまいます。
床下エアコンの暖気が大量に床上に出るように、
大きなスリットも必要になります。
東北地方や北陸地方で床下エアコンを実践している人は、
一般的な壁掛けエアコンを床下に設置している
事例がとても多いです。
一方、暑さが厳しい関東以西で床下エアコン
とする場合、夏場の冷房利用も兼ねないともったいないです。
ですから、もりぞうでは、1台のエアコンで
【しかも天井埋め込み型】
このような暖房だけではなく

こちらのような冷房も出来るシステムを
構築しております。

冷房に関しては、小屋裏に冷房専用ダクトで
冷風を送れば、家全体を冷房できます。
24時間作動していれば
1階まで効果は届きますが、1階をより強く
冷やしたい場合は、1階と2階の階間にも
冷風を吹き込みます。
延べ面積が40坪までで日射遮蔽がきちん
とできている住宅では、8月に24時間冷房しても
月間の冷房費用は5000円以内で収まることが多いです。
快適性はもちろんのこと、相対湿度も60%程度に
抑えることができ、高湿度が大好きなカビやダニ
との共存を極力避けた生活も可能となります。
これは、膨大な水分を室内に取り入れてしまう
「通風」では絶対に不可能な芸当です。
通風を全否定するつもりはありませんが、
通風が快適なのは5月と10月だと考えています。
ただ、5月は花粉症で窓を開けられない家庭も多いので、
実質的には10月に限られるでしょう。
このように省エネ住宅とは、単に基準や設備に
頼るものではありません。
上級者になればなるほど、地味であってもより
コストパフォーマンスが高いものを地道に確実に
積み上げていくものだ思います。
全てはコンセプト実現のために。。
工務店も引き付ける魅力を持っているようです。
実際、たくさんの工務店が見よう見まねでまねしています。
しかし、1台のエアコンで満足した効果が得られるのは、
最低でも旧IV地域においてQ値1.9以下、C値1以下で、
できれば南からの日射取得を多くし、
東西北面の窓は小さくするといった基本ができた上での話です。
基本ができていないのに、この方式だけまねしても
効果を期待することはできません。
また、床下だけ暖めれば快適だと考える人も
多いようですが、室内空気も暖めなければ暖かさの
実感は得にくいです。特に2階との温度差がより
激しくなってしまいます。
床下エアコンの暖気が大量に床上に出るように、
大きなスリットも必要になります。
東北地方や北陸地方で床下エアコンを実践している人は、
一般的な壁掛けエアコンを床下に設置している
事例がとても多いです。
一方、暑さが厳しい関東以西で床下エアコン
とする場合、夏場の冷房利用も兼ねないともったいないです。
ですから、もりぞうでは、1台のエアコンで
【しかも天井埋め込み型】
このような暖房だけではなく

こちらのような冷房も出来るシステムを
構築しております。

冷房に関しては、小屋裏に冷房専用ダクトで
冷風を送れば、家全体を冷房できます。
24時間作動していれば
1階まで効果は届きますが、1階をより強く
冷やしたい場合は、1階と2階の階間にも
冷風を吹き込みます。
延べ面積が40坪までで日射遮蔽がきちん
とできている住宅では、8月に24時間冷房しても
月間の冷房費用は5000円以内で収まることが多いです。
快適性はもちろんのこと、相対湿度も60%程度に
抑えることができ、高湿度が大好きなカビやダニ
との共存を極力避けた生活も可能となります。
これは、膨大な水分を室内に取り入れてしまう
「通風」では絶対に不可能な芸当です。
通風を全否定するつもりはありませんが、
通風が快適なのは5月と10月だと考えています。
ただ、5月は花粉症で窓を開けられない家庭も多いので、
実質的には10月に限られるでしょう。
このように省エネ住宅とは、単に基準や設備に
頼るものではありません。
上級者になればなるほど、地味であってもより
コストパフォーマンスが高いものを地道に確実に
積み上げていくものだ思います。
全てはコンセプト実現のために。。