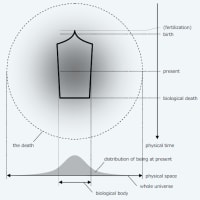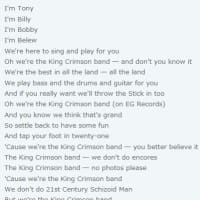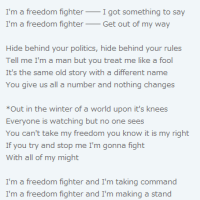第8章 人権(human rights)
8-1 地位機能から導かれる権利義務力としての権利
我々はベンサム/マッキンタイア流の懐疑論に答えることができるだろうか。わたしはできると思う。しかしそのためには、我々は普遍的人権を地位機能として認識しなければならない。それらは割り当てられた地位から導かれた権利義務力である、というように。懐疑論の真実は、顔の上に鼻があるというようには、人々が普遍的人権を持つことを見出せないということにある。そうした権利の存在は志向性相対である、というのもそれは人間が創出したものだからである。しかしそれらの存在論的地位が明確になれば、権利の存在はもはやお金・私有財産・交友といったものほどにも神秘ではなくなる。お金・私有財産・交友についての信念を無意味だと言うものはない。
一般的に言って、財産権や夫の権利(marital right)のような権利が地位機能であるということは自明であろう。つまり、それらは集合的に認識された地位から導かれる権利義務力である。それらは人々に授課(impose)※された、また集合的な認識または受容によってのみ機能しうるような権利義務力である
これが、ロビンソン・クルーソーが彼の無人島で人権を持つ、ということが的外れというか、たぶん無意味であることの理由である。彼が人権を持つという場合、それは彼がいなくなったことを知っている人々によって捜索される権利を含むのだが、つまり我々が彼を人間社会の一員だと思っているということである。
権利は地位機能であるから、それは直ちに志向性相対であるということになる。それらは常に集合的志向性によって創出され授課される。それらは、光合成や水素イオンがそうであるように自然の中で見出されるものではない。人権の創出と維持の論理的な構造によって、以下のふたつの文は、いかに論理的に矛盾するように見えたとしても無矛盾な表現として解釈される。
もしすべての表出が一義的に(univocally)解釈されるものならば、これらのふたつの文は矛盾である。けれどもこれらを無矛盾な表現である(render them consistent)と解釈する道筋が存在する。本章の目的はそれらが見かけの差異にもかかわらず、どのように無矛盾であるのかを示すことである。明らかな矛盾を解決し、懐疑論的な疑いに答えるために、我々は普遍的人権の創出の本性と、それらの存在の正当化について説明しなければならないだろう。
8-1 地位機能から導かれる権利義務力としての権利
我々はベンサム/マッキンタイア流の懐疑論に答えることができるだろうか。わたしはできると思う。しかしそのためには、我々は普遍的人権を地位機能として認識しなければならない。それらは割り当てられた地位から導かれた権利義務力である、というように。懐疑論の真実は、顔の上に鼻があるというようには、人々が普遍的人権を持つことを見出せないということにある。そうした権利の存在は志向性相対である、というのもそれは人間が創出したものだからである。しかしそれらの存在論的地位が明確になれば、権利の存在はもはやお金・私有財産・交友といったものほどにも神秘ではなくなる。お金・私有財産・交友についての信念を無意味だと言うものはない。
一般的に言って、財産権や夫の権利(marital right)のような権利が地位機能であるということは自明であろう。つまり、それらは集合的に認識された地位から導かれる権利義務力である。それらは人々に授課(impose)※された、また集合的な認識または受容によってのみ機能しうるような権利義務力である
| ※ | ・・・なんでかよくわからないが、今の今まで「impose」を「埋め込む」と訳していた。いま改めて辞書を引いてみたらそんな訳はどこにもねえ(爆笑)。またしても記憶違いである。もっとも、辞書を見ても「課する」「負わせる」「無理強いする」という訳があるだけで、これらを当てはめてもうまく通らない。これはつまり「deontology」が通常は「義務論」と訳されていることとパラレルなのである。「義務を課する」なら通るわけである。だが「権利を課する」という日本語はありえない。権利は、同じ文脈でいうなら「授ける」ものであろう。そこで、今後は「deontology」に対応する「impose」は、「deontology」を「権利義務論」と訳しているのだから、これもふたつをくっつけて「授課する」と訳す。当然ながらこれまで訳してきた部分も全部誤訳だったわけなので、この語に置き換えなければならない。 |
これが、ロビンソン・クルーソーが彼の無人島で人権を持つ、ということが的外れというか、たぶん無意味であることの理由である。彼が人権を持つという場合、それは彼がいなくなったことを知っている人々によって捜索される権利を含むのだが、つまり我々が彼を人間社会の一員だと思っているということである。
権利は地位機能であるから、それは直ちに志向性相対であるということになる。それらは常に集合的志向性によって創出され授課される。それらは、光合成や水素イオンがそうであるように自然の中で見出されるものではない。人権の創出と維持の論理的な構造によって、以下のふたつの文は、いかに論理的に矛盾するように見えたとしても無矛盾な表現として解釈される。
| 1. | 言論の自由に関する普遍的な権利はヨーロッパの啓蒙主義(European Enlightenment)の時代に存在するようになったもので、それ以前には存在しなかった。 |
| 2. | 言論の自由に関する普遍的な権利はいつでも存在するが、この権利はヨーロッパの啓蒙主義の時代において初めて認識された。 |
もしすべての表出が一義的に(univocally)解釈されるものならば、これらのふたつの文は矛盾である。けれどもこれらを無矛盾な表現である(render them consistent)と解釈する道筋が存在する。本章の目的はそれらが見かけの差異にもかかわらず、どのように無矛盾であるのかを示すことである。明らかな矛盾を解決し、懐疑論的な疑いに答えるために、我々は普遍的人権の創出の本性と、それらの存在の正当化について説明しなければならないだろう。