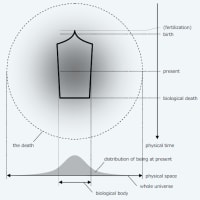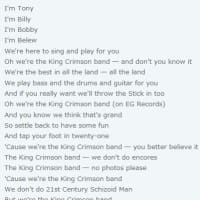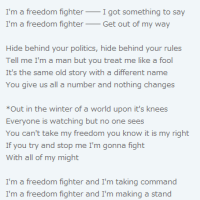結びにかえて:社会科学の存在論的基礎
人間社会の大部分は地位機能の割り当てによって権利義務的な権力関係を創出し分配する顕著な制度的構造によって構成されるものであり、その地位機能は社会の中の異なる社会的役割[を割り当てる]ものだというわたしの考えが正しいと仮定しよう。そうした説明に意味があるとして、それは社会科学の研究の実際にとって何を意味するのだろうか?一言で答えるなら「正直、わからん」である。先々の研究において何が有用でありうるかなどということはわからない。社会科学には数多くの研究分野があるわけで、少なくとも原則としては、それらは概念的な基礎を問う必要はないのである。たとえばわたしはパリで行われたピエール・ブルデュー記念講演においてこれらの主題に触れたことがあった。
その聴衆のひとり(彼は労働組合の社会学を専攻しているアメリカの社会学者だった)がわたしに告げたのは、彼の仕事はわたしの仕事が終わったところから始まるのだということだった。彼の言わんとしたことはつまり、労働組合の存在論的基礎などというものを知る必要はない、ということだろうと思われた。彼が理解しなければならないことのすべては、歴史的に特定的に位置づけられた組織の現実的な活動(operations)である[というわけである]。彼の抱いている(とわたしには思える)図式はつまり、地質学者は原子物理学の詳細について知らなくても地殻プレートの動きについて研究することができるように、彼(社会学者)は社会的存在論の詳細を理解しなくても労働組合運動について研究できるのだということである。そらまあそうだ。しかしわたしの本能が告げていることは、基礎的な問題を理解することはどんな場合でもよい考えだということである。どんな研究分野であれその基礎存在論を理解することは、その研究分野における問題への理解を深めるものであるはずだと考えることは、わたしにはずっともっともらしいことだと思える。本書のどの部分であれ、わたしは既存の社会科学についての哲学をもたらそうとは試みていない。そうではなく社会科学で研究されている実体の基礎的な存在論の論理分析を行ったのである。これはたぶん、未来の社会科学において有用であることが示されうる──逆に無用だと示されるかもしれないのだが。
オックスフォードの学部生だったころ、経済学の講師たちの中に、研究上の存在論的前提について案じている人はいなかった。わたし(たち)は貯蓄額が投資額に等しい(S=I)と教わったが、その調子には物理学において、力は質量と加速度の積に等しい(F = ma)と教わる場合と同じ響きがあったものである。我々は、限界費用が限界収入に等しいということを、水は水素と酸素の化合物であると教わる(discovered)のと同じように教わったのである。経済の現実は科学的に探求可能な世界の現実の一部として扱われていた。それよりも前、ウィスコンシン州立大学で社会学の課程を履修していたときも、そこで基礎的な存在論の問題はまったく扱われていなかった。これは以前も言ったことだが、わたしは、存在論的問題などに煩わされなくても、しばしばよい研究は行われうると思っている。
しかし探求している当の現象についての存在論について鋭い意識を持つならば、探求の全体はより深いものになるのである。たとえばお金やその他のブツ(instruments)を、あたかも物理化学生物学で研究されている自然現象であるかのように扱うことは誤りである[太字は訳者がつけた]。近年における経済危機はそれらが大規模な幻想の産物であることをはっきりさせた。誰もがその幻想を共有し確信を抱いている間は、体系はよく機能するであろう。しかしその幻想のいくつかがもはや信じられなくなると、サブプライム抵当証書(subprime mortgage instrument)がそうなったように、全体系が破綻し始める。わたしは近年における経済学の制度学派への関心の復活を歓迎する。*
この本では(少なくとも)3つの非常に強い主張を行っている。そうした主張は可能な限り強い形で主張することが重要である。なぜならそれらは容易に反駁できるからである。
探求の帰結は、すべての社会的・制度的現実は共通の構造的基盤を持っているということである。これが正しければ、社会学や経済学といった社会科学の各分野を、それぞれ基本的に異なる主題を扱う部門(branch)として扱うことは間違いだということになる。社会科学の異なる分野は当然互いに完全にガラス張り(transparent)であるべきである。人間の制度の奇妙かつ素晴らしい広がりのすべては、特別な形の言語的表象、すなわち地位機能宣言の反復適用によって権力の分布を象り、あるいは象り直すことの例である。このあとがきの最初の方では、よい地質学者となるために原子物理を詳しく知る必要はないかもしれないことの可能性について考えた。それでもやはり、自然科学のどんな分野においても、あなたはすべてが原子的な構造を持つことを理解しなければならない。社会科学の研究主題の存在論を完全に理解するためには、わたしが記述しようと試みてきた構造の理解を必要とするはずである。
わたしは社会科学と自然科学の類比から過大なものを引き出そうとは思わない。つまりわたしの説明はいささかも還元主義的なものではない。ただ、この説明が正しければ、社会科学のさまざまな分野はすべて、あらゆる社会的現実に共通な権力構造を扱うものだということになる。そして、わたしはその権力構造を創出し維持する基本的な機械論を記述しようと試みてきたのである。
人間社会の大部分は地位機能の割り当てによって権利義務的な権力関係を創出し分配する顕著な制度的構造によって構成されるものであり、その地位機能は社会の中の異なる社会的役割[を割り当てる]ものだというわたしの考えが正しいと仮定しよう。そうした説明に意味があるとして、それは社会科学の研究の実際にとって何を意味するのだろうか?一言で答えるなら「正直、わからん」である。先々の研究において何が有用でありうるかなどということはわからない。社会科学には数多くの研究分野があるわけで、少なくとも原則としては、それらは概念的な基礎を問う必要はないのである。たとえばわたしはパリで行われたピエール・ブルデュー記念講演においてこれらの主題に触れたことがあった。
| ※ | サールは生前のブルデューと親交があり、招かれてコレージュ・ド・フランスで講義したこともあるらしい。 |
その聴衆のひとり(彼は労働組合の社会学を専攻しているアメリカの社会学者だった)がわたしに告げたのは、彼の仕事はわたしの仕事が終わったところから始まるのだということだった。彼の言わんとしたことはつまり、労働組合の存在論的基礎などというものを知る必要はない、ということだろうと思われた。彼が理解しなければならないことのすべては、歴史的に特定的に位置づけられた組織の現実的な活動(operations)である[というわけである]。彼の抱いている(とわたしには思える)図式はつまり、地質学者は原子物理学の詳細について知らなくても地殻プレートの動きについて研究することができるように、彼(社会学者)は社会的存在論の詳細を理解しなくても労働組合運動について研究できるのだということである。そらまあそうだ。しかしわたしの本能が告げていることは、基礎的な問題を理解することはどんな場合でもよい考えだということである。どんな研究分野であれその基礎存在論を理解することは、その研究分野における問題への理解を深めるものであるはずだと考えることは、わたしにはずっともっともらしいことだと思える。本書のどの部分であれ、わたしは既存の社会科学についての哲学をもたらそうとは試みていない。そうではなく社会科学で研究されている実体の基礎的な存在論の論理分析を行ったのである。これはたぶん、未来の社会科学において有用であることが示されうる──逆に無用だと示されるかもしれないのだが。
オックスフォードの学部生だったころ、経済学の講師たちの中に、研究上の存在論的前提について案じている人はいなかった。わたし(たち)は貯蓄額が投資額に等しい(S=I)と教わったが、その調子には物理学において、力は質量と加速度の積に等しい(F = ma)と教わる場合と同じ響きがあったものである。我々は、限界費用が限界収入に等しいということを、水は水素と酸素の化合物であると教わる(discovered)のと同じように教わったのである。経済の現実は科学的に探求可能な世界の現実の一部として扱われていた。それよりも前、ウィスコンシン州立大学で社会学の課程を履修していたときも、そこで基礎的な存在論の問題はまったく扱われていなかった。これは以前も言ったことだが、わたしは、存在論的問題などに煩わされなくても、しばしばよい研究は行われうると思っている。
| ※ | 「しばしば」は原文ではsometimesである。どことなく「しぶしぶ」認めているような感じのすることが微笑ましい。 |
しかし探求している当の現象についての存在論について鋭い意識を持つならば、探求の全体はより深いものになるのである。たとえばお金やその他のブツ(instruments)を、あたかも物理化学生物学で研究されている自然現象であるかのように扱うことは誤りである[太字は訳者がつけた]。近年における経済危機はそれらが大規模な幻想の産物であることをはっきりさせた。誰もがその幻想を共有し確信を抱いている間は、体系はよく機能するであろう。しかしその幻想のいくつかがもはや信じられなくなると、サブプライム抵当証書(subprime mortgage instrument)がそうなったように、全体系が破綻し始める。わたしは近年における経済学の制度学派への関心の復活を歓迎する。*
| * | Lawson, Tony, Economics and Reality, New York: Routledge, 1997.[リンクは可能な限り安価なペーパーバック版の方に張っているのだが、この本、ペーパーバックのくせして無茶苦茶高価である] |
| ※ | そう言えばわたしが複雑性研究の学生として初めて哲学を意識させられたのも、こんな風な経済の問題を考えている中でのことだった。そのとき読んでいた文献の中には制度学派の文献もあったものである。 |
この本では(少なくとも)3つの非常に強い主張を行っている。そうした主張は可能な限り強い形で主張することが重要である。なぜならそれらは容易に反駁できるからである。
| (1) | 人間の制度的現実はすべて、またその意味で人類文明のほとんどすべては、単一の論理的言語的作用によって存在を開始し、かつその存在を持続する。 |
| (2) | 我々はその作用が厳密に何であるかを言うことができる。それは地位機能宣言である。 |
| (3) | 人類文明の途方もない多様さと複雑さは次のような事実によって説明される:その作用は適用対象において制約されるものではなく、再帰的なやりかたで、つまり、しばしば以前の適用の産物に対して適用されるなどして、さまざまに、また適用対象が互いに連動(interlocking)しながら何度となく繰り返し適用され、実際の人間社会の複雑な構造のすべてを創出する。 |
探求の帰結は、すべての社会的・制度的現実は共通の構造的基盤を持っているということである。これが正しければ、社会学や経済学といった社会科学の各分野を、それぞれ基本的に異なる主題を扱う部門(branch)として扱うことは間違いだということになる。社会科学の異なる分野は当然互いに完全にガラス張り(transparent)であるべきである。人間の制度の奇妙かつ素晴らしい広がりのすべては、特別な形の言語的表象、すなわち地位機能宣言の反復適用によって権力の分布を象り、あるいは象り直すことの例である。このあとがきの最初の方では、よい地質学者となるために原子物理を詳しく知る必要はないかもしれないことの可能性について考えた。それでもやはり、自然科学のどんな分野においても、あなたはすべてが原子的な構造を持つことを理解しなければならない。社会科学の研究主題の存在論を完全に理解するためには、わたしが記述しようと試みてきた構造の理解を必要とするはずである。
わたしは社会科学と自然科学の類比から過大なものを引き出そうとは思わない。つまりわたしの説明はいささかも還元主義的なものではない。ただ、この説明が正しければ、社会科学のさまざまな分野はすべて、あらゆる社会的現実に共通な権力構造を扱うものだということになる。そして、わたしはその権力構造を創出し維持する基本的な機械論を記述しようと試みてきたのである。