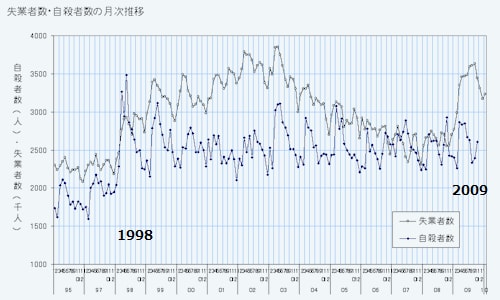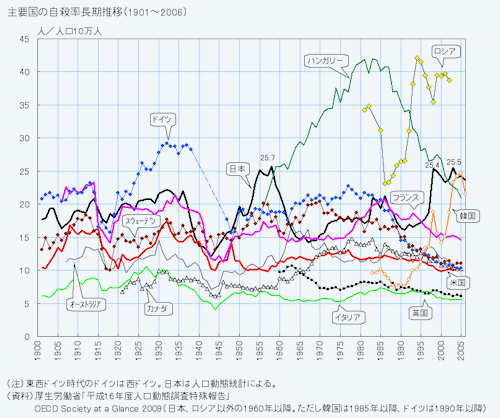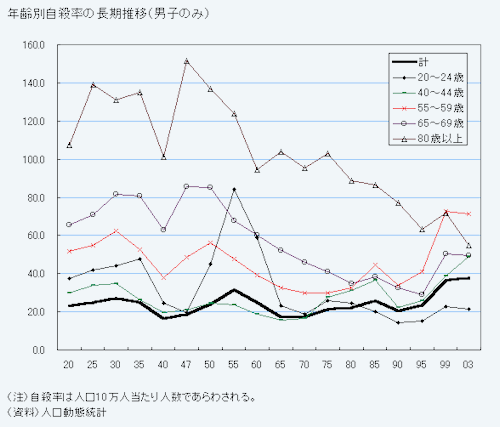上のグラフは資源エネルギー庁のサイトにある2007年までのデータと、あとはいろんなところから探してきたそれ以後のデータをくっつけたものである。
実は最初は最終エネルギー消費量のはなしを書こうとしていたわけだが、上のグラフを見てたいていの人が最初に驚くのは実質GDPの推移の方ではないかと思う。まるで「失われた20年」などなかったかのごとく順調に、おおよそ線形に単調増加しているわけである。どうしてこうなるのかというと、最近の日本経済は年1%ペースでデフレを起こしている一方で、名目GDPはほぼ横ばいである、結果上のように実質GDPは増えているわけである。また過去の高度成長期はインフレだったわけで、名目の伸びほどに実質は伸びていない、ということで結局、この半世紀近くの間、わが国の実質GDPはほぼ線形に単調増加してきたのである。
そして一方のエネルギー消費、特に民生部門の数字がこの実質GDPの推移にほぼ沿っているわけである。こちらの単位はEJ(エクサ・ジュール)で、つまり熱量換算のそのままだから、インフレもデフレもない、実際の数字のそのままなのである。
言わないと気づかないかもしれないから言うと、実質GDPや民生部門のエネルギー消費量が「線形に単調増加」しているというのは、いったい何を意味しているのか、直観的にはよくわからないわけである。GDPについてはしょっちゅう報道されているように、その増減は経済成長「率」で表示されるわけである。つまり経済規模の時間発展というのは普通は乗算的に眺められるものなのである。方程式で書けばdx/dt=cxで、これを(右辺がxの1次式つまり線形の式なので)線形方程式とか線形モデルというのである。実質GDP他の指標はそうなっていない、まるで時計が時間を刻むように増えているわけである。
それって何だと考えて、わたしがふと思ったのは「365歩のマーチ」である。1日1歩3日で3歩、3歩進んでリーマンショック(笑)、である。いや笑いごとではない。特に民生部門のエネルギー消費がそうだというのは、この指標こそは、この半世紀の間わが日本社会の人々がこぞって「汗かきべそかき」ながら歩んできたところを最もよく表示しているのではなかろうか。なんとなくそんな気がすることである。