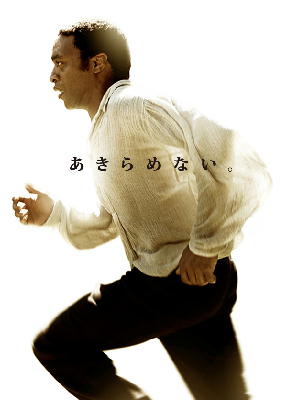映画「大いなる沈黙へ」とは、フランスアルプス山脈に立つグランド・シャトルーズ修道院を長期取材した、ドキュメンタリー映画だ。
映画「大いなる沈黙へ」とは、フランスアルプス山脈に立つグランド・シャトルーズ修道院を長期取材した、ドキュメンタリー映画だ。
それもかなり変わった映画で、立ち入りを許されたのは一人だけ。つまり監督・カメラ兼録音など、すべてを一人でこなすしかない。だからセリフというものがない。延々とムービーを回すと同時の、その実況録音しかない。それが雨の音、歩く音程度・・・ほとんど昔のサイレント映画なのだ。それが2時間55分続く。唯一あるのはミサ時のグレゴリアン・チャント風、修道士たちの生歌だけ。
 しかし私は非常に興味があった。なにしろ世界一厳しい修道院だそうで、撮影許可が出ること自体、稀有なことだそうだ。その意味では非常に価値がある。
しかし私は非常に興味があった。なにしろ世界一厳しい修道院だそうで、撮影許可が出ること自体、稀有なことだそうだ。その意味では非常に価値がある。
また「何が厳しいか?」というと、会話の厳禁だろう。なにしろ日曜日の昼食後の散歩の時だけで、後は無言で丸々一週間過ごすのだ。おしゃべり好きな人間にとっては、発狂ものだろう。
25才の時、わたしはこの修道会ではないが、カトリックの修道院に入ろうとしたことがあった。そういう意味でも大いに興味があった。
この映画の価値を、ある人は修道院を取り巻く美しいアルプスの自然に目を向けるかもしれない。また、覗き得た修道士たちの生活かもしれない。しかしそれは本質ではない。本質は沈黙なのだ。
沈黙には意味がある。神の声を聞き、御心を求めるに は、私たちが饒舌であってはならないのだ。少年サムエルのごとく「しもべは聞きます、主よ、お語り
ください」なのだ。その背景には、老修道士が語っていたように、「神は私の全てを知っておられ、私たちには善なることしか神はおできにならないのだ(という信仰を語っていた)。(自分は老いて盲目になったが)これにも神が自分の魂をきよくしてくださるお恵みなのだ」と。
は、私たちが饒舌であってはならないのだ。少年サムエルのごとく「しもべは聞きます、主よ、お語り
ください」なのだ。その背景には、老修道士が語っていたように、「神は私の全てを知っておられ、私たちには善なることしか神はおできにならないのだ(という信仰を語っていた)。(自分は老いて盲目になったが)これにも神が自分の魂をきよくしてくださるお恵みなのだ」と。
だから修道院は静寂の中、自然の音以外は静まりかえっている。人は沈黙し、ひたすら聞き役に徹して祈りに専念する。
確かに聞くことは、あれこれ願い事や求めの祈りをすることより、はるかに優ることに気づかされた。そしてこれは、かねてそうではないかと思っていた私に、ある確信を抱かせるものにもなった。
唯一疑問点をあげるとすれば、映画で幾度も登場する御言葉風なものが、おそらく聖書ではないか、または、かなりの見当外れの誤訳が聖書と同等に扱われていたことだ。これはいただけない。(神保町岩波ホールで公開中) ケパ

















 一つ・・・・「夫婦げんかは避けられないが、必ずその日の内に仲直りをする。ベッドの中までは絶対に持ち込まない」こと。放っておくと、些細なとげでも化膿をはじめてしまい、最後は壊疽になって死に至る。テニスは勝負がつくまでは時間制限がない過酷さがある。しかし夫婦間はサッカー方式でいく。つまり「その日中に」という時間制限を設け、延長しても決着がつかねば体面を考えずPKでその日の内にけりをつけてしまう。夫婦は実に一つのからだであって、勝者はいない。
一つ・・・・「夫婦げんかは避けられないが、必ずその日の内に仲直りをする。ベッドの中までは絶対に持ち込まない」こと。放っておくと、些細なとげでも化膿をはじめてしまい、最後は壊疽になって死に至る。テニスは勝負がつくまでは時間制限がない過酷さがある。しかし夫婦間はサッカー方式でいく。つまり「その日中に」という時間制限を設け、延長しても決着がつかねば体面を考えずPKでその日の内にけりをつけてしまう。夫婦は実に一つのからだであって、勝者はいない。