
「(さだまさしが)ケニアの長崎大学熱帯医学研究所から帰ったばかりの柴田紘一郎医師に出会い、彼の語るケニアに憧れたのはもう40年以上も昔のことになる。
フライング・ドクター、国境近くの村、患者達の美しい瞳、闇夜のダンス、サソリ除けの足の金輪、満天の星、フラミンゴの大群、遙かなる大地、遠く霞むキリマンジャロ山、巨大な象のシルエット……。
そのようなひとつひとつの言葉が見たこともない風景の向こうからいきなり飛び出してきて、僕の心に突き刺さったのだった。
以後プロの歌作りになってから、ずっと彼の語る青年医師の感じたケニアは僕の大切なテーマとなり、憧れとなった。・・・略・・・」

アフリカの大地で、現地の人々の為に、命をかけて、医療と心のケアのために生きた一人の日本人青年医師のストーリーは、さだ本人が若い時分に聞いた医師の実話に触発された、さだまさしの創作である。大沢たかおが映画にしたいとさだに申し出て、それでさだまさしが書き上げ、映画になった。
人が生きる、何が大切なのか、それぞれの選択のようでいて、そうでない、生きる充実度、そのことを問うている作品のようでもある。ただキリスト者としての私から見ると、東日本大震災への「絆」以上の、命を超越した永遠の希望が欲しいと欲張ってしまう。(下写真はアフリカでロケ中の主演大沢たかおとさだまさしのワンショット)
なお、さだまさしが歌っている「風に立つライオン」の歌がこの映画の公式ホームページに載っている。映画の最後にこの曲が流れ、感動を一層高めた。ぜひ視聴をお勧めするとともに、早めに映画を観られたし。ケパ















 (写真は母マリヤ兼、映画のプロデューサーの二人)ただし出来事は聖者に忠実で正確でなければならない。ラザロの場面ではキリストは外で立ってラザロに出てくるよう呼ばわった。中に入って口づけしたりはしていない。しかし、この程度なら演出として許容の範囲内ではないだろうか?
(写真は母マリヤ兼、映画のプロデューサーの二人)ただし出来事は聖者に忠実で正確でなければならない。ラザロの場面ではキリストは外で立ってラザロに出てくるよう呼ばわった。中に入って口づけしたりはしていない。しかし、この程度なら演出として許容の範囲内ではないだろうか?



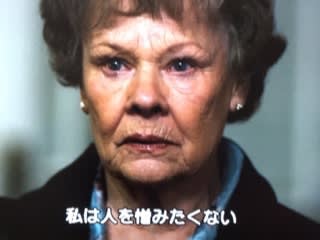




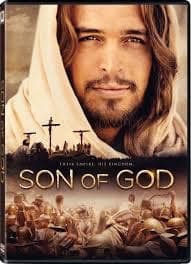 。
。









