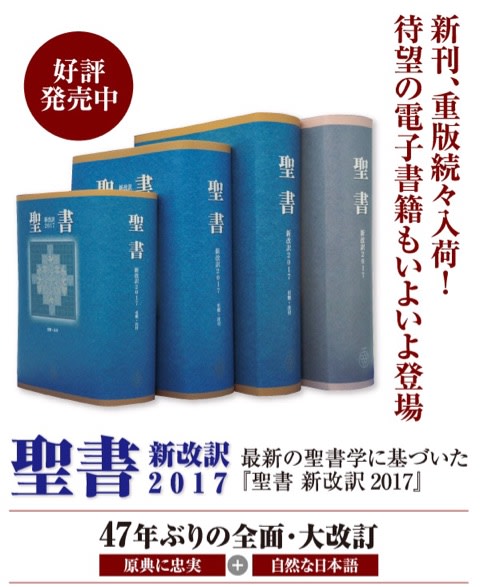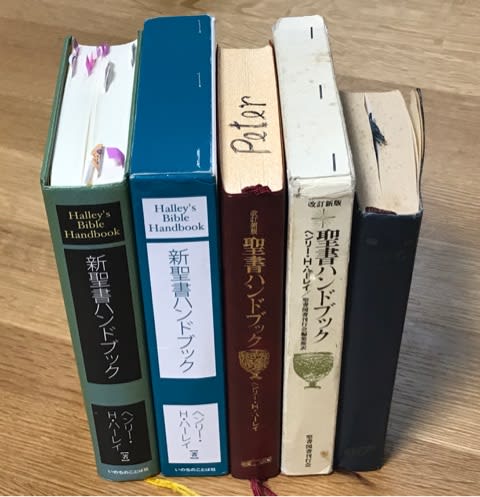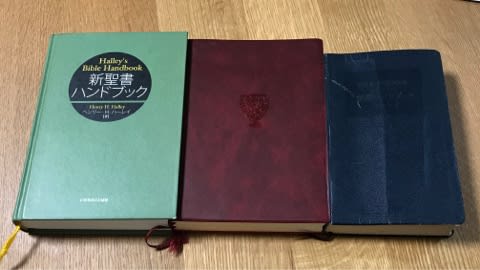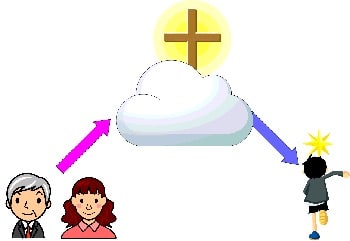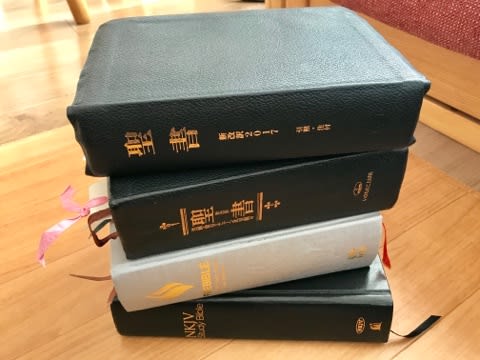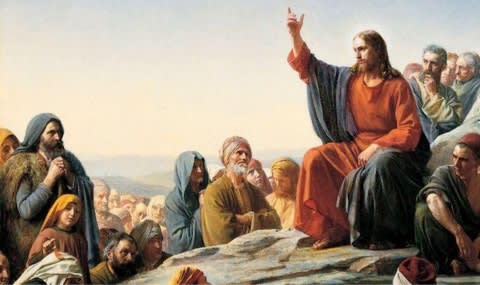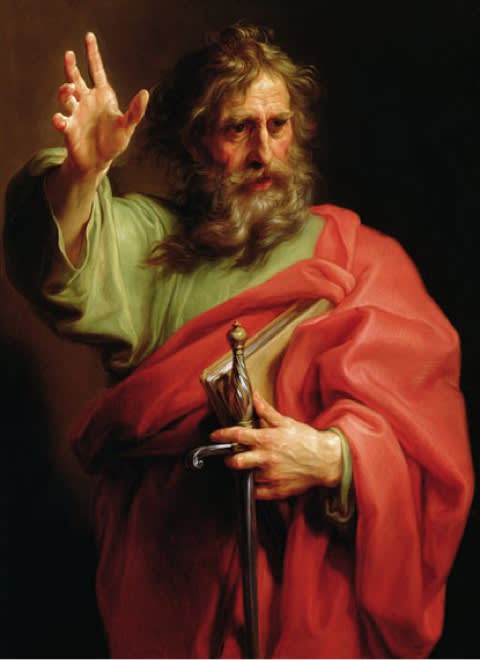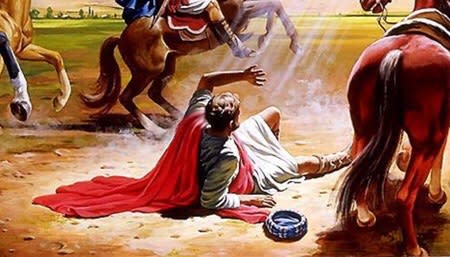時々昔の私の悪い癖で、ものごとを悲観的に見ようとする時がある。また、この能天気な私でも、人並みに恐れがやって来る時もある。
そんな時、こんなみ言葉を思い出す。
My flesh and my heart fail;
But God is the strength of my heart and my portion forever. (NKJV)
下に和訳を付けるが、断然、英語詩篇の方が心にすーっと入ってくる。failとは衰える、落ちる、ダウンすると言う意味だ。my portion 私の安住の割り当ての地は、確かなのだ。これほど安心でき素晴らしいことはない。※たまたま私が判るレベルの箇所だったのであって、実際は貧弱な英語力です。
"この身も心も尽き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩とこしえに私が受ける割り当ての地。"
(詩篇73篇26節 新改訳2017)
しかもこの後、28節、"しかし私にとって神のみそばにいることが幸せです"とある。本当にそうだ。たとえ私の体が衰え、心が萎えそうになっても、主よ、あなたの御そばに居られる幸せは、世の誰も奪うことはできない。
(キレイな私好みの色をしたガーベラ)

ケパ