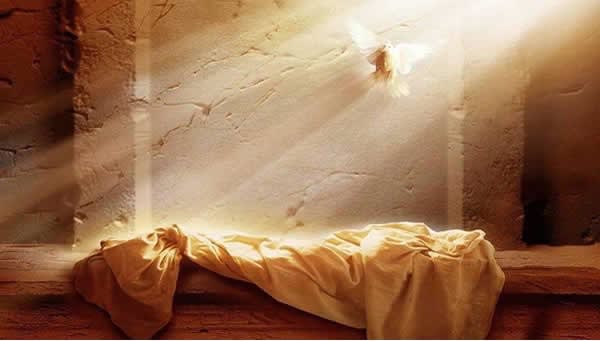イスラム教の原理主義、ISは国としての現状は滅亡寸前であるが、インターネットメディアを通しての影響力は現在も健在であるという。若者たちを惹きつけて止まないと言う。なぜだろうか?

それは彼らISがイスラム的には非常に正しいからだと、日本のイスラム研究者は指摘する(※ 飯山陽著「イスラム教の論理」より)。かつては教役者に独占されていた教典コーランが、今やネットやスマホの普及によって、一般市民にも理解できるようになった。そこで明らかになったのは、私たちが高校で習った「コーランか剣か」が正しいのであり、異教徒に対するジハード(聖戦)」は全イスラム教徒の義務である、と言うことであった。つまりイスラムの正しい教えとは、全世界はイスラムによって征服もしくは統一されなければならず、それをしない穏健なイスラム教は堕落しているというのが、そもそものムハンマド(マホメット)の教えなのだ。この教えに忠実に従って、手段を選ばず世界征服を目指すのがイスラムの原理主義なのだ。。
イスラム原理主義は、世界の平和にとって危険極まりないものだが、これと一緒くたにされて超誤解されているのが、キリスト教の原理主義である。原理主義と言うからには、キリスト教の場合は聖書に忠実ということになる。イスラム教では、コーランが最近になって公開されたのかも知れないが、キリスト教では15世紀のグーテンベルクの印刷機の発明以来、(印刷機の発明者グーテンベルク。先ず聖書を印刷した)

聖書が大量に出回り、流布されてきた。つまりキリスト教のプロテスタント信徒は、みな原理主義から起こってきま歴史があるのである。
聖書を人々が手にした時、免罪符は全く神の御心に背く犯罪的なカトリックの欺きであったし、七つの秘蹟は組織の特権化を図るものであった。たた、法王の権威はマタイ伝16章の単なるこじつけであった。(ヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂。免罪符はこの建設費のためであった)

私たちの群れ、これは言うならば聖書を唯一の拠り所とする、プロテスタント信徒の中のプロテスタント、言うならば原理主義そのものである。聖書は、"神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。"(ヨハネの福音書 3章16節)
と、神の愛を宣べ伝え、イスラムの世界を征服とは全く異なって、
"イエスは答えられた。「わたしの国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、わたしのしもべたちが、わたしをユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし、事実、わたしの国はこの世のものではありません。」"(ヨハネの福音書 18章36節)
と現世を否定された。最終的には現世も含むが、クリスチャンの国とは、霊的な神の国なのである。
ケパ

それは彼らISがイスラム的には非常に正しいからだと、日本のイスラム研究者は指摘する(※ 飯山陽著「イスラム教の論理」より)。かつては教役者に独占されていた教典コーランが、今やネットやスマホの普及によって、一般市民にも理解できるようになった。そこで明らかになったのは、私たちが高校で習った「コーランか剣か」が正しいのであり、異教徒に対するジハード(聖戦)」は全イスラム教徒の義務である、と言うことであった。つまりイスラムの正しい教えとは、全世界はイスラムによって征服もしくは統一されなければならず、それをしない穏健なイスラム教は堕落しているというのが、そもそものムハンマド(マホメット)の教えなのだ。この教えに忠実に従って、手段を選ばず世界征服を目指すのがイスラムの原理主義なのだ。。
イスラム原理主義は、世界の平和にとって危険極まりないものだが、これと一緒くたにされて超誤解されているのが、キリスト教の原理主義である。原理主義と言うからには、キリスト教の場合は聖書に忠実ということになる。イスラム教では、コーランが最近になって公開されたのかも知れないが、キリスト教では15世紀のグーテンベルクの印刷機の発明以来、(印刷機の発明者グーテンベルク。先ず聖書を印刷した)

聖書が大量に出回り、流布されてきた。つまりキリスト教のプロテスタント信徒は、みな原理主義から起こってきま歴史があるのである。
聖書を人々が手にした時、免罪符は全く神の御心に背く犯罪的なカトリックの欺きであったし、七つの秘蹟は組織の特権化を図るものであった。たた、法王の権威はマタイ伝16章の単なるこじつけであった。(ヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂。免罪符はこの建設費のためであった)

私たちの群れ、これは言うならば聖書を唯一の拠り所とする、プロテスタント信徒の中のプロテスタント、言うならば原理主義そのものである。聖書は、"神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。"(ヨハネの福音書 3章16節)
と、神の愛を宣べ伝え、イスラムの世界を征服とは全く異なって、
"イエスは答えられた。「わたしの国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、わたしのしもべたちが、わたしをユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし、事実、わたしの国はこの世のものではありません。」"(ヨハネの福音書 18章36節)
と現世を否定された。最終的には現世も含むが、クリスチャンの国とは、霊的な神の国なのである。
ケパ
















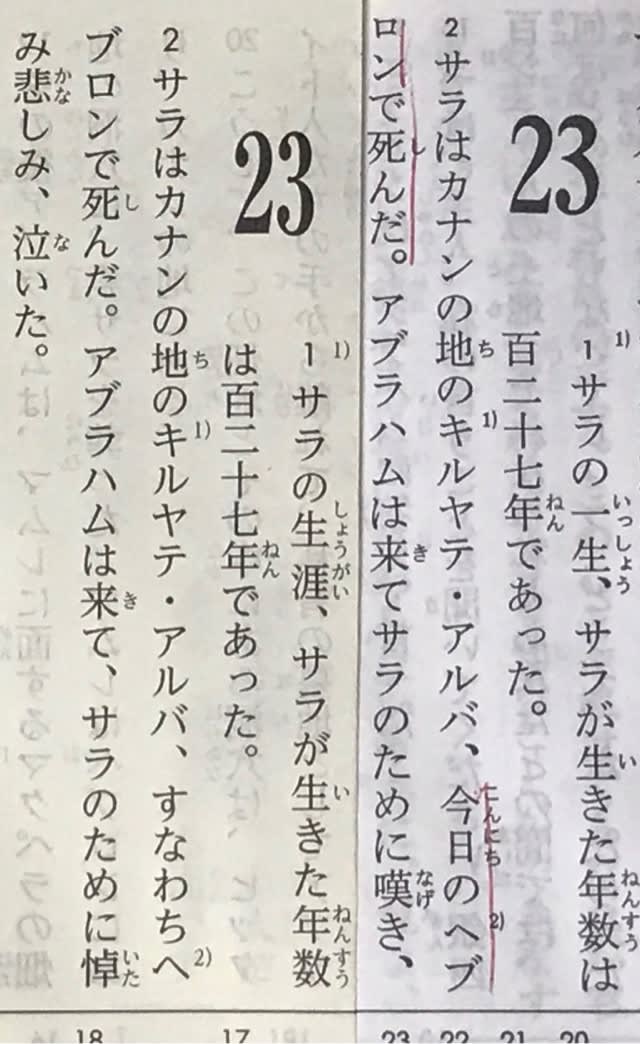






 「笛吹けど踊らず」(マタイ11:17)などである。中には日本に帰化したような「目から鱗(うろこ)」(使徒9:18)みたいなものまである。
「笛吹けど踊らず」(マタイ11:17)などである。中には日本に帰化したような「目から鱗(うろこ)」(使徒9:18)みたいなものまである。 つまり、おねだりしても、なかなか買ってくれない姉を「不正な裁判官」ではなく、「怠け者の裁判官」として言い換えているわけで、これは大いに笑えて、ナールホド、うまい❗と大受けの話となる。
つまり、おねだりしても、なかなか買ってくれない姉を「不正な裁判官」ではなく、「怠け者の裁判官」として言い換えているわけで、これは大いに笑えて、ナールホド、うまい❗と大受けの話となる。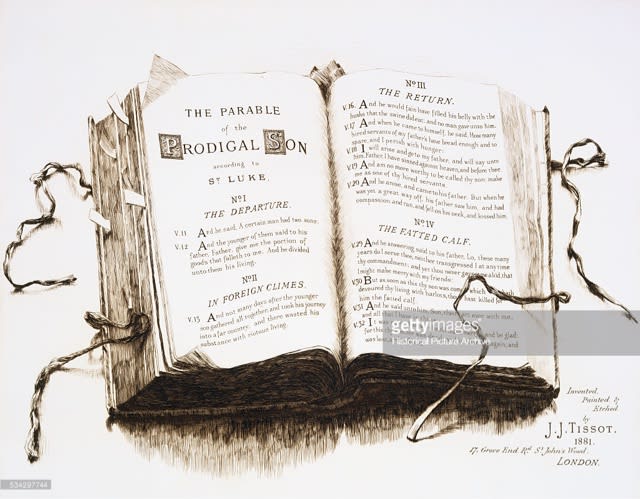
 のだけれど‥‥
のだけれど‥‥
 」
」
 。かなり離れた位置でiPhoneカメラなのでこの程度。🔵印よく見てね〜
。かなり離れた位置でiPhoneカメラなのでこの程度。🔵印よく見てね〜