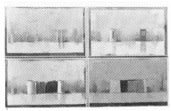同時代作家を間近に見ながら
日時:2018.2.28(土)13:30~15:30
会場:ナレッジキャピタル ナレッジサロンにて
ゲスト:潮江宏三氏(京都市美術館館長)
ナビゲーター:清澤暁子氏(コーディネーター・アートエリアB1事務局)
時代の流れと大学改革
〈観察者としての38年〉
清澤:潮江先生は、1974年から京都市立芸術大学に勤め始められて2000年代に至るまで、京芸を中心に同時代のアーティストや、今アーティストとなっている方たちが卵の時代からずっと寄り添って並走されてきました。今日は、70年代80年代90年代と流れを追いながら、当時の大学の状況、あるいは、その時の学生さんたちの興味深いエピソードなどを当時の芸術教育の状況や大学の雰囲気とともにお話いただきたいと思っております。
後半は、現在館長を務めておられる京都市美術館が、2020年リニューアルオープンに向けて、工事真最中ですので、新しく生まれ変わる美術館のこれまでの活動と、今後どういう展開を構想されているのかなどもお伺いしていきたいと思います。
潮江:私は1974年に京都大学博士課程の3年間を終えて、京都市立芸術大学美術学部の助手として着任しました。助手だったんですが、いきなり講義もやらされました。入った当初は私は木村重信先生の後任でしたので、そういう立場が求められるのかなと思ってましたので、作家さんともお酒の席によく付き合ってたんですよ。大体独身の頃は、二日酔いで講義してることも多かった。作家さんもどこかで展覧会があったらそのまま飲んで、BAR行って、はしごしてっていうようなのが70年代の雰囲気でした。
その頃はどちらかといえばべったりでしたが、やっぱり自分自身の能力も考えたら、木村先生みたいに馬力でご自身の専門の原始美術から現代美術の評論までやるのはとても私にはできません。やっぱり自分の西洋美術史という分野をしっかり固めることが大事だと考え、一定の距離を保つようにしました。ですから私のこの38年間の芸大の大半は、どちらかというと観察者としての立場を徹底させてもらいました。でもまぁ時折気が合う学生とはお酒飲んだり、しゃべったりするそういうような形で、活動させていただきました。

画像:ゲストの潮江氏(写真左)とナビゲーターの清澤氏(写真右)
〈構想設計の誕生〉
清澤:70年ごろの時代背景はどんなものでしたか?
潮江:芸大の話をする時に、「改革案」の話をせねばならんですね。1969年から70年にかけて学生運動が盛んだった時、芸大のキャンパスも荒れました。学生たちが大学の改革を求めて詰め掛けて、学校の授業ができないような状態になりました。
普通の大学はそれに応えないないままズルズルと元の体制を維持しましが、芸大はなぜかこの時に、抜本的に変えちゃったんですね。所謂、トップに一番年長の先生がおられてヒエラルキーの形で上下関係を作るということを壊したんです。平らにして、それぞれの構成メンバーが同じ資格を持つ。場合によっては学生もそれなりの権利と資格を持っているというような考え方で、大学教育を考えるという形になりました。
清澤:そうなるとどのようにして大学をまとめたのでしょう?
潮江:「素材別教室」という形をとりました。要するに日本画の場合だと「膠彩」、膠で書く技術や、膠彩の技術をやる人たちの集まり。それから洋画であれば「油画」ですね。油彩画の集まり、とかですね。陶磁器、染織、それから漆芸。その頃漆は「塗装」と書かれていますね。
その中で新しく生まれた専攻が「構想設計」です。英語で言うとコンセプチュアルアーキテクチャー。頭の中で芸術の組み立てを考えていって組み立てること。これが一番大事なんだと。そこを徹底して考えようというのが、構想設計という研究室です。その主任になったのが洋画の卒業生の関根勢之助さん。この人は元々はどっちかというと、戦後の抽象画アクションペインティングみたいな絵を描いていた人です。その人が主任になり、この構想設計にふさわしい教育方法を組み立てていって、自分自身の作風も変えていきました。後年には社会性のある原発に言及するような作品を作ったりとか、非常にコンセプチュアルな作品を作っています。その相方になった人が、日系アメリカ人の写真家、アーネスト・サトウさん。1年後に立体系の作家が一人、石の彫刻をやっている佐野賢先生が入って、構想設計という研究室が出来上がりました。ですから森村くんらは、アーネストさんのところで、写真を勉強しているんですね。
清澤:森村泰昌さんは、やはり写真科のご出身ですか。
潮江:写真じゃなくて、学部はデザインの出身。大学院で構想設計に入って、気難しいアーネストさんの助手をしてはったんです。
あとは、陶磁器は八木一夫さん。八木さんは私が来てから5年後の冬の寒いときに心臓発作で亡くなりました。八木さんは新しく来た人間に対して、こいつはどの程度のものなのかということを必ずちょっかい出してくる人なんですね。好奇心旺盛で。それで、色んな問いかけをして、要するに自分の本音見せないで、問いかけて手のひらのところで転がしながら、相手の値踏みをするという、そういう会話術が巧みな人。その当時ですと、三条小橋のところに何軒か画廊がありましたから、画廊回りしていると必ず三条小橋のあたりで八木さんがいはるんですね。それで飲み屋に引っ張りこまれてそのまま何時間かチェックが始まるわけです。中々緊張感がある楽しい会話でした。
清澤:陶磁器という専攻はこの改革以前の当初からあったんですね。
潮江:はい、もちろん。三本柱(陶磁器、染織、漆芸)は、京都の工芸と関係ありますのでね。京焼、西陣(友禅)、京漆、ですね。それに関連するものとして、この三本柱は欠かすことができないですね。もっともだけど、かといって、学校で教えていることがそのまま実生産に繋がるようなことは教えていません。
清澤:産業のための技術ではないということですね?
潮江:そうです。けれども、そういう分野はしっかり先生を置いておかないとダメだということで、この時は、染織の先生方も6人いますね。6人のうちの3人が染めで3人が織り。今は5人しかいませんが、染めが4人と織りが2人。
清澤:かなり充実してますね。
潮江:はい、今はどこの私学も工芸専攻に入る学生が少ないのでどんどん縮小して、場合によっては無くなってるところもありますけど、まぁここは変わらないと思います。それは京都という地場を考えると、変えることのできない部分ですね。
清澤:その頃の京都市美術館というのは先生が知る限りではどういう感じでしたか。
潮江:元気だったでしょう。アンデパンダン展やってましたからね。それも、京都市が費用を出してましたから。新聞社などがやるんじゃなくて、京都市がお金出してましたんで、そういう意味で言ったら凄い元気だったと思います。
清澤:同時代の美術をどんどん見せていくような側面もあったということですね。
潮江:そうです。特に両サイドのギャラリーだけではなく、真ん中の対陳列室でもやってましたから。

画像:ゲストの潮江氏(写真左)とナビゲーターの清澤氏(写真右)
芸大特有のカリキュラム
〈ガイダンス(現在の総合基礎)での交流〉
清澤:京芸のカリキュラムのひとつでもある「ガイダンス」について、簡単にご説明頂けますか。学生にとっては大きな変化というか、カリキュラムにおける転換だったと思うんですけれども。
潮江:当初は「ガイダンス」という名前で、これから自分の専門を見つけていくための予備的な授業、という考え方で始まったんですけど、今は芸術の共通の基盤を考えるという意味で「総合基礎」という名前に変わっています。
私の経験の中でいうと最も端的に実践したのは、構想設計の関根先生がガイダンスの委員長だった時ですね。私が担当した1982年の時のガイダンスは、テーマが「つくる」ということでした。前半は、穴を掘って、野焼きをするんですよ。今から何をするかという予備知識を全く与えないんです。今からする作業は、そのあたりに穴を掘る作業と、山の上へ行ってススキを刈ってくる作業だと。
穴を掘る人たちにはスコップを渡して、ただ穴を掘らすわけです。こんな大きさでこんな形で穴を掘れ。山を登る人たちには鎌を渡して山に行ってススキ刈ってこい、と。用意ができたら、今度は学生達に土を与えて、器にならないものを作れ、と。ひたすら丸いものばっかり作ってる子とか、平らなものばっかり作ってる子とか、それを寄せ集めて野焼きして、それが最初の課題です。
清澤:まさに野外作業ですね。
潮江:そうです。 だから私の主な仕事はもちろん引率していくことも仕事でしたけど、雨が降った日にどうするか。
清澤:雨天時はどうされたのですか。
潮江:雨が降った日には「言葉を使う仕事」をやらそうと思ったわけです。1つのアイデアは、新聞紙を1枚ずつ配って、その中にある主語と述語を拾い出して、最もかけ離れた組み合わせにして詩を作れということをやらせました。要するに、矛盾するようなものになると、ポエティカルなものが誕生する。これはシュルレアリスムの1つの考え方ですけど。そういうものをやらせたことはあります。言葉を使うというのはタイトルをつけたり、コンセプトを整理したりするときにやっぱり大事なことになるかと思ったので、そんなことをやらせたりしたこともありました。
清澤:ガイダンスから、総合基礎となっても、1年生時に学生たちが専攻や手法に関係なく、交流する機会になっているというのが1つの京芸の特徴となっているということですね。
評価を待たない
潮江:1980年に今の沓掛の学舎に引っ越しました。やっぱり、学校が新しくなると、新しくなった学校で次のことをしようという教員たちの意欲もあるでしょうし、学生たちの意欲もあるでしょう。1980年、81年、82年あたりの卒業生が、実は80年代の美術を切り開いていくんですね。
清澤:80年代に東山から桂の方に校舎自体が移って、今、私たちが知っている京芸は京都市内から離れた山手にあるので、学生たちは制作活動に打ち込めると同時に、少し山ごもりといった印象もありますが、移設当時は、コンクリート製の斬新な校舎という印象だったんですね。
潮江:広くなったし、それぞれの研究室もアトリエも広くなりましたしね。個人研究室も初めて持てましたから。そういう雰囲気の中で80年代の人たち、いわゆる関西派のアートシーンをつくった人たち、例えば石原友明や、山部泰司とか、そういう人たちが育っていくわけです。
彼らの一番の最大の特徴というのは、誰かが評価してくれるのを待たなかったんですね。それが彼らの生き方の特徴です。要は何をしたかというと、これと思う若手の評論家を抱き込むんですね。グループを作って、その人を頭にして展覧会のコンセプトを整理する、それでそれをメッセージとして評論家に外に出してもらう。そのパンフレットを自分たちで作るという。だから自分たち自身もちゃんと宣伝する手段まで考えてやっていた。評論家に発見されるのを待ってるのではなくて、そこまで企画してやってたんです。
清澤:関西派のグループのメンバーというのは、石原友明さんはデザインとおっしゃいましたけど京芸メンバーの中心だったのですか?
潮江:そうですよね。松井智惠とかもいるしね。
清澤:松井智惠さんは確か染織ご出身ということでしたよね。
潮江:そうです。インスタレーションをやってて、それでデビューして。もう、染織の先生は泣いていましたね。今まで考えたこともないものが出てきたから。
清澤:京芸の染織を出て、いま現代美術をされている方は結構いますね。
潮江:やなぎみわとかね。
清澤:現代美術で活躍されている方が、もともと京芸では別の専攻だったという、そういう系譜のようなものがあるんですね。
潮江:松井智惠さんもそうやし、石原も森村もデザインですからね。もともとの専攻は違いますので、だから異なった専攻の学生との出会いとか、先生との出会いとか。
清澤:それこそさっきおっしゃった、ガイダンスの時に知り出会ってとか、そういうことも要因にはなっているだろうということですね。
潮江:そうです。制作協力しますからね。
卒業生の話
〈関西派の絵描き〉
清澤:ご準備いただいたスライドをお願いします。
潮江:では日本画から。あまり変わってないものとしてお見せしています。
97年~98年は、三瀬夏之助という今、東北芸工大で頑張ってる要するに東北の日本画というのを復興させようとして頑張っている男です。4年生の時には賞をもらっていますけど、どんどん先生のところから離れていって、理解できない領域にいってる男です。

画像:三瀬夏之介《シナプスの小人》1998年
次は油画専攻に行きましょう。82年に関西派の絵描きが出てきます。その一人が池田周功です。教員が扱いかねる自己主張の強い学生でした。でもこういう人がやっぱり中心になってやっていくんですね。次は85年、この頃に児玉靖枝さんが出てきます。その時に中原浩大くんと松井紫朗くんが出てきますね。
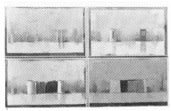
画像:児玉靖枝《思考の余白》1985年

画像:中原浩大《Elephant III(Cray Cat), Wave, Red Snow Man》1983年

画像:松井紫朗《塔》1983年
清澤:中原さん、松井さんともに、現在は彫刻の教授でいらっしゃいますね。
潮江:2人が同世代でおまけにライバルだったという関係も良かったのかなと思います。84年~85年から、ちょっと後ろの世代の関西派の後の世代が出てきます。86年には薮内美佐子がいました。

画像:藪内美佐子《毎日が新しい日》1989年
清澤:薮内さんはダムタイプの作品などで、パフォーマーとしても知られています。
潮江:そうです。彼女は実は有能な抽象画家だったんです。将来性のある抽象画家だったんです。ところがそれをやめて、そっちにいかはったんです。
清澤:ちょうど構想設計ができて10年後くらいに、ダムタイプなど世界的な評価を受けるようなグループが誕生したんですね。
潮江:90年頃から油画が変わってきました。例えば、抽象画で、すみっこまでしっかり描けてますよね。私は実は、81年〜82年にかけてイギリスに勉強しに行ったんですが、そこで実はネオ・エクスプレッショニズム、ニューペインティングがちょうどイギリスのロンドン、ペルメル街のアート・カウンシル・ギャラリーでやっていたんですね。それを目撃して帰ってきた頃くらいからしばらくして、こういう抽象表現の方向性を追求することが始まります。それでこの頃から、教員たちも抽象を描くんだったら、真ん中に構成して描くだけではなくて、オールオーバーに画面の隅っこまでしっかり構造化して描けということを指導しました。オールオーバーにすることが最大の目標です。
チュートリアルシステムでコミュニケーション
清澤:この頃の、芸大の油画研究室はどんな感じだったのですか?
潮江:油画の研究室は90年過ぎてから、自分たちの研究室のアトリエを全部真っ白に塗り替えて、その部屋で何人かで分割したりあるいは小さいところは一部屋一人で使って展示させるようにするんですね。そうすると、一人4点以上は展示できるわけです。美術館では1枚しかもって行けませんけども。そこだったら展示できるんです。
清澤:スペースがかなり広いんですね。
潮江:そうです。そうするとインスタレーション的な展示も油の作家はどんどんやっていきます。京芸の場合は油画も彫刻もそうですけど、みんなインスタレーションとか普通にやるし、そういう形でどんどん展開していきます。特に油画は油画なのに何してんねやということもどんどんやっていくんです。
90年代の半ばごろですね。特に油画が非常に自由な雰囲気でした。彫刻も大きく変化するんですね。彫刻の作家も形を作らなくなっていきます。
清澤:逆に平面的になっていったのですか。
潮江:そうです、バラバラになっていく。ものすごいクロスしますよね。彫刻の教育の方法というのは、一番大事にするのは形がどういう風に綺麗にできるかというよりもまず最初にコンセプトの議論を徹底してやります。
清澤:それは例えば陶磁器も同じなんですか。
潮江:そうです。コンセプトの議論を徹底してやります。そこからですので。技術的なものはどっちかというと二の次的と言ったら言い過ぎかもしれませんけど、そういうものは後からついてくるものだという発想です。
油画がこういう形で展開が良くなっていったのは、実は油画の研究室の教育方法に独自のものがありました。これはチュートリアルシステムといって、学生担当の複数の教員と学生との間に2週間に1回ミーティングを必ずやるんです。で、出来上がった作品持ってくる、それから自分の考えていることをメッセージとして伝える、それで教員とやり取りをする、教員は技術的な問題があればこういう解決方法があるよという教え方しかしない。できるだけ学生の考えてることを伸ばしていくような方法でやっていく。
清澤:コミュニケーションしながら考えていくということですね。
潮江:そうそう。だから先生方もすごい勉強したと思いますよ。イギリスでやられてるやり方を途中から導入してるんです。90年代頃から。
作品は詰めきると貧しくなる

画像:名和晃平《少年と神獣》1997年
潮江:名和晃平の卒業作品です。こんなん作ってたんです。97年の卒業作品です。
清澤:人型と動物の型のように見えます。
潮江:そうそう、動物は多分抜け殻なのかな。この男の子の抜け殻なのかな。
つまり彼は、今なんかストライプだけで仕事をしていたりするから、抽象的に見えたりするけど、実はこういう風な出発点ですね。意外と、作品としてロマンチックでしょ。そんなところが彼はあるんですよ。本質的にね。
清澤:名和さんは、京芸で最初の博士号だとお聞きしました。
潮江:そうです。たまたま私が指導しましたけども。論文の指導ですけどね、私の仕事は。楽しかったですよ。
清澤:博論では、作品と論文と両方必要なのですね。
潮江:そうです。作品が60%、論文が40%。それで論文は大体、原稿用紙の400字詰めで100枚は書けという設定でした。
清澤:名和さんは、今や彼の代名詞にもなっている「PixCell(ピクセル)」の概念で鹿の剥製などを透明のビーズで覆った作品をすでに作っておられましたか?
潮江:はい、ドクターの時にはもうそれをやっていました。ただその頃は中に入っているものが小さいものが多くて、靴であったり、物によってはバナナだったりしたわけです。バナナは困るんですよね。腐るんですよね。
外側のその光が乱反射するピクセルが、言うなれば我々の感性の世界の了解の仕方の微妙な誤差みたいなものを象徴してるというようなことを論文で証明しようとしたんですね。
それでドイツの美学者の論文を読んで、それに基づいて書いてました。ところが彼も実は絶不調に陥った時があったんですね。なぜそうなるかといったら、やっぱり論文を考える能力と、作品作る能力は違うんですね。論文考える能力は組み立てていって詰めていきますけど、作品は詰めていったら貧しくなるんですね。詰めていくんだけど、最後は開かれてないとあかんのですよね、作品というのは。本当に詰めきってしまうと貧しくなるんですよね。そういう苦境に実は陥っていました。
清澤:要するに頭で考えた通りに作ろうとしたらできたものは面白くない。
潮江:感じた通りに作るのではなくて、考えた通りに作ろうとしたら面白くなくなる。それがちょうど秋の終わりくらいでしたからね。「もう君、論文の大筋はできてるから、論文考えるのやめてくれ」と。「この2か月は作品に集中してみろ」と。そういう指導をしました。最後はちょっと解放して、それでその結果できたものが鹿なんですよね。その時の鹿はああいう白っぽいものではなくて、鹿にビーズ並べて、その横に反射映像が映るように、鏡を組み合わせて。虚と実が組み合わさると非常に複雑に見える、そういういい作品ができた。それで実技の先生もOKしてくれはって。それで学位を取れたんですね。
自分の枠組みを崩す

画像:児島咲子《枕と布団のまにまに》2000年
清澤:今お見せいただいているのはこれは98年の卒業制作展ですね。
潮江:一番私が衝撃を受けた人は児嶋サコ。私の中で色んなものがガラガラっと崩れた人。自分の中では美術史はひとつの方向に向かって発展していくんやというシステムがあったわけですよね。そういうものを壊したのは実はこういう人たちなんですね。児嶋サコの卒業作品には、私の中でクエスチョンマークがいっぱいで理解できない部分がいっぱいあるんですね。ぬいぐるみの中に入って、私の目の前で体をくねらすだけ、ただひたすら。
清澤:卒業制作の試問はどういうふうに進んだのでしょうか。
潮江:彼女ははっきりしたことは言わないですね。でも面白いですね、これ。不思議な。ちょっと普通の人じゃ発想できないようなものがありますよね。こういうものはね。これ認めないとあかん、と思いましたよね。そうなったらどうするか言ったら、自分が持ってた枠組みを崩して、考えなおさないと認められませんよね。排除する方が簡単ですよね。自分の芸術はこんなものだと思っているからあれはちゃう言うたらそれは簡単だけど、圧倒的な迫力と魅力があったら認めなしゃあなかったんですよね。芸大の教員として長くやってきた経験もあった上でそれでもなおかつそうしなければいけないような、理解不能だけど面白い作品が出てくる。そしたらその理解不能の軸をちょっとずらしてみないといかんなというように思いましたね。
清澤:理解不能なものでご自身の枠組みを組み替えるというのは言語を獲得されていくわけですか?
潮江:コンセプトで締め付けていったら薄くなるでしょ。だから僕はもうありのままのそのままを受け入れるような感じをとった方が自分の気持ちとしていいんじゃないか、こんなんもあるんやなと。いろんなものの感じ方にこんなんもあるだろう。例えば、ぬいぐるみの外側の毛がどうしても愛おしかったらこういう表現もあるだろうと僕は受け取りました。それが価値の低いものであるか高いものであるかは考えず。そういうこだわりがあったら、それが一番大事なものなのではないか。きっとそれは男性女性に関わらず、一人一人そういうこだわりみたいなものはあるだろうから。
こんな風に2000年ちょっと超えたくらいを境目に、すごい変わってくるんですよね。それは多分この世代の人たちは新しい感じ方を持てるんだと思います。私みたいな年寄りになったらわからないのは当たり前で、でもそこが魅力的であったらいいなと思うようになっています。こんなふうに油画はうまくいってるんだけど、日本画も多分これから変わります。
清澤:今、80年代、90年代それから2000年代と、主に京都市立芸大の中での卒業制作をスライドで見せていただくだけでも、特に油画を見てますと、時代と響きあいながらどんどん変遷しているなというのがよくわかりました。ありがとうございます。
〈京都市美術館のお話〉
現代美術への対応
清澤:2011年から館長を勤めていらっしゃる京都市美術館は、2020年の再オープンに向けて、具体的な構想はすでに固まり、工事も進んでいます。
まず、先生と市美術館と関係は長いのでしょうか?
潮江:毎年1回は芸大が展示してましたので、必ずそこへ行きますし。もちろん自分自身が大学生の頃から、通ってる美術館ですから、よく知ってるわけです。
清澤:さきほどのお話にもあったように、京都市美術館が同時代美術を紹介していた時代もあったということですが、ここ最近では、どちらかというと、あまりこう同時代の美術を取り扱っていないという印象があります。
潮江:1997年に開催した展覧会以来、現代美術の展覧会はやっていません。独自にはコレクションを活用した展覧会しかやっておりません。
清澤:今回のリニューアルプランの中でも目を引く新館では、現代アートを積極的に紹介していくという構想もありますが、これは潮江先生主導で進められたのでしょうか?
潮江:そうですね、言い出しっぺは私です。役人も説得しました。もちろん直接偉い人とは話をする機会は少ないので、間に立ってくれる人が頑張ってくれたところもあるんですけど。行政というのは、難しいんですよ。パイが決まってますから。京都の場合は、芸術センターを作ったでしょ。あれ自体は素晴らしい施設なんですけど、あれ作った時に、同じ局内だから美術館は影響を受けたわけです。
清澤:役割分担はどのような感じでしょうか。
潮江:同じ局の中に入っているんですよ。ただあっちができたらこっちの食べる部分が減るんですよ。そういう構造があったんです。その時に行政が仕分けして、京都市美術館は現代美術を扱わんでええということになったらしいです。そうすると芸術センターは、展示はできますよ。展示はできるけど作品は残らへんわけです。収蔵しませんから。そうすると、結局いつまでたっても作家たちが外に出て行く入り口のワンステップの展覧会しかできない。それが要するに他の美術館があなたのところでやったんだったらうちにも来て欲しいという作家にはなれないんです。あそこだけでは。だから次のステップを踏ますためには、うちでちゃんと現代美術をやらないかん。それで考えたことは、お金がかからないのは今の建物の中に作る。何よりも現代美術ギャラリーとなるものを作ることが大事やったんですよ。作ったら展覧会をしなきゃいけないでしょ。そういう発想です。
〈リニューアルされる美術館について〉
清澤:新しい美術館の構想の概要を教えていただけますか?


潮江:4つのポイントがあります。
ひとつめは、「未来に向けて歴史を紡いでいく美術館」。創設当初の「現代美術」、つまり京都画壇の日本画がコレクションの核になっているように、京都の未来のために、これからも現代美術を含め、収集展示しなければならない、というメッセージですね。ふたつめの「幅広い世代の人々が集う美術館」。幅広い世代に来て欲しい。つまりこれは、今の美術館は私らの世代の人が大半です。団塊の世代が大半です。そうでなくて、若い人が来ないかん。そうならないと繋がらないというね。若い人もいるし、おじいちゃんおばあちゃんもいる、じゃないとダメだと思います。若い人に来てもらうためには、若い人好みの展覧会をやらないといけない。そうするとやっぱり現代美術がいるだろうというそういうメッセージが込められています。
3つ目の「ゆったり滞在し、ゆっくり楽しめる美術館」。これは美術館の利用の仕方です。利用の仕方を抜本的に変えたいなと思ったんです。それは、今までだと、忙しく展覧会に間に合わせて時間を合わせて混みそうやったら朝早く来て、見たらすぐ帰る。そういうのやめようと。美術館には複数ギャラリーがあるから、ついでに他も見ようと。これ面白そうやから、行ったらこんなんやってるんやったらここも見て帰ろうかという場所にしたい。そのためにはそういう繋ぎのスペースが要りますよね。休憩したり、お茶飲んだり遊んだりして、リフレッシュして、次に頑張っていこうかというそういうような美術館に変えたかった。それから、もちろん当然、これから高齢化社会が訪れるわけですから、そういう人たちのために対応できるような形にしたいと。
4番目は「日本の文化芸術を牽引し、世界の人々を魅了する美術館」これは、再整備以後の最大目標。
これらを根底に置きながら、どういう美術館にしたらいいかいうことをプロポーズしてもらって出てきたのが青木淳さんの設計です。
もちろん現状の建物は保存します。目標はこれを重要文化財にすることですので、そういうようなものとして保存します。公立美術館としては二番目に古い美術館ですが最初の美術館は存在しませんので、これが美術館目的の建物としては、現存の一番古いものになります。そういうものとして残したい。文化庁も基本的には同意してますけども、いろいろ手続きがありますので、もっと先のことになると思いますけど。ですから基本的には外観はいじらないで内装もできるだけいじらない。けれども、利便性も高めなければいけませんので、いろんな工夫をしようと。
それで青木さんが考えたのは、外観をいじらないとすれば、どうやって入るかですね。うちの美術館は入ったらすぐ階段があって玄関。アプローチが短い。待つのもできないし、溜まることもできないし、夏になったらみんなが出入りしたらせっかく冷房しているのにどんどん暖気が入るし、空調が全然言うこと効かないんですね。
そういう問題を解消するためにはどうしたらいいかって青木さんが考えたのは、実はこの西側に地下があるので、地下を活用してそこを入り口にしようと。最初は暗いんですけど、正面に階段がある形ですね。あるいはもちろん左に行ったらエレベーターが付いてますし、両サイドにそうして作ると、両サイドにチケットカウンター等も置けますので、こういう場所を作ると。そうすると、奥までの引きができあがりますので、これを活用するんです。それで地下の入り口にする。そして、入る前の両脇にショップとカフェを置く。そしたらもう表から見えるし、食べてるのも見えるし、飲んでるのも見えるし、物を買っているのも見えるしという形にすると。そういう発想が青木さんの発想でした。
清澤:この地下空間というのは元々ある空間なんですよね。
潮江:ええ。当初は下足場でした。博物館に入るには多分おそらく脱いで入ったと思うんです。下駄や草履、手荷物を預かる場所だったんですね。そこから階段上がって、入ってはったんですね、美術館にね。それがそのまま残ってまして、今は完全に物置になって掃除のおばちゃんがバケツとか置いているんです。
清澤:そこを工夫し活用されるわけですよね。大陳列室はどうなるのでしょうか。
潮江:旧大陳列室というのは、今までは完全に展示場でしたが、今回からはここは完全にホールになります。だからここもゆとりのスペースがあります。例えば壁沿いのところで、ベンチを置いておけば座って休むことができるし、一息つけます。両サイドのギャラリーから両方へ入る。ここで青木さんが考えたアイデアは、上のところにキャットウォークを設けたんです。キャットウォークを設けることで、2階の部分でも東西の行き来ができるようにしたんです。
本館の南側、平安神宮の方ですね。鳥居側の1階部分がちょうど常設展示場になります。それ以外は3つあります、北側の1階と2階。それから、南側の2階。これは貸し会場にも使う。団体展なんかにも使う。そのうち、南側の2階だけは現状を残します。現状というのは、あの美術館は最初作った時にはトップサイドライトといって、一番上の斜めから採光するという設計になっています。
清澤:自然光が入るような設計ですね。
潮江:そうです。そのギャラリーに限って、自然光が入る設計をそのまま残します。それはやはり日本画や油絵描いてる人がやっぱりあれがあると、見栄えが違うというようなご意見もあるので。
もう一つの大きな変化は、北側の中庭には屋根がかかりますので、完全に中庭になります。展示場としても使えます。
それから現代アートのギャラリーですね。現代アートのギャラリーは、一階の東の奥のところに出来上がります。約1000平米で、天井高が5mです。
これは基本的には企画を中心にやります。
清澤:夜のライトアップも計画されていると聞きました。
潮江:行灯みたいな夜間照明です。これは高橋匡太という照明作家として有名な人に設計してもらいました。
清澤:高橋匡太さん、十和田市現代美術館の外壁のキューブを照らし出す作品を手がけられるなどしていて、ずっと京都を拠点に活動していらっしゃるアーティストです。非常に楽しみですね。
これまで同時代の関西美術シーンと並走されながら、現在もなお、館長として新しい美術館構想をさまざまに推進されている具体的なところもお話いただいて、話は尽きませんけれども、今日は貴重なお話を有難うございました。

【まとめ】事務局より
長年勤められていた京都市立芸術大学でのお話では、常に同時代に生きる作家と同じ眼差しで語られ、80年代の関西派のアートシーンの動向や、90年代の終わりから2000年にかけて出てくる新たな美術の価値観を持った若手作家たちに対してはご自身の枠組みを替えて受け入れていくというお話が印象に残りました。
京都市美術館に移られてからは、リニューアルに向けた構想を中心にお話いただきました。現代美術ゾーンの新設や、カフェやショップも新設されることで、より様々な人々が行き交う場所となるようなお話に、2020年のリニューアルに向けて期待が高まりました。