筋金入りの大東亜戦争正当化論者の新藤総務相の靖国参拝について、前回の記事で検証してみました。今回は、何故筋金入りなのか、について、検証し、その誤りを検証してみます。
新藤総務大臣の思想の淵源は、以下の点にあると思います。
「国のために戦った人」のことを「祖父も母も」「あまり語ろうとはしませんでした」というのは何故でしょうか。軍人恩給については、以下をご覧ください。
志村建世のブログ: 軍人恩給は生きていた 2009年9月9日
軍人恩給800万円許せるか 靖国神社問題 : リュウマの独り言 2009年9月11日
「かつての部下」と言いますが、一般の兵士が中将を訪れることがあるかどうか、この「美談」では判りません。しかし、「日本軍将兵2万1000余」を「玉砕」させた責任については、軍人恩給が出るまで、また世の中が戦争責任問題を曖昧にする時が来るまでは、その多くを語ることができなかったのではないでしょうか。
同時に新藤氏の思考の問題点、学習の問題点は、「硫黄島の地下壕に籠も」らねばならなかったところまで追い詰められてしまった「国」と「国のために」たたかわねばならなかった祖父、更に言えば、「大切な家族を守るために」と思い込まされて連れて行かれた「臣民」について、学習と思考回路が及んでいないことです。
だから、この問題については、全く独り善がりの思考を披露することになるのです。「捧げたのだと思います」とか、「だと信じ行動したのだと思います」というように、「立派に国のために仕事をした」「おじいさん」を尊敬している自分の思想を前提に兵士の思いを想像し、「将兵」と、おじいさんたちと一緒にしてしまって、正当化するのです。政治利用、歴史の偽造です
孫・新藤議員、祖父から母への - ZAKZAK 2007年2月28日
「母は戦後が大変だったのか、触れたがらなかった。細かい話はなく、『おじいさんは立派に国のために仕事をした。あなたもしっかりね』といわれてきました」と振り返る。新藤氏が祖父のことを意識しだしたのは小学校3、4年のころ。当時から、日本より米国での評価が高かったことから、「すごいな」と子供心に思っていたという。(引用ここまで)
総務大臣·新藤義孝/硫黄島に眠る英霊への祈り〔1〕 | 社会 | PHP 2013年10月10日
物心ついてから、私は祖母・義井や母から、「おじいさんは国のために戦った人だ」と聞かされてきました。しかし具体的な思い出となると、祖母も母もあまり語ろうとはしませんでした。戦争で最愛の夫を失った祖母は、言葉に尽くせぬ塗炭の苦しみを味わったようです。…終戦から数年後、軍人恩給が出るようになってから、祖母の暮らしは一息ついたと思われますが、かつての祖父の部下が訪ねてくれば、着物を質に出してお金を工面したと聞きます。祖父は自分の部下が頼ってきたら必ず助けるよう、あらかじめ祖母に話していたそうです。
硫黄島における日本軍将兵2万1000余は、絶望的な状況のなかで、なぜ最期まで苛烈な戦いぶりを貫けたのでしょうか。私なりの考えを述べたいと思います。祖父をはじめ、硫黄島の日本軍将兵は、家に残してきた大切な家族を守るために戦ったのでしょう。人間とは、自分より大切なものを守ろうとしたときこそ、自らの限界を超越した力を発揮できるものです。硫黄島の地下壕に籠もった日本軍将兵は、自分の命を捨ててでも、故郷にいる家族を守るために、苦しみに耐え自らの身を捧げたのだと思います。1日でも長く自分たちが踏みとどまることが、本土への攻撃を遅らせ国と愛する者を守ることだと信じ行動したのだと思います。(引用ここまで)
ところで、現在、憲法改悪に向けてご活躍の政治家の皆さんの世代は、祖父、もしくは父親が、大東亜戦争でご活躍され、戦後占領政策の転換の中で、大手を振って歩いてきた方々が多いのではないでしょうか。新藤大臣に典型的に、その思想が見えてくるように想います。また職業軍人である栗林氏を祖父にもつ新藤氏を使って、戦前の亡霊を全国津々浦々に席巻させるのです。ここに国民と、国際社会との最大の矛盾があります。
それでは、栗林中将はどうだったのでしょうか。あまりに美化されているように思いますので、検証してみました。以下の文章が典型のような気がします。
栗林中将が考えていたことは、「皇恩」「皇土」「皇國ノ必勝」「皇國の行手一途に思ふ」だったのです。辞世の短歌の一首目の「散るぞ悲しき」を「散るぞ口惜し」として発表した大本営の意図を新藤氏はどのように語っているのでしょうか。新藤氏が靖国神社参拝を正当化する際の「口実」である「国のために」ではなかったのです。ここに最大のスリカエとゴマカシ、トリックがあります。
「太平洋の島嶼をめぐる戦いで、日本が自軍を上回る死傷者をアメリカに強いたのは硫黄島戦だけ」と美化する日本の風潮、思考回路から、戦争を教訓化し、二度と戦争を起こしてはならないとする憲法を擁護し、活かす思想は出てきません。尖閣の島嶼をめぐるきな臭い風潮は、以下の文章を逆の視点で読み取れば、平和的解決こそ、日本の取るべき唯一の道であることが判ります。しかし、実際は全く真逆の方向へ国民を導いていこうとする力がはたらいているのです。
本来であれば、栗林中将を祖父にもつ新藤氏こそ、「日本軍将兵2万1000余」の「霊魂」を「慰霊」する新藤氏こそ、平和的解決の先頭に立つべきではないでしょうか。であるならば、被侵略国の国民の心を傷つけるような参拝は公職に身を置く限りできないはずです。しかし、新藤氏の思想と論理は逆さまです。
栗林中将の率いる部隊は最後の総攻撃を行い、米軍海兵隊と陸軍航空部隊の野営を襲撃、多くの損害を与えて殆んどが戦死を遂げたという。硫黄島の戦闘における米軍の死傷も甚大であった。「栗林とその部下は粘りに粘って、精鋭で鳴らす米海兵隊に史上最大の苦戦を強いる。結果的に硫黄島は陥落したものの、日本軍の死傷者が21,152だったのに対し、米軍は28,686名と、米軍は日本軍よりも多い死傷者を出している。戦死者だけを見れば、米軍6,821名、日本軍20,129名と日本側の方が多いが、彼我の戦力差から見れば驚くべきことである。太平洋の島嶼をめぐる戦いで、日本が自軍を上回る死傷者をアメリカに強いたのは硫黄島戦だけで、アメリカでの知名度と評価はむしろ日本より高い」と、梯久美子氏の『硫黄島栗林中将の最期』(文春新書)にある。(同書、21頁)硫黄島上陸作戦の米軍指揮官・スミス中将は、「太平洋で相手とした敵指揮官中、栗林は最も勇敢であった」と、栗林中将を称賛したという。
硫黄島総指揮官栗林忠道中将の訣別電報
今ヤ彈丸盡キ水涸レ全員反撃シ最後ノ敢闘ヲ行ハントスルニ方リ熟々皇恩ヲ思ヒ粉骨碎身モ亦悔イズ
特ニ本島ヲ奪還セザル限リ皇土永遠ニ安カラザルニ思ヒ至リ縱ヒ魂魄トナルモ誓ツテ皇軍ノ捲土重來ノ魁タランコトヲ期ス
茲ニ最後ノ關頭ニ立チ重ネテ衷情ヲ披歴スルト共ニ只管皇國ノ必勝ト安泰トヲ祈念シツツ永ヘニ御別レ申上グ
國の爲重きつとめを果し得で 矢彈盡き果て散るぞ悲しき
仇討たで野邊には朽ちじ吾は又 七度生れて矛を執らむぞ
醜草の島に蔓るその時の 皇國の行手一途に思ふ (引用ここまで)
次は、栗林中将を美化する誤りについてです。以下のように玉砕戦法を禁じていたかのように記されています。しかし、実際は、違っていました。
それは一つには、劣勢の戦局と硫黄島の戦略的位置づけがありました。いやそもそも、大東亜戦争の戦略的位置づけそのものの誤りが全てでした。それは、「主権戦・利益戦論、「満蒙は生命線」論、「ABCD包囲網」論、「大東亜共栄圏」論という戦略の誤りでした。ボタンの掛け違いが硫黄島のたたかいを規定していました。
二つ目は、日本精神錬成五誓、敢闘の誓、胆兵の戦闘心得(防衛戦闘)をみれば、帝国職業軍人の思想を使って「将兵」を死地に追いやっていったのでした。その根本は、「日本精神の根源は敬神崇祖の念より生ず」「日本精神の基幹は悠久三千年の尊厳なる国体より生ず」「日本精神の涵養は御勅諭(軍人勅諭のこと)の精神を貫徹」すること「上聖明(天皇陛下のこと)に応え奉る」にありました。
この思想が「国のために」論の始まりであり終わりであり、全てでした。この思想を新藤氏は受け継いでいるのではないでしょうか。このことについて語っているでしょうか。その情緒的言葉で粉飾し、ゴマカシていないでしょうか。日本のマスコミは、ここまで踏み込んで問い質していくべきです。曖昧にしています。これこそが新藤氏らの言動を応援している証左です。
このことは、「大東亜戦争は日本民族の自衛の戦い」「「悠久三千年の尊厳なる国体」を有する日本の独立自存を蹂躙してやま」ない「アメリカ」が「日露戦争以後事あるたびにわが国に圧迫を加えた」「日本を追い詰めハルノートを出して日本に戦争を仕掛けた」と、近代史の偽造、スリカエの延長線上にあることをみれば明瞭です。
百歩譲って、「日本民族の自衛の戦い」論を認めたとして考えてみましょう。
1、アメリカの「圧迫」に「追い詰め」られたから、戦争に突入したのはやむを得ないというのでしょうか。選択は、他になかったのでしょうか。検証しているでしょうか。
2.やむを得ず起こした戦争だからと言って、その結果について、国民やアジア諸国の人びとを塗炭の苦しみを与えたことを免罪できるでしょうか。
3.追い詰められたにもかかわらず、その選択は日米戦争しかなかったのでしょうか。それでは柳条湖事件(満州事変}はどのように説明するのでしょうか。
4.「鬼畜米英」とした、「『米鬼』とよばれるに足る悪魔の所業」と評価するアメリカと「反共」という点で一致し、「反共の防波堤」として、反共のための「浮沈空母」として同盟関係を維持発展さあせてきたことは、どのように説明するのでしょうか。
5.大東亜戦争の反省の上にたって制定された日本国憲法を「アメリカから押付けられた憲法」として「改正」し、天皇を元首に、自衛隊を国防軍に、国民の権利を「公益」優先論を使って制限していこうとしているのです。
以上の視点に立つ時、歴史の歯車の回転はメチャクチャです。
栗林はいわゆる万歳突撃を禁じ、徹底的なゲリラ戦を繰り返し、最後には壮烈なる総攻撃を敢行し玉砕した。この辞世の句は最後の総攻撃に打って出る決意を固めた栗林が大本営に宛てて発した訣別電報に添えられていたものである。尚、訣別電報および栗林の辞世は新聞で報道されたが、最後の「散るぞ悲しき」は「散るぞ口惜し」と改変されて発表された。国のために死んでいく兵士たちを「悲しき」と詠うことは国運を賭けた戦争のさなかにあっては許されないことだったのである。(引用ここまで)
栗林忠道と硫黄島の戦い(上) - 日本政策研究センター 2006年12月8日
硫黄島が大東亜戦争中最大の激戦地となったのは、その地理的位置の重要性のためである。硫黄島は小笠原諸島の南端、東京より千二百キロ、東京とマリアナ諸島のちょうど中間にある。南北八キロ、東西四キロの小さな火山島だが、小笠原諸島中最も飛行場の建設が容易であり、日本軍は既に三つの飛行場を設けていた。硫黄島は南部が平地、南端に小高い摺鉢山があり、中央より北部が低い台地であった。そこで栗林は中央及び北部の台地と摺鉢山に強固な縦深陣地を構築し、水際撃滅作戦をとらず敵を一旦上陸させた上で、南北の陣地より攻撃する持久作戦を採用することにした。栗林は可能な限り長期の戦いに持ちこみ敵の出血を強要し、渡洋爆撃を遅滞させ米軍の本土接近を阻止して、本土防衛の時間を稼ぐ捨石たらんとしたのである。平坦な硫黄島は守るには難しい地形であった。峻しい山岳が多ければ利用できるがそれは不可能である。そこで栗林が考えたのは地下洞窟陣地である。地下に陣地を作り全島を地下要塞化するしかこの島を守り抜く道はほかになしとの結論を下した。栗林はこの硫黄島の戦いの意味を十分承知していた。戦局不利の今日、やがて米軍は本土に迫る。一日でも長く持ちこたえ米軍をこの地に釘付けし、一人でも多くの敵を倒さねばならない。無論生還はあり得ない。最後は二万余将兵の玉砕あるのみだが、捨てばちな戦いをして決して死を急いではならない。本土決戦を有利にする為、長期間徹底的に戦い抜き米軍に多大な犠牲を払わせることが、栗林兵団に課せられた任務であった。
日本精神錬成五誓
一、日本精神の根源は敬神崇祖の念より生ず。我等は統一無雑の心境に立ちて益々この念を深くし、我等の責務に全身全霊を捧げんことを誓う。
二、日本精神の基幹は悠久三千年の尊厳なる国体より生ず。我等はこの精神を蹂躙する敵撃滅の為あらゆる苦難を克服することを誓う。
三、日本精神の涵養は御勅諭(軍人勅諭のこと)の精神を貫徹することにあり。我等はいよいよ至厳なる軍紀風紀を確立し、猛訓練に耐え必勝の信念を益々鞏固ならしめんことを誓う。
四、我等は国防の第一線にあり。作戦第一主義を以て日本精神を昂揚し、上聖明(天皇陛下のこと)に応え奉るとともに下殉国勇士の忠誠と銃後国民の期待に背かざらんことを誓う。
五、我等は国民の儀表(模範の意)となり、この矜持(誇りの意)と責務を自覚し、身を持すること厳に人を俟つこと寛やかに日本精神を宣化せんことを誓う。
敢闘の誓
一、我等は全力を奮って本島を守り抜かん。
一、我等は爆薬を擁きて敵の戦車にぶつかりこれを粉砕せん。
一、我等は挺身敵中に斬込み敵を鏖殺(皆殺しすること)せん。
一、我等は一発必中の射撃に依って敵を撃ち斃さん。
一、我等は各自敵十人をたおさざれば死すとも死せず。
一、我等は最後の一人となるも「ゲリラ」によって敵を悩まさん。
胆兵の戦闘心得
戦闘準備(略)
防衛戦闘
一、猛射で米鬼を滅ぼすぞ。腕を磨けよ一発必中近づけて。
二、演習の様に無暗に突込むな。打ちのめした隙に乗ぜよ他の敵弾に気をつけて。
三、一人死すとも陣地に穴があく。身守る工事と地物を生かせ。偽装遮蔽にぬかりなく。
四、爆薬で敵の戦車を打ち壊せ。敵数人を戦車とともに。これぞ殊勲の最なるぞ。
五、轟々と戦車が来ても驚くな。連射や戦車で打ちまくれ。
六、陣内に敵が入っても驚くな。陣地死守して打ち殺せ。
七、広くまばらに疎開して指揮掌握は難しい。進んで幹部に握られよ。
八、長斃れても一人で陣地を守り抜け。任務第一勲を立てよ。
九、喰わず飲まずで敵撃滅ぞ。頑張れ武夫休めず眠れぬとも。
十、一人の強さが勝の因。苦戦に砕けて死を急ぐなよ胆の兵。
十一、一人でも多く斃せば遂に勝つ。名誉の戦死は十人斃して死するのだ。
十二、負傷して頑張り戦え虜となるな。最後は敵と刺し違え。
大東亜戦争は日本民族の自衛の戦いであった。アメリカは「悠久三千年の尊厳なる国体」を有する日本の独立自存を蹂躙してやまず、日露戦争以後事あるたびにわが国に圧迫を加えた。昭和期にはそれが一層強まり日本を隷従圧殺せんとする数々の威圧を重ね、ついに日本を追い詰めハルノートを出して日本に戦争を仕掛けた。さらに、この戦争においてアメリカは日本全土に無差別爆撃を行い非戦闘員たる罪なき数十万の日本国民を殺戮し続け、止めとして広島と長崎へ原爆を落とした。それはまさに「米鬼」とよばれるに足る悪魔の所業であった。このようなアメリカを何としても打払わねばならなかったから、栗林はこうして部下に必死殉国の覚悟を固めさせたのである。将兵はこの栗林の統率に全幅の信頼をおいて奮闘の限りを尽すのである。(つづく)(引用ここまで)
以下の記事も、栗林中将を美化するものでしかないように思います。中尉時代の「論文」も検証してみる必要があるように思います。それは、総力戦となった第一次政界大戦で使用された兵器の進歩による戦術の転換と、シベリア出兵の敗北いう背景についての分析が書かれているかどうか不明だからです。以下大江志之夫『徴兵制』(岩波新書81年1月刊)の指摘です。
「歩兵はなお軍の主役であったが、その戦闘手段は小銃と銃剣から軽機関銃と手榴弾に移り、砲兵は歩兵の姉妹兵科となった。この趨勢を伝えて、日本陸軍の改革を説いた日本の将校は、『唯物主義』『必勝の信念を欠く』とされ、軍職を追われた」(引用ここまで)
栗橋中尉のその後を見れば、「民主主義や一般常識も広く学ぶべき」という評価が正しいかどうか、検証すべきです。栗林中尉が、大正デモクラシーとどのように向き合ったかなど、新藤氏は学ぶべきです。そのことを語るべきです。情緒的な言葉でゴマカスことなく。
もう一つ、「水際作戦」を変更して「捨て石作戦」の採用です。これは沖縄も同じです。こうした戦術を採用しなければならなかったのは、不思議なことではありません。「国体護持」のための「時間稼ぎ」です。全く無謀な戦術と言わなければなりません。この「過去の教義を捨て、新戦術を編み出」したとする論調こそ、多くの将兵と本土の国民を死地に追いやった思想を免罪する思想です。この段階では、近衛上奏文が出されていたのです。これらの事実を無視した「新戦術」論は、全くナンセンスというものです。
安倍首相の硫黄島訪問にみる英霊冒涜と利用、戦争責任不問の不道徳ぶりこそ、改憲の本質 2013年4月15日
栗林旧陸軍大将の論文発掘 軍の旧態鋭く批判 : 日本再生を願って ... 2009年5月22日
映画「硫黄島からの手紙」などで知られる旧日本陸軍の栗林忠道大将が、中尉だった1919(大正8)年に発表した軍の旧態を批判する論文を、出身地・長野市の「人間・栗林忠道と今井武夫を顕彰する会」(井上昭英会長)が発掘した。同会は「軍でタブー視されていた体質を批判する勇気ある内容で、栗林の面目躍如たるものがある」としている。 栗林大将は1891(明治24)年、西条村(現長野市松代町)生まれ。長野中学校(現長野高校)卒業後、陸軍士官学校に進んだ。1944(昭和19)年、中将で硫黄島守備隊総司令官に着任。米軍上陸後、大将に昇進し、最後の総攻撃で戦死した。 論文は「吾人(ごじん)ノ軍事知識以外ノ知識ノ著シク低級ナルハ争フベカラズ」と題し、陸軍将校の親睦(しんぼく)会の機関誌「偕行(かいこう)社記事」に寄稿。当時の将校が軍事以外の知識は不要としていたことを批判し、部下を心服させるためには民主主義や一般常識も広く学ぶべきだと訴えている。(引用ここまで)
過去の教義を捨て、新戦術を編み出す~~硫黄島決戦と栗林中将から 2007年2月28日
硫黄島着任後、栗林中将は海と空からの支援がまったく期待できないことを知り、手持ちの兵力を駆使して持ちこたえ、上陸してくる米軍にできる限りの損害を与える、という方針を立てた。そのために、硫黄島の地下に要塞を築き、戦車や大砲、迫撃砲を隠し、米軍を迎え撃つことにした。『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』(梯久美子、新潮社)に引用されている公刊戦史によれば、栗林中将の構想は以下の通りである。「摺鉢山、元山地区に強固な複郭拠点を編成し持久を図ると共に強力な予備隊を保有し、敵来攻の場合、一旦上陸を許し、敵が第一飛行場に進出後出撃してこれを海正面に圧迫撃滅する」。「一旦上陸を許」し、「飛行場に進出」させてから攻撃するという戦術は、日本軍の伝統であった「水際撃滅方式」の正反対である。水際撃滅方式とは、その名の通り、水際に強固な防御施設を作り、上陸してくる敵軍をその場で撃退するもの。確かに、上陸前に敵を叩くことが合理的であった時期があった。しかし、米軍は上陸前に空と海から大量の爆弾を落とし、あるいは打ち込んで水際の防御施設を粉砕、その上で一気呵成に上陸する「水陸両用作戦」を用意し、硫黄島に先立つ太平洋諸島の戦いで勝ち続けていた。(引用ここまで)
以上の美化論に対して、以下の指摘があることを掲載しておきます。名もなき庶民の皇軍兵士の思いをどのように意味づけるか、です。
一体何が目的でこんな映画を作ったのか 日刊ゲンダイ 2006年12月13日
作家の三好徹氏はこう言うのだ。
「“バンザイ突撃”を禁じ、一日でも生き延びて戦えと命じた栗林が当時としては珍しく合理的な考えの持ち主であったことは確かです。でも、栗林を英雄視するのはまったくバカげたことですよ。栗林は戦争を止めたわけじゃない。硫黄島をちょっと持ちこたえさせても意味がない。この作品を褒めちぎっているのは戦争を知らない世代だと思う。この映画からは死体の焼け焦げるにおいや火炎放射器や焼夷弾の熱さが伝わってこない。そこに現実との大きな溝があるのです」
硫黄島玉砕戦―生還者たちが語る真実 - 本が好き! 2013年10月1日 .
ではなぜ、アメリカ兵に見つかることなく生き延びることができたのか──。
大越は、重い口を開いた。
『人間の死体を三人くらい持ってきて、その人間を割いて、内臓を巻き付けたり、肉をかぶったりして、死体の山と同化するんです。日が暮れるまで、鰹節を口にくわえて、じーっとして動かないようにしてるんです。そうすると、太陽の光や、地面の熱で、血が乾いて固まって、自分の体がクゥーッとこわばってくるんですけど、夜になったら、その固くなった肉や内臓を剥がして、また違う死体を割いてかぶる。そうやって、敵の目から逃れていたんです』
栗林の物語が、かくなる無数の生死の上に成立していることをゆめ忘れてはならない。本書は証言者たちが自らの名前を晒すというその重みを考えるだけでも、梯のそれなどは及びもつかない一編と断言できる。読みやすい文体、構成もよい。ちなみに本書および放送にて登場した延々と硫黄島回想録を綴る老人の原稿は、秋草鶴次『十七歳の硫黄島』(文春新書)として結実した。(引用ここまで)
生還した越村敏雄元一等兵は次のように回想しています。
「太平洋戦争の全期間を通じて、これほどの出血を米軍に強要した戦線はなかったとして、戦史に特筆されている。だが、それだけではあの島で死んでいった二万の将兵は惨めすぎるであろう。彼らは島に揚陸されたその日から、硫黄と塩の責め苦から逃れることが出来なかった。それはこの島で死ぬまでつきまとった。燃えるような渇きが襲いかかり、激しい下痢と高熱に冒された。そして、やがてこの島に特有の恐ろしい栄養失調症にとりつかれ、果ては、立木が枯れるように無数の兵が上陸を前にして死んだ。そして痩せさらばえて生き残った人間の集団が、凄まじい火力と鋼鉄に激突して全滅した。」(越村敏雄『硫黄島守備隊』(徳間書店)7頁より)(引用ここまで)
最後に、以下の朝日の記事をどのように考えるか、このことも検証していく必要があるように思います。
栗林中将、素顔の手紙 家族らへ300通 硫黄島で指揮 - 朝日新聞デジタル 2006年12月8日
硫黄島から届いた44年11月28日付の手紙。鉛筆で、こう記されている。「敵いよいよ上陸してくれば(中略)もとより生還は期し得られざる次第にござ候。その節は遺族の事なにとぞよろしく願い上げ候」(現代仮名で表記)。家族のことを託した内容だ。直高さんは「きっと、硫黄島で手紙を書いている時が、人間性を取り戻す瞬間だったのではないでしょうか」と語る。役作りのために実家を訪れ、栗林中将の墓参りもした主演の渡辺謙さんは、演技の際、「ミリタリズム(軍国主義)を鼓吹しないよう注意した」と話す。栗林中将が最後の突撃を前にする万歳三唱の場面では、うつむいて両手を挙げ、苦悩をにじませたという。「アメリカ人と一緒にこの映画を作ったことに意義があった。硫黄島の戦いを分かり合おうとした。日本人にこの戦いを知ってもらいたい、との一念で演じました」映画「硫黄島からの手紙」は、米軍側の視点で描いた同監督作品「父親たちの星条旗」(公開中)との2部作。
◇
〈キーワード:硫黄島の戦い〉 海兵隊を主力とする米軍が45年2月19日に上陸。5日で戦闘を終える予定だったが、日本軍の予想外の反撃に遭い、戦闘は36日後の3月26日まで続いた。太平洋戦争の後半期、米軍が出した死傷者約2万8000人の被害は、日本軍を上回る唯一の戦闘となった。補給も退路もない孤島で繰り広げた日本軍の決死の戦いぶりが知られている。 (引用ここまで)













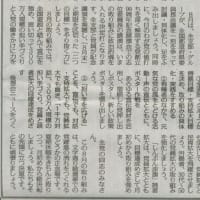

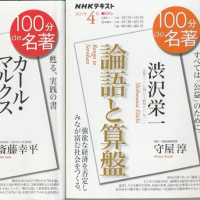




アジアの人々にとあるが、インドに対してイギリスがしたこと、インドネシアに対してオランダがしたこと、フィリピンに対してアメリカがしたことはなんなのか。
最初から日本が悪かったと決めつけた議論ですね。
ちゃんと戦争史を勉強した方が良いですよ。
コメントありがとうございます。
イギリス・オランダ・アメリカが何をやったか、悪いことをしました。当然です。中国大陸にハイエナのように利権獲得のために群がったのですから、どうしようもありません!
ということを言うのであれば、各国に止めましょう!って言えば良かったのではないでしょうか?でもやったことは同じことでした。
「やらなければやられるから仕方なかった」論が成り立つとすれば、欧米の侵略主義を批判することで、日本の侵略主義を正当化するのは潔くないのではありませんか?武士道とは、言い訳をいうことなり!正当化することなり!ということなんでしょうか?
硫黄島の兵士を殺したのは、硫黄島に襲い掛かってきたアメリカ軍であることは、ハッキリしています!しかし、「玉砕」覚悟で戦うことを選択したのは、国際法に違反しているのも事実です。『戦陣訓』で捕虜になることを恥としていた皇軍の思想がなければ、あのような悲惨なことは起こらなかったかもしれません!
インパール作戦に従軍した第31師団佐藤幸徳団長のように参謀本部や第15軍、ビルマ方面軍のデタラメに抗議し、独断撤退し、部下の命を守った師団長もいます。陸軍刑法上では死刑ですが、心身喪失と判断して、その責任を曖昧にしたのです。
詳しくはNHK取材班編「太平洋戦争 日本の敗因4 責任なき戦場インパール」(角川文庫H7)をご覧ください。
というような事例もあります。いずれにしても、硫黄島の戦闘は、戦略なき戦争に入りこみ、迷路のなかで右往左往し、その場しのぎ、場当たり的な戦術で多くの国民を殺した無謀な戦争だったのです。当然アジアの人々に対する加害の事実は糾弾されるべきことですが、日本国民を加害者に仕立てあげ、被害者に追い込んだ責任は厳しく問われなければなりません。
今安倍首相がやっていることは、全く同じ手口です。詳しくは愛国者の邪論の記事をご覧ください。この視点をもって一貫して書いています。同じ過ちを繰り返さないために!
ま、不勉強であることは、事実ですので、精進したいと思います。今後とも宜しくご指導・ご鞭撻のほどを!
高級軍人が主人公の映画は、「われらかく戦えり」的なものが多く、「反戦思想」とはおよそ無縁であるといってよいでしょう。最近ではその手の作品が多く、『真空地帯』や『戦争と人間』のような作品は作られなくなってしまった。
コメントありがとうございます。
私はあまり、というか、ほとんど映画を鑑賞していませんので、何とも言えませんが、最近「小さいおうち」を鑑賞して思ったことは、何でない日常生活をとらえて戦争を映像化することでも、いわゆる「反戦」的な主張ができるものだな、と感心しました。
さすが山田洋次監督!と思いました。
今特攻隊を賛美したり「英霊」を称賛する「風潮」が作られていますが、一つひとつ検証してみたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
このようなコメントは、如何なものでしょうか?
そもそも
「反日」ってどんな意味ですか?
「売国奴」って??
意味も解らず使っているとしたら、恥ずかしいですよ!
意味がわかっているとしたら、きちんと説明してください!
もしかしたら「あ」さんが
「反日売国奴」かも知れません!
愛国者の邪論