◎幸田露伴、「歴史」を語る
あいかわらず、清水文弥の『郷土史話』(邦光堂、一九二七)について。この本の巻頭には、三つの序文が置かれていることは、すでに述べた。順に、農政史家の小野武夫による「郷土史話に序す」、作家の幸田露伴による「序」、清水による「自序」である。
このうち、幸田露伴(一八六七~一九四七)の「序」を、まだ紹介していなかったので、本日は、これを紹介してみよう。露伴は、同書の趣旨をよく把握した上で、みずからの歴史観を開陳している。なお、幸田露伴は、清水文弥より一八歳年少で、あり、露伴にとって文弥は、ほほ「父母」の世代にあたる。
序
明治維新以来世態人情の変は驚くべきものが有る。大なるは政体の変から、微なるは民俗の変まで、何から何まで旧い物を留めないやうになつてゐる。これは国内の必然の趨勢から然様〈サヨウ〉なつたのでも有るが、一〈ヒトツ〉にはまた世界の自然の機運からも然様なつたのである。それで大正の今日に至つてはもはや吾人は我等の父母や祖父母の時代の社会の組織をも風俗の状態をも知ることが無いやうになり、当時の人々の思想をも感情をも殆んど解せぬまでに立至つてゐる。
然し我等は前の時代の人々の奴隷では無いが、正しく父母の子であり、祖父母の孫であり、我等の血は我等の父母祖父母の血を受け紹いで〈ウケツイデ〉ゐるのである。我等は我等の父母祖父母等と無関係の地に立つて居るものではない。我等と我等先人との間には、相呼応し、相関連するものがあるのである。我等は我等先人の良い子孫であらねばならぬ。我等は今日の個人として発達し進歩すると同時に我等先人の良い子孫として、我等の血の中に内在するところの我等先人の遺徳を揚げ余栄を発するものとして、自ら立ちたいものである。先人は先人である、我等は我等であるとして、関せす焉〈エン〉の態度を持ちたくはない。【以下、次回】


















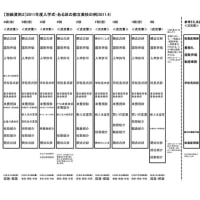
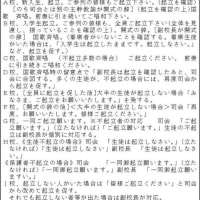








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます