
例によって図書館から借りてきた本で「昭和天皇と戦争」という本を読んだ。
著者はピーター・ウエッツラーというアメリカ人で、外国人が見た昭和史と言ってもいい。
ただこれは明らかに学術書の部類に入るもので、文献に非常に重きを置いた歴史書となっている。
非常に分厚で、重厚な本であったが、最初から読み進んでいくと、文献の出典の根拠がさもこれ見よがしに羅列されているので、いささか面くらった。
文献として文書とかメモ、あるいは個人の日記が、次から次へと出てきて、「だからこうなんだ!」という形で論理が進行しているが、歴史としての学問はそうあらねばならないかもしれないが、市井の一読書人としてはいささか興ざめである。
あの人が「言った言わない」、「書いてある書いてない」、「書類があるない」ということをあまりにも強調しすぎて、そのことによって物事を決めつける手法が学術的であるとするならば、それはいわゆる井戸端会議の延長でしかない。
特に日記などというものが歴史的資料などになりうるものであろうか。
自分自身日記を付けるときに、それを備忘録、あるいは後世の歴史的な資料になることを考えて付けているであろうか。
日記などというものは、確かに、後から思いだしてみれば、あの時はこういうことがあった、ああいうことがあった、と思い出す資料にはなるが、最初からそれをあてにして書くものではない。
書く時点では人に見せることも、何かの資料になるなどと考えて書くものではなく、ただ本当に自分の心の中を、自分に素直に書くものであって、それを歴史的な資料にするなどということは本人の想定外にことであろう。
しかし、こういう歴史学者はその日記に対して非常に大きな歴史上の価値を見出して、だからこそ、それを自分の学問上の獲物として、これ見よがしに誇示しているのではなかろうか。
この分厚で重厚な歴史書も、そういう意味からすると、週刊誌の報ずる芸能界のゴシップ記事のようなものになり下がってしまっている。
ただその対象が、芸能界の餓鬼のようなタレントの行状ではなく、天皇の周囲を取り巻く政府要人の行状を書き連ねているだけで、その場に描かれていることは、週刊誌の記事とあまり変わっているようには見えない。
今世間を賑わしている酒井法子のゴシップと同じで、彼女が警察に捕まったことによって、彼女の夫の立場、彼女の子供のこと、彼女の両親がどういう行動をとっているかを克明に暴いている図と同じである。
こういうことが歴史上の学問なのであろうか?
学問というものは掘り下げていけばいくほど市井の人間の関心から遠ざかるものである。
当然といえば当然のことで、専門的になればなるほど普通の素人にとっては面白くなくなってくるのだから、そういう人の心が離れていくのも無理のないことではある。
この本の表題は、昭和天皇と戦争ということで、まるまる昭和史そのものであるが、歴史を語る時、今の視線、視点で当時を眺めてはならないと思う。
外国の歴史家、特に近現代をテーマにしている歴史家が、この轍を踏んではならない。
外国人であろうとなかろうと、昭和天皇を語ろうとすると、先の戦争への関与は避けて通れないテーマであることは論を待たない。
その時、天皇陛下一人だけを俎上に乗せて語るということもあり得ないわけで、歴史という時は時系列の中でものごとを考えなければならないと思う。
天皇一人だけを俎上に乗せて、彼が対米戦争の開戦の決断、終戦の決断を「した、しない」と論じてみても意味をなさない筈だ。
日本の歴史という時系列の中で、たまたま昭和初期という部分を抽出しただけのことで、前後のつながりを無視して、その部分だけを声高に叫ぶということは意味をなしていないと思う。
この本の主題は、あくまでも昭和天皇に在るわけで、そこに焦点を当てて描かれているが、彼は一人で屹立しているわけではないので、彼を取り巻く周囲の裾野を描く際に、その人達の文献や日記を資料として用いているわけだが、それがあまりにもこれ見よがしになっているので、週刊誌のゴシップ記事の裏を、これ見よがしに表わしている図と同じに見える。
近衛が「ああ言った、こう言った」、木戸が「ああ言った、こう言った」、東條が「ああ言った、こう言った」の羅列では読む方は興が醒めてしまう。
しかし、この著者の意図が、表題が示している通り、昭和天皇と戦争の関わりを解くことを目的とするものであるとするならば、どうしても明治憲法まで遡らなければならないと思う。
日本の昭和初期の悲劇は、明治憲法の不備の中にあったと私個人は考えている。
この本は、天皇の統帥権に関しての記述が全く無いわけではないが極めて少なく、著者は明らかに天皇の統帥権というものを見おとしていると思う。
それに反して我々、日本人の物事の決め方、いわゆるコンセンサスの醸成の仕方には詳しく立ち入っているが、統帥権に関しては見おとしている節がある。
我々が昭和の初期に奈落の底に転がり落ちた最大の理由は、大きく言えば明治憲法の不備であり、明治憲法のどこが不備であったかと問えば、それは統帥権である。
我々、日本民族というのは実に創意工夫に優れた民族であって、連綿と続く歴史をこの創意工夫で乗り切ってきたわけだが、昭和初期の日本の政治家が、天皇陛下の権利であるところの統帥権というものを政治の場に引き込んで、それを政治的に利用したということも創意工夫の一つの例であった。
これは当時の政治家が党利党略のためにパンドラの箱の蓋を開けてしまったわけで、明らかに党離党略で政権を引き寄せんがために、政府に煮え湯を飲ませんがために、窮余の一策として創意工夫を重ね、知恵を絞った挙句、「統帥権干犯」という迷解答を得たわけである。
明治憲法の中には、この統帥権が規定されていたので、ある以上それを使うというのは普通の人の思考であって、問題はここで人間の理性というか知性というものが一向に作用していない点にある。
ロンドン軍縮会議で決めて来た事が、統帥権の干犯にあたるのではないか、という問題提起を政友会の鳩山一郎らが国会で提起したわけであるが、それに対して当時の知識人、国会議員、政府要人らの理性とか知性というのは一体どうなっていたのであろう。
誰一人として整合性のある、合理的で、説得力のある回答を示していないわけで、回答が曖昧なものだから、その後、次から次へとその問題を出すとアメーバ―の自然増殖のように収拾がつかなくなり、混乱の際に至ってしまったわけである。
この本は、昭和天皇一人に焦点を当てているので、彼とその周りの一部の人間しか描かれてれていないが、昭和の悲劇の大部分は、それ以下の人達によって形作らていると思う。
戦後の左翼思想に偏向した教育では、昭和の悲劇の張本人は、こういうレベルの人の責任に帰すと主張しているが、本質は、我々日本の大衆の側にあると思う。
昭和5年に起きた統帥権干犯問題でも、よくよくこの問題を掘り下げ見れば、日本政府の全権大使の決めて来た事を、統帥権干犯だと問題提起したのは野党の側にいた鳩山一郎らであって、彼等は野党として国民の代表であり、大衆の代表であったことになる。
その国民あるいは大衆が、軍縮協定を非難しているわけで、その裏の心理を推察すれば、「軍拡してもっと軍国主義を盛り上げよ」と言っていることになる。
平和主義のマ逆で、戦争を大いにやりましょうという思考である。
この現実は、明らかに鳩山一郎に代表される日本の民衆、大衆というものが軍国主義を推し進め、アジアの覇権を握ることを容認し、そうありたいと願い、そうあるべきだと思っていたということである。
これは明らかに当時の日本の政府の上層部の考えていることとは矛盾しているわけで、政府の上層部はそういう傾向を極力抑え込もうとしていたが、社会の底辺をなす民衆大衆というレベルでは、アジアでの覇者を夢見ていたわけである。
人が集まって形作っている社会というのは、常に激動している。
昭和天皇一人に焦点を当て、彼一人の物語を紡ごうと思っても、それは不可能なことで、日米開戦の意志、あるいは終戦の決断が、彼一人の問題ということはあり得ない。
それは社会の動き、世界の動きと密接に関連している。
彼が平和主義者であったかどうかという問題も、極めてナンセンスことで、そういうレッテル貼りそのものが意味のない議論だと思う。
しかし、昭和の初期という時代のことを考えると、人間にとって教育とは一体何なのか、という疑問にぶつかってしまう。
教育もさることながら、人間の知性とか理性というのも、人間の悲劇を救うことになんら貢献していないように見えてならない。
この本の主題は、昭和天皇が日米開戦のゴーサインをどういう形で出したかを追求しようとして、その過程を克明に資料に基づいて探索しているが、我々が心すべきことは、そういう状況下で人間の理性や知性は如何に機能するかの探求でなければならない。
人間は群をなして社会を作り、その社会は常に激動しているわけで、その激動に如何に対応して、如何に効率的あるいは能動的に身を処して、最も少ない努力で最も大きい効果を狙うか、を思索しなければならない。
21世紀の今日、地球は人間の増加に対応しきれないぐらい過密化し、環境問題が姦しいが、ここで新しく誕生してきた民主党の鳩山由紀生は、世間に向けて良い格好しいの環境改善プランをぶち上げた。
この大風呂敷は、それはそれなりに価値があると思う。
それが目標となって技術が進めば、それはそれで結構なことであるが、問題はその後で、そういう日本の進んだ環境技術を世界にばらまいて、地球そのものを救済すると発想である。
この発想の中に、世間を知らないお坊ちゃん的な思考が横たわっている。
一口で、技術の開発と言ったところで、昔の田舎にあった田んぼの脇の泉のように、地から自然に沸き出てくるものではない。
技術者の血のにじむような努力、乾いたタオルを絞るようなアイデアのねん出、あちこちに頭を下げてまわる金のねん出、そういう経過を経て技術が開発されるわけで、そういう現実を見たこともない高所から眺めて、そういうものを「地球全体の救済のために、世界中にばらまけ」というのは、あまりにも能天気な思考だと思う。
21世紀の今日において、民主党の鳩山由紀生がこういう能天気なことを言いふらしているが、これに対して日本の知性・理性を代表する賢人の反応は一体どうなっているのであろう。
正面切った反対論は未だに出ていないようであるが、ことほど左様に、人間が教育によって習得した人としての理性あるいは知性というものは、人間の存在にどのように機能しているのであろう。
高等教育というものが、ただただ個人が高収入を得るための免罪符であっていいものだろうか。
世の中が進んで、人々が容易に高等教育を享受できるようになった結果として、そういう人々は、多様な思考、考え方、発想が出来るようになったので、上からの指示命令には素直に応じなくなってなって、社会はますます混迷の度を深める。
高等教育の目的が、個人の理性や知性により磨きを掛けて、一歩でも二歩でも価値多き人間をめざすものだとすると、その結果として、自分の国家の指針に素直に従わない人士を数多く輩出することになり、教育の目的が逆効果になってしまう。
昭和の初期の日本を眺めた時、そこで社会をリードしてきた人々の理念、理想、知性、理性、教養というのは、どういうものであったのだろう。
戦後の左翼的な教育では、天皇制による上からの抑圧に抗しきれず、人々は苦難を強いられた、という論法になるが、日比谷公園焼打ち事件、統帥権干犯問題、ちょうちん行列などの有り様から推察すると、昭和の軍国主義というのは、案外下からのボトムアップの軍国主義ではなかったかと思う。
当然そこにはメデイアが絡んでくるのは必然であろうが、こういう状況下で、人間の理性や知性を発揮する場も当然ながらメデイアだと思う。
当時、「治安維持法があったので、ものが言えなかった」というのは、戦後に生き延びた知識人の常とう句であるが、これは彼等インテリ―の自己弁護の弁明にすぎず、本当は行動する勇気がなかっただけのことである。
戦後、ヤミ米の取り締まり(食管法)を順守して、一切ヤミ米を購入せず、餓死した裁判官が一人いたが、こういう人ならば「治安維持法があったからものが言えなかった」と胸を張っていえるが、それ以外の人には、それをいう権利はない筈だ。
問題は、高等教育を受け、理性も知性も人並み以上に備えた知識人が、一言も体制に異議を差し挟まず、順応してしまったことだ。
そして、戦後というものの言える時代になると、治安維持法があってものが言えなかったという論理を展開しているわけで、この日和見、この風見鶏、この変節の中に、彼等が受けた高等教育の理性や知性は如何様に機能していたのであろう。
結局のところ、高等教育によって成人に達してから後付けされた知識や教養では、その人の持つ本来の人間性を左右できずに、人の理性や知性というものは、教育では如何ともし難いものだということであろう。
この本は東條英機を案外買っており、昭和天皇は彼を信用していた、と述べているが、私もそう思う。
日本では東條英機は日米開戦をした総理大臣という位置づけて極めて人気がないが、日本という内側から眺める光景と、外国人という外側からの視点では大いに違って当然である。
問題は、この部分に潜んでいるようで、東條がいくら天皇に忠実たらんと努力しても、東條の手元に来る情報が支離滅裂で、その上天皇に様々な人が情報を提供するでは、結果として政治としての対応が出来ないのも当然である。
政治というものは、人が人のために良かれと思ってするわけで、ただただ自己の利益の追求のみではない筈である。
そして社会なり国家というものは、為政者をトップに据えたピラミッド型の体制を形作っているわけで、トップがいくら民のためを思って施策を施しても、中間のものがそれを横取りしてしまっては、為政者の民を思う心は下々のものまで伝わらない。
歴史を語ると言ったとき、我々は往々にしてピラミット型のトップの為政者に焦点を当てがちであるが、国家や社会の腐敗は、ピラミッドの中間層の組織破壊、メルトダウンに起因しているように思う。
著者はピーター・ウエッツラーというアメリカ人で、外国人が見た昭和史と言ってもいい。
ただこれは明らかに学術書の部類に入るもので、文献に非常に重きを置いた歴史書となっている。
非常に分厚で、重厚な本であったが、最初から読み進んでいくと、文献の出典の根拠がさもこれ見よがしに羅列されているので、いささか面くらった。
文献として文書とかメモ、あるいは個人の日記が、次から次へと出てきて、「だからこうなんだ!」という形で論理が進行しているが、歴史としての学問はそうあらねばならないかもしれないが、市井の一読書人としてはいささか興ざめである。
あの人が「言った言わない」、「書いてある書いてない」、「書類があるない」ということをあまりにも強調しすぎて、そのことによって物事を決めつける手法が学術的であるとするならば、それはいわゆる井戸端会議の延長でしかない。
特に日記などというものが歴史的資料などになりうるものであろうか。
自分自身日記を付けるときに、それを備忘録、あるいは後世の歴史的な資料になることを考えて付けているであろうか。
日記などというものは、確かに、後から思いだしてみれば、あの時はこういうことがあった、ああいうことがあった、と思い出す資料にはなるが、最初からそれをあてにして書くものではない。
書く時点では人に見せることも、何かの資料になるなどと考えて書くものではなく、ただ本当に自分の心の中を、自分に素直に書くものであって、それを歴史的な資料にするなどということは本人の想定外にことであろう。
しかし、こういう歴史学者はその日記に対して非常に大きな歴史上の価値を見出して、だからこそ、それを自分の学問上の獲物として、これ見よがしに誇示しているのではなかろうか。
この分厚で重厚な歴史書も、そういう意味からすると、週刊誌の報ずる芸能界のゴシップ記事のようなものになり下がってしまっている。
ただその対象が、芸能界の餓鬼のようなタレントの行状ではなく、天皇の周囲を取り巻く政府要人の行状を書き連ねているだけで、その場に描かれていることは、週刊誌の記事とあまり変わっているようには見えない。
今世間を賑わしている酒井法子のゴシップと同じで、彼女が警察に捕まったことによって、彼女の夫の立場、彼女の子供のこと、彼女の両親がどういう行動をとっているかを克明に暴いている図と同じである。
こういうことが歴史上の学問なのであろうか?
学問というものは掘り下げていけばいくほど市井の人間の関心から遠ざかるものである。
当然といえば当然のことで、専門的になればなるほど普通の素人にとっては面白くなくなってくるのだから、そういう人の心が離れていくのも無理のないことではある。
この本の表題は、昭和天皇と戦争ということで、まるまる昭和史そのものであるが、歴史を語る時、今の視線、視点で当時を眺めてはならないと思う。
外国の歴史家、特に近現代をテーマにしている歴史家が、この轍を踏んではならない。
外国人であろうとなかろうと、昭和天皇を語ろうとすると、先の戦争への関与は避けて通れないテーマであることは論を待たない。
その時、天皇陛下一人だけを俎上に乗せて語るということもあり得ないわけで、歴史という時は時系列の中でものごとを考えなければならないと思う。
天皇一人だけを俎上に乗せて、彼が対米戦争の開戦の決断、終戦の決断を「した、しない」と論じてみても意味をなさない筈だ。
日本の歴史という時系列の中で、たまたま昭和初期という部分を抽出しただけのことで、前後のつながりを無視して、その部分だけを声高に叫ぶということは意味をなしていないと思う。
この本の主題は、あくまでも昭和天皇に在るわけで、そこに焦点を当てて描かれているが、彼は一人で屹立しているわけではないので、彼を取り巻く周囲の裾野を描く際に、その人達の文献や日記を資料として用いているわけだが、それがあまりにもこれ見よがしになっているので、週刊誌のゴシップ記事の裏を、これ見よがしに表わしている図と同じに見える。
近衛が「ああ言った、こう言った」、木戸が「ああ言った、こう言った」、東條が「ああ言った、こう言った」の羅列では読む方は興が醒めてしまう。
しかし、この著者の意図が、表題が示している通り、昭和天皇と戦争の関わりを解くことを目的とするものであるとするならば、どうしても明治憲法まで遡らなければならないと思う。
日本の昭和初期の悲劇は、明治憲法の不備の中にあったと私個人は考えている。
この本は、天皇の統帥権に関しての記述が全く無いわけではないが極めて少なく、著者は明らかに天皇の統帥権というものを見おとしていると思う。
それに反して我々、日本人の物事の決め方、いわゆるコンセンサスの醸成の仕方には詳しく立ち入っているが、統帥権に関しては見おとしている節がある。
我々が昭和の初期に奈落の底に転がり落ちた最大の理由は、大きく言えば明治憲法の不備であり、明治憲法のどこが不備であったかと問えば、それは統帥権である。
我々、日本民族というのは実に創意工夫に優れた民族であって、連綿と続く歴史をこの創意工夫で乗り切ってきたわけだが、昭和初期の日本の政治家が、天皇陛下の権利であるところの統帥権というものを政治の場に引き込んで、それを政治的に利用したということも創意工夫の一つの例であった。
これは当時の政治家が党利党略のためにパンドラの箱の蓋を開けてしまったわけで、明らかに党離党略で政権を引き寄せんがために、政府に煮え湯を飲ませんがために、窮余の一策として創意工夫を重ね、知恵を絞った挙句、「統帥権干犯」という迷解答を得たわけである。
明治憲法の中には、この統帥権が規定されていたので、ある以上それを使うというのは普通の人の思考であって、問題はここで人間の理性というか知性というものが一向に作用していない点にある。
ロンドン軍縮会議で決めて来た事が、統帥権の干犯にあたるのではないか、という問題提起を政友会の鳩山一郎らが国会で提起したわけであるが、それに対して当時の知識人、国会議員、政府要人らの理性とか知性というのは一体どうなっていたのであろう。
誰一人として整合性のある、合理的で、説得力のある回答を示していないわけで、回答が曖昧なものだから、その後、次から次へとその問題を出すとアメーバ―の自然増殖のように収拾がつかなくなり、混乱の際に至ってしまったわけである。
この本は、昭和天皇一人に焦点を当てているので、彼とその周りの一部の人間しか描かれてれていないが、昭和の悲劇の大部分は、それ以下の人達によって形作らていると思う。
戦後の左翼思想に偏向した教育では、昭和の悲劇の張本人は、こういうレベルの人の責任に帰すと主張しているが、本質は、我々日本の大衆の側にあると思う。
昭和5年に起きた統帥権干犯問題でも、よくよくこの問題を掘り下げ見れば、日本政府の全権大使の決めて来た事を、統帥権干犯だと問題提起したのは野党の側にいた鳩山一郎らであって、彼等は野党として国民の代表であり、大衆の代表であったことになる。
その国民あるいは大衆が、軍縮協定を非難しているわけで、その裏の心理を推察すれば、「軍拡してもっと軍国主義を盛り上げよ」と言っていることになる。
平和主義のマ逆で、戦争を大いにやりましょうという思考である。
この現実は、明らかに鳩山一郎に代表される日本の民衆、大衆というものが軍国主義を推し進め、アジアの覇権を握ることを容認し、そうありたいと願い、そうあるべきだと思っていたということである。
これは明らかに当時の日本の政府の上層部の考えていることとは矛盾しているわけで、政府の上層部はそういう傾向を極力抑え込もうとしていたが、社会の底辺をなす民衆大衆というレベルでは、アジアでの覇者を夢見ていたわけである。
人が集まって形作っている社会というのは、常に激動している。
昭和天皇一人に焦点を当て、彼一人の物語を紡ごうと思っても、それは不可能なことで、日米開戦の意志、あるいは終戦の決断が、彼一人の問題ということはあり得ない。
それは社会の動き、世界の動きと密接に関連している。
彼が平和主義者であったかどうかという問題も、極めてナンセンスことで、そういうレッテル貼りそのものが意味のない議論だと思う。
しかし、昭和の初期という時代のことを考えると、人間にとって教育とは一体何なのか、という疑問にぶつかってしまう。
教育もさることながら、人間の知性とか理性というのも、人間の悲劇を救うことになんら貢献していないように見えてならない。
この本の主題は、昭和天皇が日米開戦のゴーサインをどういう形で出したかを追求しようとして、その過程を克明に資料に基づいて探索しているが、我々が心すべきことは、そういう状況下で人間の理性や知性は如何に機能するかの探求でなければならない。
人間は群をなして社会を作り、その社会は常に激動しているわけで、その激動に如何に対応して、如何に効率的あるいは能動的に身を処して、最も少ない努力で最も大きい効果を狙うか、を思索しなければならない。
21世紀の今日、地球は人間の増加に対応しきれないぐらい過密化し、環境問題が姦しいが、ここで新しく誕生してきた民主党の鳩山由紀生は、世間に向けて良い格好しいの環境改善プランをぶち上げた。
この大風呂敷は、それはそれなりに価値があると思う。
それが目標となって技術が進めば、それはそれで結構なことであるが、問題はその後で、そういう日本の進んだ環境技術を世界にばらまいて、地球そのものを救済すると発想である。
この発想の中に、世間を知らないお坊ちゃん的な思考が横たわっている。
一口で、技術の開発と言ったところで、昔の田舎にあった田んぼの脇の泉のように、地から自然に沸き出てくるものではない。
技術者の血のにじむような努力、乾いたタオルを絞るようなアイデアのねん出、あちこちに頭を下げてまわる金のねん出、そういう経過を経て技術が開発されるわけで、そういう現実を見たこともない高所から眺めて、そういうものを「地球全体の救済のために、世界中にばらまけ」というのは、あまりにも能天気な思考だと思う。
21世紀の今日において、民主党の鳩山由紀生がこういう能天気なことを言いふらしているが、これに対して日本の知性・理性を代表する賢人の反応は一体どうなっているのであろう。
正面切った反対論は未だに出ていないようであるが、ことほど左様に、人間が教育によって習得した人としての理性あるいは知性というものは、人間の存在にどのように機能しているのであろう。
高等教育というものが、ただただ個人が高収入を得るための免罪符であっていいものだろうか。
世の中が進んで、人々が容易に高等教育を享受できるようになった結果として、そういう人々は、多様な思考、考え方、発想が出来るようになったので、上からの指示命令には素直に応じなくなってなって、社会はますます混迷の度を深める。
高等教育の目的が、個人の理性や知性により磨きを掛けて、一歩でも二歩でも価値多き人間をめざすものだとすると、その結果として、自分の国家の指針に素直に従わない人士を数多く輩出することになり、教育の目的が逆効果になってしまう。
昭和の初期の日本を眺めた時、そこで社会をリードしてきた人々の理念、理想、知性、理性、教養というのは、どういうものであったのだろう。
戦後の左翼的な教育では、天皇制による上からの抑圧に抗しきれず、人々は苦難を強いられた、という論法になるが、日比谷公園焼打ち事件、統帥権干犯問題、ちょうちん行列などの有り様から推察すると、昭和の軍国主義というのは、案外下からのボトムアップの軍国主義ではなかったかと思う。
当然そこにはメデイアが絡んでくるのは必然であろうが、こういう状況下で、人間の理性や知性を発揮する場も当然ながらメデイアだと思う。
当時、「治安維持法があったので、ものが言えなかった」というのは、戦後に生き延びた知識人の常とう句であるが、これは彼等インテリ―の自己弁護の弁明にすぎず、本当は行動する勇気がなかっただけのことである。
戦後、ヤミ米の取り締まり(食管法)を順守して、一切ヤミ米を購入せず、餓死した裁判官が一人いたが、こういう人ならば「治安維持法があったからものが言えなかった」と胸を張っていえるが、それ以外の人には、それをいう権利はない筈だ。
問題は、高等教育を受け、理性も知性も人並み以上に備えた知識人が、一言も体制に異議を差し挟まず、順応してしまったことだ。
そして、戦後というものの言える時代になると、治安維持法があってものが言えなかったという論理を展開しているわけで、この日和見、この風見鶏、この変節の中に、彼等が受けた高等教育の理性や知性は如何様に機能していたのであろう。
結局のところ、高等教育によって成人に達してから後付けされた知識や教養では、その人の持つ本来の人間性を左右できずに、人の理性や知性というものは、教育では如何ともし難いものだということであろう。
この本は東條英機を案外買っており、昭和天皇は彼を信用していた、と述べているが、私もそう思う。
日本では東條英機は日米開戦をした総理大臣という位置づけて極めて人気がないが、日本という内側から眺める光景と、外国人という外側からの視点では大いに違って当然である。
問題は、この部分に潜んでいるようで、東條がいくら天皇に忠実たらんと努力しても、東條の手元に来る情報が支離滅裂で、その上天皇に様々な人が情報を提供するでは、結果として政治としての対応が出来ないのも当然である。
政治というものは、人が人のために良かれと思ってするわけで、ただただ自己の利益の追求のみではない筈である。
そして社会なり国家というものは、為政者をトップに据えたピラミッド型の体制を形作っているわけで、トップがいくら民のためを思って施策を施しても、中間のものがそれを横取りしてしまっては、為政者の民を思う心は下々のものまで伝わらない。
歴史を語ると言ったとき、我々は往々にしてピラミット型のトップの為政者に焦点を当てがちであるが、国家や社会の腐敗は、ピラミッドの中間層の組織破壊、メルトダウンに起因しているように思う。










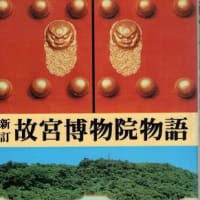




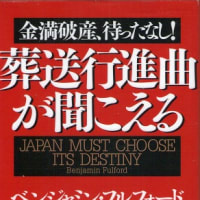

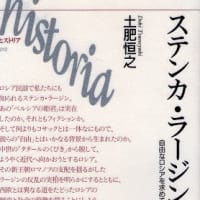
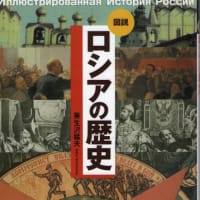

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます