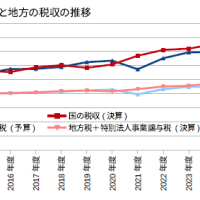評価には基準がいる。経済運営は、成長させたら成功、できなければ失敗で良かろう。そうであれば、アベノミクスの評価は、1.6%成長の2013暦年は成功で、ゼロ成長の2014暦年は失敗となる。何が良くて、何がダメだったのか。浜田宏一先生が「アベノミクス経済学」の書と位置づける『世界が日本経済をうらやむ日』を手元に置きつつ、少しばかり考えてみたい。
………
新著の内容は、端的に言えば、大胆な金融緩和がいかに景気浮揚に有効かを説明しようとするものだ。基本は、「期待に働きかけ、投資を促す」というものだが、これには議論も多いところだろう。もっとも、金融緩和が通貨安と資産高をもたらし、それが輸出増や消費増を引き出して、この需要により設備投資や雇用が創られるというのであれば、賛同者は、かなり増えるに違いない。
こういう効果があって、2013年は1.6%成長を実現したわけだが、野田民主党政権下の2012年でも1.8%成長をしていた。そのため、アベノミクスの功績を確かめるには、もう少し細かく見る必要がある。ノダノミクスの場合は、前年に東日本大震災の大打撃があり、そこからの回復だけで高成長を確保できたという事情があった。実際、2012年1-3月期は、前期比で年率4.6%もの成長を果たしている。
ところが、その後は、3期連続でマイナス成長に沈んでしまう。欧州危機が起こり、打ち続く円高と世界経済の停滞によって、輸出が減少したことが大きい。この停滞を打開したのがアベノミクスだった。大胆な金融緩和を標榜し、一気に円安と株高へと転換した。2013年の各四半期の輸出は、戻した程度に過ぎず、2012年の水準を超えはしなかったが、このコントラストが人々に鮮やかな印象を残したのである。
円安への転換は、時期に恵まれていた面もあるが、チャンスを逃さずに捕まえたことは、素直に評価すべきだろう。経済運営では、なすべきことの逆をして失敗するのは、よくあることだからだ。まさに、2014年4月の消費増税は、それだった。年度成長率の見通しを1.4%としておきながら、マイナス0.9%へ転落することになるのだから、経済運営の見込み違いは、明白である。
………
浜田先生は、第二の矢である財政出動にはあまり触れず、消費増税はアベノミクスの外に置くかの感がある。しかし、2013年の1.6%成長のうち、政府消費と公的資本形成の寄与度は、合わせて0.8を占める。財政出動は極めてよく効いたと評すべきであろう。他方、金融緩和が効くはずの設備投資は、寄与度0.1であり、前年や前々年の0.5を大きく下回った。また、輸出は、プラスに転じたものの、0.2であった。
消費増税については、1%ずつに刻むべしといったことを、浜田先生は、かねがね言っておられたように記憶する。結果が分かった今となれば、補正予算と法人減税を条件に、増税を容認したことは、残念であった。前年度との比較で、補正予算が縮小していることを見過ごしてはならなかったし、今年度の機械受注などの結果に照らせば、法人減税に、多大な期待はできなかったのである。
これとは裏腹に、消費増税という財政政策は、絶大な威力を発揮した。、ここ数年の毎期0.5%成長のトレンドと比較すれば、年間で13兆円も消費を落ち込ませた。これは、増税で抜かれる所得8兆円に加え、駆け込みの反動減5兆円も戻らなかったことを意味する。デフレ下の財政政策は極めて強力で、金融政策や法人減税で補うのは、いかに困難かを、端無くも証明したと言えよう。
………
日本の金融政策に関して、浜田先生は、1998年の新日銀法の施行以来、十分な金融緩和が行われなかったと見ておられるようだが、リーマンショック前は、金融緩和によって、かなりの効果を上げていたと、筆者は考えている。それは、ちょうど、第一次安倍内閣の頃であり、金融緩和によって円キャリートレードが発生して、円安バブルによる輸出と設備投資の急増が起こっていたからである。
問題は、輸出→所得→消費という、いつもの波及パターンが起こらなかったことだ。それは、当時の安倍政権は、補正で2.5兆円、本予算で4兆円の公債金の減額を行い、緊縮財政で好循環を阻害していたからである。つまり、今のアベノミクスで金融緩和と消費増税を組み合わせたのと同じことを、前もしていたわけである。金融緩和に依存し、緊縮財政を甘く見たゆえの失敗は、繰り返されたことになる。
金融緩和の成果を、緊縮財政が食い尽くし、景気回復が十分でないうちに、外部環境が移ろいでしまえば、不況のまま、金融緩和は取り残される。そして、次の不況への対応として、更なる金融緩和が求められ、前代未聞のものに深まって行く。リーマンショック後、日本が米欧の金融緩和競争に遅れを取った背景には、こうした事情があり、一概に日銀のせいとは言えないところがある。
………
結局、アベノミクスという大規模な実験から得られた教訓は、デフレからの脱出には、金融緩和も、財政出動も、両方が必要という、至って平凡なものである。むしろ、金融緩和の効果は限られていて、これに緊縮財政をオーバーライドする力はなく、組み合わせるに際しては、その分量を慎重に見極めなければならない。これが欠くべからざる要諦であろう。
2014年のアベノミクスは、これを守らず、再び失敗した。前回の失敗について、「もっと金融緩和をしておけば」という誤った教訓を得ていたからと思われる。ただし、今回は、総選挙という非常手段で再増税路線を打破し、三度、失敗を上塗りする愚は回避した。幸い、今回の消費増税は、致命傷にならずに済んでいる。もう少し鉱工業生産が落ち、ノダ後退の時の水準を割っていれば、リストラに着火していたかもしれない。
さて、これからである。相変わらず、財政政策の計量を怠っているために、2015年度は、「無意識」のまま、国、地方、社会保険で計8兆円の緊縮財政を行っている。原油安という天恵がなければ、低成長に喘ぐところだった。そうすると、今までのところ、アベノミクスとは、しょせん、金融緩和と緊縮財政の組み合わせであり、巡り会わせで、ある程度の成功を確保したという歴史的評価になると考えられる。むろん、アベノミクスは継続中であるから、変わり得るものではあるが。
(昨日の日経)
新幹線のインド採用有力。生産回復で鉱工業生産4.0%増、国内消費足踏み。人民元2年4月ぶり安値。介護職の派遣料金が上昇。
※第一生命の新家さんが指摘するように、鉱工業生産は出来過ぎだ。原指数の前年度比を見るにつけ、季節調整の問題もあるように思う。12月はやけに低かったし、12月の消費総合指数は大きく下方修正されたりした。商業動態は小売業と卸売業がようやく収束し、家計調査は大きく落ちていた所得の回帰が一服した。このところの消費は、指標が乱れていて、本当に読みにくい。まあ低迷中ということではある。
(今日の日経)
保育・医療の特区で規制緩和。厚年基金の8割が解散決定。
………
新著の内容は、端的に言えば、大胆な金融緩和がいかに景気浮揚に有効かを説明しようとするものだ。基本は、「期待に働きかけ、投資を促す」というものだが、これには議論も多いところだろう。もっとも、金融緩和が通貨安と資産高をもたらし、それが輸出増や消費増を引き出して、この需要により設備投資や雇用が創られるというのであれば、賛同者は、かなり増えるに違いない。
こういう効果があって、2013年は1.6%成長を実現したわけだが、野田民主党政権下の2012年でも1.8%成長をしていた。そのため、アベノミクスの功績を確かめるには、もう少し細かく見る必要がある。ノダノミクスの場合は、前年に東日本大震災の大打撃があり、そこからの回復だけで高成長を確保できたという事情があった。実際、2012年1-3月期は、前期比で年率4.6%もの成長を果たしている。
ところが、その後は、3期連続でマイナス成長に沈んでしまう。欧州危機が起こり、打ち続く円高と世界経済の停滞によって、輸出が減少したことが大きい。この停滞を打開したのがアベノミクスだった。大胆な金融緩和を標榜し、一気に円安と株高へと転換した。2013年の各四半期の輸出は、戻した程度に過ぎず、2012年の水準を超えはしなかったが、このコントラストが人々に鮮やかな印象を残したのである。
円安への転換は、時期に恵まれていた面もあるが、チャンスを逃さずに捕まえたことは、素直に評価すべきだろう。経済運営では、なすべきことの逆をして失敗するのは、よくあることだからだ。まさに、2014年4月の消費増税は、それだった。年度成長率の見通しを1.4%としておきながら、マイナス0.9%へ転落することになるのだから、経済運営の見込み違いは、明白である。
………
浜田先生は、第二の矢である財政出動にはあまり触れず、消費増税はアベノミクスの外に置くかの感がある。しかし、2013年の1.6%成長のうち、政府消費と公的資本形成の寄与度は、合わせて0.8を占める。財政出動は極めてよく効いたと評すべきであろう。他方、金融緩和が効くはずの設備投資は、寄与度0.1であり、前年や前々年の0.5を大きく下回った。また、輸出は、プラスに転じたものの、0.2であった。
消費増税については、1%ずつに刻むべしといったことを、浜田先生は、かねがね言っておられたように記憶する。結果が分かった今となれば、補正予算と法人減税を条件に、増税を容認したことは、残念であった。前年度との比較で、補正予算が縮小していることを見過ごしてはならなかったし、今年度の機械受注などの結果に照らせば、法人減税に、多大な期待はできなかったのである。
これとは裏腹に、消費増税という財政政策は、絶大な威力を発揮した。、ここ数年の毎期0.5%成長のトレンドと比較すれば、年間で13兆円も消費を落ち込ませた。これは、増税で抜かれる所得8兆円に加え、駆け込みの反動減5兆円も戻らなかったことを意味する。デフレ下の財政政策は極めて強力で、金融政策や法人減税で補うのは、いかに困難かを、端無くも証明したと言えよう。
………
日本の金融政策に関して、浜田先生は、1998年の新日銀法の施行以来、十分な金融緩和が行われなかったと見ておられるようだが、リーマンショック前は、金融緩和によって、かなりの効果を上げていたと、筆者は考えている。それは、ちょうど、第一次安倍内閣の頃であり、金融緩和によって円キャリートレードが発生して、円安バブルによる輸出と設備投資の急増が起こっていたからである。
問題は、輸出→所得→消費という、いつもの波及パターンが起こらなかったことだ。それは、当時の安倍政権は、補正で2.5兆円、本予算で4兆円の公債金の減額を行い、緊縮財政で好循環を阻害していたからである。つまり、今のアベノミクスで金融緩和と消費増税を組み合わせたのと同じことを、前もしていたわけである。金融緩和に依存し、緊縮財政を甘く見たゆえの失敗は、繰り返されたことになる。
金融緩和の成果を、緊縮財政が食い尽くし、景気回復が十分でないうちに、外部環境が移ろいでしまえば、不況のまま、金融緩和は取り残される。そして、次の不況への対応として、更なる金融緩和が求められ、前代未聞のものに深まって行く。リーマンショック後、日本が米欧の金融緩和競争に遅れを取った背景には、こうした事情があり、一概に日銀のせいとは言えないところがある。
………
結局、アベノミクスという大規模な実験から得られた教訓は、デフレからの脱出には、金融緩和も、財政出動も、両方が必要という、至って平凡なものである。むしろ、金融緩和の効果は限られていて、これに緊縮財政をオーバーライドする力はなく、組み合わせるに際しては、その分量を慎重に見極めなければならない。これが欠くべからざる要諦であろう。
2014年のアベノミクスは、これを守らず、再び失敗した。前回の失敗について、「もっと金融緩和をしておけば」という誤った教訓を得ていたからと思われる。ただし、今回は、総選挙という非常手段で再増税路線を打破し、三度、失敗を上塗りする愚は回避した。幸い、今回の消費増税は、致命傷にならずに済んでいる。もう少し鉱工業生産が落ち、ノダ後退の時の水準を割っていれば、リストラに着火していたかもしれない。
さて、これからである。相変わらず、財政政策の計量を怠っているために、2015年度は、「無意識」のまま、国、地方、社会保険で計8兆円の緊縮財政を行っている。原油安という天恵がなければ、低成長に喘ぐところだった。そうすると、今までのところ、アベノミクスとは、しょせん、金融緩和と緊縮財政の組み合わせであり、巡り会わせで、ある程度の成功を確保したという歴史的評価になると考えられる。むろん、アベノミクスは継続中であるから、変わり得るものではあるが。
(昨日の日経)
新幹線のインド採用有力。生産回復で鉱工業生産4.0%増、国内消費足踏み。人民元2年4月ぶり安値。介護職の派遣料金が上昇。
※第一生命の新家さんが指摘するように、鉱工業生産は出来過ぎだ。原指数の前年度比を見るにつけ、季節調整の問題もあるように思う。12月はやけに低かったし、12月の消費総合指数は大きく下方修正されたりした。商業動態は小売業と卸売業がようやく収束し、家計調査は大きく落ちていた所得の回帰が一服した。このところの消費は、指標が乱れていて、本当に読みにくい。まあ低迷中ということではある。
(今日の日経)
保育・医療の特区で規制緩和。厚年基金の8割が解散決定。