3月分の経済指標を踏まえると、1-3月期の消費はゼロ成長に終わるのではないか。そうなると、成長率は前期を下回るので、アベノミクスは再失速という評価になろう。原油安メリットは未だしで、ベアの昨年比の拡大幅はわずかだ。アベノミクスは、成長のモメンタムを失った可能性がある。今年度、民需に期待し、公需を減らして成長率の寄与度を-0.6に落とすことにした政策判断の妥当性が問われよう。
………
まず、商業動態だが、先日も触れたように、1-3月期の季節調整済指数の前期比は、卸売業で-0.6%、小売業で-2.1%という落ち込みぶりだ。家計調査は、二人以上の世帯の実質消費支出(除く住居等)の前期比は0.0となった。今回、「除く住居等」を重視するのは、実質実収入の推移からすると、「除かない」方にはブレがあると見るからだ。
そして、鉱工業生産の消費財出荷は、前月差が+0.4であるから、単純に3月の消費総合指数が同じだけ伸びるとすると、消費総合指数の前期比も0.0となる。以上からすれば、1-3月期の消費について、ゼロ成長を予測しても、おかしくないと考える。もっとも、鉱工業生産の消費財出荷そのものは、前期比+2.9であるから、もう少し消費が伸びると見ることもできなくはない。
消費の伸びが止まった理由は、家計調査を見れば分かる。勤労者世帯の実質実収入が停滞しているからだ。前期比では1.0増であるが、ゲタで上がっているだけで、12月から3月にかけて0.2しか増えていない。12月までの実質実収入の回復は、消費税対応で強く絞り込まれたものが徐々に戻る過程だったのであり、それはもう終わったということだろう。
………
ここで、毎月勤労統計を見てみよう。現金給与総額の前年同期比は、7-9月期1.1%、10-12月期0.4%、1-3月期0.2%と弱まっている。実質賃金は、1-3月期に幾分マイナスを戻したが、3月の数字からすると続きそうにない。これは常用雇用についても言える。前年同月比は、前年に伸びた時期のウラにさしかかり、減速することになろう。
労働力調査でも、就業者の前年同月比は、増加数が3か月連続で低下しており、弱まりがうかがえる。季節調整値では、1,2月の一進一退から、3月は-10万人となった。職業紹介状況に目を移すと、新規求人数の季節調整値は2か月連続の減である。前年同月比で見ても、求人倍率は、有効、新規ともに、水準は高いが、峠を迎えているとも受け取れる状況だ。
結局、アベノミクスは、消費増税のショックからの戻りという推進力を使い切ったわけである。これに代わる原油安メリットは、企業収益以外には目立つものがなく、そうこうするうちに、反転して60ドル台へ迫っている。頼みの綱のベアは、連合加盟の組合でも、前年からの増加幅は0.1%程という結果だった。政府は、経済見通しで、公需の寄与度を-0.6にすると宣言していたが、民需の弱さという見込み違いが起こっている。
………
今後のアベノミクスを占うため、もう少し長いスパンで数字を眺めることにしよう。下の図は鉱工業生産の推移である。3月は前月比で若干の減少であり、このところの局面については、「緩やかな回復」という見方が一般的である。これを大震災以降の流れとして見直すと、また別の見方が現れる。
鉱工業生産は、大震災から9か月ほどで立ち直りを見せるが、円高無策のノダ後退でズルズルと低下してしまう。それが、アベノミクスによる円安株高の転換により、消費増税の直前には、震災後のピークの回復に成功する。しかし、これを一気の消費増税がブチ壊す。消費財は、大きく落ち込み、1月に復活したかに見えたが、2,3月は減衰した。これに対して、投資財は、揺れつつも多少の低下で踏みとどまっている。
アベノミクスの本質は、金融緩和と緊縮財政の組み合わせである。投資財が踏みとどまっているのだから、金融緩和は奏功したと言えよう。他方、大規模な増税をしたのだから、消費財が落ち込むのも当然だ。日本経済は素直な結果を出している。そして、合わせてみれば、全体としての停滞であり、物価上昇率の再低下であった。アベノミクスは、大震災後のピークさえ取り戻せないレベルで、さ迷っているのが実態であり、新たな領域へ抜けていくだけのモメンタムも欠いているのである。
(図)

………
過去を振り返るなら、第一次安倍政権の経済運営も、金融緩和下の緊縮財政であり、同様の停滞を招いている。異なるのは、金融緩和と緊縮財政の規模を、一層、極端にしたことだ。そして、今回、またも金融緩和の成果は緊縮財政に食われ、異様な金融緩和が取り残されて、後始末に不安が募ることになった。
前回は、安倍政権の失敗の後、米国のバブルが弾け、日本経済は、停滞から転落へ押し流された。足元でも、成長の推進力が失われる中で、中国はバブル崩壊がくすぶり、米国は、欧州の金融緩和と緊縮財政によるドル高で、減速を見せている。経済環境に変遷はつきものなのである。いつも晴天に恵まれ、運に助けてもらえるとは限らないんだよ。
残念ながら、現在、検討が進められている経済政策は、ダウンサイド・リスクへの備えではなく、財政再建目標の達成のための社会保障の削減である。気が早いと言うか、一点張りと言うか、目の前の減速には、とんと関心がないようだ。鉱工業生産の動きを見れば、足りないのは消費であり、これを押し上げる政策がなければ、全体の浮上もままならないのが分からないのだろうか。
………
消費へのテコ入れは、1-3月期GDPで、アベノミクスの再失速がハッキリしてから取りかかれば良いと甘く見られているのかもしれない。しかし、既に、民間調査機関の予想は、平均で1.5%成長となり、これまでの強気さが影を潜めている。1.5%成長は、10-12月期と変わらなく見えるかもしれないが、中身が悪い。10-12月期に0.5%増だった消費が0.2%へ減速するというもので、売れ残りの在庫増によって、成長が補われる構図にある。在庫増になると、4-6月期GDPの足まで引っ張ることになる。
設備投資については、鉱工業生産の投資財の動向からは堅調と思われるが、10-12月期は、その「除く輸送機械」の出荷が前期比で+3.0もあったのに、GDPの設備投資は-0.1%にとどまった。これを勘案すると、1-3月の前期比が+1.4にあっても要注意である。しかも、1月が主に外需で突出し、2,3月は伸び悩んでいるのだから、とても安心できない。加えて、1-3月期の外需は、マイナス寄与であろう。
民間エコノミストでさえ、強気を修正しているのだから、まして、経済運営の衝にある者は、常に両面のリスクに備えて、政策を用意しておかなければなるまい。まあ、言うだけムダだとは思うがね。需要追加策は、悪化が誰の目にも明らかになり、官邸に怒られてから泥縄式で準備し、後手に回るくらいが、財政赤字の日本のためには良いという程度の認識なのかもしれない。
………
どんな政策を用意すべきかは、本コラムの「ニッポンの理想」を知る読者には言うまでもないだろう。昨日の日経によれば、配偶者控除を消費増税の2017年に新制度にするらしいが、本当に女性の活躍を願うなら、正すべきは税の103万円の壁ではなく、保険料の130万円の壁である。こちらには、配偶者特別控除という、壁を登る階段すらないのだから。
もっとも、壁に階段を設けるには、保険料の軽減と税による補填が必要だ。つまりは、女性の活躍の支援を推進力にするとしても、カネのかからない範囲までなのだろう。2014年度の税収上ブレが1.9兆円にもなり、財政再建目標の達成時期が2025年より早まりそうなのに、成長が減速していても、そっちのけで、社会保障の削減にばかり熱中している。これが日本の経済運営である。
(昨日の日経)
配偶者控除を2017年に新制度に。NPOの報酬の少なさ。非製造業2割強が最高益、訪日客や法人需要で、小売業・外食は苦戦。1-3月期GDP1.5%増予想・民間10社。原油反発60ドルに迫る。4月軽自動車は4年ぶりの減少率。
(今日の日経)
車生産、国内に回帰。ベア実施の中小が大幅増。行き詰まる中国の土地財政。少ないデータで本質解析・スパースモデリング。
………
まず、商業動態だが、先日も触れたように、1-3月期の季節調整済指数の前期比は、卸売業で-0.6%、小売業で-2.1%という落ち込みぶりだ。家計調査は、二人以上の世帯の実質消費支出(除く住居等)の前期比は0.0となった。今回、「除く住居等」を重視するのは、実質実収入の推移からすると、「除かない」方にはブレがあると見るからだ。
そして、鉱工業生産の消費財出荷は、前月差が+0.4であるから、単純に3月の消費総合指数が同じだけ伸びるとすると、消費総合指数の前期比も0.0となる。以上からすれば、1-3月期の消費について、ゼロ成長を予測しても、おかしくないと考える。もっとも、鉱工業生産の消費財出荷そのものは、前期比+2.9であるから、もう少し消費が伸びると見ることもできなくはない。
消費の伸びが止まった理由は、家計調査を見れば分かる。勤労者世帯の実質実収入が停滞しているからだ。前期比では1.0増であるが、ゲタで上がっているだけで、12月から3月にかけて0.2しか増えていない。12月までの実質実収入の回復は、消費税対応で強く絞り込まれたものが徐々に戻る過程だったのであり、それはもう終わったということだろう。
………
ここで、毎月勤労統計を見てみよう。現金給与総額の前年同期比は、7-9月期1.1%、10-12月期0.4%、1-3月期0.2%と弱まっている。実質賃金は、1-3月期に幾分マイナスを戻したが、3月の数字からすると続きそうにない。これは常用雇用についても言える。前年同月比は、前年に伸びた時期のウラにさしかかり、減速することになろう。
労働力調査でも、就業者の前年同月比は、増加数が3か月連続で低下しており、弱まりがうかがえる。季節調整値では、1,2月の一進一退から、3月は-10万人となった。職業紹介状況に目を移すと、新規求人数の季節調整値は2か月連続の減である。前年同月比で見ても、求人倍率は、有効、新規ともに、水準は高いが、峠を迎えているとも受け取れる状況だ。
結局、アベノミクスは、消費増税のショックからの戻りという推進力を使い切ったわけである。これに代わる原油安メリットは、企業収益以外には目立つものがなく、そうこうするうちに、反転して60ドル台へ迫っている。頼みの綱のベアは、連合加盟の組合でも、前年からの増加幅は0.1%程という結果だった。政府は、経済見通しで、公需の寄与度を-0.6にすると宣言していたが、民需の弱さという見込み違いが起こっている。
………
今後のアベノミクスを占うため、もう少し長いスパンで数字を眺めることにしよう。下の図は鉱工業生産の推移である。3月は前月比で若干の減少であり、このところの局面については、「緩やかな回復」という見方が一般的である。これを大震災以降の流れとして見直すと、また別の見方が現れる。
鉱工業生産は、大震災から9か月ほどで立ち直りを見せるが、円高無策のノダ後退でズルズルと低下してしまう。それが、アベノミクスによる円安株高の転換により、消費増税の直前には、震災後のピークの回復に成功する。しかし、これを一気の消費増税がブチ壊す。消費財は、大きく落ち込み、1月に復活したかに見えたが、2,3月は減衰した。これに対して、投資財は、揺れつつも多少の低下で踏みとどまっている。
アベノミクスの本質は、金融緩和と緊縮財政の組み合わせである。投資財が踏みとどまっているのだから、金融緩和は奏功したと言えよう。他方、大規模な増税をしたのだから、消費財が落ち込むのも当然だ。日本経済は素直な結果を出している。そして、合わせてみれば、全体としての停滞であり、物価上昇率の再低下であった。アベノミクスは、大震災後のピークさえ取り戻せないレベルで、さ迷っているのが実態であり、新たな領域へ抜けていくだけのモメンタムも欠いているのである。
(図)

………
過去を振り返るなら、第一次安倍政権の経済運営も、金融緩和下の緊縮財政であり、同様の停滞を招いている。異なるのは、金融緩和と緊縮財政の規模を、一層、極端にしたことだ。そして、今回、またも金融緩和の成果は緊縮財政に食われ、異様な金融緩和が取り残されて、後始末に不安が募ることになった。
前回は、安倍政権の失敗の後、米国のバブルが弾け、日本経済は、停滞から転落へ押し流された。足元でも、成長の推進力が失われる中で、中国はバブル崩壊がくすぶり、米国は、欧州の金融緩和と緊縮財政によるドル高で、減速を見せている。経済環境に変遷はつきものなのである。いつも晴天に恵まれ、運に助けてもらえるとは限らないんだよ。
残念ながら、現在、検討が進められている経済政策は、ダウンサイド・リスクへの備えではなく、財政再建目標の達成のための社会保障の削減である。気が早いと言うか、一点張りと言うか、目の前の減速には、とんと関心がないようだ。鉱工業生産の動きを見れば、足りないのは消費であり、これを押し上げる政策がなければ、全体の浮上もままならないのが分からないのだろうか。
………
消費へのテコ入れは、1-3月期GDPで、アベノミクスの再失速がハッキリしてから取りかかれば良いと甘く見られているのかもしれない。しかし、既に、民間調査機関の予想は、平均で1.5%成長となり、これまでの強気さが影を潜めている。1.5%成長は、10-12月期と変わらなく見えるかもしれないが、中身が悪い。10-12月期に0.5%増だった消費が0.2%へ減速するというもので、売れ残りの在庫増によって、成長が補われる構図にある。在庫増になると、4-6月期GDPの足まで引っ張ることになる。
設備投資については、鉱工業生産の投資財の動向からは堅調と思われるが、10-12月期は、その「除く輸送機械」の出荷が前期比で+3.0もあったのに、GDPの設備投資は-0.1%にとどまった。これを勘案すると、1-3月の前期比が+1.4にあっても要注意である。しかも、1月が主に外需で突出し、2,3月は伸び悩んでいるのだから、とても安心できない。加えて、1-3月期の外需は、マイナス寄与であろう。
民間エコノミストでさえ、強気を修正しているのだから、まして、経済運営の衝にある者は、常に両面のリスクに備えて、政策を用意しておかなければなるまい。まあ、言うだけムダだとは思うがね。需要追加策は、悪化が誰の目にも明らかになり、官邸に怒られてから泥縄式で準備し、後手に回るくらいが、財政赤字の日本のためには良いという程度の認識なのかもしれない。
………
どんな政策を用意すべきかは、本コラムの「ニッポンの理想」を知る読者には言うまでもないだろう。昨日の日経によれば、配偶者控除を消費増税の2017年に新制度にするらしいが、本当に女性の活躍を願うなら、正すべきは税の103万円の壁ではなく、保険料の130万円の壁である。こちらには、配偶者特別控除という、壁を登る階段すらないのだから。
もっとも、壁に階段を設けるには、保険料の軽減と税による補填が必要だ。つまりは、女性の活躍の支援を推進力にするとしても、カネのかからない範囲までなのだろう。2014年度の税収上ブレが1.9兆円にもなり、財政再建目標の達成時期が2025年より早まりそうなのに、成長が減速していても、そっちのけで、社会保障の削減にばかり熱中している。これが日本の経済運営である。
(昨日の日経)
配偶者控除を2017年に新制度に。NPOの報酬の少なさ。非製造業2割強が最高益、訪日客や法人需要で、小売業・外食は苦戦。1-3月期GDP1.5%増予想・民間10社。原油反発60ドルに迫る。4月軽自動車は4年ぶりの減少率。
(今日の日経)
車生産、国内に回帰。ベア実施の中小が大幅増。行き詰まる中国の土地財政。少ないデータで本質解析・スパースモデリング。


















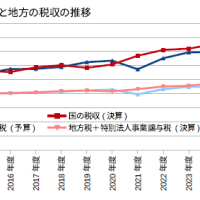





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます