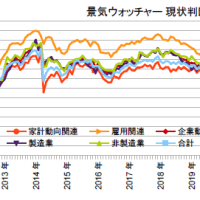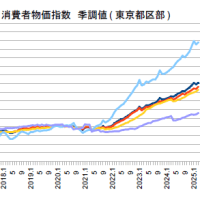長く生きていると、現実が間違っていると言い出す人と、自分が間違っていると疑う人の二つのタイプがあることが分かってくる。臆病な筆者は後の方だ。経済について、いろいろと説明を試みてきたが、どこかに穴があるのじゃないかと心配してしまう。これまで失敗もしてきただけにね。
他方、世の中には、羨ましいほどの自信家もいる。「巨額の財政赤字を抱える日本は、必ず破綻する」なんて言う人は、その類だと思う。筆者も昔は破綻を心配していた。金利も高かったし、「100兆円の背信」(1985年刊)という本を読んでは、こんな政治では危ういなと感じていたものだった。
しかし、それから20年が経ち、国債は700兆円を超えても、兆しすら見られない。こうなっても、「いや必ず起こるんだ」と叫び続けるのも一つの在り方とは思うが、信念の薄い筆者は、これには何か理由があるのではと疑ってしまう。そして、GDP統計などを調べては、いろいろと理由を探して来たのである。
………
財政赤字を考えるときに重要なのは、誰が貸しているかである。財政赤字は、誰かの貯蓄を使う行為だからだ。したがって、財政赤字を削減する際には、同時に誰かの貯蓄を減らさないといけない。財政赤字の削減を結構と思う人は多いが、それが家計や企業の貯蓄を減らすことと同義だとと知ると、違和感を持つのではないか。
もちろん、家計が消費を増やし、企業が投資を増やすという形で貯蓄を減らしてくれるなら、何の問題もない。けれども、それらが政策的に難しいことは、改めて言うまでもなかろう。残念ながら、「財政赤字の削減は、政治が増税を決断すればできる」と信じると同時に、消費や投資を増やすことが未解決の課題だと公言する「矛盾した考え」の持ち主も多い。
「増税決定の次は、成長戦略だ」とする日経の論説は、その典型である。少なくとも彼らは、成長戦略が上手く行かなかったら、増税を取りやめようとは、露ほども思ってないだろう。こうした「矛盾した考え」に基づいて経済運営を舵取りしたら、失敗は目に見えている。あとは、増税の時点で偶然にも高消費・高投資になっていることを祈るしかない。
………
歴史的に貯蓄の主体を見ると、1997年までは、社会保障基金があった。何のことはない、公的年金が家計所得を吸い上げて、消費を不足ぎみにし、財政が公的年金の貯蓄を借りて公共事業を打ち、需要を補っていたのである。おそらく、年金積立金の増強などしていなければ、財政赤字は必要なかっただろう。こうした構図は、GDP統計を見れば、誰でも確認できる。(詳しくは「壮大なる愚行」を参照)
財政と社会保障を連結した政府部門全体で見れば、赤字は大したものではなかったから、クラウディングアウトによる金利高騰などの弊害は起こりようがなく、所得を吸い上げていたのだから、インフレもあり得ない。財政破綻など、心配するほどムダだったのである。財政当局の危機感は、GDP統計で政府部門全体も見ずに、担当する国の財政しか考えないという視野狭窄の産物だった。
ところが、ここで財政当局は史上最大級の愚行を犯してしまう。あらぬ危機感に駆られ、1997年に過激な緊縮財政を行い、それまでの経済構造を壊してしまう。デフレ財政のショックによって失業が急増し、家計は所得を減らし、年金保険料も十分に払えなくなって、社会保障基金まで赤字に転落してしまう。「財政再建」を敢行して、問題のなかった政府部門全体の収支を赤字構造に破壊してしまったのだから、これほどの愚行もあるまい。
これ以降、財政赤字を賄う貯蓄の出し手が交代する。それは企業であった。財政による需要の吸い上げで内需が伸びなくなったために、企業は設備投資の意欲を失い、企業に資金が滞留するようになった。また、成長しない経済では、正社員を雇うという人的投資も不要になり、社会保険料の軽い非正規を増やした。これも、資金が社会保障基金から企業へと滞留先が変わるように作用した。
こうしたことは、企業が望んだものではない。財政の愚行がもたらした経済環境の変化に対応したまでのことである。需要のないところに設備投資はできないし、労働力が余っているのに高賃金を払う言われもない。高配当をするのは、成長によって株主に報いることができなくなったからだし、法人減税を望むのは、低投資で原価償却が減ったためである。TPPを叫ぶのは外需にしか頼れないゆえだ。別に国民を裏切りたいわけではないのである。
………
こうした状況を変えるには、震災からの生産回復による所得増から、消費増、設備投資増、雇用増、所得増という景気拡大の循環を大切に育てていかねばならない。これまで財政当局は、国民の目を欺き、あらゆる手管で緊縮財政を仕掛けてきたが、復興事業を抱えたために、さすがに足を引張れなくなった。それが現下における、誰もが予想しなかった高成長の背景になっている。
日本経済は、欧州と比較すれば、規制も緩く、社会保障負担も軽く、技術も資本もある。愚劣で極端な財政運営さえしなければ、「成長戦略」などなしに、自力で成長していく。それを現実が証明しつつある。成長は財政赤字のGDP比率の分母を大きくするし、2006年度並みへの大幅な税収回復も見られよう。日本経済は、財政再建をしないことによって、財政破綻から遠のいて行く。財政破綻を心待ちにする人にとって、現実は間違い続けるだろう。
あとは、2014年4月までに、巨額の財政赤字の謎に気づいてほしいものだと思う。高成長と税収回復を目の当たりにすれば、一気増税という経済を壊しかねない危険な財政運営を敢行しようとは思わないだろう。現実が間違っているなら、過激な財政で破綻させてみせるなんて、冗談にもならない。そのくらいの理性は、日本人は持っていると信じている。
※KitaAlpsさん、新著を楽しみにしてますよ。
(今日の日経)
車・機械が積極投資、新エネ重点。全体では4.3%増。経済連携ASEAN頼み。復興インデックス。ネット配信で放送補完。トリドリの思惑、仲間の目で利他。読書・家族進化論。
※補追
日本の国債残高が他国に例がないほど巨大なのは、年金などの公的資産が大きいだけでなく、独特の経済運営に因る。緊縮財政を貫けば、国債残高は積み上がらないし、放漫財政を続ければ、インフレが加速して、やはり積み上げられなくなる。日本の場合、不況の時には放漫財政をするが、回復しだすと早々と緊縮財政を始めて成長の芽を摘むという「猛アクセルと急ブレーキ」が特徴で、こんな不可思議な政策をしているから、巨大債務という奇観が見られるのである。
他方、世の中には、羨ましいほどの自信家もいる。「巨額の財政赤字を抱える日本は、必ず破綻する」なんて言う人は、その類だと思う。筆者も昔は破綻を心配していた。金利も高かったし、「100兆円の背信」(1985年刊)という本を読んでは、こんな政治では危ういなと感じていたものだった。
しかし、それから20年が経ち、国債は700兆円を超えても、兆しすら見られない。こうなっても、「いや必ず起こるんだ」と叫び続けるのも一つの在り方とは思うが、信念の薄い筆者は、これには何か理由があるのではと疑ってしまう。そして、GDP統計などを調べては、いろいろと理由を探して来たのである。
………
財政赤字を考えるときに重要なのは、誰が貸しているかである。財政赤字は、誰かの貯蓄を使う行為だからだ。したがって、財政赤字を削減する際には、同時に誰かの貯蓄を減らさないといけない。財政赤字の削減を結構と思う人は多いが、それが家計や企業の貯蓄を減らすことと同義だとと知ると、違和感を持つのではないか。
もちろん、家計が消費を増やし、企業が投資を増やすという形で貯蓄を減らしてくれるなら、何の問題もない。けれども、それらが政策的に難しいことは、改めて言うまでもなかろう。残念ながら、「財政赤字の削減は、政治が増税を決断すればできる」と信じると同時に、消費や投資を増やすことが未解決の課題だと公言する「矛盾した考え」の持ち主も多い。
「増税決定の次は、成長戦略だ」とする日経の論説は、その典型である。少なくとも彼らは、成長戦略が上手く行かなかったら、増税を取りやめようとは、露ほども思ってないだろう。こうした「矛盾した考え」に基づいて経済運営を舵取りしたら、失敗は目に見えている。あとは、増税の時点で偶然にも高消費・高投資になっていることを祈るしかない。
………
歴史的に貯蓄の主体を見ると、1997年までは、社会保障基金があった。何のことはない、公的年金が家計所得を吸い上げて、消費を不足ぎみにし、財政が公的年金の貯蓄を借りて公共事業を打ち、需要を補っていたのである。おそらく、年金積立金の増強などしていなければ、財政赤字は必要なかっただろう。こうした構図は、GDP統計を見れば、誰でも確認できる。(詳しくは「壮大なる愚行」を参照)
財政と社会保障を連結した政府部門全体で見れば、赤字は大したものではなかったから、クラウディングアウトによる金利高騰などの弊害は起こりようがなく、所得を吸い上げていたのだから、インフレもあり得ない。財政破綻など、心配するほどムダだったのである。財政当局の危機感は、GDP統計で政府部門全体も見ずに、担当する国の財政しか考えないという視野狭窄の産物だった。
ところが、ここで財政当局は史上最大級の愚行を犯してしまう。あらぬ危機感に駆られ、1997年に過激な緊縮財政を行い、それまでの経済構造を壊してしまう。デフレ財政のショックによって失業が急増し、家計は所得を減らし、年金保険料も十分に払えなくなって、社会保障基金まで赤字に転落してしまう。「財政再建」を敢行して、問題のなかった政府部門全体の収支を赤字構造に破壊してしまったのだから、これほどの愚行もあるまい。
これ以降、財政赤字を賄う貯蓄の出し手が交代する。それは企業であった。財政による需要の吸い上げで内需が伸びなくなったために、企業は設備投資の意欲を失い、企業に資金が滞留するようになった。また、成長しない経済では、正社員を雇うという人的投資も不要になり、社会保険料の軽い非正規を増やした。これも、資金が社会保障基金から企業へと滞留先が変わるように作用した。
こうしたことは、企業が望んだものではない。財政の愚行がもたらした経済環境の変化に対応したまでのことである。需要のないところに設備投資はできないし、労働力が余っているのに高賃金を払う言われもない。高配当をするのは、成長によって株主に報いることができなくなったからだし、法人減税を望むのは、低投資で原価償却が減ったためである。TPPを叫ぶのは外需にしか頼れないゆえだ。別に国民を裏切りたいわけではないのである。
………
こうした状況を変えるには、震災からの生産回復による所得増から、消費増、設備投資増、雇用増、所得増という景気拡大の循環を大切に育てていかねばならない。これまで財政当局は、国民の目を欺き、あらゆる手管で緊縮財政を仕掛けてきたが、復興事業を抱えたために、さすがに足を引張れなくなった。それが現下における、誰もが予想しなかった高成長の背景になっている。
日本経済は、欧州と比較すれば、規制も緩く、社会保障負担も軽く、技術も資本もある。愚劣で極端な財政運営さえしなければ、「成長戦略」などなしに、自力で成長していく。それを現実が証明しつつある。成長は財政赤字のGDP比率の分母を大きくするし、2006年度並みへの大幅な税収回復も見られよう。日本経済は、財政再建をしないことによって、財政破綻から遠のいて行く。財政破綻を心待ちにする人にとって、現実は間違い続けるだろう。
あとは、2014年4月までに、巨額の財政赤字の謎に気づいてほしいものだと思う。高成長と税収回復を目の当たりにすれば、一気増税という経済を壊しかねない危険な財政運営を敢行しようとは思わないだろう。現実が間違っているなら、過激な財政で破綻させてみせるなんて、冗談にもならない。そのくらいの理性は、日本人は持っていると信じている。
※KitaAlpsさん、新著を楽しみにしてますよ。
(今日の日経)
車・機械が積極投資、新エネ重点。全体では4.3%増。経済連携ASEAN頼み。復興インデックス。ネット配信で放送補完。トリドリの思惑、仲間の目で利他。読書・家族進化論。
※補追
日本の国債残高が他国に例がないほど巨大なのは、年金などの公的資産が大きいだけでなく、独特の経済運営に因る。緊縮財政を貫けば、国債残高は積み上がらないし、放漫財政を続ければ、インフレが加速して、やはり積み上げられなくなる。日本の場合、不況の時には放漫財政をするが、回復しだすと早々と緊縮財政を始めて成長の芽を摘むという「猛アクセルと急ブレーキ」が特徴で、こんな不可思議な政策をしているから、巨大債務という奇観が見られるのである。