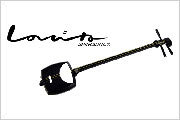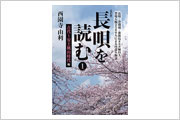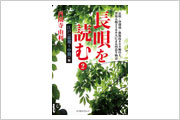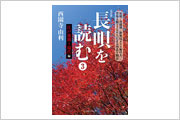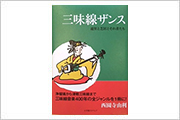母親の英才教育を受けた六三郎は、めきめきと頭角を現した。
恐らくは素人では手に負えなくなったのだろう。
今をときめく杵屋正次郎(1世)に入門させた。
何といっても長唄は花形産業だ。
正次郎はこの頃のご多分にもれず、もともとは浅草の奥山(浅草寺の左奥辺り。吉原への抜け道となる)
で独楽の曲芸、松井源水一座の三味線を弾いていたのだが、六三郎(2世)に引き抜かれ長唄の三味線弾きに転向した。
六三郎は、名門杵屋宗家三代目、初世六三郎の子で、ずっと森田座のタテ三味線だったが、
このたび(1768年)富士田吉治とコンビを組んで中村座に移籍。
この時、六三郎はリメイクを終えた正次郎を森田座にデビューさせた。
もちろんこの時点ではまだ六三郎(4世)は生まれていない。
この11年後にオギャーと生まれ、6才頃に正次郎に入門するのだから。
六三郎が8才になった時、あの富士田吉治が死に、23才の時に師匠正次郎が死んだ。
そして子供の時からのライバルだった師匠の息子が2世正次郎を継ぎ、
川原崎座(森田座の控櫓)のタテ三味線に昇格(1805年)。
だが、天はこの天才を放ってはおかなかった。
2世没後、六三郎の3世を名乗っていた杵屋六左衛門(9世。杵屋宗家8代目の子。養父に実子ができたため分派)
が六三郎に白羽の矢を立て、4世六三郎を継がせたのだ(1808年)。
そして再興なった森田座のタテ三味線に大抜擢(正次郎は市村座に移籍)。
恐らくは素人では手に負えなくなったのだろう。
今をときめく杵屋正次郎(1世)に入門させた。
何といっても長唄は花形産業だ。
正次郎はこの頃のご多分にもれず、もともとは浅草の奥山(浅草寺の左奥辺り。吉原への抜け道となる)
で独楽の曲芸、松井源水一座の三味線を弾いていたのだが、六三郎(2世)に引き抜かれ長唄の三味線弾きに転向した。
六三郎は、名門杵屋宗家三代目、初世六三郎の子で、ずっと森田座のタテ三味線だったが、
このたび(1768年)富士田吉治とコンビを組んで中村座に移籍。
この時、六三郎はリメイクを終えた正次郎を森田座にデビューさせた。
もちろんこの時点ではまだ六三郎(4世)は生まれていない。
この11年後にオギャーと生まれ、6才頃に正次郎に入門するのだから。
六三郎が8才になった時、あの富士田吉治が死に、23才の時に師匠正次郎が死んだ。
そして子供の時からのライバルだった師匠の息子が2世正次郎を継ぎ、
川原崎座(森田座の控櫓)のタテ三味線に昇格(1805年)。
だが、天はこの天才を放ってはおかなかった。
2世没後、六三郎の3世を名乗っていた杵屋六左衛門(9世。杵屋宗家8代目の子。養父に実子ができたため分派)
が六三郎に白羽の矢を立て、4世六三郎を継がせたのだ(1808年)。
そして再興なった森田座のタテ三味線に大抜擢(正次郎は市村座に移籍)。