日本近代文学の森へ (119) 志賀直哉『暗夜行路』 7 誤解 「前篇第一 一 」その4
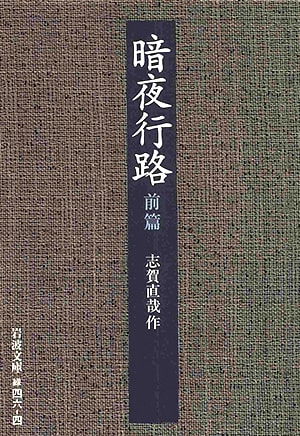
2019.7.17
謙作が茶の間で着物を着替えていると、座敷から阪口と竜岡の話声が聞こえてくる。
二人は如何にも呑気な調子で話していた。謙作は何だか自分だけが鯱張(しゃちこば)っているような変な気がした。皆が平気でいる中に一人怒っている自分が狐につままれたように馬鹿気ても見えた。そして彼は一人不愉快を感じた。
謙作は、いったい阪口はどういう魂胆でやってきたのだろうといろいろ推測して、阪口に何と言ってやろうかという考えで亢奮していたので、二人の呑気な話声が「不愉快」だった。
しかし、二人の会話もよく聞いてみると決して呑気なものではなかった。
「いやな小説だ。それもいいが、中に出て来る気の利かない友達は僕をモデルにして書いてあるのだ。昨日見てすっかり腹を立てて、今朝起きぬけに出掛けて、怒ってやった所だ」
阪口は新聞から眼を放さず、にやにや笑っていた。竜岡は一人いい続けた。
「大部分空想だというが、怪しいものだ。阪口のやりそうな事だ」
阪口はこんなにいわれても別に不愉快な顔もしなかった。彼の腹は解らなかった。しかし彼の行為の上の趣味からいって、こんなにいわれながらただにやにやしている事は確かに彼自身気に入っているに違いなかった。そういう所に優越を彼は示そうとしている。また―つは竜岡が全然異(ちが)う仕事をしている所からも、その余裕を持てるらしかった。竜岡はその年工科大学を出て発動機の研究のため近く仏蘭西へ行くつもりでいる。
「他人の気持を見透(みとお)したような書きぶりが一番不愉快だといってやったんだよ。《たま》(《 》は傍点。以下同。)には当る事もあるが、人間の気持は直ぐ動いているから、次の瞬間にはもうそれを反省しているし、或る場合、同時に反対した二つの気持を持っている事もある。ところが阪ロの書く物では主人公に都合のいい気持だけが見られて、不都合な方にはまるで色盲なんだ」
「もう解ったよ。何遍繰返したって同じ事だ」阪口もちょっと不快(いや)な顔をした。
「今朝から散々油をしぼっているんだよ」竜岡は謙作の方を向いて多少神経的に笑った。
「しつっこい奴だ」と阪口が独語(ひとりごと)のようにいった。
「ええ?」竜岡もむっとしていった。「この位の事をいわれて君に腹を立つ資格はないよ。腹を立つなら、もっといくらでもいうよ。君は一トかど悪者がっているが、悪者としてちっともなってないじゃないか。書いたものでは相当悪者らしいが、要するに安っぽい偽悪者だ。──堕胎が何だい」竜岡はつっぱなすようにいった。彼は今まで快活らしくはしていたが、その実阪口のにやにやした態度に不愉快を感じていたらしかった。そして、それを破裂さした。竜岡は小柄な阪口に較べては倍もあるような大男で、その上柔道が三段であった。そういう点からも阪口はすっかり圧迫されてしまった。謙作は先刻(さっき)から阪口に対する自分の態度を如何(どう)決めていいかわからないでいる内に竜岡がこんな風にやってしまったので、その白けた一座をどうしていいか分らなかった。そのまま三人は黙っていた。
竜岡は竜岡で、「中に出て来る気の利かない友達は僕をモデルにして書いてある」と言う。謙作も、竜岡も、阪口の小説に出てくる「友達」が、自分をモデルにしていると思い込んでいるのが面白いし、意外だ。
謙作の気持ちのところを読んでいると、モデルは謙作以外にありえないように思えるのだが、竜岡の言葉を聞くと、え? って感じだ。二人とも自分だって思うってことは、二人とも思い当たるフシがあるってことで、それを阪口に「見透かされた」ことに不快を感じているわけだ。
こういうことってどこにもあるような気がする。つまり、人間は多かれ少なかれ自意識過剰で、「友達」って書いてあるだけで、あ、オレのことか? って勝手に思い、その思い込みで読んでしまう。阪口に対する感情や言動は、仲間なら似ているところもあるだろうから、「オレだ!」と思うフシは至るところにあるわけだ。
ほんとのところは多分「友達」は謙作なんだろうが、それを竜岡が勝手に思い違いしているのが、阪口には愉快なのかもしれない。だからニヤニヤ笑っているとも考えられる。
謙作がどう思っているか阪口はまだ知らないにしても、竜岡が誤解するぐらいだから、阪口の書き方はそれほど個人を髣髴とさせる具体性がないのだろう。それだけ抽象度が高いともいえて、せっかく、そのように抽象的に書いているのに、竜岡が自らオレだと名乗り出て憤慨やるかたないのが、可笑しいのかもしれない。それはそれでよく分かる。
竜岡の憤慨ぶりは、どうもこの小説だけから来るのではなくて、日頃の阪口の言動から来ているらしい。その点では、謙作と同じだ。謙作も阪口には日頃からため込んできた「不愉快」があり、それがこの小説で決定的になったのだ。
で、二人に共通する阪口への「不愉快」は、竜岡の言葉では、「他人の気持を見透(みとお)したような書きぶり」であり、謙作の場合は、「主人公が他人の心を隅から隅まで見抜いたような」ところということになる。お前の心の中なんか、オレにはお見通しだぜ、といったような態度をとられたら、誰だって不愉快になる。とくに、謙作や竜岡のような自意識過剰な自信家にとっては耐えられないことだろう。
いや、それほどの自信家でも自意識過剰でなくても、他人に自分の心を「見透かされる」ことほど腹立たしいことはないといえる。それは、ほとんどの場合、「誤解」だからである。いや「誤解」というのは不正確かもしれない。正確にいえば、「自分の認識とはずれている」ということだろう。
たとえば、謙作の場合、その女中に対する気持ちは「嫌いではなかった」のだが、阪口がその気持ちを「見透かして」、「謙作は女中が内心好きだったのだ。」と書くと、謙作からすれば、「そうじゃない」と言いたくなるわけだ。「嫌いではない」と「好き」は同じじゃないかということにはならなくて、そういうふうに言語化してまとめられるとやっぱり「本当の気持ち」とは違うものになる。違うものになるけれど、一部は当たっているので、無視できない。そうかといって、その「違い」を事細かに言語化することはできない。
謙作の場合に限らず、こうしたことは、よく起こるのだ。だから、まかり間違っても、「結局さあ、君の気持ちっていうのはこういうことなんでしょ?」って言ってはダメだ。「結局」は禁物なのだ。それが「当たらずといえども遠からず」であった場合、相手は必ず「見透かされた」と思って不愉快になる。誰だって「他人にオレの気持ちが分かってたまるか」と内心思っている。それは、自分の気持ちが単純なものであるはずがないと思いたいからだ。




















