日本近代文学の森へ (135) 志賀直哉『暗夜行路』 22 「愛子とのこと」⑵──父への不快 「前篇第一 五」その2
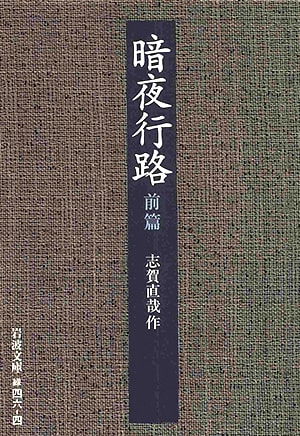
2019.11.17
葬儀での白無垢姿の愛子に、謙作は初めて可憐だと感じ、それからは、愛子への愛情を心に秘めていた。愛子はまだ子どもだと思っていたからだが、現実には愛子には結婚の話が舞い込んでくるようになっていた。
愛子の女学校の卒業期が近づくに従ってぼつぼつ結婚の話が起った。謙作は自分の申出が万々一にも不成功に終る事はないと信じていたが、それでも何か知れぬ不安が、とても六ヶしそうに私語(ささや)く事もあった。しかし彼はこの不安を謂(い)われないものと考えていた。自分の臆病からだと思っていた。彼はこれを愛子の母に打明けたものか、慶太郎に打明けたものかと考えた。愛子の母に打明けるという事は如何にも彼女の好意につけ込むような気がしていやだった。しかし慶太郎に一番先きにいうのも彼は何となく気が進まなかった。仕事の相違、人生に対する考え方の相違、それらから互に相手を軽蔑する気持が作られていた。慶太郎は今、大阪のある会社に出ている。そして彼は最近その会社の社長の娘と結婚する事になっているが、それにもかなり不純な気持があった。慶太郎は彼にそれを平気で公言していた。謙作は万々(ばんばん)断られる事はないと信じながらも、こういう慶太郎に打明けて行く事は何だか気が進まなかった。
彼はやはり本郷の家の人に打明けて、父の方から、彼方(むこう)に話してもらうより他ないと思った。
高等女学校の卒業は17歳ぐらいなので、愛子より5歳上の謙作は、この時22歳ぐらい。今で言えば、高校2年ぐらいで、お見合いの話が舞い込むというのは、隔世の感があるけれど、ぼくがまだ大学生の頃には、付き合っていた彼女にはやはりお見合いの話が来始めていたから、50年ほど前までは、明治時代とそんなに大きな隔たりはないわけである。
時代は変わったというときに、科学技術の発展のことばかりが語られるけれど、こうした「結婚事情」などの観点から見ると、また別の時代の移り変わりが見えておもしろい。
それにしても、謙作は、どうしてこんなに自信家なのだろうか。「自分の申出が万々一にも不成功に終る事はないと信じていた」という自信はいったいどこから来るのだろうか。その割には不安も大きくて、打ち明ける相手に迷うのだ。その相手というのは、間違っても愛子その人ではない。これもまた時代を感じることのひとつだ。
愛子の兄の慶太郎は、勤め先の会社の社長と結婚することに(それを公言することに)なんのためらいもない男。そういう点で、謙作とは気質が違い、それがお互いの軽蔑のもとなっている。
謙作は、愛子の母に打ち明けることさえ、「如何にも彼女の好意につけ込むような気がしていやだった」というような潔癖な性格で、これは芸者の登喜子に対するときも変わらない。芸者に言い寄るのに、自分の欲望を顕わにすることを恥じる潔癖さは、倫理感というよりは、美意識のようなものだ。
会社の社長の娘と結婚するからといって、それが必ずしも「不純」な動機とは限らないけれど、それを「平気で公言」するところに、慶太郎の美意識の欠如を謙作は嗅ぎ取っているのだろう。
結局、謙作は父に相談することにする。ところが、この父は謙作とは妙に疎遠なのだ。けれども、そうするしかない。
一体彼は止むを得ぬ場合の他は滅多に父とは話をしなかった。それは子供からの習慣で、二人の間ではほとんど気にも止めない事だったが、さてそういう事を頼みに行こうとすると、それがやはり妙に億劫な気がした。しかしある夜、彼は思い切って父にそれを頼みに行った。
「彼方で承知すれば、よかろう」と父はいった。「しかしお前も今は分家して、戸主になっているのだから、そういう事も余り此方(こっち)に頼らずに、なるべく、自身でやって見たらいいだろう。俺はその方がいいと思うが、どうだ」
この父との「疎遠感」には、深い理由があるわけだが、まだここではそれが明らかになっていない。そのため、滅多に父とは話さないということが「子供からの習慣」であり、頼み事も「妙に億劫な気がした」というような、捉えどころのない感覚として語られている。
そして父の答。普通に読めば、別に反対されたわけじゃないから、いちおうほっとしたぐらいに謙作は受け取ったのかと思おうと、実はそんなことはない。むしろ、この答を「不快」に思うのだ。人間って、複雑だ。
謙作は最初から父の快い返事を予期していなかった。しかし予期通りにしろ、やはり彼はかなり不快(いや)な気持がした。彼は悪い予期は十二分にして行ったつもりでも、それでも万一として気持のいい父の態度を空想していたのが事実だった。ところが父の答えは予期より少し悪かった。変に冷たく、薄気味悪い調子があった。何故乗気で進もうとする自分の第一歩に、父がこんなちょっと躓(つまづ)かすような調子を見せるのだろう。彼には父の気持が解らなかった。
いったい謙作が言う「気持のいい父の態度」とはどのようなものだったのか。試験問題にでもしたいような箇所である。
「そうか、そりゃよかった。愛子はお前とは幼なじみだし、いい子だからな。よし、そういうことならオレがなんとか話をつけよう。なあに、心配するな。オレに任せろ!」てな反応だろうか。それが謙作が「万一として」期待していた態度だったのだろう。
その「万が一」の期待はもちろん見事に実現しなかったわけだが、それなら、「最初から父の快い返事を予期していなかった」謙作の「予期」とはどういうものだったのか。「十二分にして行った」「悪い予期」は、もちろん頭から反対するということだろうが、それはなかった。
父の言葉は、「向こうがいいんなら、いいと思うよ。でも、お前も一人前になったんだから、オレに相談するんじゃなくて、自分でやったら?」てことだろう。それを謙作は「変に冷たく、薄気味悪い調子」だと謙作は受け取る。その父の答と、その調子が、「予期より少し悪かった」というのだ。
となると、謙作の「予期」は、おおよかったなと喜ぶ父ではもちろんなく、といって、ムキになって反対する父でもない。結局のところ、そこにあったのは「いつもの父」だったのではないか。だから謙作は「やはり不快な気持ちがした」のだ。「やはり」というのは、父の「親身になってくれない」態度を予期していたということで、その態度や調子が、改めて「不快」の念を謙作の中に呼び起こした。
そればかりか、その「予期」より「少し悪い」というのは、父の冷たさはもとより、「薄気味悪い調子」が、謙作にはどうしても理解できないものとしてクローズアップされたということだろう。
「何故乗気で進もうとする自分の第一歩に、父がこんなちょっと躓(つまづ)かすような調子を見せるのだろう。」という思い。それは父に対する根本的な不快の念で、「序章」に念入りに書かれていたことでもあったのだ。



















