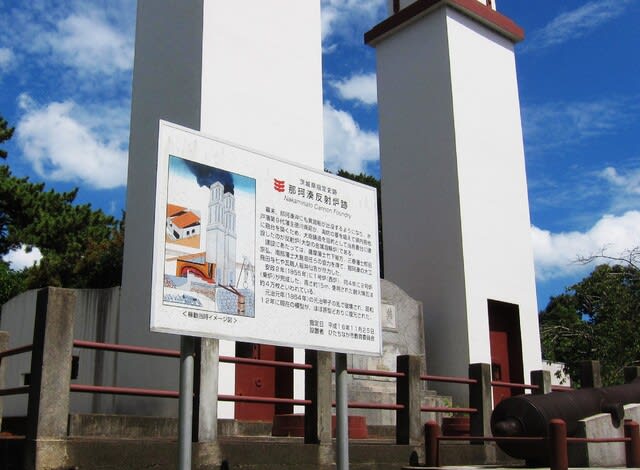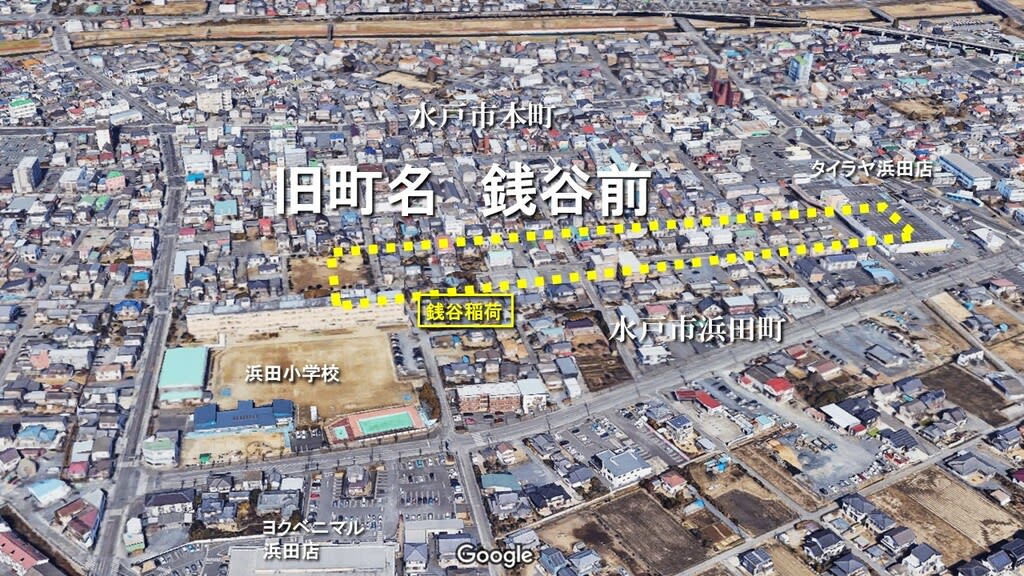茨城町、鉾田市、大洗町にまたがる涸沼(ひぬま)は周囲約22km、湖水面積9.35㎢に及ぶ関東唯一の汽水湖です。シジミやハゼ釣りでも知られ、また野鳥の宝庫でもあり、望遠レンズのカメラマンにも人気の自然いっぱいの湖沼です。

この涸沼には、自然が造り出した沖に突き出た地形、砂洲(さす)があり、google航空写真ではっきりと分かります。
砂洲とは、河川によって運ばれた砂礫が、風や沿岸流によって堆積してできた砂嘴(さし)が成長して、やや沖合に細長く伸びた地形です。砂州の代表的な例は「天橋立」、砂嘴の例は「三保の松原」といわれます。

涸沼の砂州は北側が「親沢公園」、南側が「網掛(あがけ)公園」になっています。

親沢公園は、涸沼に突き出した一画に松林などの林が手入れよく並ぶ景勝地になっています。最大25張りのテント設営可能なキャンプ場もあり、ロケーションの素晴らしさから人気があるそうです。

松の木の間から筑波山が、山容がよりどっしりした形で見えています。ここからは「ダイヤモンド筑波」が10月10日前後に見られると出会ったカメラマンの情報です。

ヒガンバナも咲いていました。釣りをしていた方に聞いたら、今年のハゼは水温が高いせいかぜんぜん当りがないと嘆いていました。

さて対岸の網掛公園、広々としていますが夏草の刈り取りがまだのようです。

突き出した砂洲の湾曲した部分が良く分かります、大きなボラがたくさん水面から飛んでいますが、ここでも釣り人の釣果は散々なようです。ボラは水中の酸素濃度が低下しているため酸素を取り込もうと飛ぶので、魚の活性が低下している状況になり魚は釣れないという説もあります。

こちらは涸沼の出口に近い「広浦公園」…この一帯は、以前は沖合400mくらいまで黒松の生えた細長く突き出た岬状の砂州で「常陸の天橋立」と言われたそうですが、干拓等の埋め立てにより現在は砂嘴となっています。

あんば様で知られる大杉神社の鳥居とコブハクチョウ、多分ここに住み付いている個体です。

ここは、風波と東日本大震災時の0.2mの地盤沈降により侵食が進んだことから、平成25年(2013)久慈川の河床堆積土砂2,000 ㎥を運び込みましたが、まだ浸食が続いているようで砂浜がずいぶん後退しています。

水戸藩9代藩主徳川斉昭公が選定した水戸八景「広浦の秋月」の碑です。左側には保勝碑が建っていますが、常陸太田産の寒水石(大理石)のため、風雨に晒され細かい文字はよく読めなくなっています。
ところでこの涸沼は平成27(2015)年に、スズガモ、オオセッカ、オオワシの生息・越冬地としてラムサール条約湿地に登録されました。
※ラムサール条約とは「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい1971年イランのラムサールで開催された国際会議で採択された、湿地の保全と利用、学習に関する条約です。
沿岸の自治体である鉾田市と茨城町では、ラムサール条約に関連した水鳥湿地の保護施設を今年度中に開設することになっています。

4月にオープンした鉾田市の「みのわ水鳥センター」です。観察センタ3階の屋上からは広々とした湖水を眺められ、また双眼鏡の無料貸し出しも行われています。

湖岸堤防には遊歩道があり、野鳥などの営巣地や水性植物の群落となる湿地の中には木道が敷かれて観察や散策、釣りには絶好のポイントになりました。

古墳のような高台には、お子様に人気の芝生の滑り台スロープが設置されています。

この施設のちょうど対岸には、沿岸自治体の茨城町が建設中の「涸沼水鳥湿地センター」が間もなく完成の予定です。(完成予想図は茨城町のウェブページよりお借りしました)

この一画にある「いこいの村涸沼」は、日本一の宿泊率を誇る国民宿舎「鵜の岬」の姉妹館として人気の茨城県営の宿泊施設です。夏の大プールや64ホールの林間芝生コースを完備したグラウンドゴルフ場も好評です。

また、34.5haの広大な敷地を誇る涸沼自然公園は、自然を丸ごと取り込んだ中に広場や遊戯施設が散在しており、隣接して規模の大きいテントサイト、オートキャンプ場も備えています。
海抜0mのため海の干満の影響で最大40cmくらい水位が上下する涸沼…、砂州や砂嘴ができやすくこれが葦原となり、海水と淡水が混じり合うため鳥たちの餌となる魚類やシジミなども豊富で、冬になるといろんな鳥類の群れで湖面がにぎわいます。この自然いっぱいの涸沼の豊かな生態系を後世に残そうと水質浄化や自然環境の保全に取り組む運動が行われています。